安芸の歴史 安芸氏の繁栄
- HOME
- -
- 安芸の歴史 安芸氏の繁栄
担当 : 安芸市歴史民俗資料館 / 掲載日 : 2025/02/12
安芸氏
安芸氏は、壬申の乱(672年)で土佐へ追放になった蘇我赤兄の子孫として伝えられ、在地豪族として郡司から荘官、地頭となって安芸庄を支配し、繁栄の基礎をつくりました。
延慶元年(1308)に安芸城を築城し、戦国期には土佐七雄の一人に数えられ、「安芸五千貫」を領有する大豪族として、安芸郡ばかりでなく、香美郡の東部にまで進出して、 土佐国東部で最大の勢力を誇るようになりました。しかし、永禄12年(1569)土佐統一をめざす長宗我部元親に攻められ、激戦の末に敗れました。
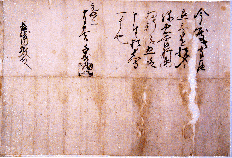
長崎内蔵助宛安芸国虎書状
永禄12年7月長宗我部氏との最後の決戦を前に籠城を呼びかけた書状。
安芸城跡

延慶元年(1308)安芸親氏によって築かれたといわれています。城は安芸平野のほぼ中央にあり、標高41m、東西100m、南北190mの長楕円形をした平山城の頂上からは、安芸平野や太平洋を一望できます。 城の広さは約10ヘクタールで、周辺に内堀を設け、その掘った土で土塁を築き城壁とし、東の安芸川、北の城ヶ淵、西の矢の川、南の溝辺の堀を外堀として天然の要塞をつくりあげていました。 今も詰のほか、二の段、三の段などの曲輪や堀切、虎口の遺構、大手門の枡形などが残り、かつての栄華がしのばれます。
安芸国虎墓

安芸城最後の城主である安芸国虎は、土佐統一を進めていた長宗我部元親と対立し、激しい抗争を繰り返しました。
永禄12年(1569)7月、元親は、7200人の兵をひきいて金岡城(安芸郡芸西村)を落城させ、これに対し国虎は5300人の兵を集めて、八流(安芸市)で守りを固めました。 八流は海に面した自然の要害でしたが、長宗我部軍の奇策により動揺した安芸軍は総崩れとなり撤退します。そして、この間に長宗我部軍が安芸軍内の協力者の先導で山越えし、城の背後から攻め込んだため、安芸軍は全軍城に引き揚げ、立て籠もることとなりました。 籠城は24日間に及びましたが、敵に内通する者が出て、城内の井戸に毒を投げ入れたため、ついに国虎は城を明け渡すことを決心します。国虎は一子千寿丸を阿波へ落ちのびさせ、夫人を生家の一条家(中村市)のもとに送り返した後、全将兵の助命を条件に浄貞寺に入り、8月11日自刃しました。 その墓は、殉死した有沢、黒岩両家老の墓に守られるように、今も浄貞寺に残っています。
※安芸 安芸国虎を滅ぼした長宗我部氏は、「安芸」を「安喜」と改め、明治になるまで「安喜」が使われました。
安芸市歴史民俗資料館
電話:0887-34-3706