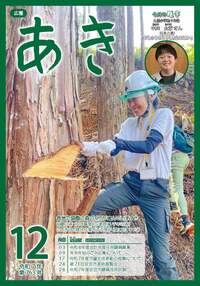議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 尾原進一
質疑、質問者:尾原進一議員
応答、答弁者:市長、企画調整課長、農林課長兼農業委員会事務局長、副市長、危機管理課長、建設課長、消防長、商工観光水産課長、生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長
○徳久研二議長 以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 通告に基づきまして、一般質問をいたします。
まず、本年1月1日に発生しました震度7による能登半島巨大地震により亡くなられた方々や被災された皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早い復興をお祈りを申し上げます。
要旨といたしまして、市長の政治生命についていうことで、最初の1番の市長の選挙公約についてと、2番目の南海トラフ巨大地震対策について、そして3番目に高知東部自動車道完成に向け、安芸市の観光戦略について伺う。そして4番目に、国民宿舎あきの現在までの経緯について、4点にわたって質問をしたいと思います。よろしくお願いをします。
まず、1番目の市長の選挙公約について伺ってまいります。
(1)の小・中学校給食についてを伺います。
学校給食法が公示されたのは、非常に古い昭和29年のことでございましたが、安芸市が市制発足した年でございました。この法律の第4条に義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならないと明記されております。平成5年第1回定例会におきまして、学校完全給食実施に関する請願を土居小学校PTAの皆さんが議会に提出し、紹介議員として私も名前を連ねておりました。この請願が提出された頃の全国の学校給食実施率は、公立小学校では95%に対し、安芸市では27%で非常に低いパーセントでございました。横山市政になるまで長い間実施されませんでした。市長にお伺いをいたします。
横山さんが教育長のときに、小学校・中学校給食センターでの実施検討会なるものを立ち上げたと私は記憶をしておりますが、その当時の状況をまずお伺いをいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
平成16年度からの施設建設に向け、実施計画まで以前取組を進めておりましたが、国の三位一体改革の影響により、安芸市の財政状況が厳しさを増したことから、事業を凍結した経過がございます。私が教育長時代の平成23年、24年頃だったと思いますが、当時家庭の事情による子供の朝食の欠食率や給食を実施していない市内の小学校において、昼食を食べない子供や時々しか食べない子供がいることも学校から報告があり、また学校給食法が平成21年に改正され、従来の学校給食の実施に加え、学校給食を活用した食に関する指導の実施等が新たに規定され、食育の推進がより重要になりました。
そして、徐々に本市の財政状況の改善についても道筋が見えたことや、完全給食の実施は食育の推進にとどまらず、近い将来必ず発生すると言われている南海トラフ地震の際には、非常炊き出し用施設としての活用も可能となる施設として、凍結していた学校給食の実施について検討するため、平成24年5月に安芸市学校給食検討委員会を立ち上げたところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございました。私は昭和61年にこの市議会議員に当選をさせていただいて、和食市政から横山市政まで5人の市長と一緒に市政に参画してまいりましたが、学校給食に関しては歴代の教育長は誰もがやろうとしませんでした。その理由が、先ほど市長が答弁にありましたけれども、行政の財政難、あるいは三位一体改革、そういったようなことで随分と遅れてまいったわけですが、今答弁にありましたセンター方式なるものの立ち上げと検討会を立ち上げ、すぐに小学校・中学校の給食が実施をされました。
長い間、実施されなかったところは先ほども言いましたけれども、この給食センターが高台の現在の清水寺岡に建設をされました。そして来る南海トラフ巨大地震に対しても、災害に対しても対応できるということもお伺いをいたしております。この関係者ももちろん、市民の方も大変喜んでおると思います。
次に、(2)の新火葬場建設についてお伺いをいたします。
この火葬場建設につきましても、津久茂町の位置が伊尾木の黒瀬谷ということで、簡単に言いますけれども議会で随分時間がかかりました。そして安芸市の一番の重要な課題でもあり悲願でもございましたが、そうした時期に安芸市長選がございました。その後、火葬場建設は津久茂町以外で建設するという市長の公約を掲げた横山氏が市長に当選をされまして、伊尾木黒瀬谷と場所を決定をされました。
私の場合、新火葬場建設につきましては、当初から伊尾木の黒瀬谷ということをこの議会でも発言もしてまいりました。なぜならば、土地については安芸市の市有地であり、そして進入道路につきましてもメルトセンターの完成によってついておる、そういったこともあって、そしてまた、安芸市街地を見下ろす絶景な場所であり、下には伊尾木の墓地公園がございまして、そんなそしてまたもう1点、何よりも好条件であったのは、民家がないいうこともあり、これだけの好条件のそろったところはほかにはない。ただ一つ、伊尾木の地域の住民合意をいただくということであったと思います。
市長は、その当時どのようなことであったのか、まずお伺いをいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど尾原議員のほうからもおっしゃられましたが、新火葬場の設置場所は用地取得の必要性、用地取得が可能か、それから造成費、アクセス度、水道そして民家、人家から200メートル以上離れていることや、景観等を判断基準に市内を調査した結果、黒瀬谷に決定した経緯がございますので、結果として尾原議員の思いと同じであったというふうに思っております。
なお、当然、黒瀬谷への建設に反対の方もいらっしゃいましたので、1人でも多くの方に御理解をいただかなければならないという思いでございました。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございました。地元の合意をいただいたいうことで完成になったわけですが、立派な杜の聖苑が完成に至ったというわけですが、安芸市の場合、単独で火葬建設となったわけですが、この当時には私はこのような施設は広域でやったほうがいいだろうという認識でおりましたけれども、東日本の巨大地震、そしてまた能登半島のああいった大きな地震を見ておりますと、やはり安芸市の火葬場は単独でやったほうが私はよかったかなという思いが今でもしておるわけでございます。大変市長も公約に掲げて完成に至ったということで、大変御苦労もされたと思います。
それから次に、安芸染井保育所と安芸保育所の高台移転につきましては、市長選の公約には私が記憶しておるところではなかったじゃなかろうかと思いますが、その辺は市長にお伺いしたいと思います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私の公約にはございませんでしたが、私が市長以前からもそういう課題がありましたので、それ順次取り組んでいったということでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 次に、(3)の庁舎建設についてをお伺いいたします。
東庁舎は建設から60年以上経過しておりまして、耐震性の不備や設備の老朽化や南海トラフ地震、また東日本大災害等の対策を考えた結果、平成25年新庁舎建設検討委員会が発足して10回の検討委員会の結果、答申が提出されました。私もこの委員会に議長として、7回目から途中からメンバーとして参加した経緯がございます。市役所が移転する場合、事務所移転の条例の非常に難しい条例がありましたけれども、議会の3分の2の議決が必要であり、2度にわたり否決となったことは御承知のとおりですが、このことにより、緊急防災・減災事業債の期限切れやその対応にも時間を要し結果、事業も運用できることとはなりました。
昨年12月2日、庁舎落成式典となったわけですが、東日本大震災での教訓を生かすということから、新庁舎移転は浸水区域以外の市役所が機能することであったと思うが、市長の思いをお伺いします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 旧庁舎は老朽化や耐震性の不備などの課題に踏まえまして、南海トラフ地震による津波で6.5メートル浸水するという予測が示され、災害時にも機能できる市庁舎の整備は喫緊の課題でございました。
また、東日本大震災や平成28年熊本地震で庁舎が被災した自治体では、復旧・復興に大きな遅れが生じておりましたことから、これらを教訓としまして新庁舎の建設に当たりましては、市民の命と財産を守ることを最優先に、災害時における防災拠点機能の維持と被災後の市民生活や復興・復旧に向けた行政機能の維持を確保するため、津波浸水想定区域外での庁舎建設に取り組まなければならないという思いでございました。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 緊急防災・減災事業債の期限切れということが、私どもも市長も議会も大変心配をしておりましたけれども、国会議員の皆様はじめ、多数の方々のおかげで延長ということで、再々延長ということで現在の新庁舎が落成に至ったわけですが、思い出してみますと平成25年にこの検討委員会を立ち上げまして、完成までちょうど10年かかったいうことで大変な執行部の方も議会の人も大変な心配もしておったわけですが、やっと完成をしたことで肩の荷を下ろしたということでございます。庁舎完成までには、ロシアがウクライナに侵略することで、世界の食料や重油、そして物価の高騰やコロナ禍の中で資材高騰で頭を大変痛めたことと思います。
安芸市のここ四、五年を顧みますと、安芸川の氾濫による大変な災害がありましたけれども、県による砂利の撤去や江川川の改修工事や土居・高台寺の市営住宅の建設や新庁舎建設、統合中学校の建設など、東部自動車道の工事、そして安芸道路の高規格自動車道、安芸中央インター線の整備など、そしてまた加えて伊尾木インター線の道路のなどなど建設などの工事でダンプカーや重機、生コン、そして人、今までにない私が経験したことのない安芸市のすばらしい動きがありました。国道55号線も渋滞に至るほどの状況が続いておりまして、安芸市民も大変感動もし喜んでおる状況が今でも続いておると思います。
昨年12月2日、安芸新庁舎落成式典が現地で執り行われましたが、出席者の国会議員の祝辞挨拶の中で、横山市長は非常に運がいいとそのようなユニークなうれしい言葉をいただいたわけですが、私の視点で言わせれば確かに運も政治家にとっては大事ですけれども、やはり横山市長は人柄だと思いますし、それを後押ししてくれる安芸市職員が最も大きな事業をやり遂げてくれたということに私は尽きると思っております。市長の認識をお伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 これまでの取組につきまして、議員から職員共々御評価をいただきましたことに、素直に受け止めたいと思います。御礼を申し上げます。
議員の言われるように公共公用施設、そしてインフラ整備が日々進捗しておりますので、私の周りでもしばらく安芸市から遠ざかり戻ってこられた方は、まちの変化に驚かれている方もたくさんおります。
こうした様々な整備が進む中で、市民や子供たちの命を守ることを最優先に取り組んだ庁舎と中学校建設への道のり、そしてこのたびの完成は万感こもごもいたる思いでございます。先ほど議員から運や人柄といったお話もいただきましたが、私としては安芸市への思い入れや市政への信念、行動を信じていただき、ともに汗をかいてくれた多くの職員やお力添えをいただいた関係の皆様、そしてほかならぬ市民の皆様の御理解と御支援があったからでございます。
新庁舎開庁の3日前、先ほどからお話が出ておりますが、1月1日能登半島地震が発生いたしました。人口減少というかつてない厳しい時代の中、来る南海トラフ地震への備えに公共的施設が市民の命を守り暮らしを支える機能、役割をしっかりと果たせるよう防災・減災に強いまちづくりにも取り組んでいかなければならないと痛感をしております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございます。
次に、(3)の市立安芸中学校、そして市役所跡地についてのお伺いをいたします。
令和5年3月に、市役所庁舎及び市立安芸中学校跡地活用に関する報告書が提出されております。市長のこの内容についての認識をお伺いいたします。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後3時
再開 午後3時6分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど、市立中学校、市役所跡地について伺うを(3)を(4)でございますので訂正をいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 市立安芸中学校、市役所跡地についてということで、今期定例会冒頭の施政方針で御説明いたしましたように、いただいた跡地活用報告書には何度も目を通しまして、市民の願いや思いといった新たなまちづくりを望む声に、私もそれぞれの跡地にはどういったものがふさわしいのか考えを巡らせてまいりました。
この報告書には両施設の周辺や将来の立地特性を見据え、市の未来に思いを寄せる市民の御意見や御提案として活用の可能性がある機能が丁寧に整理されております。また、それぞれの跡地活用の理念として、旧庁舎は多様な世代が交流し、にぎわいやつながりを醸成する空間、中学校についてはスポーツ、学び、ビジネスなど新たなチャレンジを創造する空間と表現されており、これらのフレーズは様々な市民の声をバランスよく的確に捉らまえた活用の基本方針として分かりやすいものであると受け止めております。
今後は、この報告書にある理念を基に基本構想を策定することとし、来年度予定しております基本計画の作成や民間活力導入可能性調査を速やかに実施してまいりたいと考えております。
以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 市長答弁で今議会にも提出をされておると思いますけれども、基本構想を立ち上げるというようなことになっておりますけれども、この内容につきまして市立安芸中学校の跡地の利用活用については、スポーツ、健康づくり、宿泊、観光、教育文化交流、企業誘致、移住、そのほかの報告となっておるわけですが、この中で移住が取り上げておられます。その中で、移住希望者のお試し住宅と移住者支援住宅とありますが、いずれも教室を活用し宿泊施設を整備し、移住者向けの住宅を整備するということであったように思います。
先般聞いた話では、高知県下でも安芸市は移住に関することが2番目であるというような報告も受けておりますが、1次産業が盛んな本市でも人材不足は重要な課題であります。重点施策等の考えがどのような、答弁しにくいと思いますけれども、市長のお考えを、認識を伺いたいと思います。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えをいたします。
令和4年度における市外からの移住実績は過去最高となる211組274人となっております。また、県外からの移住実績はそのうちの87組111人と、高知市に次いで2番目の移住実績となっております。本市に転入された方には市独自のアンケート調査を実施しており、農林業での就業を希望して移住される方も毎年一定数いらっしゃいます。1次産業の担い手確保につながる移住希望者への効果的な情報発信や受皿体制を強化することは、重要な取組であります。
市立安芸中学校跡地活用におきましては、市民の皆様から教室を改修した移住者支援に係る受皿整備など、施設の特性を生かした活用に関する様々な御意見を頂戴しておりまして、どのような活用方法ができるのか、来年度の基本計画や民間活力等導入可能性調査での分析、検証の中で検討してまいりたいと考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) よろしくお願いしたいと思います。
それでは、市役所の跡地についてお伺いをいたしますが、市長は公約でも旧庁舎を取り壊して更地にするというようなことを記憶にありますが、一体いつ頃をめどにそういったことになるのか、市長のお考えを聞きたい。よろしくお願いします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
まず、次年度取り組む基本計画の完成時期につきましては、庁舎と中学校の2施設あることから、通常よりやや時間を要し、令和6年度末を目途に活用策の具体案を議会や市民の皆様にお示ししたいと考えており、令和7年度の前半には両施設の活用策を集約した基本計画の最終版を策定する予定でございます。
この基本計画策定と並行し、民間活力等導入可能性調査を行いますが、具体的にどういった機能や規模の施設にするのか、また民間活力なのか、これまでどおりの手法なのか、調査結果によりこれからのスケジュールは明確になるものでございます。
このため旧庁舎の解体予定につきましては、現時点でいつ頃とお答え、お伝えすることができないものですが、令和7年度から令和8年度には設計を発注し、その後解体工事に取り組みたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁では、中学校跡地、市役所の跡地も基本構想を立ち上げて、その結果7年頃にという答弁であったかのように思っております。
それでは南海トラフ巨大地震対策についてお伺いいたします。
(1)の安芸市施設園芸農家の重油タンクの現状とこれからの課題についてお伺いいたします。
安芸市内で重油タンク2,000リットルですが2キロ、どれだけの数を把握しているのか、まずお伺いいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
本市での施設園芸におけます農業用の燃料タンク、重油タンクにつきましては、市内の重油タンクのほとんどがJA所有のもので、農家に貸し出す形より設置されておるものでございます。JA高知県の調査によりますと、令和5年3月末時点でJA所有の重油タンクが市内には938基が設置されております。JA高知県以外の所有分の正確な基数は把握できておりませんが、恐らく1,000基以上の重油タンクが設置されているものと推察されるものでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 938基ですかの答弁がございましたけれども、その中で南海トラフ巨大地震での浸水区域にある重油タンクはどのくらいあるのか。分かっていればお伺いします。
併せて近年、炭酸ガス発生装置の灯油のタンクが設置もされておりますけれども、お伺いをいたします。この向かって北側のこの道沿いにも白いタンクが四、五基ありますけれども、ここから見てみますと赤のタンクが基準値のそういったことをしてないタンクがほとんどあるような状況でございまして、まず先ほどの浸水区域内のタンクの数はどれくらいあるのか、把握しておればお伺いします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 まず、重油タンクについてでございますけれども、JA高知県所有分のみの御報告になりますが、令和5年3月末時点の重油タンク938基のうちL1想定の津波浸水区域内に90基があるものでございまして、次にL2想定の津波浸水区域内においては346基が設置されており、JA高知県が所有するタンクの約46%にあたる436基が津波浸水区域内に設置されているものとのことでございました。
次に、炭酸ガス発生装置の灯油タンクにつきましては、安芸農業振興センターによる調査では、平成23年度以降の事業導入実績が325基となっていることから、これと同数程度の灯油タンクが設置されているものと推察をされます。このうち津波浸水区域内にある基数につきましては、現時点では把握はできていないところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) なかなか浸水区内にあるタンクが幾らかと言ってもなかなか調べようがないぐらい難しいかなという思いはいたします。
それでは県の次世代園芸、レンタル事業を含めて、整備したタンクの過去3年間の経緯をお伺いします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えします。
県の事業であります園芸用ハウス整備事業、または農業用の燃料タンク対策事業を活用して防災対策が講じられた重油タンクにつきましては、令和5年度に19基、令和4年度に15基、令和3年度に28基で直近3か年の合計で62基の整備が図られているところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 3年間で62基というようなデータが報告がありましたけれども、ロシアによるウクライナの侵攻による資材の高騰で、10アールあたりのハウス建設が従来の倍ほどになってレンタル事業へ手を挙げる方が非常に少なくなっている状況ではないかと思います。このような状況では耐震性のある重油タンク設置は、間もなく来ると言われております南海トラフ巨大地震にはとても間に合わない、そういうふうに私は考えるところですが、これはどのように認識をされるのか、まずお伺いします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
施設園芸農業を取り巻く状況につきましては、農業用資材の価格高騰でハウス建設コストが上昇する中、本市におきましても農業者や新規就農者が新たな設備投資をちゅうちょする傾向が見られるところでございます。
こうした中、重油タンクの防災対策につきましては、さらなる農家負担を要する反面、農業者の収益増加には直接つながるものでなく、場合によってはハウスの減築を強いられるなどの理由から既設タンクの耐震化を図る農業用燃料タンク対策事業におけます近年の事業活用実績が伸び悩んでいるところでございます。
一方、施設園芸が盛んで重油タンクの設置数が多い本市におきましては、地震発生後の津波火災による甚大な被害が想定されており、また能登半島地震での報道による家屋倒壊や火災などの映像を見ますと、議員も御指摘のとおり、重油タンクにおける防災対策は待ったなしの状況であるというふうに認識をしております。
このため、令和6年度からは県の農業振興センターやJA高知県と連携し、農業者を対象とした講演会などの開催を通じて防災意識の醸成を図るとともに、燃料タンク対策事業の活用を促すための推進枠として新たに予算も計上しておるところでございます。引き続き災害に強い園芸産地の維持強化に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 答弁がございましたけれども、私の認識では安芸市は特に施設園芸が盛んでありまして、重油タンクの設置が先ほど説明がございましたけれども、数にしたらなかなかこれはもうよそにないようなタンクを設置しておるというようなことで、ちょうど昭和47年に大きな台風がありまして、この安芸地方にも大変な被害がありました。そのときに重油のタンクが2,000リットルが田んぼでごろごろしておったというような状況でして、今までの重油タンクは4つの足の上にそのままタンクが乗っておるというような状況で、大きな風にも弱いし、地震が来ればとてもではないですけれども倒れると。そして重油が残っておればまけるというようなことで、津波が来て引き潮で持っていかれるのか、来たときに倒れるのか、地震で倒れるのか、いずれにしてもタンクが倒れて重油が流出するということが必ずこれは想定よりももう現実味がある話でして、そのときに必ず火災が発生するわけでして、引き潮でもあるいは反対の潮でも重油がまけて民家に、瓦礫に火がつく、そしたら大火になるということが必ずこういったことが今までの教訓では分かっておりますので、県が2分の1、市が2分の1とかいうことも発表されておりますけれども、これは副市長にお伺いしたいですが、担当課だけではなしに、これ全庁的にはやっぱし防災対策として取り組む必要があるのではないかと思いますので、副市長の答弁を願いたいと思います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
急な質問でちょっとびっくりしておりますけれど、議員の御指摘のとおり、これは安芸市全体での問題であろうかと思います。担当の農林課ということになりますけれど、そういった防災対策も踏まえて総合的に対応していきたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) それでは、2番目の市内のガソリンスタンドについてお伺いします。
安芸市のガソリンスタンドは民間、JAを含めて何か所あるのか、まずお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
現在、安芸市内のガソリンスタンドは、全部で9か所あります。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 9か所のうち、浸水区域外のスタンドは幾つあるのか、答弁お願いします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
発生頻度の高い地震による津波、いわゆるL1津波の浸水想定では7か所のガソリンスタンドが浸水しないものと想定しています。また、最大クラスの地震によるL2津波の浸水想定においては、株式会社JAエナジーこうちの安芸北給油所と東川給油所の2か所が浸水しないものと想定しており、平野部においては株式会社JAエナジーこうち安芸北給油所の1か所となります。
以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど答弁いただきましたが、北支所と東川支所とこの2か所だという報告がありましたけれども、現在統合中学校の開校により今工事をしておりますけれども、恐らく年度が変わっての工事になろうかと思いますけれども、北支所のどういったことになるのかいうことをまずお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
市道中道線の歩道整備に伴いまして、ガソリンスタンド施設への用地影響幅、道路による用地影響幅は約5メートル程度必要となりますことから、既存の給油施設や地下タンクへの影響が生じることとなります。
このため、現位置でのガソリンスタンド経営は物理的に困難であると認識しております。なお、令和6年度当初予算には、これらに係る用地補償費を計上しておりまして、JA高知県との協議が整い次第、用地補償契約を締結することとしております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 答弁ありがとうございました。私の伺っておるのは歩道が3.5メートルということを承知しておりますが、先ほどの答弁では5メートルということを初めて聞きましたけれども、それでは今の北支所のスタンドがなくなると思いますけれども、移転先が分かっておれば。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
ただいまちょっとJAと協議をしておりまして、一応移転先のあてとしましてはJA北支所の北側にあるサポートハウスの土地の一角を今のところ想定してお話させていただいて、協議しております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) まだそしたら想定ということですので、決定ではないがですね、分かりました。
それでは3番目に移りたいと思います。安芸市消防分団員定数減についてお伺いをいたします。
先般、NHKのテレビを見ておりますと、全国放送で消防団員の減の問題については放映されておりましたけれども、安芸市の消防分団員についても定員が282名ということで、昨年の決算委員会で私もお聞きをして驚いたわけですが、そのときの状況が40数名減であるというようなことで、40数名言いましたら1分団が25名から20名いうことで2分団が少なくなるかなというように認識をしておりますが、今年の1月7日に安芸市消防団員の出初め式がありました。
それで今年の各分団に入団された方が団員が9名というような報告を聞いたわけですが、けれども年度が終わってみたらその9名が10名になり、欠員がまた生じるであろうということに予測されますが、非常に心配をしておるところですが、来る南海巨大大地震についても津波につきましても全国的に言いますと12万人定員が減になっておるということも承知をしておりますが、安芸市の早急なこれは対応をしていかなければ間に合わないと。
一時はここ20年までに至らんと思いますけれども、市役所の職員とかJAの職員とかいろんな方を勧誘をして団員になってもらったというような経緯もありましたが、そしてまた加えて消防署の職員が入団をされてないという現状がありますけれども、定年なのか何かの思いが、事情があって入団されてないのか、そこら辺を一つ消防のほうにもちょっと御答弁を願いたいと思います。
○徳久研二議長 消防長。
○久川 陽消防長 本市の消防団は昭和29年8月1日に結成し、団員総数314名、定数は334名、当時の人口は2万9,841名でしたが、人口の減少とともに団員数も減少してきており、令和5年4月1日現在の団員総数は240名、定数は282名、人口は1万6,097名となっております。その理由としまして、退団する人数が増えているものの新たに入団する人が減少傾向にあることが挙げられます。
早急な対応という御質問ですが、消防団員を増やすというよりは現状をいかに維持していくかが喫緊の課題と考えておりますので、職員はもとより消防団員の協力を得ながら取り組んでまいりたいと考えております。具体的にはこれまでと同様、JAなどの事業所の職員や市職員への入団促進、広報等で啓発を引き続き行ってまいります。
それと消防本部を退職された方への入団のことでございますけれども、過去これまでに入団を依頼したことやOBの方から入団したいいう声もありませんので、現状そういった形となっております。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁で意外な答弁を聞きましたけれども、現状維持いうようなことを私はこれはもうちょっと反省せないかん答弁じゃないかなと。なぜなら、やはり東南海が明日来るかもしれないというような状況ですので、やはり前向きに行政としてどう取り組んでいくのかいうことを私は質問をしておりますので、やはり改善すべきは改善する、そして団の定員に人口が減ったじゃなしに、現状はこういうところですということは私が先ほどから住宅の問題につきましても言っておりますので、やはり安芸市は安芸市の市民を守るというようなことでの質問ですので、前向きな答弁をいただきたかったわけですが、よろしくお願いしたいと思います。
次に、安芸市の消防団の各分団は以前、初午という行事がありました。各分団がそれぞれその地域を回って協力金といいますか、いわゆる団の1年の経費を賄うといった意味でここにお金を集めてそれを1年間の運営費用に充てるというようなことが、これはもう慣例として長いこと続いておった状況でしたけれども、それはもういけないというようなことで現在に至っておるところでございますけれども、先般、団員の方にお聞きをしましたら、非常に団の運営上に困っておるというようなことで、前は私も消防団員として16年間土居分団におりましたけれども、やはり初午とか出初めとか、そして夏には夏季鍛錬、今ポンプ操法ということになっておりますけれども缶送りとかソフトボール大会とかいろんな行事があって、非常にそうやって団員の懇話を深める機会もあったわけですが、最近はどうもそういったことかも分かりませんけれども、運営上非常に窮屈になっておるというようなこともお聞きをいたしておりますが、そういった処遇改善をもうちょっと改善をしなければ、そしてまた消防団員の勧誘にもかうといった意味からも、もうちょっとやっぱし努力をするべきではなかろうかと思いますけれども、もう一度御答弁をお願いします。
○徳久研二議長 消防長。
○久川 陽消防長 消防分団の運営に困っているとの御質問ですが、各分団長が集まる幹部会において、運営上必要とするものがあれば消防本部まで提案するよう伝えていますので、提案等があれば検討の上、予算の範囲で対応させていただきたいと思います。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど質問したように全国放映がNHKでありましたけれども、団員が3万6,500円、そして1回の出動で8,000円と値上げはしておると思いますけれども、最近では生活環境の向上や変化などで火災が非常に少なくなっておりまして、出動の回数も少なくなっておるのが現状ではなかろうかと思います。
こういったときのことも踏まえて、全国が一律に決めておるのか、この団員の報酬といいますかそれが一律であるのか、市町村によって違うのかいうことが分かっておればお聞きをしたいと思います。
○徳久研二議長 消防長。
○久川 陽消防長 消防団員の報酬等につきましては、令和3年4月13日付消防庁長官通知の消防団員の報酬等の基準の作成についてにおいて、年額報酬の額は団員の階級のものについては3万6,500円を標準額とする。団員より上位の階級にある者等については、業務の負荷や職責等を勘案して標準額と均衡の取れた額とする。
次に、出動報酬の額は災害に関する出動については、1日あたり8,000円を標準額とすると通知されております。
本市につきましては、現在消防庁の基準額を満たしていることから、今すぐ標準報酬額等を上げることは考えておりませんが、国の動向を注視しながら、県内の他市町村の状況と比較して著しく差がある場合は検討していきたいと考えております。
また、一律かということでございますけれども、高知県内でも基準額より上のところもあれば下のところもございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど答弁がありましたけれども、やはり待遇の問題だと思う一因があるかなと思いますので、やはり準公務員ですので待遇をよくしないと改善が図れないということは明々白々ですので、そういった努力を消防署だけにとどまらず、団長にとどまらず、やはりこれは全庁的にもこれは取り組んでいただきたいいうことをお願いしたいと思います。
それから次に、(4)の安芸市都市計画審議会計画についてお伺いをいたします。
安芸市の都市計画では、ちょうど高知国体がありまして、その当時安芸高の前までその都市計画で道路が開通したということで、その後、都市審議会では安芸橋までつくというようなことにたしか予定では聞いたことがあるわけですが、それともう一つ、高知安芸商工会議所の北へ、海岸まで都市計画審議会での話で道を抜くというようなことは私も薄々ですが聞いておりました。これは非常にとにかく商工会議所から南へいうことは、この安芸中央インター線とつながってもおりますし、安芸町内の避難道路としても十分すばらしい道ということになりやせんかなということで、分かっておれば審議会のその方針等をお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えをいたします。
御質問の道路、2路線ございますけれども、まず1つが元気館南側から東方面へ海岸堤防沿いを通り、江ノ川河口付近、安芸市浄化センター東側を経由しまして、国道55号の安芸橋西詰につながる都市計画道路海岸線の未整備区間、延長960メートルと、安芸商工会議所東側から海岸までを南北に直線でつなぐ都市計画道路中央線の未整備区間、延長230メートル、この2路線となります。
両路線とも都市計画法に基づき都市計画決定された道路であり、令和2年3月に策定した安芸市都市計画マスタープランにおいて、新規道路の整備として位置づけされております。なお、この安芸市都市計画マスタープランは、令和2年から10年程度の期間の目標を定めたものでありまして、まず海岸線の未整備区間につきましては令和5年度に測量設計に着手したところです。
次に、中央線でございますけれども、この都市計画マスタープランにおきまして産業の活性化や利便性、安全性の向上など、道路ネットワークの形成及び渋滞緩和対策として整備が位置づけされております。議員御指摘のとおり、国道55号から市役所新庁舎へ続く県道安芸中インター線が整備されたことから、防災・減災対策の観点からも海岸線から市街地に至る南北のルート整備については当然必要であるものと認識しております。
また、今後の見通しについてですが、以前にも同様の御質問があり答弁した経緯がございます。現在、主要なもので高規格道路関連の周辺整備事業として、あき病院球場線、ムネカネ線、吉川線、また通学路対策として、中道線、西木戸一の宮線、市庁舎南側から県道黒岩東浜線を結ぶシガヤシキ線、先ほど申しました海岸線など大型路線を中心に数多くの市道整備を実施中でありますことから、これらの進捗も踏まえながら現時点におきましては2020年代の後半、令和7年から11年度の間には着手することを目標としております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁で着手をしたと、海岸線まで商工会議所からいうことですが、見通しにつきましてもお聞きしましたけれども、私もムネカネ線とかシガヤシキ線とかいうことが中央インターへつなげるといったことも承知をしております。やはりその件とは別に私の伺っておるのは、安芸市の町内もっと人口が多いところの方を救うといった意味からも、これは早く実現していただきたいということがございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、次の質問へ移りたいと思います。
(3)の東部自動車道完成に向け、安芸市の観光戦略についてをお伺いしたいと思います。
市内の観光戦略につきましては、以前から私も言ってきておりますが、議会の研修や他の会議や観光などで全国の観光地を見てきたところですが、駅や道の駅、観光地でよく見るのは大型観光の看板ですが、そこの市内の観光地の紹介をはじめ、宿泊施設やトイレ、公園、そのほか各名所など多くの観光客が熱心に見ている光景を目にしております。
私の言いたいのは、点と点でつながっておりますし非常に分かりやすく、そこに行ってみようという気持ちになり、安芸市に来られた方々を一時でも長く見てもらうような戦略が必要と考えます。市内の観光地に大型看板は幾つあるのか、まずお伺いいたします。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 観光案内板の設置状況についてお答えをいたします。
市作成の観光案内板をカリヨン広場北、安芸ドーム西側、江ノ川上公園、旧市役所庁舎前、安芸駅前、溝ノ辺公園、土居公民館、彌太郎生家駐車場、伊尾木洞観光案内所の9か所に設置をしておりますほか、観光情報センター内にはタッチパネルによる観光案内システムを導入し、市内観光スポットへの周遊誘導を行っております。
ほかに、県設置の広域看板が安芸駅と観光情報センターの2か所にございます。さらに、安芸広域市町村圏事務組合設置の東部広域看板が赤野休憩所北側にございますほか、施設改修に伴い一時退避しておりました道の駅大山の広域看板も年度内に再設置をする予定でございます。
以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 確かにその場所についても説明がありましたけれども、私の言いたい看板は、やはり大きなパネルで大型の看板が私の言いたいところですが、普通の看板ならあまり見ないと思います。大きな看板で安芸市の先ほど言いましたけれども、それぞれの観光地、それぞれの施設、それぞれのトイレいったことが、滞在型につながるような看板が設置をしてほしいとこう思っておるところでございまして、これも戦略的なやっぱりことではないかなと思うところでございます。
それでは続きまして、その看板の設置ですが、西の玄関では赤野に今、岩崎彌太郎氏の大きな看板がありますし、ようこそとこういった歓迎の意味だと思いますけれども、東には下山の伊尾木洞という看板が設置をされておりますが、これは非常に市民に、それから観光を訪れる方にも受けておるというような評判も聞いておりますので、こういった努力を絶えず商工のほうもしていただきたいなという思いがございます。
それでは次に、廓中ふるさと館への大型バスなど進入道路についてお伺いいたします。
廓中ふるさと館建設の経緯につきましては、私も承知をしております。当時、土居公民館で地元の説明会がございまして、現在の場所となりました。そのときにも発言もいたしましたが、西の県道からも非常に入りにくい。そして土居小学校から北への進入道路も非常に入りにくい。そしてもう1点、東の安芸物部線からも分かりやすく入りづらい、また道路が狭隘でありますし、今まで私の一般質問での答弁では野良時計の駐車場へとめて、土居廓中を散策して廓中ふるさと館に行ってもらうということでございました。
私に言わせれば、このような状況では非常にもったいないと私は思っております。南海トラフ巨大地震対策として土居保育所も浸水区域内と考えているが、高台移転も含めて将来的に大型観光バスの乗り入れができるように私は思いますけれども、その考えをお伺いをいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
廓中ふるさと館までの大型バスの乗り入れにつきましては、以前にも議員から何度か同様の御質問がございました。現状の方針について特段変わりはございませんが、道路整備の観点から改めてお答えいたします。
御質問の場所は県道安芸物部線からふるさと館への進入ルートであります。簡易的ではありますが、大型バスが南から北へ進み、西へ左折する際の走行軌跡図というものを描いてみました。現状の道路が非常にクランク形状になっているいうことからですね、現道を拡幅しても大型バスの進入及び通行は不可能でありました。このため、大型バスの通行を確保するためには新たなルートを検討する必要があり、先ほど議員が言われてました保育所の高台移転による保育所跡地の用地が確保できたとしましても、住家等への影響が避けられません。
また、ふるさと館の駐車スペース、西方面へ通り抜けができないことによる回転場の確保、狭いスペースでの一般車両との混雑など、安全面においても十分な対策が必要となることから、現時点におきましては整備する方針に至っていない状況です。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 建設課のほうから先ほど答弁いただきましたけれども、現状用地を買収しても大型のバスが入らないと、こういうことですか。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 先ほど申しました走行軌跡図を入れてみたところですね、保育所の用地、または入り口にちょうどお家が2軒ほどございますけれども、その家もかかってしまうということです。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 分かりました。困難ですと、こういうことですね。
それでは(3)の江ノ川上公園の書碑を書道美術館の前に移設をしてはどうかということをお伺いします。
江ノ川上公園に建立してあった岩崎彌太郎さんの銅像を、ここにあっても整合性がないので生家に移設をしたらどうですかと、私が以前一般質問をしたことがあります。その当時の答弁では、観光協会が寄贈してくれたものだから動かせないと、こういった答弁でございました。このことは後の質問でも申し上げますけれども、その後、高規格道路、安芸道路、安芸中央インター道路により、江ノ川上公園のど真ん中をこの道が走るようになりまして、岩崎彌太郎氏の銅像は生家へ移転しておりました。
私に言わせれば、計画性に妙に欠けるんじゃないかと当時思っておりました。土居ハシオザン永禅寺の境内に南不乗先生の書いた書道名家顕彰碑があるが、知っておれば知っておらないのか、まずお伺いをいたします。
○徳久研二議長 生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長 お答えいたします。
境内に立派な顕彰碑があることは存じております。以上でございます。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございます。この書道名家顕彰碑は、安芸市の生んだ偉大な書家の川谷横雲先生をはじめ、川谷尚亭ほか7名の偉大な先達を長く後世に伝えるという内容でございまして、南先生がこの碑を山まで見に行って、そしてあまりにも立派な碑ですので河原で安芸の業者が掘ったと、南不乗先生の書であります。そういった非常に貴重な碑でございまして、江ノ川上公園も以前とは異なり、インター線により公園そのものが2か所となっており、7つの書碑やトイレなど一体性に欠けるような形となっているように思います。そして訪れる方もほとんど姿を私は見たことがないような状況ではないのかと私は思っております。
現在、書道美術館や歴史民俗資料館など、土地も含めて五藤家から安芸市に寄贈していただいておる状況です。私は書道美術館の前に江ノ川上公園の書碑と永禅寺の境内にある書道名家顕彰碑を寄贈していただいて移設をし、書道美術館を訪れた方々にこの歴史のある碑を見ていただいて、書道美術館、歴史民俗資料館に入館してもらうことを望んでおります。このように将来に展望を持った戦略が必要であると考えるが、担当課の考えをお聞きしたいと思います。
○徳久研二議長 生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長 お答えいたします。
議員がおっしゃるとおり、何事も将来を見据えた戦略を持つことは必要なことだと考えております。書道の振興につきましては、安芸書道振興協議会と連携して取り組んでおります。令和4年度に安芸書道振興協議会が江ノ川上公園の愛称を募集し、100名の方から募集をいただきました。そのうち79名が市内の小学生からの応募でございまして、江ノ川上公園の書碑の認知度が向上したのではないかと考えております。
移設に関しましては、書道美術館の建設に御尽力いただきました南不乗先生をはじめ、偉大な書家の先生方の功績は大きなものであると認識しております。その先生方の功績を広く伝えるためには書碑と書道美術館の連携は欠かすことのできないものであると認識しておりますが、書碑を移設するに当たりましては、所有者や関係者の意向を尊重する必要があり、市の一存で決めることはなかなかできないものと考えております。
また、歴史民俗資料館の南の広場には、五藤家の顕彰碑が建立されており、当広場は憩いの広場でもあり、地域住民の集いの広場ともなっておりますので、広くゆったりとした場所として今後も残していきたいと考えております。
今後も様々な方法で書道と書道美術館、歴史民俗資料館と一体的に取り組んでいかなければならないと認識しておりますので、引き続き安芸市書道振興協議会と連携し、書道文化の振興に取り組んでまいります。以上でございます。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁でより分かったような分からんような答弁だと私は思いますけれども、副市長にもう1点お伺いします。
私も書の世界では現日会との長いお付き合いがあります。亡くなられた先生方もおります。安芸市は全国を代表する書家を輩出しており、言わば書の殿堂でもあり、書碑を移設することによって相乗効果や整合性、また費用対効果も出てくるのではないか、そう私は思いますが、副市長の答弁を願います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
書碑の移設につきましては、先ほど生涯学習課長が答弁しましたように、書碑建立のこれまでの経緯や関係者の意向も尊重しなければならないと考えておりまして、市一存では決められないと考えております。今後におきましては、関係者の皆様の御意見も聞きながら対応しなければならないというふうに考えておりますけれど、この書碑と書道美術館、これは書道をはじめとします観光素材をつなげることや、また書を通じての交流を深める取組などによりましても一定の相乗効果も期待できるのではないかというふうに考えております。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) どうもありがとうございます。諸般の事情は私も分かります。けれどもやっぱし、この東部自動車道が開通に当たっての戦略は私は質問をしております。どうやって安芸市が観光で売り出すのか。安芸市は非常にすばらしい財産を持っております。三菱、彌太郎にしかり、弘田龍太郎にしかり、そして書家も全国でも屈指の書家を輩出しておりますし、野良時計もある。伊尾木洞もある。岩崎彌太郎邸もある。タイガータウンの市でもある。切りがないぐらいほかと比べたら大きな財産を持っております。これをどうやって生かすのか。点と点がつながってないのが私に言わせれば現状である。
これは観光ボランティアの方にもお伺いをしなくても大体分かります。非常にもったいない。このこれをどうやって活用して前へ進めて、観光を進めていくのか。滞在型にするのか、そしてそういったコースにするのかいうことの課題がたくさんありますし、やはりそういった戦略が私は必要ではないのか。どこそこがどんな事情で、先ほども岩崎彌太郎に生家の話もしましたけれども、やはり戦略がない。いろんな方に相談してみないかん、これは当然です。ですから私も永禅寺の住職にも了解をもらっております。寄贈してください、了解です。そして一般質問をしております。
やはりそういった努力の上にやっぱり戦略というものは描かなかったら、前にもいろんな答弁を聞いたことがありますけれども、その事情をクリアしないと安芸の市の観光の先が見えないといったことが現実ですので、どうやってクリアするのかいうことがやっぱし担当課の課長会でなしに、全庁的にどうしたらこれ生かせるのかいうことを私は期待しておりますので、ぜひ皆さん方も努力をしていただきたいと思います。
次に、休憩がいいですか。
○徳久研二議長 休憩しましょうか、暫時休憩いたします。
休憩 午後4時6分
再開 午後4時12分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) それでは最後の質問に入りたいと思います。4番目の国民宿舎あきの現在までの経緯についてまず、お伺いいたします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
国民宿舎あきは昭和48年4月に開業し、平成13年3月まで28年間の営業をもって閉館いたしました。その後20年以上にわたる長い期間、利用実績はなく放置した状態となっておりました。
こうした中、平成30年11月、民間事業者の方から市に国民宿舎あきを簡易宿泊施設として利活用したいとの相談及び活用の事業計画が提案されました。これを受け、諸課題を整理いたしまして、令和2年11月、当該施設等を活用した事業提案型プロポーザルにより、優先交渉権者を決定いたしました。このときの財産処分価格は土地と建物の評価額、そして解体する費用を合わせてマイナス評価として1円での譲渡価格を設定いたしまして、同年12月議会に財産処分の議案を提出し、委員会に付託されました。
しかしながら、総務文教委員会により、譲渡後の施設維持や譲渡価格などについて疑義があるため継続審議となり、その後、現地調査が行われ翌年、令和3年2月、同委員会において再度御審議をいただいたところ、譲渡価格を1円としておりました当該財産の不動産鑑定評価により適正価格を把握することや、建物に使用されているアスベストへの適正な対策の検討、またプロポーザルの周知、公募期間の確保や、これは短かったということですね、民間譲渡における後年度の適正な利活用の担保など、これらの課題を整理するよう、さらなる御指摘をいただきました。
このため、令和3年度は不動産鑑定評価やアスベスト調査を行い、その他の指摘事項の改善策もまとめた上で、令和4年5月臨時会閉会後の議員協議会において、今後の進め方も含めて御説明を申し上げたところですが、議員の皆様からは将来的な建物取壊しの担保が不十分であることや、鑑定評価額を上回る費用が既に投入されていることは適正な価格とは言えないといった御意見などをいただくこととなりました。
また、アスベストを含む老朽化が著しい現施設を将来にわたり安全に利用させることが可能なのかといった懸念する御意見や、市費で建物、この施設を取り壊してから更地の状態で利活用を検討すべきではないかなどといった新たな御提案もございましたため、当該財産処分の手法については引き続き検討が必要な状態となっているところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 国民宿舎あきは開業以来28年間という営業をもって閉鎖をしました。20年以上にわたって放置された状況になっておるということでございます。廃業に至ったことは私の記憶では、当時井津市長さんと新人との選挙公約に始まって、そのように思っております。当時の市長は阪神タイガースにキャンプに残ってもらうため、国民宿舎を取り壊し、温泉を掘削してリゾートホテルにしたい。一方は閉館するということでありました。結果は新人が当選し、国民宿舎あきは閉館、廃業し、放置されたままに現在に至っておると私は思っております。
当時、国民宿舎あきは私も監査委員もしておりましたが、お遍路客がたくさん利用しており、黒字経営となっておりましたが、全国的に国民宿舎は老朽化し、建て替えする状態となっており、どこの市町村も課題となっておった状況でございました。国民宿舎あきの玄関前に鹿持雅澄の歌碑があり、皆さん方御承知ではないかと思いますけれども、廃業して以来そのまま放置されているとパソコンで調べてみると、そういったことが出てきました。
この愛妻の歌碑は、天保2年に鹿持が高知市福井に妻菊子を残して、室戸の羽根の村役人として赴任する途中に読んだ歌で、秋風の福井の里に妹をおきて、安芸の大山、超え勝てぬかも、この歌を書家の手島3兄弟の高松慕真先生が書いたものであって、この立派な碑をこの場所に放置しておくのは忍びないと私も思いまして、安芸市役所にも市にも提言をいたしましたけれども、財政的に厳しいということで断られました。
何とかしなくてはと、この愛妻の碑を寄贈してくれた安芸市観光協会に相談したところ、移設してもよろしいとの報告を直接もらいました。そして私も所属する高知安芸ライオンズクラブの事業として、大山岬の浜千鳥公園へ移設をしました。これは鹿持雅澄の愛妻の碑が刻んである歌、この鹿持雅澄は国学者であり歌人であります。高知城の正門から入って天守閣に途中に山内一豊の妻の馬と一緒に碑がありますが、その真ん前にこの鹿持雅澄の愛妻の碑があります。今度行くときがあれば見てください。そうした偉人でございます。しかもこの歌碑は大山が刻んでありますので、ほかへ移設することは私はまかりならんと、それで大山のライオンズクラブが管理をさせていただいておる童謡の里の浜千鳥公園へ移設をしました。
そういったことも事実を今思い出しておりますけれども、安芸市がどうしてもそれをやらなかったいうことで、もう1つまたライオンズクラブが寄贈しておったこいのぼりの碑、弘田龍太郎のあれもようしないいうことで、土居の野良時計にライオンズクラブが移設をしました。いろんなことで私も提言をしてきましたけれども、当時の市では対応をするどころか門前払いでした。やはりこういった先目が見えてない、こういったことが私は事実、皆さんにもお知らせしちょかないかんということで今回一般質問にも取り上げたわけですが、非常に残念な当時思いがしました。
もう1点残念なのは、この国民宿舎が閉館して間もなく私も一般質問で言いました。土佐市の民間の業者が土佐市から払下げを受けて国民宿舎を営業しておる。すぐに私も土佐市へ飛んで経営者と話も聞きまして、一般質問もしましたけれども、何も返事もなかった。非常に残念な思いがした今日に至っておる、そういったことでそのまんま放置をされて20年にもなった。何にもしてないいうことが私は非常に残念で、今日先ほど課長から説明がありましたけれども、1円のいうことなお話もありましたけれども、それ以前に遡ればそういうような背景があって、私がこのどうしようもないということで一般質問を取り上げて今回やらせていただいておる状況ですが、そういった背景があって誰も続けなかった、選挙公約でいうことの背景があってのことだと私は認識しております。
それで今後の取組ですが、先ほど課長の答弁でもありましたけれども、このまま塩漬けにしておいてもいい結果が出ない。私は決算委員会でも随分取り上げて、この問題を改善したらどうですかということも提言を随分してきましたけれども、大幅な改善策は取られなかったということが現状であり、非常に残念であり、このような状況ではやはり議会ももうちょっと我々も改善もせないかんだろうし、安芸市も改善の方向へ向かってもらわないと、このまま国民宿舎を放置しても何にもならない。
そして最近では、どうもお荷物になっているような状況になっております。先ほど一般質問しましたけれども、内容につきまして説明しましたけれども、その当時なら閉館して廃業した当時なら幾らでも手が打てただろうと私はそう認識しておりますし、そんなことを言ってはいけませんけれども、これから安芸市がどうするのかいうことを市民に対しても、やはりはっきりした方向づけを持って発表していただきたいというように思っておりますので、私はこれは答弁に困ると思いますので、答弁は要りませんので、以上をもって一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○徳久研二議長 以上で、13番尾原進一議員の一般質問は終結いたしました。
お諮りいたします。
本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長 御異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこの程度にとどめることとし、明日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって延会いたします。
延会 午後4時24分
応答、答弁者:市長、企画調整課長、農林課長兼農業委員会事務局長、副市長、危機管理課長、建設課長、消防長、商工観光水産課長、生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長
○徳久研二議長 以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 通告に基づきまして、一般質問をいたします。
まず、本年1月1日に発生しました震度7による能登半島巨大地震により亡くなられた方々や被災された皆様にお見舞いを申し上げます。一日も早い復興をお祈りを申し上げます。
要旨といたしまして、市長の政治生命についていうことで、最初の1番の市長の選挙公約についてと、2番目の南海トラフ巨大地震対策について、そして3番目に高知東部自動車道完成に向け、安芸市の観光戦略について伺う。そして4番目に、国民宿舎あきの現在までの経緯について、4点にわたって質問をしたいと思います。よろしくお願いをします。
まず、1番目の市長の選挙公約について伺ってまいります。
(1)の小・中学校給食についてを伺います。
学校給食法が公示されたのは、非常に古い昭和29年のことでございましたが、安芸市が市制発足した年でございました。この法律の第4条に義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならないと明記されております。平成5年第1回定例会におきまして、学校完全給食実施に関する請願を土居小学校PTAの皆さんが議会に提出し、紹介議員として私も名前を連ねておりました。この請願が提出された頃の全国の学校給食実施率は、公立小学校では95%に対し、安芸市では27%で非常に低いパーセントでございました。横山市政になるまで長い間実施されませんでした。市長にお伺いをいたします。
横山さんが教育長のときに、小学校・中学校給食センターでの実施検討会なるものを立ち上げたと私は記憶をしておりますが、その当時の状況をまずお伺いをいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
平成16年度からの施設建設に向け、実施計画まで以前取組を進めておりましたが、国の三位一体改革の影響により、安芸市の財政状況が厳しさを増したことから、事業を凍結した経過がございます。私が教育長時代の平成23年、24年頃だったと思いますが、当時家庭の事情による子供の朝食の欠食率や給食を実施していない市内の小学校において、昼食を食べない子供や時々しか食べない子供がいることも学校から報告があり、また学校給食法が平成21年に改正され、従来の学校給食の実施に加え、学校給食を活用した食に関する指導の実施等が新たに規定され、食育の推進がより重要になりました。
そして、徐々に本市の財政状況の改善についても道筋が見えたことや、完全給食の実施は食育の推進にとどまらず、近い将来必ず発生すると言われている南海トラフ地震の際には、非常炊き出し用施設としての活用も可能となる施設として、凍結していた学校給食の実施について検討するため、平成24年5月に安芸市学校給食検討委員会を立ち上げたところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございました。私は昭和61年にこの市議会議員に当選をさせていただいて、和食市政から横山市政まで5人の市長と一緒に市政に参画してまいりましたが、学校給食に関しては歴代の教育長は誰もがやろうとしませんでした。その理由が、先ほど市長が答弁にありましたけれども、行政の財政難、あるいは三位一体改革、そういったようなことで随分と遅れてまいったわけですが、今答弁にありましたセンター方式なるものの立ち上げと検討会を立ち上げ、すぐに小学校・中学校の給食が実施をされました。
長い間、実施されなかったところは先ほども言いましたけれども、この給食センターが高台の現在の清水寺岡に建設をされました。そして来る南海トラフ巨大地震に対しても、災害に対しても対応できるということもお伺いをいたしております。この関係者ももちろん、市民の方も大変喜んでおると思います。
次に、(2)の新火葬場建設についてお伺いをいたします。
この火葬場建設につきましても、津久茂町の位置が伊尾木の黒瀬谷ということで、簡単に言いますけれども議会で随分時間がかかりました。そして安芸市の一番の重要な課題でもあり悲願でもございましたが、そうした時期に安芸市長選がございました。その後、火葬場建設は津久茂町以外で建設するという市長の公約を掲げた横山氏が市長に当選をされまして、伊尾木黒瀬谷と場所を決定をされました。
私の場合、新火葬場建設につきましては、当初から伊尾木の黒瀬谷ということをこの議会でも発言もしてまいりました。なぜならば、土地については安芸市の市有地であり、そして進入道路につきましてもメルトセンターの完成によってついておる、そういったこともあって、そしてまた、安芸市街地を見下ろす絶景な場所であり、下には伊尾木の墓地公園がございまして、そんなそしてまたもう1点、何よりも好条件であったのは、民家がないいうこともあり、これだけの好条件のそろったところはほかにはない。ただ一つ、伊尾木の地域の住民合意をいただくということであったと思います。
市長は、その当時どのようなことであったのか、まずお伺いをいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど尾原議員のほうからもおっしゃられましたが、新火葬場の設置場所は用地取得の必要性、用地取得が可能か、それから造成費、アクセス度、水道そして民家、人家から200メートル以上離れていることや、景観等を判断基準に市内を調査した結果、黒瀬谷に決定した経緯がございますので、結果として尾原議員の思いと同じであったというふうに思っております。
なお、当然、黒瀬谷への建設に反対の方もいらっしゃいましたので、1人でも多くの方に御理解をいただかなければならないという思いでございました。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございました。地元の合意をいただいたいうことで完成になったわけですが、立派な杜の聖苑が完成に至ったというわけですが、安芸市の場合、単独で火葬建設となったわけですが、この当時には私はこのような施設は広域でやったほうがいいだろうという認識でおりましたけれども、東日本の巨大地震、そしてまた能登半島のああいった大きな地震を見ておりますと、やはり安芸市の火葬場は単独でやったほうが私はよかったかなという思いが今でもしておるわけでございます。大変市長も公約に掲げて完成に至ったということで、大変御苦労もされたと思います。
それから次に、安芸染井保育所と安芸保育所の高台移転につきましては、市長選の公約には私が記憶しておるところではなかったじゃなかろうかと思いますが、その辺は市長にお伺いしたいと思います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私の公約にはございませんでしたが、私が市長以前からもそういう課題がありましたので、それ順次取り組んでいったということでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 次に、(3)の庁舎建設についてをお伺いいたします。
東庁舎は建設から60年以上経過しておりまして、耐震性の不備や設備の老朽化や南海トラフ地震、また東日本大災害等の対策を考えた結果、平成25年新庁舎建設検討委員会が発足して10回の検討委員会の結果、答申が提出されました。私もこの委員会に議長として、7回目から途中からメンバーとして参加した経緯がございます。市役所が移転する場合、事務所移転の条例の非常に難しい条例がありましたけれども、議会の3分の2の議決が必要であり、2度にわたり否決となったことは御承知のとおりですが、このことにより、緊急防災・減災事業債の期限切れやその対応にも時間を要し結果、事業も運用できることとはなりました。
昨年12月2日、庁舎落成式典となったわけですが、東日本大震災での教訓を生かすということから、新庁舎移転は浸水区域以外の市役所が機能することであったと思うが、市長の思いをお伺いします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 旧庁舎は老朽化や耐震性の不備などの課題に踏まえまして、南海トラフ地震による津波で6.5メートル浸水するという予測が示され、災害時にも機能できる市庁舎の整備は喫緊の課題でございました。
また、東日本大震災や平成28年熊本地震で庁舎が被災した自治体では、復旧・復興に大きな遅れが生じておりましたことから、これらを教訓としまして新庁舎の建設に当たりましては、市民の命と財産を守ることを最優先に、災害時における防災拠点機能の維持と被災後の市民生活や復興・復旧に向けた行政機能の維持を確保するため、津波浸水想定区域外での庁舎建設に取り組まなければならないという思いでございました。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 緊急防災・減災事業債の期限切れということが、私どもも市長も議会も大変心配をしておりましたけれども、国会議員の皆様はじめ、多数の方々のおかげで延長ということで、再々延長ということで現在の新庁舎が落成に至ったわけですが、思い出してみますと平成25年にこの検討委員会を立ち上げまして、完成までちょうど10年かかったいうことで大変な執行部の方も議会の人も大変な心配もしておったわけですが、やっと完成をしたことで肩の荷を下ろしたということでございます。庁舎完成までには、ロシアがウクライナに侵略することで、世界の食料や重油、そして物価の高騰やコロナ禍の中で資材高騰で頭を大変痛めたことと思います。
安芸市のここ四、五年を顧みますと、安芸川の氾濫による大変な災害がありましたけれども、県による砂利の撤去や江川川の改修工事や土居・高台寺の市営住宅の建設や新庁舎建設、統合中学校の建設など、東部自動車道の工事、そして安芸道路の高規格自動車道、安芸中央インター線の整備など、そしてまた加えて伊尾木インター線の道路のなどなど建設などの工事でダンプカーや重機、生コン、そして人、今までにない私が経験したことのない安芸市のすばらしい動きがありました。国道55号線も渋滞に至るほどの状況が続いておりまして、安芸市民も大変感動もし喜んでおる状況が今でも続いておると思います。
昨年12月2日、安芸新庁舎落成式典が現地で執り行われましたが、出席者の国会議員の祝辞挨拶の中で、横山市長は非常に運がいいとそのようなユニークなうれしい言葉をいただいたわけですが、私の視点で言わせれば確かに運も政治家にとっては大事ですけれども、やはり横山市長は人柄だと思いますし、それを後押ししてくれる安芸市職員が最も大きな事業をやり遂げてくれたということに私は尽きると思っております。市長の認識をお伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 これまでの取組につきまして、議員から職員共々御評価をいただきましたことに、素直に受け止めたいと思います。御礼を申し上げます。
議員の言われるように公共公用施設、そしてインフラ整備が日々進捗しておりますので、私の周りでもしばらく安芸市から遠ざかり戻ってこられた方は、まちの変化に驚かれている方もたくさんおります。
こうした様々な整備が進む中で、市民や子供たちの命を守ることを最優先に取り組んだ庁舎と中学校建設への道のり、そしてこのたびの完成は万感こもごもいたる思いでございます。先ほど議員から運や人柄といったお話もいただきましたが、私としては安芸市への思い入れや市政への信念、行動を信じていただき、ともに汗をかいてくれた多くの職員やお力添えをいただいた関係の皆様、そしてほかならぬ市民の皆様の御理解と御支援があったからでございます。
新庁舎開庁の3日前、先ほどからお話が出ておりますが、1月1日能登半島地震が発生いたしました。人口減少というかつてない厳しい時代の中、来る南海トラフ地震への備えに公共的施設が市民の命を守り暮らしを支える機能、役割をしっかりと果たせるよう防災・減災に強いまちづくりにも取り組んでいかなければならないと痛感をしております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございます。
次に、(3)の市立安芸中学校、そして市役所跡地についてのお伺いをいたします。
令和5年3月に、市役所庁舎及び市立安芸中学校跡地活用に関する報告書が提出されております。市長のこの内容についての認識をお伺いいたします。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後3時
再開 午後3時6分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど、市立中学校、市役所跡地について伺うを(3)を(4)でございますので訂正をいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 市立安芸中学校、市役所跡地についてということで、今期定例会冒頭の施政方針で御説明いたしましたように、いただいた跡地活用報告書には何度も目を通しまして、市民の願いや思いといった新たなまちづくりを望む声に、私もそれぞれの跡地にはどういったものがふさわしいのか考えを巡らせてまいりました。
この報告書には両施設の周辺や将来の立地特性を見据え、市の未来に思いを寄せる市民の御意見や御提案として活用の可能性がある機能が丁寧に整理されております。また、それぞれの跡地活用の理念として、旧庁舎は多様な世代が交流し、にぎわいやつながりを醸成する空間、中学校についてはスポーツ、学び、ビジネスなど新たなチャレンジを創造する空間と表現されており、これらのフレーズは様々な市民の声をバランスよく的確に捉らまえた活用の基本方針として分かりやすいものであると受け止めております。
今後は、この報告書にある理念を基に基本構想を策定することとし、来年度予定しております基本計画の作成や民間活力導入可能性調査を速やかに実施してまいりたいと考えております。
以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 市長答弁で今議会にも提出をされておると思いますけれども、基本構想を立ち上げるというようなことになっておりますけれども、この内容につきまして市立安芸中学校の跡地の利用活用については、スポーツ、健康づくり、宿泊、観光、教育文化交流、企業誘致、移住、そのほかの報告となっておるわけですが、この中で移住が取り上げておられます。その中で、移住希望者のお試し住宅と移住者支援住宅とありますが、いずれも教室を活用し宿泊施設を整備し、移住者向けの住宅を整備するということであったように思います。
先般聞いた話では、高知県下でも安芸市は移住に関することが2番目であるというような報告も受けておりますが、1次産業が盛んな本市でも人材不足は重要な課題であります。重点施策等の考えがどのような、答弁しにくいと思いますけれども、市長のお考えを、認識を伺いたいと思います。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えをいたします。
令和4年度における市外からの移住実績は過去最高となる211組274人となっております。また、県外からの移住実績はそのうちの87組111人と、高知市に次いで2番目の移住実績となっております。本市に転入された方には市独自のアンケート調査を実施しており、農林業での就業を希望して移住される方も毎年一定数いらっしゃいます。1次産業の担い手確保につながる移住希望者への効果的な情報発信や受皿体制を強化することは、重要な取組であります。
市立安芸中学校跡地活用におきましては、市民の皆様から教室を改修した移住者支援に係る受皿整備など、施設の特性を生かした活用に関する様々な御意見を頂戴しておりまして、どのような活用方法ができるのか、来年度の基本計画や民間活力等導入可能性調査での分析、検証の中で検討してまいりたいと考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) よろしくお願いしたいと思います。
それでは、市役所の跡地についてお伺いをいたしますが、市長は公約でも旧庁舎を取り壊して更地にするというようなことを記憶にありますが、一体いつ頃をめどにそういったことになるのか、市長のお考えを聞きたい。よろしくお願いします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
まず、次年度取り組む基本計画の完成時期につきましては、庁舎と中学校の2施設あることから、通常よりやや時間を要し、令和6年度末を目途に活用策の具体案を議会や市民の皆様にお示ししたいと考えており、令和7年度の前半には両施設の活用策を集約した基本計画の最終版を策定する予定でございます。
この基本計画策定と並行し、民間活力等導入可能性調査を行いますが、具体的にどういった機能や規模の施設にするのか、また民間活力なのか、これまでどおりの手法なのか、調査結果によりこれからのスケジュールは明確になるものでございます。
このため旧庁舎の解体予定につきましては、現時点でいつ頃とお答え、お伝えすることができないものですが、令和7年度から令和8年度には設計を発注し、その後解体工事に取り組みたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁では、中学校跡地、市役所の跡地も基本構想を立ち上げて、その結果7年頃にという答弁であったかのように思っております。
それでは南海トラフ巨大地震対策についてお伺いいたします。
(1)の安芸市施設園芸農家の重油タンクの現状とこれからの課題についてお伺いいたします。
安芸市内で重油タンク2,000リットルですが2キロ、どれだけの数を把握しているのか、まずお伺いいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
本市での施設園芸におけます農業用の燃料タンク、重油タンクにつきましては、市内の重油タンクのほとんどがJA所有のもので、農家に貸し出す形より設置されておるものでございます。JA高知県の調査によりますと、令和5年3月末時点でJA所有の重油タンクが市内には938基が設置されております。JA高知県以外の所有分の正確な基数は把握できておりませんが、恐らく1,000基以上の重油タンクが設置されているものと推察されるものでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 938基ですかの答弁がございましたけれども、その中で南海トラフ巨大地震での浸水区域にある重油タンクはどのくらいあるのか。分かっていればお伺いします。
併せて近年、炭酸ガス発生装置の灯油のタンクが設置もされておりますけれども、お伺いをいたします。この向かって北側のこの道沿いにも白いタンクが四、五基ありますけれども、ここから見てみますと赤のタンクが基準値のそういったことをしてないタンクがほとんどあるような状況でございまして、まず先ほどの浸水区域内のタンクの数はどれくらいあるのか、把握しておればお伺いします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 まず、重油タンクについてでございますけれども、JA高知県所有分のみの御報告になりますが、令和5年3月末時点の重油タンク938基のうちL1想定の津波浸水区域内に90基があるものでございまして、次にL2想定の津波浸水区域内においては346基が設置されており、JA高知県が所有するタンクの約46%にあたる436基が津波浸水区域内に設置されているものとのことでございました。
次に、炭酸ガス発生装置の灯油タンクにつきましては、安芸農業振興センターによる調査では、平成23年度以降の事業導入実績が325基となっていることから、これと同数程度の灯油タンクが設置されているものと推察をされます。このうち津波浸水区域内にある基数につきましては、現時点では把握はできていないところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) なかなか浸水区内にあるタンクが幾らかと言ってもなかなか調べようがないぐらい難しいかなという思いはいたします。
それでは県の次世代園芸、レンタル事業を含めて、整備したタンクの過去3年間の経緯をお伺いします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えします。
県の事業であります園芸用ハウス整備事業、または農業用の燃料タンク対策事業を活用して防災対策が講じられた重油タンクにつきましては、令和5年度に19基、令和4年度に15基、令和3年度に28基で直近3か年の合計で62基の整備が図られているところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 3年間で62基というようなデータが報告がありましたけれども、ロシアによるウクライナの侵攻による資材の高騰で、10アールあたりのハウス建設が従来の倍ほどになってレンタル事業へ手を挙げる方が非常に少なくなっている状況ではないかと思います。このような状況では耐震性のある重油タンク設置は、間もなく来ると言われております南海トラフ巨大地震にはとても間に合わない、そういうふうに私は考えるところですが、これはどのように認識をされるのか、まずお伺いします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
施設園芸農業を取り巻く状況につきましては、農業用資材の価格高騰でハウス建設コストが上昇する中、本市におきましても農業者や新規就農者が新たな設備投資をちゅうちょする傾向が見られるところでございます。
こうした中、重油タンクの防災対策につきましては、さらなる農家負担を要する反面、農業者の収益増加には直接つながるものでなく、場合によってはハウスの減築を強いられるなどの理由から既設タンクの耐震化を図る農業用燃料タンク対策事業におけます近年の事業活用実績が伸び悩んでいるところでございます。
一方、施設園芸が盛んで重油タンクの設置数が多い本市におきましては、地震発生後の津波火災による甚大な被害が想定されており、また能登半島地震での報道による家屋倒壊や火災などの映像を見ますと、議員も御指摘のとおり、重油タンクにおける防災対策は待ったなしの状況であるというふうに認識をしております。
このため、令和6年度からは県の農業振興センターやJA高知県と連携し、農業者を対象とした講演会などの開催を通じて防災意識の醸成を図るとともに、燃料タンク対策事業の活用を促すための推進枠として新たに予算も計上しておるところでございます。引き続き災害に強い園芸産地の維持強化に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 答弁がございましたけれども、私の認識では安芸市は特に施設園芸が盛んでありまして、重油タンクの設置が先ほど説明がございましたけれども、数にしたらなかなかこれはもうよそにないようなタンクを設置しておるというようなことで、ちょうど昭和47年に大きな台風がありまして、この安芸地方にも大変な被害がありました。そのときに重油のタンクが2,000リットルが田んぼでごろごろしておったというような状況でして、今までの重油タンクは4つの足の上にそのままタンクが乗っておるというような状況で、大きな風にも弱いし、地震が来ればとてもではないですけれども倒れると。そして重油が残っておればまけるというようなことで、津波が来て引き潮で持っていかれるのか、来たときに倒れるのか、地震で倒れるのか、いずれにしてもタンクが倒れて重油が流出するということが必ずこれは想定よりももう現実味がある話でして、そのときに必ず火災が発生するわけでして、引き潮でもあるいは反対の潮でも重油がまけて民家に、瓦礫に火がつく、そしたら大火になるということが必ずこういったことが今までの教訓では分かっておりますので、県が2分の1、市が2分の1とかいうことも発表されておりますけれども、これは副市長にお伺いしたいですが、担当課だけではなしに、これ全庁的にはやっぱし防災対策として取り組む必要があるのではないかと思いますので、副市長の答弁を願いたいと思います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
急な質問でちょっとびっくりしておりますけれど、議員の御指摘のとおり、これは安芸市全体での問題であろうかと思います。担当の農林課ということになりますけれど、そういった防災対策も踏まえて総合的に対応していきたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) それでは、2番目の市内のガソリンスタンドについてお伺いします。
安芸市のガソリンスタンドは民間、JAを含めて何か所あるのか、まずお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
現在、安芸市内のガソリンスタンドは、全部で9か所あります。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 9か所のうち、浸水区域外のスタンドは幾つあるのか、答弁お願いします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
発生頻度の高い地震による津波、いわゆるL1津波の浸水想定では7か所のガソリンスタンドが浸水しないものと想定しています。また、最大クラスの地震によるL2津波の浸水想定においては、株式会社JAエナジーこうちの安芸北給油所と東川給油所の2か所が浸水しないものと想定しており、平野部においては株式会社JAエナジーこうち安芸北給油所の1か所となります。
以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど答弁いただきましたが、北支所と東川支所とこの2か所だという報告がありましたけれども、現在統合中学校の開校により今工事をしておりますけれども、恐らく年度が変わっての工事になろうかと思いますけれども、北支所のどういったことになるのかいうことをまずお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
市道中道線の歩道整備に伴いまして、ガソリンスタンド施設への用地影響幅、道路による用地影響幅は約5メートル程度必要となりますことから、既存の給油施設や地下タンクへの影響が生じることとなります。
このため、現位置でのガソリンスタンド経営は物理的に困難であると認識しております。なお、令和6年度当初予算には、これらに係る用地補償費を計上しておりまして、JA高知県との協議が整い次第、用地補償契約を締結することとしております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 答弁ありがとうございました。私の伺っておるのは歩道が3.5メートルということを承知しておりますが、先ほどの答弁では5メートルということを初めて聞きましたけれども、それでは今の北支所のスタンドがなくなると思いますけれども、移転先が分かっておれば。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
ただいまちょっとJAと協議をしておりまして、一応移転先のあてとしましてはJA北支所の北側にあるサポートハウスの土地の一角を今のところ想定してお話させていただいて、協議しております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) まだそしたら想定ということですので、決定ではないがですね、分かりました。
それでは3番目に移りたいと思います。安芸市消防分団員定数減についてお伺いをいたします。
先般、NHKのテレビを見ておりますと、全国放送で消防団員の減の問題については放映されておりましたけれども、安芸市の消防分団員についても定員が282名ということで、昨年の決算委員会で私もお聞きをして驚いたわけですが、そのときの状況が40数名減であるというようなことで、40数名言いましたら1分団が25名から20名いうことで2分団が少なくなるかなというように認識をしておりますが、今年の1月7日に安芸市消防団員の出初め式がありました。
それで今年の各分団に入団された方が団員が9名というような報告を聞いたわけですが、けれども年度が終わってみたらその9名が10名になり、欠員がまた生じるであろうということに予測されますが、非常に心配をしておるところですが、来る南海巨大大地震についても津波につきましても全国的に言いますと12万人定員が減になっておるということも承知をしておりますが、安芸市の早急なこれは対応をしていかなければ間に合わないと。
一時はここ20年までに至らんと思いますけれども、市役所の職員とかJAの職員とかいろんな方を勧誘をして団員になってもらったというような経緯もありましたが、そしてまた加えて消防署の職員が入団をされてないという現状がありますけれども、定年なのか何かの思いが、事情があって入団されてないのか、そこら辺を一つ消防のほうにもちょっと御答弁を願いたいと思います。
○徳久研二議長 消防長。
○久川 陽消防長 本市の消防団は昭和29年8月1日に結成し、団員総数314名、定数は334名、当時の人口は2万9,841名でしたが、人口の減少とともに団員数も減少してきており、令和5年4月1日現在の団員総数は240名、定数は282名、人口は1万6,097名となっております。その理由としまして、退団する人数が増えているものの新たに入団する人が減少傾向にあることが挙げられます。
早急な対応という御質問ですが、消防団員を増やすというよりは現状をいかに維持していくかが喫緊の課題と考えておりますので、職員はもとより消防団員の協力を得ながら取り組んでまいりたいと考えております。具体的にはこれまでと同様、JAなどの事業所の職員や市職員への入団促進、広報等で啓発を引き続き行ってまいります。
それと消防本部を退職された方への入団のことでございますけれども、過去これまでに入団を依頼したことやOBの方から入団したいいう声もありませんので、現状そういった形となっております。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁で意外な答弁を聞きましたけれども、現状維持いうようなことを私はこれはもうちょっと反省せないかん答弁じゃないかなと。なぜなら、やはり東南海が明日来るかもしれないというような状況ですので、やはり前向きに行政としてどう取り組んでいくのかいうことを私は質問をしておりますので、やはり改善すべきは改善する、そして団の定員に人口が減ったじゃなしに、現状はこういうところですということは私が先ほどから住宅の問題につきましても言っておりますので、やはり安芸市は安芸市の市民を守るというようなことでの質問ですので、前向きな答弁をいただきたかったわけですが、よろしくお願いしたいと思います。
次に、安芸市の消防団の各分団は以前、初午という行事がありました。各分団がそれぞれその地域を回って協力金といいますか、いわゆる団の1年の経費を賄うといった意味でここにお金を集めてそれを1年間の運営費用に充てるというようなことが、これはもう慣例として長いこと続いておった状況でしたけれども、それはもういけないというようなことで現在に至っておるところでございますけれども、先般、団員の方にお聞きをしましたら、非常に団の運営上に困っておるというようなことで、前は私も消防団員として16年間土居分団におりましたけれども、やはり初午とか出初めとか、そして夏には夏季鍛錬、今ポンプ操法ということになっておりますけれども缶送りとかソフトボール大会とかいろんな行事があって、非常にそうやって団員の懇話を深める機会もあったわけですが、最近はどうもそういったことかも分かりませんけれども、運営上非常に窮屈になっておるというようなこともお聞きをいたしておりますが、そういった処遇改善をもうちょっと改善をしなければ、そしてまた消防団員の勧誘にもかうといった意味からも、もうちょっとやっぱし努力をするべきではなかろうかと思いますけれども、もう一度御答弁をお願いします。
○徳久研二議長 消防長。
○久川 陽消防長 消防分団の運営に困っているとの御質問ですが、各分団長が集まる幹部会において、運営上必要とするものがあれば消防本部まで提案するよう伝えていますので、提案等があれば検討の上、予算の範囲で対応させていただきたいと思います。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど質問したように全国放映がNHKでありましたけれども、団員が3万6,500円、そして1回の出動で8,000円と値上げはしておると思いますけれども、最近では生活環境の向上や変化などで火災が非常に少なくなっておりまして、出動の回数も少なくなっておるのが現状ではなかろうかと思います。
こういったときのことも踏まえて、全国が一律に決めておるのか、この団員の報酬といいますかそれが一律であるのか、市町村によって違うのかいうことが分かっておればお聞きをしたいと思います。
○徳久研二議長 消防長。
○久川 陽消防長 消防団員の報酬等につきましては、令和3年4月13日付消防庁長官通知の消防団員の報酬等の基準の作成についてにおいて、年額報酬の額は団員の階級のものについては3万6,500円を標準額とする。団員より上位の階級にある者等については、業務の負荷や職責等を勘案して標準額と均衡の取れた額とする。
次に、出動報酬の額は災害に関する出動については、1日あたり8,000円を標準額とすると通知されております。
本市につきましては、現在消防庁の基準額を満たしていることから、今すぐ標準報酬額等を上げることは考えておりませんが、国の動向を注視しながら、県内の他市町村の状況と比較して著しく差がある場合は検討していきたいと考えております。
また、一律かということでございますけれども、高知県内でも基準額より上のところもあれば下のところもございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほど答弁がありましたけれども、やはり待遇の問題だと思う一因があるかなと思いますので、やはり準公務員ですので待遇をよくしないと改善が図れないということは明々白々ですので、そういった努力を消防署だけにとどまらず、団長にとどまらず、やはりこれは全庁的にもこれは取り組んでいただきたいいうことをお願いしたいと思います。
それから次に、(4)の安芸市都市計画審議会計画についてお伺いをいたします。
安芸市の都市計画では、ちょうど高知国体がありまして、その当時安芸高の前までその都市計画で道路が開通したということで、その後、都市審議会では安芸橋までつくというようなことにたしか予定では聞いたことがあるわけですが、それともう一つ、高知安芸商工会議所の北へ、海岸まで都市計画審議会での話で道を抜くというようなことは私も薄々ですが聞いておりました。これは非常にとにかく商工会議所から南へいうことは、この安芸中央インター線とつながってもおりますし、安芸町内の避難道路としても十分すばらしい道ということになりやせんかなということで、分かっておれば審議会のその方針等をお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えをいたします。
御質問の道路、2路線ございますけれども、まず1つが元気館南側から東方面へ海岸堤防沿いを通り、江ノ川河口付近、安芸市浄化センター東側を経由しまして、国道55号の安芸橋西詰につながる都市計画道路海岸線の未整備区間、延長960メートルと、安芸商工会議所東側から海岸までを南北に直線でつなぐ都市計画道路中央線の未整備区間、延長230メートル、この2路線となります。
両路線とも都市計画法に基づき都市計画決定された道路であり、令和2年3月に策定した安芸市都市計画マスタープランにおいて、新規道路の整備として位置づけされております。なお、この安芸市都市計画マスタープランは、令和2年から10年程度の期間の目標を定めたものでありまして、まず海岸線の未整備区間につきましては令和5年度に測量設計に着手したところです。
次に、中央線でございますけれども、この都市計画マスタープランにおきまして産業の活性化や利便性、安全性の向上など、道路ネットワークの形成及び渋滞緩和対策として整備が位置づけされております。議員御指摘のとおり、国道55号から市役所新庁舎へ続く県道安芸中インター線が整備されたことから、防災・減災対策の観点からも海岸線から市街地に至る南北のルート整備については当然必要であるものと認識しております。
また、今後の見通しについてですが、以前にも同様の御質問があり答弁した経緯がございます。現在、主要なもので高規格道路関連の周辺整備事業として、あき病院球場線、ムネカネ線、吉川線、また通学路対策として、中道線、西木戸一の宮線、市庁舎南側から県道黒岩東浜線を結ぶシガヤシキ線、先ほど申しました海岸線など大型路線を中心に数多くの市道整備を実施中でありますことから、これらの進捗も踏まえながら現時点におきましては2020年代の後半、令和7年から11年度の間には着手することを目標としております。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁で着手をしたと、海岸線まで商工会議所からいうことですが、見通しにつきましてもお聞きしましたけれども、私もムネカネ線とかシガヤシキ線とかいうことが中央インターへつなげるといったことも承知をしております。やはりその件とは別に私の伺っておるのは、安芸市の町内もっと人口が多いところの方を救うといった意味からも、これは早く実現していただきたいということがございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、次の質問へ移りたいと思います。
(3)の東部自動車道完成に向け、安芸市の観光戦略についてをお伺いしたいと思います。
市内の観光戦略につきましては、以前から私も言ってきておりますが、議会の研修や他の会議や観光などで全国の観光地を見てきたところですが、駅や道の駅、観光地でよく見るのは大型観光の看板ですが、そこの市内の観光地の紹介をはじめ、宿泊施設やトイレ、公園、そのほか各名所など多くの観光客が熱心に見ている光景を目にしております。
私の言いたいのは、点と点でつながっておりますし非常に分かりやすく、そこに行ってみようという気持ちになり、安芸市に来られた方々を一時でも長く見てもらうような戦略が必要と考えます。市内の観光地に大型看板は幾つあるのか、まずお伺いいたします。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 観光案内板の設置状況についてお答えをいたします。
市作成の観光案内板をカリヨン広場北、安芸ドーム西側、江ノ川上公園、旧市役所庁舎前、安芸駅前、溝ノ辺公園、土居公民館、彌太郎生家駐車場、伊尾木洞観光案内所の9か所に設置をしておりますほか、観光情報センター内にはタッチパネルによる観光案内システムを導入し、市内観光スポットへの周遊誘導を行っております。
ほかに、県設置の広域看板が安芸駅と観光情報センターの2か所にございます。さらに、安芸広域市町村圏事務組合設置の東部広域看板が赤野休憩所北側にございますほか、施設改修に伴い一時退避しておりました道の駅大山の広域看板も年度内に再設置をする予定でございます。
以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 確かにその場所についても説明がありましたけれども、私の言いたい看板は、やはり大きなパネルで大型の看板が私の言いたいところですが、普通の看板ならあまり見ないと思います。大きな看板で安芸市の先ほど言いましたけれども、それぞれの観光地、それぞれの施設、それぞれのトイレいったことが、滞在型につながるような看板が設置をしてほしいとこう思っておるところでございまして、これも戦略的なやっぱりことではないかなと思うところでございます。
それでは続きまして、その看板の設置ですが、西の玄関では赤野に今、岩崎彌太郎氏の大きな看板がありますし、ようこそとこういった歓迎の意味だと思いますけれども、東には下山の伊尾木洞という看板が設置をされておりますが、これは非常に市民に、それから観光を訪れる方にも受けておるというような評判も聞いておりますので、こういった努力を絶えず商工のほうもしていただきたいなという思いがございます。
それでは次に、廓中ふるさと館への大型バスなど進入道路についてお伺いいたします。
廓中ふるさと館建設の経緯につきましては、私も承知をしております。当時、土居公民館で地元の説明会がございまして、現在の場所となりました。そのときにも発言もいたしましたが、西の県道からも非常に入りにくい。そして土居小学校から北への進入道路も非常に入りにくい。そしてもう1点、東の安芸物部線からも分かりやすく入りづらい、また道路が狭隘でありますし、今まで私の一般質問での答弁では野良時計の駐車場へとめて、土居廓中を散策して廓中ふるさと館に行ってもらうということでございました。
私に言わせれば、このような状況では非常にもったいないと私は思っております。南海トラフ巨大地震対策として土居保育所も浸水区域内と考えているが、高台移転も含めて将来的に大型観光バスの乗り入れができるように私は思いますけれども、その考えをお伺いをいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
廓中ふるさと館までの大型バスの乗り入れにつきましては、以前にも議員から何度か同様の御質問がございました。現状の方針について特段変わりはございませんが、道路整備の観点から改めてお答えいたします。
御質問の場所は県道安芸物部線からふるさと館への進入ルートであります。簡易的ではありますが、大型バスが南から北へ進み、西へ左折する際の走行軌跡図というものを描いてみました。現状の道路が非常にクランク形状になっているいうことからですね、現道を拡幅しても大型バスの進入及び通行は不可能でありました。このため、大型バスの通行を確保するためには新たなルートを検討する必要があり、先ほど議員が言われてました保育所の高台移転による保育所跡地の用地が確保できたとしましても、住家等への影響が避けられません。
また、ふるさと館の駐車スペース、西方面へ通り抜けができないことによる回転場の確保、狭いスペースでの一般車両との混雑など、安全面においても十分な対策が必要となることから、現時点におきましては整備する方針に至っていない状況です。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 建設課のほうから先ほど答弁いただきましたけれども、現状用地を買収しても大型のバスが入らないと、こういうことですか。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 先ほど申しました走行軌跡図を入れてみたところですね、保育所の用地、または入り口にちょうどお家が2軒ほどございますけれども、その家もかかってしまうということです。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 分かりました。困難ですと、こういうことですね。
それでは(3)の江ノ川上公園の書碑を書道美術館の前に移設をしてはどうかということをお伺いします。
江ノ川上公園に建立してあった岩崎彌太郎さんの銅像を、ここにあっても整合性がないので生家に移設をしたらどうですかと、私が以前一般質問をしたことがあります。その当時の答弁では、観光協会が寄贈してくれたものだから動かせないと、こういった答弁でございました。このことは後の質問でも申し上げますけれども、その後、高規格道路、安芸道路、安芸中央インター道路により、江ノ川上公園のど真ん中をこの道が走るようになりまして、岩崎彌太郎氏の銅像は生家へ移転しておりました。
私に言わせれば、計画性に妙に欠けるんじゃないかと当時思っておりました。土居ハシオザン永禅寺の境内に南不乗先生の書いた書道名家顕彰碑があるが、知っておれば知っておらないのか、まずお伺いをいたします。
○徳久研二議長 生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長 お答えいたします。
境内に立派な顕彰碑があることは存じております。以上でございます。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) ありがとうございます。この書道名家顕彰碑は、安芸市の生んだ偉大な書家の川谷横雲先生をはじめ、川谷尚亭ほか7名の偉大な先達を長く後世に伝えるという内容でございまして、南先生がこの碑を山まで見に行って、そしてあまりにも立派な碑ですので河原で安芸の業者が掘ったと、南不乗先生の書であります。そういった非常に貴重な碑でございまして、江ノ川上公園も以前とは異なり、インター線により公園そのものが2か所となっており、7つの書碑やトイレなど一体性に欠けるような形となっているように思います。そして訪れる方もほとんど姿を私は見たことがないような状況ではないのかと私は思っております。
現在、書道美術館や歴史民俗資料館など、土地も含めて五藤家から安芸市に寄贈していただいておる状況です。私は書道美術館の前に江ノ川上公園の書碑と永禅寺の境内にある書道名家顕彰碑を寄贈していただいて移設をし、書道美術館を訪れた方々にこの歴史のある碑を見ていただいて、書道美術館、歴史民俗資料館に入館してもらうことを望んでおります。このように将来に展望を持った戦略が必要であると考えるが、担当課の考えをお聞きしたいと思います。
○徳久研二議長 生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○藤田隆史生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長 お答えいたします。
議員がおっしゃるとおり、何事も将来を見据えた戦略を持つことは必要なことだと考えております。書道の振興につきましては、安芸書道振興協議会と連携して取り組んでおります。令和4年度に安芸書道振興協議会が江ノ川上公園の愛称を募集し、100名の方から募集をいただきました。そのうち79名が市内の小学生からの応募でございまして、江ノ川上公園の書碑の認知度が向上したのではないかと考えております。
移設に関しましては、書道美術館の建設に御尽力いただきました南不乗先生をはじめ、偉大な書家の先生方の功績は大きなものであると認識しております。その先生方の功績を広く伝えるためには書碑と書道美術館の連携は欠かすことのできないものであると認識しておりますが、書碑を移設するに当たりましては、所有者や関係者の意向を尊重する必要があり、市の一存で決めることはなかなかできないものと考えております。
また、歴史民俗資料館の南の広場には、五藤家の顕彰碑が建立されており、当広場は憩いの広場でもあり、地域住民の集いの広場ともなっておりますので、広くゆったりとした場所として今後も残していきたいと考えております。
今後も様々な方法で書道と書道美術館、歴史民俗資料館と一体的に取り組んでいかなければならないと認識しておりますので、引き続き安芸市書道振興協議会と連携し、書道文化の振興に取り組んでまいります。以上でございます。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 先ほどの答弁でより分かったような分からんような答弁だと私は思いますけれども、副市長にもう1点お伺いします。
私も書の世界では現日会との長いお付き合いがあります。亡くなられた先生方もおります。安芸市は全国を代表する書家を輩出しており、言わば書の殿堂でもあり、書碑を移設することによって相乗効果や整合性、また費用対効果も出てくるのではないか、そう私は思いますが、副市長の答弁を願います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
書碑の移設につきましては、先ほど生涯学習課長が答弁しましたように、書碑建立のこれまでの経緯や関係者の意向も尊重しなければならないと考えておりまして、市一存では決められないと考えております。今後におきましては、関係者の皆様の御意見も聞きながら対応しなければならないというふうに考えておりますけれど、この書碑と書道美術館、これは書道をはじめとします観光素材をつなげることや、また書を通じての交流を深める取組などによりましても一定の相乗効果も期待できるのではないかというふうに考えております。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) どうもありがとうございます。諸般の事情は私も分かります。けれどもやっぱし、この東部自動車道が開通に当たっての戦略は私は質問をしております。どうやって安芸市が観光で売り出すのか。安芸市は非常にすばらしい財産を持っております。三菱、彌太郎にしかり、弘田龍太郎にしかり、そして書家も全国でも屈指の書家を輩出しておりますし、野良時計もある。伊尾木洞もある。岩崎彌太郎邸もある。タイガータウンの市でもある。切りがないぐらいほかと比べたら大きな財産を持っております。これをどうやって生かすのか。点と点がつながってないのが私に言わせれば現状である。
これは観光ボランティアの方にもお伺いをしなくても大体分かります。非常にもったいない。このこれをどうやって活用して前へ進めて、観光を進めていくのか。滞在型にするのか、そしてそういったコースにするのかいうことの課題がたくさんありますし、やはりそういった戦略が私は必要ではないのか。どこそこがどんな事情で、先ほども岩崎彌太郎に生家の話もしましたけれども、やはり戦略がない。いろんな方に相談してみないかん、これは当然です。ですから私も永禅寺の住職にも了解をもらっております。寄贈してください、了解です。そして一般質問をしております。
やはりそういった努力の上にやっぱり戦略というものは描かなかったら、前にもいろんな答弁を聞いたことがありますけれども、その事情をクリアしないと安芸の市の観光の先が見えないといったことが現実ですので、どうやってクリアするのかいうことがやっぱし担当課の課長会でなしに、全庁的にどうしたらこれ生かせるのかいうことを私は期待しておりますので、ぜひ皆さん方も努力をしていただきたいと思います。
次に、休憩がいいですか。
○徳久研二議長 休憩しましょうか、暫時休憩いたします。
休憩 午後4時6分
再開 午後4時12分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) それでは最後の質問に入りたいと思います。4番目の国民宿舎あきの現在までの経緯についてまず、お伺いいたします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
国民宿舎あきは昭和48年4月に開業し、平成13年3月まで28年間の営業をもって閉館いたしました。その後20年以上にわたる長い期間、利用実績はなく放置した状態となっておりました。
こうした中、平成30年11月、民間事業者の方から市に国民宿舎あきを簡易宿泊施設として利活用したいとの相談及び活用の事業計画が提案されました。これを受け、諸課題を整理いたしまして、令和2年11月、当該施設等を活用した事業提案型プロポーザルにより、優先交渉権者を決定いたしました。このときの財産処分価格は土地と建物の評価額、そして解体する費用を合わせてマイナス評価として1円での譲渡価格を設定いたしまして、同年12月議会に財産処分の議案を提出し、委員会に付託されました。
しかしながら、総務文教委員会により、譲渡後の施設維持や譲渡価格などについて疑義があるため継続審議となり、その後、現地調査が行われ翌年、令和3年2月、同委員会において再度御審議をいただいたところ、譲渡価格を1円としておりました当該財産の不動産鑑定評価により適正価格を把握することや、建物に使用されているアスベストへの適正な対策の検討、またプロポーザルの周知、公募期間の確保や、これは短かったということですね、民間譲渡における後年度の適正な利活用の担保など、これらの課題を整理するよう、さらなる御指摘をいただきました。
このため、令和3年度は不動産鑑定評価やアスベスト調査を行い、その他の指摘事項の改善策もまとめた上で、令和4年5月臨時会閉会後の議員協議会において、今後の進め方も含めて御説明を申し上げたところですが、議員の皆様からは将来的な建物取壊しの担保が不十分であることや、鑑定評価額を上回る費用が既に投入されていることは適正な価格とは言えないといった御意見などをいただくこととなりました。
また、アスベストを含む老朽化が著しい現施設を将来にわたり安全に利用させることが可能なのかといった懸念する御意見や、市費で建物、この施設を取り壊してから更地の状態で利活用を検討すべきではないかなどといった新たな御提案もございましたため、当該財産処分の手法については引き続き検討が必要な状態となっているところでございます。以上です。
○徳久研二議長 13番 尾原進一議員。
○13 番(尾原進一議員) 国民宿舎あきは開業以来28年間という営業をもって閉鎖をしました。20年以上にわたって放置された状況になっておるということでございます。廃業に至ったことは私の記憶では、当時井津市長さんと新人との選挙公約に始まって、そのように思っております。当時の市長は阪神タイガースにキャンプに残ってもらうため、国民宿舎を取り壊し、温泉を掘削してリゾートホテルにしたい。一方は閉館するということでありました。結果は新人が当選し、国民宿舎あきは閉館、廃業し、放置されたままに現在に至っておると私は思っております。
当時、国民宿舎あきは私も監査委員もしておりましたが、お遍路客がたくさん利用しており、黒字経営となっておりましたが、全国的に国民宿舎は老朽化し、建て替えする状態となっており、どこの市町村も課題となっておった状況でございました。国民宿舎あきの玄関前に鹿持雅澄の歌碑があり、皆さん方御承知ではないかと思いますけれども、廃業して以来そのまま放置されているとパソコンで調べてみると、そういったことが出てきました。
この愛妻の歌碑は、天保2年に鹿持が高知市福井に妻菊子を残して、室戸の羽根の村役人として赴任する途中に読んだ歌で、秋風の福井の里に妹をおきて、安芸の大山、超え勝てぬかも、この歌を書家の手島3兄弟の高松慕真先生が書いたものであって、この立派な碑をこの場所に放置しておくのは忍びないと私も思いまして、安芸市役所にも市にも提言をいたしましたけれども、財政的に厳しいということで断られました。
何とかしなくてはと、この愛妻の碑を寄贈してくれた安芸市観光協会に相談したところ、移設してもよろしいとの報告を直接もらいました。そして私も所属する高知安芸ライオンズクラブの事業として、大山岬の浜千鳥公園へ移設をしました。これは鹿持雅澄の愛妻の碑が刻んである歌、この鹿持雅澄は国学者であり歌人であります。高知城の正門から入って天守閣に途中に山内一豊の妻の馬と一緒に碑がありますが、その真ん前にこの鹿持雅澄の愛妻の碑があります。今度行くときがあれば見てください。そうした偉人でございます。しかもこの歌碑は大山が刻んでありますので、ほかへ移設することは私はまかりならんと、それで大山のライオンズクラブが管理をさせていただいておる童謡の里の浜千鳥公園へ移設をしました。
そういったことも事実を今思い出しておりますけれども、安芸市がどうしてもそれをやらなかったいうことで、もう1つまたライオンズクラブが寄贈しておったこいのぼりの碑、弘田龍太郎のあれもようしないいうことで、土居の野良時計にライオンズクラブが移設をしました。いろんなことで私も提言をしてきましたけれども、当時の市では対応をするどころか門前払いでした。やはりこういった先目が見えてない、こういったことが私は事実、皆さんにもお知らせしちょかないかんということで今回一般質問にも取り上げたわけですが、非常に残念な当時思いがしました。
もう1点残念なのは、この国民宿舎が閉館して間もなく私も一般質問で言いました。土佐市の民間の業者が土佐市から払下げを受けて国民宿舎を営業しておる。すぐに私も土佐市へ飛んで経営者と話も聞きまして、一般質問もしましたけれども、何も返事もなかった。非常に残念な思いがした今日に至っておる、そういったことでそのまんま放置をされて20年にもなった。何にもしてないいうことが私は非常に残念で、今日先ほど課長から説明がありましたけれども、1円のいうことなお話もありましたけれども、それ以前に遡ればそういうような背景があって、私がこのどうしようもないということで一般質問を取り上げて今回やらせていただいておる状況ですが、そういった背景があって誰も続けなかった、選挙公約でいうことの背景があってのことだと私は認識しております。
それで今後の取組ですが、先ほど課長の答弁でもありましたけれども、このまま塩漬けにしておいてもいい結果が出ない。私は決算委員会でも随分取り上げて、この問題を改善したらどうですかということも提言を随分してきましたけれども、大幅な改善策は取られなかったということが現状であり、非常に残念であり、このような状況ではやはり議会ももうちょっと我々も改善もせないかんだろうし、安芸市も改善の方向へ向かってもらわないと、このまま国民宿舎を放置しても何にもならない。
そして最近では、どうもお荷物になっているような状況になっております。先ほど一般質問しましたけれども、内容につきまして説明しましたけれども、その当時なら閉館して廃業した当時なら幾らでも手が打てただろうと私はそう認識しておりますし、そんなことを言ってはいけませんけれども、これから安芸市がどうするのかいうことを市民に対しても、やはりはっきりした方向づけを持って発表していただきたいというように思っておりますので、私はこれは答弁に困ると思いますので、答弁は要りませんので、以上をもって一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○徳久研二議長 以上で、13番尾原進一議員の一般質問は終結いたしました。
お諮りいたします。
本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長 御異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこの程度にとどめることとし、明日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって延会いたします。
延会 午後4時24分
添付ファイル1 一般質問 尾原進一 (PDFファイル 487KB)