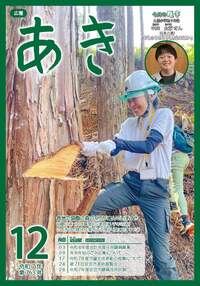議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 川島憲彦
質疑、質問者:川島憲彦議員
応答、答弁者:教育次長兼学校教育課長、市長、企画調整課長、農林課長兼農業委員会事務局長、市民保険課長、選挙管理委員会事務局長
再開 午後0時59分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
10番 川島憲彦議員。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 一般質問を行います。まず初めにお断りをしておきます。通告書には、質問2点目、消滅自治体問題についてで3点質問点を上げておりますが、この議会の開会挨拶の中に消滅自治体への市長のコメントも一部ありましたので、それだけを聞くのはやめてですね、1番、2番をひっつけて質問をいたしたいと思います。まず、一極集中の問題だけに質問を絞らないということで、第1、第2を含めて一つにまとめて質問を行います。
また、質問の中でいろんな状況等で、私の思いとか含めて、少し長くなる面がありますが御了承いただきたいと思います。
まず、教育問題について伺います。
教育問題で、まず初めに、残業と教員の確保について。この点について伺いますが、全国で教員の残業が多く、また、家庭に持ち込んで仕事をしなければならないなど数年来の大きな問題となっております。これは、国はこれまで教員の残業の上限を月45時間と定めておりましたが、文科省の22年度調査では、月45時間を超えて残業している教員が小学校で64.5%、中学校で77.1%もおります。教員は残業代が支給されず、給特法におきまして、基本給にこれまで4%を乗じるだけの金額が給与として含まれておりまして、これは平均1万5,000円。今回これらを10%に引き上げた模様ですが、これでも平均3万8,000円の上乗せとなります。労働基準法では残業代の割増は1.25倍と定めておりまして、10%を上乗せしても全くこの額には届きません。これにより本当に働かせ放題、こういう言葉が出ております。まさにこのことではないでしょうか。
学校現場は大変な事態になっているのではないかと想定します。先ほどの文科省の調査による小学校教員は、1時間授業を1こまとして平均で1週間に24こまの授業で、ほとんどが空き時間がなく、授業の準備や子供への対応がほとんどできない状況とのことであります。これにより、教員の多忙化が子供たちにどのように跳ね返っているのかを考えれば、まさに子供が犠牲になっているのではないかと考えざるを得ません。先生と子供の声にしっかり寄り添う対応で現状をどう打開していくのか。このことを望む声が多くあります。
安芸市の学校現場が現在どのような状況であるか、どのように把握されているのかをまずお伺いいたします。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 はい、お答えいたします。
子供の教育に影響が及びますため、教員の働き方改革が喫緊の課題として進められている状況にあります。全国の状況はおっしゃられたとおりだと思います。
本市でもですね、近年精神疾患を引き起こす教員も目立つようになってきておりまして、ちょっと対応と一緒になってしまいますが、令和2年に示されました文部科学省の指針というものがございまして、そちらに基づいて教育職員の在校等時間の適切な管理としまして、定時に退校する日の設定をするとか事務事業の見直しのほか休暇の確保、それから業務の持ち帰りの軽減、働き方改革に関するアンケートの実施など、教員の健康と福祉の確保を図るように対策を講じております。
そして、令和4年度から教員の業務を負担するという観点で、負担軽減として市の会計年度任用職員としまして教員業務支援員を積極的に配置をしております。先生方からは特別支援教育支援員の配置も含めて安芸市は非常に手厚いという評価もいただいております。それでも時期によりますけれども、月45時間を超える時間外勤務といいますか、在校等時間になりますけども、そういった時間が発生している教員というのは少なくはなく、さらに対策を講じていかなくてはというふうに考えているところです。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私の指摘した状況が安芸市にもあって支援員を配置したというところで、教員の過重負担の軽減をするということも行っておる。しかしその中で、なかなか解決できない問題があるという答弁でありました。
次の質問に移りますが、少子化に合わせ教員の数を減らしたことで、産休や育休で休む教員の補充もできないなどを含め、教員不足が教員の長時間労働に拍車をかけるなど、残業問題と教員の不足は切り離せない問題だと思います。自宅への持ち帰り残業を含め1日11時間半に上り、これらによる長時間労働で精神疾患を引き起こしたり、長時間労働で教員への夢と生きがいを失い、希望が持てず、教員になったばかりの若い教員が早期退職をしたり、教員になることを夢に見てきた学生が教員になることを諦める、こういう学生がいるなど、まさに成り手不足に拍車をかけることなどの影響からこうした教員不足が続いているものと思います。
必要な教員の確保ができているのか。また、非正規職員を補充するのではなく正規職員の確保も重要かと私は思います。
安芸市の学校において必要な教員の確保ができているのかを伺っておきます。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
市の教員確保の件でございます。必要な教員の確保ということでございますが、県費負担教職員制度ということでやっておりまして、任命権や人事権につきましては高知県にあります。現在お尋ねの安芸市に教員が不足しておるという実態につきましては、そういった実態はありませんが、正規の教諭が配置されておらず講師の配置校が多々見受けられるような状況にあります。
以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 教員は不足はしていないが、いわゆる臨時教員がおる実態だという答弁でありました。
私がこの質問の中に申しましたように、やはり臨時教員を雇用するということは、やむを得ず急にできたから、取りあえずは補充をするということで行うべきものじゃないかと思います。常時、残業がどんどん増えて、精神疾患までなるような今の残業の問題、これは人手不足そのものであると私は思います。だから今の先生方の中にも、きちんと必要な教職を整えて、そして、このような残業をするような学校ではなくて、子供に寄り添いながら、余裕を持って子供の分かる授業のために時間を割いていく。こういうことが一番教育の中で大事な問題であると私は思います。そのことがイコール必要な教員の確保ではないかと思います。
もちろん、私は市町村に教員を雇用する。そういう役割が果たせれないということは百も承知です。しかし、県の教育委員会と安芸市の教育委員会との話は、子供の教育を支えるためにこのようなことはぜひやってくれ、こういう要望をいかにこれまで県教育委員会に届けてきたのかを含め、現場の先生方の苦しみ、努力はしておるけど、努力をすればするほど自宅に持ち帰ってせざるを得ない。このことで11時間も過重労働を迫られる。こういう状況をなくさない限り、私はこの問題は解決しない問題であると私は断言できると思います。
また、現場の先生方の思いも同じことではないでしょうか。これしっかりつかんで対応していくことが地域の自治体の教育委員会の大きな仕事ではないかと。このことを痛切に思うものでありますので、ぜひともこのために力を注いでいただきたい。
次に、不登校と児童虐待、いじめ防止対策について伺います。
22年度の児童生徒の不登校は、前年度比で5万4,108名、22.1%の増で29万9,048名だったという報告が文科省から出ております。また、児童生徒の自殺は513名と、高止まりであることが厚労省の発表があります。
そして、23年度において、18歳未満の虐待通告児童数は、前年度比6.1%増の12万2,806人と、これまた過去最多を記録していることが警察庁の発表が出ております。
全国の児童相談所が対応した虐待に関する相談におきましては21万9,170件で、これも過去最多の模様であります。
このように、少子化が進む中において、子供を取り巻く状況は誠に深刻な状況ではないかと思います。
不登校問題については、ある大学教授は、心の傷は幼児期からの受験競争の激化などで生じている。不登校を生まない教育を模索することが最も重要である。子供の意見表明権を尊重する学校づくりとして、テスト中心を改め個人尊重のクラスづくりが必要として、そのために、少人数学級の編成と教員の増員が不可欠であると大学教授は申しております。
また、子供を評価する前に心の理解が大切で、様々な場面で出てくる子供の言葉を宝のように大切にする教育、これが最も大事であると述べております。
そして、現在は学力テストが行われ、県別、市町村別にその結果が公表されております。学力テストへの賛否は多々あると思いますが、はるか過去の話でありますが私の体験を言わせていただきます。
私が中学校のとき、担任の主任が私のクラスのみ学力テストを行いました。私はそのときに、覚えておるのは、たった1枚のテストで人間の能力が分かるわけがない。こういう思いで、私は学力テストへの反対を担任に述べ、自分の意思で白紙提出を行いました。当時の全国学力テストはいろいろ問題が起きて、その後も中止となりましたが、現在は復活しておりますが、今も賛否の意見が分かれているところです。
しかし、学校教育の原点は、成長の過程で助け合って必要な授業内容を理解し、成長させていくことだと私は考えます。
そして、学力競争の中に置かれた子供で、子供の心の傷が発生し、不登校の原因になったときには、専門家の意見にあるように、子供を尊重する教育を徹底することではないかと考えます。学校へ行きたくないという声を真摯に受け止め、心の傷をケアし、十分な休養を子供に保障し、最初に相談する教員やスクールカウンセラーが特別に重要だということや、親が子供に大丈夫だよというサインを出せることが大切であるという専門家の意見も参考にして、子供への心ある対応が重要だと思います。
大変指摘が長くなりましたが、これらについて安芸市の教育、どのような認識でしょうか。また、不登校などの安芸市の現状と対策について伺っておきます。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 はい、お答えいたします。
不登校の状況は、先ほどもおっしゃられたように昨年の10月、文科省から令和4年度の不登校児童の生徒数が過去最多になったというニュースが報じられました。本市の児童虐待、いじめについての深刻度につきましては全国に比べると高くはないと、これは言い方が問題になるかもしれませんが、という認識をしておりますけれども、不登校児童生徒数につきましては、昨年小学校は減少に転じたものの中学校は増加傾向にあります。
本市の不登校の要因としましては、小学校での不登校児童が継続して中学校でも不登校となっていること、学習のつまずき、それから対人関係、家庭環境などが複雑に絡み合っていると分析をされています。
その不登校対策として、川北小学校奈比賀分校に教育支援センターを設置して、指導員と支援員4名が地域と連携しまして、精力的に不登校児童生徒の予防やその居場所づくりを行って、学校復帰に努めております。
また、保護者からのニーズも増えておりまして、市外のフリースクールへの通学でありますとかオンラインの学習システムなど、教育手段の問合せも増えておるような状況にございます。
今後ですね、人員も含めて、いま一歩踏み込んだ対応を検討していく必要があるのではないかと考えるところであります。
いずれにしましても、議員のおっしゃるように学力テストなどが、競争社会っていうものが不登校の因果関係という部分で関与しているかどうか、しっかりとはようお答えしませんが、教員が子供と関わる時間が確保されることによりまして、この不登校要因の解消につながり、または緩和されるなど、その効果があるものと考えております。
したがいまして、市としまして引き続き教職員の健康と福祉の確保を図るための努力をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 不登校は中学校のほうに若干増加しておるということです。
いじめについて報告がなかったように思いますが、いじめは現在どんなような状況ですか。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 いじめの認知件数になりますけれども、令和元年に小学校・中学校合わせまして282件という大きな件数を出しました。その後、これ認知件数ですので徐々に下がってきておりまして、先ほど文科省の調査で出てきた令和4年度の時点では90件ということでございまして、決して低い数字ではありませんが、大ごとになる前に初期対応をしたり、家児相なんかが入ったり、スクールソーシャルワーカーとか、そういった関係機関が入って初期対応に応じており、大きな問題にはつながっていないという意味で、大きなことにはなっていないというふうに申し上げました。件数はあります。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 令和4年度で90件とか把握をされておるということがありましたが、やはりいじめ問題、不登校問題ということの中から子供の自殺も発生しておる。これが考えられますので、やっぱり1人の子供を育てる。これは家族にとっても大変なことでありますが、やっぱり学校へ通う中でこのようなことが生じない教育がいかに大事かということを考えざるを得ません。やはり学校現場の状況を先生方に絶えず聞く。また、子供へのアンケートなんかも含めてですね、なかなか子供もいじめがあってもそれが言えない。言ったらまたいじめが大きくなる。そういうふうな事態を、いじめを受ける子供はそれを真っ先に心配することではないでしょうか。やはりそのようなためらいが起きないように、日常的な学校教育の現場でしっかりと子供と寄り添い、子供の精神状況、また、友達との関係をしっかりとつかんでいくということが必要かと思います。ぜひとも教育委員会挙げてですね、このことにぜひとも強く思いを持っていただきたい。そして先生とも協議を続けていくということも含めて申し添えておきたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
次に、消滅自治体問題について伺います。
まず初めに、さきのように申し上げましたので、次の1、2を含めてまとめて質問もさせていただきたいと思います。
消滅自治体問題について伺いますが、民間の有識者グループの人口戦略会議は、若い女性が半減して消滅する可能性があると分析した自治体のリストを公開し、高知県内においては安芸市を含む25自治体が上げられました。しかし、私はこの60年来、地域の人口減少はずっと減り、減少し続けてきました。
その原因は、若者が仕事を求め、都市部に居住地で生活することを選ばざるを得ない状況が最大のものであり、いわゆる東京への一極集中そのものであると私は考えます。この点につきましては、今議会の、先ほど言いましたように、開会挨拶でも市長も東京への一極集中による社会構造の是正が必要と述べているように、この点につきましては、私も同様の認識であると思います。
私は、青年期においては、生まれたこの地で生活をすることを私は決めてまいりました。しかし多くの同級生や知人は、様々な理由におきましてふるさとから遠く離れ生活をしております。
安芸市の人口減少に関わることを考えれば、農家の減少や個人商店の衰退と閉店、これらが真っ先に上げられると考えられます。私たちの周りでは、たばこや米や酒屋の商店はほとんど姿を消しました。この最大の理由は、大型量販店の進出の増加と、これらの大型量販店へ販売許可を下ろした。そして、これらによりほとんどの個人商店が姿を消しました。農林漁業も外国からの輸入拡大で、全国においても厳しい経営状況の中で個人事業の後継者の減少が続いています。これら全てが、国の政策で行われたと言っても過言ではないと私は思います。
これを解決するのは、国のこれまでの東京一極集中イコール都市部への集中といえますが、これらの見直しを行い、地域の人口拡大に向けた支援を行うことだと私は考えます。
市長に改めて伺いますが、消滅自治体問題の可能性があるとされたことをどのように受け止めたのか、お聞きしたいと思います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 安芸市が消滅自治体の可能性があるとされたがどのように受け止めているのかということでございますが、今回安芸市が消滅可能性都市に該当したことは、客観的なデータに基づき算定された将来推計の結果と受け止めており、人口減少に歯止めがかかっていないことに一層危機感を抱いているところでございます。
ただし、今後30年以内に自治体が消滅する可能性があるという、このインパクトの強い言葉をあまり重く受け止め過ぎると市民の皆様を過度な不安やまち自体にもはや魅力がないといったミスリードを引き起こす懸念もあると思います。
また、この言葉は、以前も報道でもございましたが、島根県とか高知の濵田知事とか、それから町村会とかでもそういう反論といいますか、コメントが載っておりましたが、自治体の人口減少対策への努力が足りていない結果のように、これまでの取組が否定され、レッテルを貼られたかのようにも感じ取っております。この言葉だけを捉まえますと消滅という言葉だけが踊ることのないよう、国民の行動変容が前向きになるような文言を慎重に選定されるべきであったのではないかというふうに思っております。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) また後からも述べますが、やはり今回の有識者会議が発表したということでありますが、これはまさにね、私は国が発表したと同じだと私は受け止めてます。そして、国の責任をよそにおいて自治体の責任かのようにいっておる。そして、しかも、その原因、最大の理由が、若い女性が減少して子供を産まなくなったと、女性問題にもすり替えております。これにとっては非常にいかがなものかと私は思いますし、次の質問に移りますが、消滅自治体問題につきましては、人口減少の原因に、先ほど申し上げましたように、若年女性の人口減少を問題にし、日本全体の問題を自治体の問題にして取上げ市町村の責任にしていますが、先に上げましたように、これは国の責任であると私は思います。
また、若年女性の人口減少問題にしておりますが、これは女性の責任を押しつける一つの圧力と取れるのではないかとも思います。
国がこの30年、経済界の求めに応じ、あらゆる職種の働き方を本来の正規雇用から非正規雇用に切り替え、そのことによって若い世代の給料が上がらない状況をつくり上げ、若い世代を中心に暮らしが大変な時代となりました。
また、社会保障切捨てと社会保険料の負担の引上げにてさらに暮らしが厳しくなり、コロナ禍で結婚もできない。子供を育てる生活費が工面できないなどの理由で、少子化という人口減の状況が全国で起こったのではないでしょうか。また、結婚や出産はその人々の選択の自由であり、個人の尊厳に関わる問題でもあります。一人一人が幸せに暮らせる環境をつくることが国と自治体の役割であり、中でもその責任は国にあると思います。東京一極集中の是正は待ったなしで、様々な人が対等に、希望に応じて働き、安心して暮らせる地域をつくることが大切であると私は考えます。
消滅可能自治体と言われる自治体には、どこにも人間が生きていく上で欠かせない豊かな自然と文化に恵まれておりまして、人口戦略会議が最後のチャンスというような浮き足立つ必要は私はないと思います。
先ほども指摘したように、一人一人が幸せに暮らせる環境をどのようにつくることが国と自治体の大きな役割であると思います。その一方の自治体の今後の対策をどのように考えているのか伺っておきたいと思います。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 はい、お答えをいたします。
人口減少対策に特効薬のようなものはなく、地道にいろんなことに取り組んでいかなければならないと考えております。
市の取組として、先に少し成果のほうをお話ししたいと思いますけれども、令和5年度の県外からの移住実績が75組93人と、県内では高知市、四万十町に次いで3番目の上位の実績となっておりまして、移住施策に取り組み始めて以降毎年上位の結果を維持してきております。この移住施策は本市の強みでございまして、この特徴をずっと伸ばしていきたいなというふうな思いはございます。近年は起業を志す移住者の方、起業したいというふうに言われる方が増えてきておりますことから、起業者の受皿となる店舗等を調査し、空き店舗バンクを開設できるよう本年取り組んでおります。
また、本市へ企業進出したいというふうに検討している事業者からの問合せも今や数件ございまして、雇用の確保と経済浮揚につながる取組を目下全力で進めているところでございます。
こうした移住や企業誘致のほか、出会いの機会創出や結婚支援、子育て及び教育支援の充実について現状とニーズのギャップ、問題課題の解消につながる施策を精力的に展開し、成果を上げてまいりたいと考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) はい、ありがとうございます。特にこの5年間、令和5年度の移住の結果とか県下で3位、また起業を希望する移住者に支援をしていくと。また会社を安芸市で興したいというようなことについては現実にあり、実現していきたいということでございます。
私は、県外からの移住はもちろんですが、安芸市で生まれた人々が安芸市で暮らすようにいかにしていくか。これが最も私は大事ではないかと思います。後継者をつくっていく。また、農家においても、もちろんのこと、後継者をつくる。そして、安芸市で生きていく。そういうような人口を確保していく。このことが何よりも私は大事でないかと思いますので、やっぱり市民の努力等をいかに支援をしていくか。若い世代のそういう支援をいかにしていくか。これらに尽きるのではないかなと思います。そういう面にもぜひとも市民の意見を聞いて、そして安芸市で生きていく。そういう気持ちを育てていく安芸市であってほしいと、このように願っておるものでございますので、やっぱり全庁を挙げて頑張っていただきたい、このように思うものでありますので、これらを付け加えて次の質問に移ります。
次に、農業問題についてであります。
これも大変厳しい状況でありますが、まず、我が国の食料自給率の件について伺いますが、日本の食料自給率は現在38%であります。食料の大半を輸入に頼っている状況であります。
この原因は、農業での生活が厳しく、他の職業に切り替えて生活を支えざるを得ない状況が全国で起き、後継者が育たず、高齢化で農家の減少に至ってきた。このこと。
また、主食の米の生産を減らす国の方針も大きな要因であったと私は認識しています。以前は、米の生産を支えるために国は農家から高く米を買取り、消費者には安く販売するという二重価格補償制度において食料を確保してまいりました。若い方はこれらのことは知らない方も多くありますが、私らが青年期のときは、米については、農家から高く買い消費者には安く売る。これを国の責任として行ってきた。こういうことでありました。しかし、今ではその面影もないという時代です。
食料自給率を向上させることは、食料確保政策において第一の課題でなければならないと思います。そのためには、農業後継者の確保と拡大であり、農地を余すことなく活用し、同時に水の確保など豊かな自然を守り、安心・安全な食料の確保のために農家を支える対策が何よりも重要であると思います。米の生産だけでなく野菜や果樹生産農家や酪農や漁業の皆さんへの支援も同様であります。こうした国民の食料確保に直結する人々を支えることが国と自治体の役割と言っても過言ではありません。これらのことをしっかり国が行うことを求めると同時に、自治体も農家とともに頑張り、必要な対策をすべきと考えますが、どのように対応するのか伺います。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
御質問のとおり、日本のカロリーベースの食料自給率は令和4年度で38%と、ここ数年は37から38%での推移となっており、令和2年度に策定されております現行の基本計画での自給率目標である令和12年度の45%には届いていない状況でございます。この食料自給率の向上につきましては、生活に不可欠な食料を将来にわたって安定的に供給し続けるためにも重要な取組であると認識をしております。
本市におきましては、議員も御承知のとおり、ナスやピーマンなどの施設園芸、そしてユズの産地でございます。ハウス以外では水田において稲作が行われており、これらの農地を維持していくためには水田での稲作が必要不可欠なものとなります。
米の販売単価につきましては、直近では回復基調にありますが、以前よりの販売単価の低下傾向に加え、昨今の肥料価格等の高騰などもありまして、稲作での農業経営は非常に厳しい状況と思われますので、今後におきましては耕作できない農地所有者の増加などが懸念されるところでございます。
こうした状況の中、本市での対応ということでございますが、本市では担い手の確保・育成、農業経営の安定・向上、生産基盤の充実などを柱に農業振興に取り組んでおります。農業後継者を含めました研修段階から就農までをトータル的にサポートする新規就農者の確保・育成対策に引き続き取り組むほか、農業生産の面におきましては、本年度末までに策定すべく現在取り組んでおります地域計画の策定に向けた集落ごとの座談会を通じて、まずは現状の把握に努めたいと考えております。この地域計画では、10年後の地域営農の姿を一筆ごとに定めた目標地図を作成する必要がございますので、農業生産の基盤となる農地の圃場整備ですとか用排水路等の整備改修など、それぞれの地域の実情に応じた生産基盤の整備等の支援策の検討・実施につなげてまいります。
また、持続可能な農業の実現に向け、重要な点としましては、国で仕組みづくりに向け検討が進められております農産物の適正価格、生産コストの価格転嫁の問題の解決が重要であるというふうに認識をしております。このため品目ごとに検討されているこの仕組みが本市の実情に沿ったものとなるよう、必要に応じて国や県への要望など、現場の声をつなげてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁では、様々なことについて必要に応じて取り組んでいきたいということが述べられました。
私は、国の食料自給率の確保は最も大事であると思います。今、政府は戦争の準備、実はしてますよね。敵基地攻撃能力の保持というて43兆円の軍事費用を当てると。しかしですね、日本を外国が仮に攻めるとしたら武器は要りませんよ。食料ストップさえすれば3か月で日本は駄目になりますよ。食料がないんですから、日本は。38%、国の人口の僅か38%分しかないですよ。あとの62%分の国民はどうなりますか。死ねというのも一緒ですよ。国と国とのいさかい、争いが起きた場合。戦争はしない、平和な世界をつくる、その根本には食料自給率を高める。このこと以外にないじゃないですか。日本を攻め落とすことは簡単ですよ。輸入さえ止めればいいですから。そのような国民の命と暮らしを支えるための政治が一番先に考えたら、自給率を高めることじゃないでしょうか。このことを申し添え、次の2点目の質問に移ります。
農業基本法について伺います。
国会において、食料・農業・農村基本法改定案が賛成多数にて可決をされました。この法改定では、自給率の向上は投げ捨てました。さらなる食料輸入に依存するというものであり、輸入を続ける、これをさらに拡大するという、ここに依存するというものであって、参議院農水委員会において参考人として招かれた農民運動全国連合会会長が、この改定案に対し反対の意見陳述をいたしております。その内容は、今、食と農の危機はかつてなく深刻。国民の関心、不安がかつてないものがある。今こそ政治が本気で食料増産を掲げ、日本農業の再生を目指す農業基本法をつくり上げてほしいと述べました。また、基幹的農業従事者が120万人減った中で、改定案には新規就農対策がない。大事なことは、規模の大小問わず全ての家族農業を政策対象にし、家族経営の果たす役割を再評価し、農業再生の主人公とすることですと述べ、世界の食料生産が不安定な中、改定案がさらなる輸入依存を掲げているのは大きな間違いで、日本で作れるものは精一杯作り、どうしても足りない分を輸入する政策に転換すべきとして、農村政策の基本は地域農業を再生することですと。日本には農業と農村が必要とする国民合意をつくり上げるような基本法改定のこの議論を強く要望しますと締めくくっております。まさにこのとおりではないかと私は思います。
これからの日本農業再生と国民の命を守る食料自給率を上げることは最重要課題であると考えます。農村政策の基本は地域農業を再生することと思いますが、行政の考えを伺っておきます。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 国の食料・農業・農村基本法についての御質問でございますが、この改正案につきましては、本年5月29日に成立されたものでございます。この改正に向けた審議等におきましては、日本の先ほどの食料自給率をはじめとした農業におけます課題などについて議論されたところでございます。その中で、行政の考えとの御質問でございますけれども、御質問のとおり、農業を支える全国の産地、いわゆる地域農業の維持発展は必要不可欠であるという認識を持っております。
現在、本市におきましては、施設園芸との複合経営をはじめ、米の作業受委託や農地の貸し借りによって比較的大規模に稲作をやられている農家の方々により地域の水田が守られており、その経営規模といたしましては、大部分が家族単位による中小規模の経営体であり、法人化等の経営体を含め、多様な経営体によって地域農業が支えられている状況でございます。
持続可能な農業、農村の実現、持続的な営農の実現に向けましては、農業基本法の改正に当たっての国会等での議論の内容を確認しますと、農産物における販売価格への価格転嫁という点が非常に重要であると考えておりますし、農家の方々も強く望まれている点だというふうに認識をしております。
このため、先ほどの答弁と重複いたしますけれども、国のほうで農産物の適正価格に向けた仕組みづくりにしっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、本市の実情に沿ったものとなるよう必要に応じて国や県に対して要望してまいりたいというふうに考えております。
また、地域計画策定のための地域ごとの話合いの場におきまして、家族経営体への支援を含め、本市での地域の実情を踏まえた地域農業の将来の在り方を検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後2時
再開 午後2時8分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほど農林課長から答弁をいただきました。ぜひ様々なことについて安芸市で農業従事者を増やす、そういう対策、人口増につながるような対策をぜひ取っていただきたいと思いますが、まず、農業問題については、一般的に米は作れば作るほど赤字だという状況であります。一つの資料によりますと、農家の米作りの時給が10円だそうです。時給が10円、10時間働いて100円、30日働いて3,000円、1年間で3万6,000円。これが米作りの時給だそうです。やればやるほど赤字。必要なことは、そういう米を作る、農産物を作るために頑張る人々の暮らしをいかに支えていくか。これが自給率を高める第一のことではないでしょうか。県に対しても国に対してもこの点をきちんとやっぱり求めていく。安芸市の農業を支える政策の要にもしていく必要があるかと思いますので、それらを特に求めて、次の質問に入ります。
次に、マイナンバーカードについて質問をいたします。
私は、この質問に入る前に申しておきますが、紙の保険証、何ら今まで問題がないのに、なぜ12月2日からこれをやめるのか納得がいきません。紙の保険証を残す。この願いを、思いを私は持っておりますので、それらを質問点の中心に据えて質問をしていきます。
もちろん、マイナンバー保険証、マイナンバーカードは安芸市の責任ではありませんが、これは最大は国の政策におけることであると思います。
政府は多くの国民が反対するマイナンバーをひもづけにして、国民の個人情報を結びつける制度をつくり、まず手始めに保険証をマイナンバーカードと一体にするとして、この12月から紙の保険証を廃止するとしています。
私は、マイナンバー制度において、医療や収入や税金などの個人情報をひもづけにすることは、個人情報の漏えいなどによる詐欺被害を助長するとして反対の考えからマイナンバーカードはつくっておりません。そして、議会からも給与等でマイナンバーカードを求められますが、一切銀行にもこれらは記入しておりません。
また、これまでマイナンバーカードにおいて、医療窓口などにおいての多くの不具合も生じ、窓口対応に大きなしわ寄せや、行政の窓口対応においても、これまでの紙の保険証で何も問題は起こらなかったのに、マイナンバーカードの対応に多くの職員が新たに対応に追われるという事態になったことと思います。
そして、今のマイナ保険証利用率は僅か6%であるという状況です。マイナンバーカードをつくりたくない。もしくは、一旦はつくったものの病院窓口での不具合で医療保険証としての取扱いでの不祥事が多発し、マイナ保険証をつくった人は70%おりますが、先ほど申しましたように、利用率は僅か6%という状況であります。
マイナ保険証をつくらない人やマイナンバーカードを返納した人がいますが、国保などの保険料はきちんと払っているのに紙の保険証廃止で保険証が発行されない市民が発生します。
政府はマイナンバー保険証を持たない国民には、新たな紙の医療保険の証明書を発行するとしています。証明書です。マイナンバーカードを持たない人の中には、証明書の発行を知らない市民もいるものと想定します。証明書の発行は、どの時期にどのように発行されるのか。また、市民に対してこのことの周知を図ることが必要だと考えます。どのように周知を図る考えなのかなど伺います。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
まず、全体の制度から説明させていただきます。
健康保険証の廃止を定めたマイナンバー法等の一部を改正する法律の施行により、今年12月2日から保険証を発行する制度がなくなり、発行済みの有効な保険証は最長1年間利用ができます。その後はマイナ保険証かマイナ保険証の登録をしていない方に発行される資格確認書を利用し、医療機関を受診していただくようになります。マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録をしているマイナンバーカードのことです。
議員がおっしゃっている新たな紙の証明書は、資格確認書のことになりますが、被保険者資格の確認に必要な項目が記載されており、これまでの保険証と同様に医療機関窓口で提示して受診ができるものです。
交付については、当分の間、マイナ保険証の登録をしていない方全員に御本人からの申請なしで職権で交付することになっております。
次に、安芸市の国保において、紙の証明書、資格確認書がどのように発行されるのか。どのように周知を図るかについて説明させていただきます。今年の8月1日から来年7月末までの1年間の有効期限がある保険証を7月下旬に御自宅へ発送します。この保険証は最長1年間利用できますが、12月2日以降は、出生、転入、社会保険喪失などにより新たに国保資格を取得する方、また、保険証を紛失した方で、マイナ保険証の登録をしていない方には随時資格確認書を発行します。また、令和7年7月には、マイナ保険証の登録をしていない方全員に資格確認書を一斉に発送します。
そして、市民の皆様への周知ですが、今月下旬に発行される7月号広報あきへの掲載、7月下旬に御自宅へ送付される保険証にお知らせ文書を同封、ホームページへのお知らせ記事掲載などを予定しております。
議員のおっしゃるとおり、全ての被保険者が必要なときに必要な医療が受けられる状態を確保するため、被保険者証の廃止に伴う事務を適時、適切に実施するとともに、制度改正の周知広報を丁寧に行うことが必要だと考えます。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 加えてちょっと伺いますが、証明書を発行されて、その後紛失した場合は届出をしたらすぐ発行されますか。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 証明書を紛失して届出をした場合に資格確認書がすぐに発行されるかということですね。
12月2日以前でしたら保険証をお出しできます。12月2日以降は資格確認書を発行することができます。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
続いて、次の質問を行いますが、マイナンバーカードとのひもづけにおいて、私はさきに述べましたように、今後、銀行や医療状況や収入、税金など、多くの個人情報がひもづけにされ、一旦情報漏えいが行われれば、さきに言いましたように詐欺被害は防ぎ切れません。アメリカや韓国でも社会問題になった模様でありますが、先般のある報道におきましては、本人がカードでの預金引き出しをした覚えがないのに預金引き出しの通知が来たとの内容の報道がありました。このような事例が今後も多く起きることが予想されます。これは、恐らく何らかのことによりまして、この人物のいわゆるマイナンバーを含めて個人情報が漏えいされ、勝手にこれらの預金の引き出しカードがつくられたのではないかという予想も報道の中にありましたが、もう一面ですね、この個人情報を企業が活用できるようにすることであります。個人情報を企業に活用するいうようなことも行われるというものでありますが、このように企業の利益誘導のために個人情報のひもづけの活用拡大を図ることも行うことはいかがなものかと考えますが、このマイナ制度の拡大の問題についてどのような認識であるのか伺っておきます。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えいたします。
マイナ制度に関する御指摘につきまして、マイナ保険証等における一連のトラブルは、マイナンバーカードの利用に対し国民の信頼を大きく揺るがす事案であると認識しております。医療保険に限らず税情報など、マイナンバーにひもづけをして利用する機会は、国がマイナンバーカードのデジタル社会の実現に向けて制度設計を行っているものであり、先頃5月に施行された改正マイナンバー法においても、海外でマイナンバーカードが継続利用できたり、医師や保育士など国家資格などがマイナンバー利用事務に追加されたりして利用がさらに拡大されました。国民にとって多くの手続がマイナンバーカードで取れることは、国の目指すデジタル社会の創出ではあります。
しかしながら、マイナンバーカードをめぐる相次ぐトラブルは、国民の不安をいまだ払拭できていない状況にあります。
12月には、現在の紙の保険証が原則廃止されるという新たな局面を迎えます。マイナンバーカードの利用に不慣れな方やマイナ保険証の携帯が困難な高齢者などにも利活用しやすい安全・安心なデジタル化の実現を目指して、国の責任において制度の円滑な運用ができる仕組みづくりに努めてほしいと考えております。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) はい、ありがとうございました。
次に、最後の質問、期日前投票についてに入ります。
まず、この質問に入る前にですね、今日、偶然でありますが次のようなことがありました。私どもは、毎月19日行動を戦争反対、平和を守り、命と暮らしを守る。このような観点で、その時々の政治状況の問題、これらをポスターにして道行く人々に訴えておる月一度の私どもの仲間同士の催しであります。これをやっておる途中に高齢の女性が私たちの横を通っていまして、信号で立ち止まったときに私に話しかけてきたことがあります。それは何かと言いますと、今の政治状況、いわゆる昨日の国会の模様をその人はテレビで見ておったらしいです。裏金問題、この問題を今後の法律改正といいますか、それらが出たときに、その模様を見ながら、私に偶然でありますがこう話しかけてきました。私のような素人があのテレビを見ても腹が立つと。一つも反省してない。問題解決に至らんような法律をつくって腹が立ついうことを私に話しかけてきた女性です。私はそのときに、そうやね、次の選挙では投票に行って、自分の意思を投票所にぶつけないかんねと、こう話しました。そしたら、その女性は、私は毎回選挙には行きゆうけど一つ困ったことがあると。期日前投票してきたけんど今度は遠うなったきんよう行かんと。こういうことが、そのときにその女性のほうから話が進みました。ちょうど今日の期日前投票の問題であります。
そこで伺いますが、そのようなことも、今日偶然たまたま会った人が立ち止まって言うのには、恐らく前の市役所の近くの方だと思います。そういう方がこのように言ってました。今後の選挙において期日前投票をどこに開設するのかを伺います。これまでは、旧庁舎の敷地内において期日前投票所を開設してきましたが、庁舎の移転にて新庁舎は交通の便が少なく、車を持たない有権者が、新庁舎は公共交通では4回も乗換えが必要で不便なので旧庁舎付近で期日前投票所を開設してほしいという要望がありました。これはずっと前に聞いた話で今日の人の話ではありません。これらの要望を検討して、どこに開設するのかを決めることが必要だと私は考えますが、今後どのように検討していくのか伺います。
○徳久研二議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
期日前の投票所は、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、これまで選挙管理委員会の事務局があり、登録内容が保管されております市役所の敷地内に設置してきました。期日前の投票所は、市内の全域からお越しになる有権者に対応するため、これまでと同様、新しい庁舎の敷地内に設置することを現時点では考えております。
それでですね、投票の当日は、これまで同様に市内の各地域に投票所が設置されますので、まずはそちらのほうが御利用できないかということも考えていただければと思います。
また、期日前の投票所は期間が複数日にわたりますので、来庁の日時を調整して御利用いただくことも考えていただければと思います。
複数の場所に期日前の投票所を置くためには、重複の投票が起こらないような対策や人の確保や費用の問題があります。今後の投票率も見ながら検討していきたいと思います。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) この新庁舎の敷地内で期日前投票所を開設すると。また何かあったら検討するという答弁でありました。それもそのとおりかと思いますが、やはり多くの人が、この期日前投票に限らず、庁舎が遠くなったから、自転車や歩くだけの人がここへ来るのはなかなか困難だということを、さきの議会でも私市民の方からの声を代弁して提案もしたこともありますが、これは元気バスの運行を増やすこととして取り上げたことですが、やはりこの期日前投票というのは、一人でも多くの投票をしていただく。国民の選挙というその権利を行使する機会をつくる、この場であると私は思います。そういう場合に、今日偶然でありますが、さきに紹介した女性の高齢者の方からの声は、この人1人ではないと私は思います。多くの方のこのような思いを持っておる方がたくさんあろうかと思います。やはり投票の権利を投票所で行うという、本来の投票日に行うというのが基本でありますが、そこにはなかなかいろんな理由で行けない人がおります。そのために期日前投票、これらを設けていると思うんです。やっぱりその場所を多くの人が行きやすいようなところへ構えるということが私は大事ではないかと思いますので、まだ選挙の日は、次の衆議院選挙いつ行われるか分かりません。やっぱりまだ時間が十分ありますので、今日の私と高齢御婦人との会話の中に出てきたようなこと、ぜひとも検討いただいて対応していただくことを強く求めて質問を終わります。ありがとうございました。
○徳久研二議長 以上で、10番 川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
応答、答弁者:教育次長兼学校教育課長、市長、企画調整課長、農林課長兼農業委員会事務局長、市民保険課長、選挙管理委員会事務局長
再開 午後0時59分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
10番 川島憲彦議員。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 一般質問を行います。まず初めにお断りをしておきます。通告書には、質問2点目、消滅自治体問題についてで3点質問点を上げておりますが、この議会の開会挨拶の中に消滅自治体への市長のコメントも一部ありましたので、それだけを聞くのはやめてですね、1番、2番をひっつけて質問をいたしたいと思います。まず、一極集中の問題だけに質問を絞らないということで、第1、第2を含めて一つにまとめて質問を行います。
また、質問の中でいろんな状況等で、私の思いとか含めて、少し長くなる面がありますが御了承いただきたいと思います。
まず、教育問題について伺います。
教育問題で、まず初めに、残業と教員の確保について。この点について伺いますが、全国で教員の残業が多く、また、家庭に持ち込んで仕事をしなければならないなど数年来の大きな問題となっております。これは、国はこれまで教員の残業の上限を月45時間と定めておりましたが、文科省の22年度調査では、月45時間を超えて残業している教員が小学校で64.5%、中学校で77.1%もおります。教員は残業代が支給されず、給特法におきまして、基本給にこれまで4%を乗じるだけの金額が給与として含まれておりまして、これは平均1万5,000円。今回これらを10%に引き上げた模様ですが、これでも平均3万8,000円の上乗せとなります。労働基準法では残業代の割増は1.25倍と定めておりまして、10%を上乗せしても全くこの額には届きません。これにより本当に働かせ放題、こういう言葉が出ております。まさにこのことではないでしょうか。
学校現場は大変な事態になっているのではないかと想定します。先ほどの文科省の調査による小学校教員は、1時間授業を1こまとして平均で1週間に24こまの授業で、ほとんどが空き時間がなく、授業の準備や子供への対応がほとんどできない状況とのことであります。これにより、教員の多忙化が子供たちにどのように跳ね返っているのかを考えれば、まさに子供が犠牲になっているのではないかと考えざるを得ません。先生と子供の声にしっかり寄り添う対応で現状をどう打開していくのか。このことを望む声が多くあります。
安芸市の学校現場が現在どのような状況であるか、どのように把握されているのかをまずお伺いいたします。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 はい、お答えいたします。
子供の教育に影響が及びますため、教員の働き方改革が喫緊の課題として進められている状況にあります。全国の状況はおっしゃられたとおりだと思います。
本市でもですね、近年精神疾患を引き起こす教員も目立つようになってきておりまして、ちょっと対応と一緒になってしまいますが、令和2年に示されました文部科学省の指針というものがございまして、そちらに基づいて教育職員の在校等時間の適切な管理としまして、定時に退校する日の設定をするとか事務事業の見直しのほか休暇の確保、それから業務の持ち帰りの軽減、働き方改革に関するアンケートの実施など、教員の健康と福祉の確保を図るように対策を講じております。
そして、令和4年度から教員の業務を負担するという観点で、負担軽減として市の会計年度任用職員としまして教員業務支援員を積極的に配置をしております。先生方からは特別支援教育支援員の配置も含めて安芸市は非常に手厚いという評価もいただいております。それでも時期によりますけれども、月45時間を超える時間外勤務といいますか、在校等時間になりますけども、そういった時間が発生している教員というのは少なくはなく、さらに対策を講じていかなくてはというふうに考えているところです。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私の指摘した状況が安芸市にもあって支援員を配置したというところで、教員の過重負担の軽減をするということも行っておる。しかしその中で、なかなか解決できない問題があるという答弁でありました。
次の質問に移りますが、少子化に合わせ教員の数を減らしたことで、産休や育休で休む教員の補充もできないなどを含め、教員不足が教員の長時間労働に拍車をかけるなど、残業問題と教員の不足は切り離せない問題だと思います。自宅への持ち帰り残業を含め1日11時間半に上り、これらによる長時間労働で精神疾患を引き起こしたり、長時間労働で教員への夢と生きがいを失い、希望が持てず、教員になったばかりの若い教員が早期退職をしたり、教員になることを夢に見てきた学生が教員になることを諦める、こういう学生がいるなど、まさに成り手不足に拍車をかけることなどの影響からこうした教員不足が続いているものと思います。
必要な教員の確保ができているのか。また、非正規職員を補充するのではなく正規職員の確保も重要かと私は思います。
安芸市の学校において必要な教員の確保ができているのかを伺っておきます。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
市の教員確保の件でございます。必要な教員の確保ということでございますが、県費負担教職員制度ということでやっておりまして、任命権や人事権につきましては高知県にあります。現在お尋ねの安芸市に教員が不足しておるという実態につきましては、そういった実態はありませんが、正規の教諭が配置されておらず講師の配置校が多々見受けられるような状況にあります。
以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 教員は不足はしていないが、いわゆる臨時教員がおる実態だという答弁でありました。
私がこの質問の中に申しましたように、やはり臨時教員を雇用するということは、やむを得ず急にできたから、取りあえずは補充をするということで行うべきものじゃないかと思います。常時、残業がどんどん増えて、精神疾患までなるような今の残業の問題、これは人手不足そのものであると私は思います。だから今の先生方の中にも、きちんと必要な教職を整えて、そして、このような残業をするような学校ではなくて、子供に寄り添いながら、余裕を持って子供の分かる授業のために時間を割いていく。こういうことが一番教育の中で大事な問題であると私は思います。そのことがイコール必要な教員の確保ではないかと思います。
もちろん、私は市町村に教員を雇用する。そういう役割が果たせれないということは百も承知です。しかし、県の教育委員会と安芸市の教育委員会との話は、子供の教育を支えるためにこのようなことはぜひやってくれ、こういう要望をいかにこれまで県教育委員会に届けてきたのかを含め、現場の先生方の苦しみ、努力はしておるけど、努力をすればするほど自宅に持ち帰ってせざるを得ない。このことで11時間も過重労働を迫られる。こういう状況をなくさない限り、私はこの問題は解決しない問題であると私は断言できると思います。
また、現場の先生方の思いも同じことではないでしょうか。これしっかりつかんで対応していくことが地域の自治体の教育委員会の大きな仕事ではないかと。このことを痛切に思うものでありますので、ぜひともこのために力を注いでいただきたい。
次に、不登校と児童虐待、いじめ防止対策について伺います。
22年度の児童生徒の不登校は、前年度比で5万4,108名、22.1%の増で29万9,048名だったという報告が文科省から出ております。また、児童生徒の自殺は513名と、高止まりであることが厚労省の発表があります。
そして、23年度において、18歳未満の虐待通告児童数は、前年度比6.1%増の12万2,806人と、これまた過去最多を記録していることが警察庁の発表が出ております。
全国の児童相談所が対応した虐待に関する相談におきましては21万9,170件で、これも過去最多の模様であります。
このように、少子化が進む中において、子供を取り巻く状況は誠に深刻な状況ではないかと思います。
不登校問題については、ある大学教授は、心の傷は幼児期からの受験競争の激化などで生じている。不登校を生まない教育を模索することが最も重要である。子供の意見表明権を尊重する学校づくりとして、テスト中心を改め個人尊重のクラスづくりが必要として、そのために、少人数学級の編成と教員の増員が不可欠であると大学教授は申しております。
また、子供を評価する前に心の理解が大切で、様々な場面で出てくる子供の言葉を宝のように大切にする教育、これが最も大事であると述べております。
そして、現在は学力テストが行われ、県別、市町村別にその結果が公表されております。学力テストへの賛否は多々あると思いますが、はるか過去の話でありますが私の体験を言わせていただきます。
私が中学校のとき、担任の主任が私のクラスのみ学力テストを行いました。私はそのときに、覚えておるのは、たった1枚のテストで人間の能力が分かるわけがない。こういう思いで、私は学力テストへの反対を担任に述べ、自分の意思で白紙提出を行いました。当時の全国学力テストはいろいろ問題が起きて、その後も中止となりましたが、現在は復活しておりますが、今も賛否の意見が分かれているところです。
しかし、学校教育の原点は、成長の過程で助け合って必要な授業内容を理解し、成長させていくことだと私は考えます。
そして、学力競争の中に置かれた子供で、子供の心の傷が発生し、不登校の原因になったときには、専門家の意見にあるように、子供を尊重する教育を徹底することではないかと考えます。学校へ行きたくないという声を真摯に受け止め、心の傷をケアし、十分な休養を子供に保障し、最初に相談する教員やスクールカウンセラーが特別に重要だということや、親が子供に大丈夫だよというサインを出せることが大切であるという専門家の意見も参考にして、子供への心ある対応が重要だと思います。
大変指摘が長くなりましたが、これらについて安芸市の教育、どのような認識でしょうか。また、不登校などの安芸市の現状と対策について伺っておきます。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 はい、お答えいたします。
不登校の状況は、先ほどもおっしゃられたように昨年の10月、文科省から令和4年度の不登校児童の生徒数が過去最多になったというニュースが報じられました。本市の児童虐待、いじめについての深刻度につきましては全国に比べると高くはないと、これは言い方が問題になるかもしれませんが、という認識をしておりますけれども、不登校児童生徒数につきましては、昨年小学校は減少に転じたものの中学校は増加傾向にあります。
本市の不登校の要因としましては、小学校での不登校児童が継続して中学校でも不登校となっていること、学習のつまずき、それから対人関係、家庭環境などが複雑に絡み合っていると分析をされています。
その不登校対策として、川北小学校奈比賀分校に教育支援センターを設置して、指導員と支援員4名が地域と連携しまして、精力的に不登校児童生徒の予防やその居場所づくりを行って、学校復帰に努めております。
また、保護者からのニーズも増えておりまして、市外のフリースクールへの通学でありますとかオンラインの学習システムなど、教育手段の問合せも増えておるような状況にございます。
今後ですね、人員も含めて、いま一歩踏み込んだ対応を検討していく必要があるのではないかと考えるところであります。
いずれにしましても、議員のおっしゃるように学力テストなどが、競争社会っていうものが不登校の因果関係という部分で関与しているかどうか、しっかりとはようお答えしませんが、教員が子供と関わる時間が確保されることによりまして、この不登校要因の解消につながり、または緩和されるなど、その効果があるものと考えております。
したがいまして、市としまして引き続き教職員の健康と福祉の確保を図るための努力をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 不登校は中学校のほうに若干増加しておるということです。
いじめについて報告がなかったように思いますが、いじめは現在どんなような状況ですか。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 いじめの認知件数になりますけれども、令和元年に小学校・中学校合わせまして282件という大きな件数を出しました。その後、これ認知件数ですので徐々に下がってきておりまして、先ほど文科省の調査で出てきた令和4年度の時点では90件ということでございまして、決して低い数字ではありませんが、大ごとになる前に初期対応をしたり、家児相なんかが入ったり、スクールソーシャルワーカーとか、そういった関係機関が入って初期対応に応じており、大きな問題にはつながっていないという意味で、大きなことにはなっていないというふうに申し上げました。件数はあります。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 令和4年度で90件とか把握をされておるということがありましたが、やはりいじめ問題、不登校問題ということの中から子供の自殺も発生しておる。これが考えられますので、やっぱり1人の子供を育てる。これは家族にとっても大変なことでありますが、やっぱり学校へ通う中でこのようなことが生じない教育がいかに大事かということを考えざるを得ません。やはり学校現場の状況を先生方に絶えず聞く。また、子供へのアンケートなんかも含めてですね、なかなか子供もいじめがあってもそれが言えない。言ったらまたいじめが大きくなる。そういうふうな事態を、いじめを受ける子供はそれを真っ先に心配することではないでしょうか。やはりそのようなためらいが起きないように、日常的な学校教育の現場でしっかりと子供と寄り添い、子供の精神状況、また、友達との関係をしっかりとつかんでいくということが必要かと思います。ぜひとも教育委員会挙げてですね、このことにぜひとも強く思いを持っていただきたい。そして先生とも協議を続けていくということも含めて申し添えておきたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
次に、消滅自治体問題について伺います。
まず初めに、さきのように申し上げましたので、次の1、2を含めてまとめて質問もさせていただきたいと思います。
消滅自治体問題について伺いますが、民間の有識者グループの人口戦略会議は、若い女性が半減して消滅する可能性があると分析した自治体のリストを公開し、高知県内においては安芸市を含む25自治体が上げられました。しかし、私はこの60年来、地域の人口減少はずっと減り、減少し続けてきました。
その原因は、若者が仕事を求め、都市部に居住地で生活することを選ばざるを得ない状況が最大のものであり、いわゆる東京への一極集中そのものであると私は考えます。この点につきましては、今議会の、先ほど言いましたように、開会挨拶でも市長も東京への一極集中による社会構造の是正が必要と述べているように、この点につきましては、私も同様の認識であると思います。
私は、青年期においては、生まれたこの地で生活をすることを私は決めてまいりました。しかし多くの同級生や知人は、様々な理由におきましてふるさとから遠く離れ生活をしております。
安芸市の人口減少に関わることを考えれば、農家の減少や個人商店の衰退と閉店、これらが真っ先に上げられると考えられます。私たちの周りでは、たばこや米や酒屋の商店はほとんど姿を消しました。この最大の理由は、大型量販店の進出の増加と、これらの大型量販店へ販売許可を下ろした。そして、これらによりほとんどの個人商店が姿を消しました。農林漁業も外国からの輸入拡大で、全国においても厳しい経営状況の中で個人事業の後継者の減少が続いています。これら全てが、国の政策で行われたと言っても過言ではないと私は思います。
これを解決するのは、国のこれまでの東京一極集中イコール都市部への集中といえますが、これらの見直しを行い、地域の人口拡大に向けた支援を行うことだと私は考えます。
市長に改めて伺いますが、消滅自治体問題の可能性があるとされたことをどのように受け止めたのか、お聞きしたいと思います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 安芸市が消滅自治体の可能性があるとされたがどのように受け止めているのかということでございますが、今回安芸市が消滅可能性都市に該当したことは、客観的なデータに基づき算定された将来推計の結果と受け止めており、人口減少に歯止めがかかっていないことに一層危機感を抱いているところでございます。
ただし、今後30年以内に自治体が消滅する可能性があるという、このインパクトの強い言葉をあまり重く受け止め過ぎると市民の皆様を過度な不安やまち自体にもはや魅力がないといったミスリードを引き起こす懸念もあると思います。
また、この言葉は、以前も報道でもございましたが、島根県とか高知の濵田知事とか、それから町村会とかでもそういう反論といいますか、コメントが載っておりましたが、自治体の人口減少対策への努力が足りていない結果のように、これまでの取組が否定され、レッテルを貼られたかのようにも感じ取っております。この言葉だけを捉まえますと消滅という言葉だけが踊ることのないよう、国民の行動変容が前向きになるような文言を慎重に選定されるべきであったのではないかというふうに思っております。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) また後からも述べますが、やはり今回の有識者会議が発表したということでありますが、これはまさにね、私は国が発表したと同じだと私は受け止めてます。そして、国の責任をよそにおいて自治体の責任かのようにいっておる。そして、しかも、その原因、最大の理由が、若い女性が減少して子供を産まなくなったと、女性問題にもすり替えております。これにとっては非常にいかがなものかと私は思いますし、次の質問に移りますが、消滅自治体問題につきましては、人口減少の原因に、先ほど申し上げましたように、若年女性の人口減少を問題にし、日本全体の問題を自治体の問題にして取上げ市町村の責任にしていますが、先に上げましたように、これは国の責任であると私は思います。
また、若年女性の人口減少問題にしておりますが、これは女性の責任を押しつける一つの圧力と取れるのではないかとも思います。
国がこの30年、経済界の求めに応じ、あらゆる職種の働き方を本来の正規雇用から非正規雇用に切り替え、そのことによって若い世代の給料が上がらない状況をつくり上げ、若い世代を中心に暮らしが大変な時代となりました。
また、社会保障切捨てと社会保険料の負担の引上げにてさらに暮らしが厳しくなり、コロナ禍で結婚もできない。子供を育てる生活費が工面できないなどの理由で、少子化という人口減の状況が全国で起こったのではないでしょうか。また、結婚や出産はその人々の選択の自由であり、個人の尊厳に関わる問題でもあります。一人一人が幸せに暮らせる環境をつくることが国と自治体の役割であり、中でもその責任は国にあると思います。東京一極集中の是正は待ったなしで、様々な人が対等に、希望に応じて働き、安心して暮らせる地域をつくることが大切であると私は考えます。
消滅可能自治体と言われる自治体には、どこにも人間が生きていく上で欠かせない豊かな自然と文化に恵まれておりまして、人口戦略会議が最後のチャンスというような浮き足立つ必要は私はないと思います。
先ほども指摘したように、一人一人が幸せに暮らせる環境をどのようにつくることが国と自治体の大きな役割であると思います。その一方の自治体の今後の対策をどのように考えているのか伺っておきたいと思います。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 はい、お答えをいたします。
人口減少対策に特効薬のようなものはなく、地道にいろんなことに取り組んでいかなければならないと考えております。
市の取組として、先に少し成果のほうをお話ししたいと思いますけれども、令和5年度の県外からの移住実績が75組93人と、県内では高知市、四万十町に次いで3番目の上位の実績となっておりまして、移住施策に取り組み始めて以降毎年上位の結果を維持してきております。この移住施策は本市の強みでございまして、この特徴をずっと伸ばしていきたいなというふうな思いはございます。近年は起業を志す移住者の方、起業したいというふうに言われる方が増えてきておりますことから、起業者の受皿となる店舗等を調査し、空き店舗バンクを開設できるよう本年取り組んでおります。
また、本市へ企業進出したいというふうに検討している事業者からの問合せも今や数件ございまして、雇用の確保と経済浮揚につながる取組を目下全力で進めているところでございます。
こうした移住や企業誘致のほか、出会いの機会創出や結婚支援、子育て及び教育支援の充実について現状とニーズのギャップ、問題課題の解消につながる施策を精力的に展開し、成果を上げてまいりたいと考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) はい、ありがとうございます。特にこの5年間、令和5年度の移住の結果とか県下で3位、また起業を希望する移住者に支援をしていくと。また会社を安芸市で興したいというようなことについては現実にあり、実現していきたいということでございます。
私は、県外からの移住はもちろんですが、安芸市で生まれた人々が安芸市で暮らすようにいかにしていくか。これが最も私は大事ではないかと思います。後継者をつくっていく。また、農家においても、もちろんのこと、後継者をつくる。そして、安芸市で生きていく。そういうような人口を確保していく。このことが何よりも私は大事でないかと思いますので、やっぱり市民の努力等をいかに支援をしていくか。若い世代のそういう支援をいかにしていくか。これらに尽きるのではないかなと思います。そういう面にもぜひとも市民の意見を聞いて、そして安芸市で生きていく。そういう気持ちを育てていく安芸市であってほしいと、このように願っておるものでございますので、やっぱり全庁を挙げて頑張っていただきたい、このように思うものでありますので、これらを付け加えて次の質問に移ります。
次に、農業問題についてであります。
これも大変厳しい状況でありますが、まず、我が国の食料自給率の件について伺いますが、日本の食料自給率は現在38%であります。食料の大半を輸入に頼っている状況であります。
この原因は、農業での生活が厳しく、他の職業に切り替えて生活を支えざるを得ない状況が全国で起き、後継者が育たず、高齢化で農家の減少に至ってきた。このこと。
また、主食の米の生産を減らす国の方針も大きな要因であったと私は認識しています。以前は、米の生産を支えるために国は農家から高く米を買取り、消費者には安く販売するという二重価格補償制度において食料を確保してまいりました。若い方はこれらのことは知らない方も多くありますが、私らが青年期のときは、米については、農家から高く買い消費者には安く売る。これを国の責任として行ってきた。こういうことでありました。しかし、今ではその面影もないという時代です。
食料自給率を向上させることは、食料確保政策において第一の課題でなければならないと思います。そのためには、農業後継者の確保と拡大であり、農地を余すことなく活用し、同時に水の確保など豊かな自然を守り、安心・安全な食料の確保のために農家を支える対策が何よりも重要であると思います。米の生産だけでなく野菜や果樹生産農家や酪農や漁業の皆さんへの支援も同様であります。こうした国民の食料確保に直結する人々を支えることが国と自治体の役割と言っても過言ではありません。これらのことをしっかり国が行うことを求めると同時に、自治体も農家とともに頑張り、必要な対策をすべきと考えますが、どのように対応するのか伺います。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
御質問のとおり、日本のカロリーベースの食料自給率は令和4年度で38%と、ここ数年は37から38%での推移となっており、令和2年度に策定されております現行の基本計画での自給率目標である令和12年度の45%には届いていない状況でございます。この食料自給率の向上につきましては、生活に不可欠な食料を将来にわたって安定的に供給し続けるためにも重要な取組であると認識をしております。
本市におきましては、議員も御承知のとおり、ナスやピーマンなどの施設園芸、そしてユズの産地でございます。ハウス以外では水田において稲作が行われており、これらの農地を維持していくためには水田での稲作が必要不可欠なものとなります。
米の販売単価につきましては、直近では回復基調にありますが、以前よりの販売単価の低下傾向に加え、昨今の肥料価格等の高騰などもありまして、稲作での農業経営は非常に厳しい状況と思われますので、今後におきましては耕作できない農地所有者の増加などが懸念されるところでございます。
こうした状況の中、本市での対応ということでございますが、本市では担い手の確保・育成、農業経営の安定・向上、生産基盤の充実などを柱に農業振興に取り組んでおります。農業後継者を含めました研修段階から就農までをトータル的にサポートする新規就農者の確保・育成対策に引き続き取り組むほか、農業生産の面におきましては、本年度末までに策定すべく現在取り組んでおります地域計画の策定に向けた集落ごとの座談会を通じて、まずは現状の把握に努めたいと考えております。この地域計画では、10年後の地域営農の姿を一筆ごとに定めた目標地図を作成する必要がございますので、農業生産の基盤となる農地の圃場整備ですとか用排水路等の整備改修など、それぞれの地域の実情に応じた生産基盤の整備等の支援策の検討・実施につなげてまいります。
また、持続可能な農業の実現に向け、重要な点としましては、国で仕組みづくりに向け検討が進められております農産物の適正価格、生産コストの価格転嫁の問題の解決が重要であるというふうに認識をしております。このため品目ごとに検討されているこの仕組みが本市の実情に沿ったものとなるよう、必要に応じて国や県への要望など、現場の声をつなげてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁では、様々なことについて必要に応じて取り組んでいきたいということが述べられました。
私は、国の食料自給率の確保は最も大事であると思います。今、政府は戦争の準備、実はしてますよね。敵基地攻撃能力の保持というて43兆円の軍事費用を当てると。しかしですね、日本を外国が仮に攻めるとしたら武器は要りませんよ。食料ストップさえすれば3か月で日本は駄目になりますよ。食料がないんですから、日本は。38%、国の人口の僅か38%分しかないですよ。あとの62%分の国民はどうなりますか。死ねというのも一緒ですよ。国と国とのいさかい、争いが起きた場合。戦争はしない、平和な世界をつくる、その根本には食料自給率を高める。このこと以外にないじゃないですか。日本を攻め落とすことは簡単ですよ。輸入さえ止めればいいですから。そのような国民の命と暮らしを支えるための政治が一番先に考えたら、自給率を高めることじゃないでしょうか。このことを申し添え、次の2点目の質問に移ります。
農業基本法について伺います。
国会において、食料・農業・農村基本法改定案が賛成多数にて可決をされました。この法改定では、自給率の向上は投げ捨てました。さらなる食料輸入に依存するというものであり、輸入を続ける、これをさらに拡大するという、ここに依存するというものであって、参議院農水委員会において参考人として招かれた農民運動全国連合会会長が、この改定案に対し反対の意見陳述をいたしております。その内容は、今、食と農の危機はかつてなく深刻。国民の関心、不安がかつてないものがある。今こそ政治が本気で食料増産を掲げ、日本農業の再生を目指す農業基本法をつくり上げてほしいと述べました。また、基幹的農業従事者が120万人減った中で、改定案には新規就農対策がない。大事なことは、規模の大小問わず全ての家族農業を政策対象にし、家族経営の果たす役割を再評価し、農業再生の主人公とすることですと述べ、世界の食料生産が不安定な中、改定案がさらなる輸入依存を掲げているのは大きな間違いで、日本で作れるものは精一杯作り、どうしても足りない分を輸入する政策に転換すべきとして、農村政策の基本は地域農業を再生することですと。日本には農業と農村が必要とする国民合意をつくり上げるような基本法改定のこの議論を強く要望しますと締めくくっております。まさにこのとおりではないかと私は思います。
これからの日本農業再生と国民の命を守る食料自給率を上げることは最重要課題であると考えます。農村政策の基本は地域農業を再生することと思いますが、行政の考えを伺っておきます。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 国の食料・農業・農村基本法についての御質問でございますが、この改正案につきましては、本年5月29日に成立されたものでございます。この改正に向けた審議等におきましては、日本の先ほどの食料自給率をはじめとした農業におけます課題などについて議論されたところでございます。その中で、行政の考えとの御質問でございますけれども、御質問のとおり、農業を支える全国の産地、いわゆる地域農業の維持発展は必要不可欠であるという認識を持っております。
現在、本市におきましては、施設園芸との複合経営をはじめ、米の作業受委託や農地の貸し借りによって比較的大規模に稲作をやられている農家の方々により地域の水田が守られており、その経営規模といたしましては、大部分が家族単位による中小規模の経営体であり、法人化等の経営体を含め、多様な経営体によって地域農業が支えられている状況でございます。
持続可能な農業、農村の実現、持続的な営農の実現に向けましては、農業基本法の改正に当たっての国会等での議論の内容を確認しますと、農産物における販売価格への価格転嫁という点が非常に重要であると考えておりますし、農家の方々も強く望まれている点だというふうに認識をしております。
このため、先ほどの答弁と重複いたしますけれども、国のほうで農産物の適正価格に向けた仕組みづくりにしっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、本市の実情に沿ったものとなるよう必要に応じて国や県に対して要望してまいりたいというふうに考えております。
また、地域計画策定のための地域ごとの話合いの場におきまして、家族経営体への支援を含め、本市での地域の実情を踏まえた地域農業の将来の在り方を検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後2時
再開 午後2時8分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほど農林課長から答弁をいただきました。ぜひ様々なことについて安芸市で農業従事者を増やす、そういう対策、人口増につながるような対策をぜひ取っていただきたいと思いますが、まず、農業問題については、一般的に米は作れば作るほど赤字だという状況であります。一つの資料によりますと、農家の米作りの時給が10円だそうです。時給が10円、10時間働いて100円、30日働いて3,000円、1年間で3万6,000円。これが米作りの時給だそうです。やればやるほど赤字。必要なことは、そういう米を作る、農産物を作るために頑張る人々の暮らしをいかに支えていくか。これが自給率を高める第一のことではないでしょうか。県に対しても国に対してもこの点をきちんとやっぱり求めていく。安芸市の農業を支える政策の要にもしていく必要があるかと思いますので、それらを特に求めて、次の質問に入ります。
次に、マイナンバーカードについて質問をいたします。
私は、この質問に入る前に申しておきますが、紙の保険証、何ら今まで問題がないのに、なぜ12月2日からこれをやめるのか納得がいきません。紙の保険証を残す。この願いを、思いを私は持っておりますので、それらを質問点の中心に据えて質問をしていきます。
もちろん、マイナンバー保険証、マイナンバーカードは安芸市の責任ではありませんが、これは最大は国の政策におけることであると思います。
政府は多くの国民が反対するマイナンバーをひもづけにして、国民の個人情報を結びつける制度をつくり、まず手始めに保険証をマイナンバーカードと一体にするとして、この12月から紙の保険証を廃止するとしています。
私は、マイナンバー制度において、医療や収入や税金などの個人情報をひもづけにすることは、個人情報の漏えいなどによる詐欺被害を助長するとして反対の考えからマイナンバーカードはつくっておりません。そして、議会からも給与等でマイナンバーカードを求められますが、一切銀行にもこれらは記入しておりません。
また、これまでマイナンバーカードにおいて、医療窓口などにおいての多くの不具合も生じ、窓口対応に大きなしわ寄せや、行政の窓口対応においても、これまでの紙の保険証で何も問題は起こらなかったのに、マイナンバーカードの対応に多くの職員が新たに対応に追われるという事態になったことと思います。
そして、今のマイナ保険証利用率は僅か6%であるという状況です。マイナンバーカードをつくりたくない。もしくは、一旦はつくったものの病院窓口での不具合で医療保険証としての取扱いでの不祥事が多発し、マイナ保険証をつくった人は70%おりますが、先ほど申しましたように、利用率は僅か6%という状況であります。
マイナ保険証をつくらない人やマイナンバーカードを返納した人がいますが、国保などの保険料はきちんと払っているのに紙の保険証廃止で保険証が発行されない市民が発生します。
政府はマイナンバー保険証を持たない国民には、新たな紙の医療保険の証明書を発行するとしています。証明書です。マイナンバーカードを持たない人の中には、証明書の発行を知らない市民もいるものと想定します。証明書の発行は、どの時期にどのように発行されるのか。また、市民に対してこのことの周知を図ることが必要だと考えます。どのように周知を図る考えなのかなど伺います。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
まず、全体の制度から説明させていただきます。
健康保険証の廃止を定めたマイナンバー法等の一部を改正する法律の施行により、今年12月2日から保険証を発行する制度がなくなり、発行済みの有効な保険証は最長1年間利用ができます。その後はマイナ保険証かマイナ保険証の登録をしていない方に発行される資格確認書を利用し、医療機関を受診していただくようになります。マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録をしているマイナンバーカードのことです。
議員がおっしゃっている新たな紙の証明書は、資格確認書のことになりますが、被保険者資格の確認に必要な項目が記載されており、これまでの保険証と同様に医療機関窓口で提示して受診ができるものです。
交付については、当分の間、マイナ保険証の登録をしていない方全員に御本人からの申請なしで職権で交付することになっております。
次に、安芸市の国保において、紙の証明書、資格確認書がどのように発行されるのか。どのように周知を図るかについて説明させていただきます。今年の8月1日から来年7月末までの1年間の有効期限がある保険証を7月下旬に御自宅へ発送します。この保険証は最長1年間利用できますが、12月2日以降は、出生、転入、社会保険喪失などにより新たに国保資格を取得する方、また、保険証を紛失した方で、マイナ保険証の登録をしていない方には随時資格確認書を発行します。また、令和7年7月には、マイナ保険証の登録をしていない方全員に資格確認書を一斉に発送します。
そして、市民の皆様への周知ですが、今月下旬に発行される7月号広報あきへの掲載、7月下旬に御自宅へ送付される保険証にお知らせ文書を同封、ホームページへのお知らせ記事掲載などを予定しております。
議員のおっしゃるとおり、全ての被保険者が必要なときに必要な医療が受けられる状態を確保するため、被保険者証の廃止に伴う事務を適時、適切に実施するとともに、制度改正の周知広報を丁寧に行うことが必要だと考えます。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 加えてちょっと伺いますが、証明書を発行されて、その後紛失した場合は届出をしたらすぐ発行されますか。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 証明書を紛失して届出をした場合に資格確認書がすぐに発行されるかということですね。
12月2日以前でしたら保険証をお出しできます。12月2日以降は資格確認書を発行することができます。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
続いて、次の質問を行いますが、マイナンバーカードとのひもづけにおいて、私はさきに述べましたように、今後、銀行や医療状況や収入、税金など、多くの個人情報がひもづけにされ、一旦情報漏えいが行われれば、さきに言いましたように詐欺被害は防ぎ切れません。アメリカや韓国でも社会問題になった模様でありますが、先般のある報道におきましては、本人がカードでの預金引き出しをした覚えがないのに預金引き出しの通知が来たとの内容の報道がありました。このような事例が今後も多く起きることが予想されます。これは、恐らく何らかのことによりまして、この人物のいわゆるマイナンバーを含めて個人情報が漏えいされ、勝手にこれらの預金の引き出しカードがつくられたのではないかという予想も報道の中にありましたが、もう一面ですね、この個人情報を企業が活用できるようにすることであります。個人情報を企業に活用するいうようなことも行われるというものでありますが、このように企業の利益誘導のために個人情報のひもづけの活用拡大を図ることも行うことはいかがなものかと考えますが、このマイナ制度の拡大の問題についてどのような認識であるのか伺っておきます。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えいたします。
マイナ制度に関する御指摘につきまして、マイナ保険証等における一連のトラブルは、マイナンバーカードの利用に対し国民の信頼を大きく揺るがす事案であると認識しております。医療保険に限らず税情報など、マイナンバーにひもづけをして利用する機会は、国がマイナンバーカードのデジタル社会の実現に向けて制度設計を行っているものであり、先頃5月に施行された改正マイナンバー法においても、海外でマイナンバーカードが継続利用できたり、医師や保育士など国家資格などがマイナンバー利用事務に追加されたりして利用がさらに拡大されました。国民にとって多くの手続がマイナンバーカードで取れることは、国の目指すデジタル社会の創出ではあります。
しかしながら、マイナンバーカードをめぐる相次ぐトラブルは、国民の不安をいまだ払拭できていない状況にあります。
12月には、現在の紙の保険証が原則廃止されるという新たな局面を迎えます。マイナンバーカードの利用に不慣れな方やマイナ保険証の携帯が困難な高齢者などにも利活用しやすい安全・安心なデジタル化の実現を目指して、国の責任において制度の円滑な運用ができる仕組みづくりに努めてほしいと考えております。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) はい、ありがとうございました。
次に、最後の質問、期日前投票についてに入ります。
まず、この質問に入る前にですね、今日、偶然でありますが次のようなことがありました。私どもは、毎月19日行動を戦争反対、平和を守り、命と暮らしを守る。このような観点で、その時々の政治状況の問題、これらをポスターにして道行く人々に訴えておる月一度の私どもの仲間同士の催しであります。これをやっておる途中に高齢の女性が私たちの横を通っていまして、信号で立ち止まったときに私に話しかけてきたことがあります。それは何かと言いますと、今の政治状況、いわゆる昨日の国会の模様をその人はテレビで見ておったらしいです。裏金問題、この問題を今後の法律改正といいますか、それらが出たときに、その模様を見ながら、私に偶然でありますがこう話しかけてきました。私のような素人があのテレビを見ても腹が立つと。一つも反省してない。問題解決に至らんような法律をつくって腹が立ついうことを私に話しかけてきた女性です。私はそのときに、そうやね、次の選挙では投票に行って、自分の意思を投票所にぶつけないかんねと、こう話しました。そしたら、その女性は、私は毎回選挙には行きゆうけど一つ困ったことがあると。期日前投票してきたけんど今度は遠うなったきんよう行かんと。こういうことが、そのときにその女性のほうから話が進みました。ちょうど今日の期日前投票の問題であります。
そこで伺いますが、そのようなことも、今日偶然たまたま会った人が立ち止まって言うのには、恐らく前の市役所の近くの方だと思います。そういう方がこのように言ってました。今後の選挙において期日前投票をどこに開設するのかを伺います。これまでは、旧庁舎の敷地内において期日前投票所を開設してきましたが、庁舎の移転にて新庁舎は交通の便が少なく、車を持たない有権者が、新庁舎は公共交通では4回も乗換えが必要で不便なので旧庁舎付近で期日前投票所を開設してほしいという要望がありました。これはずっと前に聞いた話で今日の人の話ではありません。これらの要望を検討して、どこに開設するのかを決めることが必要だと私は考えますが、今後どのように検討していくのか伺います。
○徳久研二議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
期日前の投票所は、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、これまで選挙管理委員会の事務局があり、登録内容が保管されております市役所の敷地内に設置してきました。期日前の投票所は、市内の全域からお越しになる有権者に対応するため、これまでと同様、新しい庁舎の敷地内に設置することを現時点では考えております。
それでですね、投票の当日は、これまで同様に市内の各地域に投票所が設置されますので、まずはそちらのほうが御利用できないかということも考えていただければと思います。
また、期日前の投票所は期間が複数日にわたりますので、来庁の日時を調整して御利用いただくことも考えていただければと思います。
複数の場所に期日前の投票所を置くためには、重複の投票が起こらないような対策や人の確保や費用の問題があります。今後の投票率も見ながら検討していきたいと思います。以上です。
○徳久研二議長 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) この新庁舎の敷地内で期日前投票所を開設すると。また何かあったら検討するという答弁でありました。それもそのとおりかと思いますが、やはり多くの人が、この期日前投票に限らず、庁舎が遠くなったから、自転車や歩くだけの人がここへ来るのはなかなか困難だということを、さきの議会でも私市民の方からの声を代弁して提案もしたこともありますが、これは元気バスの運行を増やすこととして取り上げたことですが、やはりこの期日前投票というのは、一人でも多くの投票をしていただく。国民の選挙というその権利を行使する機会をつくる、この場であると私は思います。そういう場合に、今日偶然でありますが、さきに紹介した女性の高齢者の方からの声は、この人1人ではないと私は思います。多くの方のこのような思いを持っておる方がたくさんあろうかと思います。やはり投票の権利を投票所で行うという、本来の投票日に行うというのが基本でありますが、そこにはなかなかいろんな理由で行けない人がおります。そのために期日前投票、これらを設けていると思うんです。やっぱりその場所を多くの人が行きやすいようなところへ構えるということが私は大事ではないかと思いますので、まだ選挙の日は、次の衆議院選挙いつ行われるか分かりません。やっぱりまだ時間が十分ありますので、今日の私と高齢御婦人との会話の中に出てきたようなこと、ぜひとも検討いただいて対応していただくことを強く求めて質問を終わります。ありがとうございました。
○徳久研二議長 以上で、10番 川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
添付ファイル1 一般質問 川島憲彦 (PDFファイル 437KB)