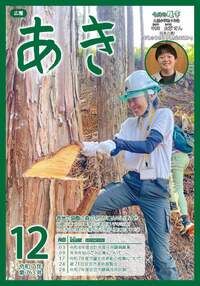議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 徳広洋子
質疑、質問者:徳広洋子
応答、答弁者:危機管理課長、市長、健康介護課長、農林課長兼農業委員会事務局長、市民保険課長、選挙管理委員会事務局長
議事の経過
開議 午前10時
○徳久研二議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 通告に従い、一般質問をいたします。
1、災害防災対策について。
1、気象防災アドバイザーの連携による本市の取組について質問いたします。
近年激甚化、頻発化、大規模化する気象災害は、1市町村だけではなく、複数地域にまたがり、いつ訪れるか分からない多発的な自然災害について、平時から高度な知識を有する気象防災アドバイザーを活用しながら備えることは、自治体の防災対策を支援する上で、大変有意義だと言われます。
2020年7月豪雨に見舞われて、熊本県内の被災地では、自治体ごとに対策を講じていく際に、気象台からの気象情報について、気象台OBのアドバイスが役に立ったとの教訓を踏まえ、気象防災アドバイザーとしては、出水期を前に、防災マニュアルの作成や見直し、防災訓練への協力など幅広い活動が想定されており、自治体の防災力を向上させる即戦力として期待をされています。気象台OBも対象に加わり、47都道府県1人以上の配備ができるようですが、気象防災アドバイザーの活動についてお伺いをいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
気象防災アドバイザーとは、気象庁退職者で防災経験のある者や、気象予報士で、気象防災アドバイザー研修を修了した者など、一定の要件を満たす者になります。
気象防災アドバイザーの業務は、まず市町村等の地方公共団体と雇用契約を結び、平時は職員への研修、訓練の企画、運営等の人材育成、地域住民への防災対策の普及啓発を行い、災害時には避難情報発令についての市長、市長への進言、担当職員への気象情報の見通しや解説などを、気象防災の知識を生かした活動をしてもらうものになります。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 次に、本市の気象防災アドバイザーとの連携、また取組と効果をお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
高知地方気象台に問い合わせたところ、現在、高知県内の気象防災アドバイザーは1名しかおらず、その方はふだんの仕事の都合上、兼業ができない方とのことです。
しかしながら、安芸市は平時から県や気象庁による訓練、研修、講演会などにも参加し、災害時の対応も高知地方気象台とホットラインを構築しており、気象台からの防災支援メール、警報発令の事前の情報提供や直接の架電により、安芸市ピンポイントの今後の気象状況の見込みなど、きめ細かい情報をいただいております。
また、台風時などに避難情報を発令する判断に参考とする重要な情報・助言については、気象台長から直接市長にも電話連絡をいただき対応しています。
現状、気象台との連携で対応できているものと認識していますが、気象防災アドバイザーとの連携につきましては、今後、気象台とも相談し、研究していきたいと考えています。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 気象防災アドバイザーとの連携の取組について進めていただけますよう、よろしくお願いをいたします。
2、個別避難計画において、本市の防災トイレについてお伺いをいたします。
地震や台風、豪雨などの災害時には、高齢者や障害者が自ら避難することが困難な避難行動支援者への避難計画において、実際に多くの人が集まる避難所では、いろんな方が避難直後から必要となるトイレに多くの問題が起きてきます。
避難所でのストレスでトイレ問題は上位を占めています。特に、高齢者や障害者の方は、衛生面に対しての不安と敬遠から感染症や病気のリスクが高まり、災害関連死を引き起こす可能性が高まることは、過去の災害時の教訓となっています。
個別避難計画において、本市ではどこまで防災トイレについて考えているのか、どのような計画をされているのかお伺いをいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
避難所における要配慮者への対応として、お答えさせていただきます。
避難所などには105基のポータブルトイレとトイレ用テントを備蓄しています。このうち、個別避難計画を作成している避難行動要支援者の方に対応したトイレの備蓄につきましては、障害者対応トイレは19基、感染症対策として、排せつ物を自動でラッピング処理できる電動トイレは25基の備蓄があります。
また、避難所となる小中学校など9か所には、延べ17基の地下埋設型の大規模仮設トイレを設置しており、大規模仮設トイレ1基当たりに障害者用トイレブースを2台ずつ備えています。
以上となります。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
次に、トイレトレーラーの整備推進についてお伺いをいたします。
災害時、避難所には、自宅を失った人などたくさんの人が避難します。そんな避難所で最も困るトイレ問題が深刻化されています。トイレに並ぶことなく使用するためには、避難者50人につき1台のトイレが必要だと言われています。
トイレトレーラーは、災害時を想定し設計された移動設置型水洗トイレで、個室4室を有し、長期使用時の衛生環境維持に配慮した機能を備え、手洗い台、換気扇など電源においても、屋根に太陽光パネルが設置されるなど、平時においての使用も可能で、イベント会場等にも移動設置し、使用できます。現在の防災対策で備えてほしい必要不可欠な設備だと思っております。
能登半島地震では、高知市のトイレトレーラーが派遣されて利用をされています。助かった命を失わないように、避難生活の衛生的な環境整備のため、各自治体に1台のトイレトレーラーの常備が必要と言われています。
本市において整備推進への所見を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
最近頻繁に報道されておりますこのトイレトレーラーにつきましては、今後、導入に向けて現在検討しているところでございます。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
ユニバーサルデザイントイレのように、車椅子使用者、オストメイト対応の設備、おむつ替えシート、ベビーチェア、子供連れなど、多様な人が利用できるなどの多機能を備えるトイレとともに、災害時だけでなく、多くの人が集まるイベント会場など、平時への設置が望まれております。今後、整備推進をよろしくお願いを申し上げます。
次に、4、福祉防災計画でのBPSD対策についてお伺いいたします。
先日、福祉防災上級コーチによる、みんなで助かるみんなでつくる個別避難計画と題した防災研修会に参加して、東日本大震災、能登半島地震、また過去の豪雨災害の教訓から、最新の防災情報など、福祉防災について視聴でき、発災直後から避難所の避難生活環境において、高齢者や、障害者の問題が多く上がっていることを知りました。
その中で、災害時に在宅認知症の高齢者が、3日以上の避難生活においては環境に適応し切れず、BPSDの発症が原因となり、周囲とトラブルが起き、避難所にとどまれない家族が多く出てしまったと聞きました。
本市では、このような避難生活の問題に、どのような対策を考えているのかお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
まず、私のほうから、避難所運営マニュアルについて、答弁させていただきます。
認知症や精神疾患をお持ちの方に限らず、市内の各避難所単位で策定している避難所運営マニュアルでは、まず、受付の際に、要配慮者の方の把握や生活支援について聞き取りなどを行い、必要に応じて避難所の中での要配慮者スペースへ誘導することとなっています。
また、一般避難所での対応が困難な方については、福祉避難所への避難や受入れの可否を検討することとなっています。以上です。
○徳久研二議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 続きまして、私のほうから、初めにBPSDの内容と、次に対策について答弁させていただきます。
BPSDは行動心理症状のことで、周囲の不適切なケアや身体の不調や不快、ストレスや不安などの心理状態が原因となって現れる症状です。災害時は誰もがストレスや不安にさらされます。精神的な変化として、気分の落ち込み、意欲・食欲の低下、いら立ちなどが見られ、その多くは一時的なもので自然に回復しますが、ストレスが長引くと長期化し、鬱病やパニック発作などの精神疾患の診断がつくこともあります。
議員の御指摘のとおり、とりわけ災害弱者と呼ばれる高齢者などは、災害時の生活に適応することが難しく、ストレスの度合いが高いため、特に配慮が必要で、安心して避難生活を送るための重要な対策は、行動心理症状の方の混乱や不安の原因を理解することであると言われております。
本市の対策としましては、避難先で御本人が安心できる環境的配慮が行えるよう、日頃からの備え、顔なじみの関係づくり、理解促進のための普及啓発に取り組んでおります。また、災害時におきまして、症状が悪化し、医療機関での治療が必要な場合には、安芸市災害対策本部が高知県保健医療調整支部に患者受入れの要請を行います。さらに、必要に応じて災害派遣精神医療チームの派遣要請を行うこととしております。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) これまでの災害において、高齢者や障害者、乳幼児を支援するための計画など、いつ起こるか分からない緊急事態に平時から備えるべき重要な計画は、被災された現場からの声を生かし、一人一人ができることを見つけることが、地震や自然災害など緊急の混乱を防ぎ、被害を抑えると言われています。誰一人取り残さないための対策、本市においても、過去の教訓を生かし、さらに具体化し、新たなことを発信していただけますようお願いをいたします。
次の質問に移ります。
2、本市のアピアランスケアの実態と取組をお伺いいたします。
がんやがんの治療による外見の変化に対するケアについてお伺いいたします。
がんは現在2人に1人かかると言われていますが、検診の普及や先進の早期発見技術や治療技術が進む中、今は治る病気と言われています。がんが治った人や治療を受けている人も、社会生活を両立しながら暮らせる人はますます増えると思われます。
こうした中で注目されているのは、アピアランスケアです。アピアランスには外見という意味があります。がん患者の方は、手術や抗がん剤、放射線などで体に傷跡が残ったり、皮膚や爪の色が変わったり、脱毛といった外見に変化が生じることがあります。がん患者や家族にとって、治療前とは異なる自分の姿や家族の姿に悩むことも多いと思います。
こうした外見の変化に関する悩みに対して、医学的・心理的に支援するのがアピアランスケアです。そこで本市では、アピアランスケアについてどのような取組がされているのかお伺いをいたします。
○徳久研二議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 本市におきましては、がん検診に関することなどの一般相談に随時対応しております。
アピアランスケアにつきましては、がんの治療、療養生活などの医学的・心理的支援に関する専門相談であることから、がん患者や家族の相談窓口として、がん診療連携拠点病院や県などが設置しているがん相談支援センターへのつなぎを行っております。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 患者の方にとって外見の変化は、職場や学校生活、また通勤・通学においてもストレスは多くなり、子供や若者や女性などへの影響は多いものがあります。アピアランスの変化に悩む市民の心理的苦痛を軽減し、社会への復帰や参加を支援するために、本市で医療用ウィッグ、胸部補整具などの購入費用の助成についても取組をお願いをいたします。
次の質問に移ります。
みどり認定について、本市の取組をお伺いいたします。
みどり食料システム法は、2022年、令和4年7月に施行された法律です。どのような法律なのか、目的や具体的内容、認定制度についてお伺いいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えをいたします。
みどりの認定制度についての概要等の御質問でございますが、国におきまして環境と調和の取れた食料システムの構築に向け、令和3年5月にみどりの食料システム戦略を策定し、中長期的な観点から、調達、生産、加工、流通、消費の各段階における環境負荷低減の取組が推進されているところでございます。
このみどりの食料システム戦略では、農林水産業においてCO2排出ゼロや化学農薬、化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積拡大など、2050年までに目指すべき目標が掲げられており、この戦略を実現するため、令和4年7月にみどりの食料システム法が施行されております。
この法律に基づきまして、国のほうでは、基本方針も示されているところでございます。この法律におきましては、農林水産業の生産者や関連事業者が行う環境負荷低減を図るための活動計画について、国や都道府県が認定する計画認定制度、いわゆるみどり認定制度を設け、環境負荷低減に取り組む生産者や、新技術の提供を行う事業者を支援しているところでございます。
以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 御説明ありがとうございます。
みどり認定を受けるメリットと、本市の取組をお伺いいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 このみどり認定制度には、環境負荷低減に取り組む農林水産業の生産者を対象にした都道府県による認定と、新技術の提供などを通して持続可能な食料生産を支える機械や資材メーカー、支援サービス業者、食品業者などを対象にした国による認定の2通りの認定がございます。
都道府県が認定します農林水産業の生産者において、認定を受けた場合のメリットといたしましては、設備投資の際の所得税や法人税の税制優遇や国庫補助事業の優先採択などの支援が受けられることとなっております。
また、本市での取組といたしましては、現在、JA高知県安芸地区におきまして、市内3か所の集出荷場の将来的な再編統合に向け、具体的な協議・検討が進められておりますが、新施設の整備費用に対する財源として国の有利な財源であります強い農業づくり総合支援交付金が想定されているところでございます。
本交付金の事業採択に当たりましては、みどり認定取得が非常に優位に働くと考えられますことから、集出荷場の再編統合に関しても大きなメリットがあるというふうに考えております。このため、生産者の環境負荷低減の取組を支援するとともに集出荷場再編計画の円滑な進捗に向け、JA高知県ですとか、安芸農業振興センターと連携しながら、生産者によりますみどり認定取得を推進してまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
次の質問に移ります。
お悔やみ窓口の対応についてお伺いをいたします。
本市では、お悔やみ窓口は総合案内所の一角に設けられています。御遺族の心情に寄り添い、丁寧な説明がされていると思います。令和4年12月議会で御遺族の負担軽減を図るために、ワンストップで対応するお悔やみコーナーを設置してはと質問をいたしました。当時担当課よりは、できる限り御遺族の方は座ったままで、職員が移動するよう努めています。今後も御遺族の心情に寄り添い、御負担にならないよう、丁寧かつスムーズに、そして分かりやすく説明に努めてまいりますとの答弁をいただきましたが、設置には至っていません。
昨年9月議会で3番議員からも質問がありました。私のほうにも、その後に市民の方より御要望として伺っております。大切な人を亡くされたばかりの御遺族の状況を少しでも理解した上で、お悔やみコーナーの設置をお考えいただき、市民の方からいただきました御要望を御検討いただきたいと願っております。
そこで、市民のお悔やみ窓口の対応についてお考えをお伺いいたします。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お悔やみ窓口につきましては、一昨年の12月議会で徳広議員、昨年の9月議会に佐藤議員から御質問をいただいておりますが、再度お答えいたします。
1つの窓口に遺族の方が座ったままで、関係する全ての課の手続をすることができるワンストップ窓口については、これまでの答弁でも述べてきましたように、市民保険課、税務課では、複数の係での手続になりますが、御遺族は座ったままで、職員側が移動して対応しております。
ただ、課がまたがれば、関係する課に直接出向いていただいております。その理由としましては、担当課には、業務に精通した職員が在籍をしており、専用の端末で最新の情報を見ながら、より正確なことをお伝えして、手続をしていただけるからです。
1か所の窓口で手続を済ませるワンストップ窓口となると、手続に関する全ての業務、法律などを含めた知識を持った職員が必要になります。また、手続によって手続を取れる人が違うこともあり、窓口に来られた遺族の方1人に全てをお伝えすることができない場合もあります。そういったことから、現在の各課を回っていただくほうがより効率的であると考えます。
現在の方法でも、実際に御不便を感じられた方がいらっしゃったのは、御遺族の心情に応じた対応が十分でなかったと思われますが、手続を1か所の窓口で済ませるワンストップ窓口は、これまでの答弁どおり、現時点では考えておりません。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 御答弁ありがとうございます。
本市独自の取組として、ぜひ考えていただきたくて質問をいたしております。御家族を亡くした市民に寄り添う対応を心がけ、市民の皆様から喜んでいただける市民サービスをと願っております。
他市では、ワンストップでは実現されていないかもしれませんが、県外ではされているところもありますので、御検討をお願いいたします。
最後に、投票用支援カード導入についてお伺いいたします。
期日前や当日投票の投票所においては、声に出すのはちょっとと手助けをためらうような静寂さを感じている方の思いを込めて質問をいたします。
投票所において、投票にお手伝いが必要な方や投票所の係員と意思疎通に不安を感じる方の投票が円滑に行えるよう、誰もが気軽に投票できる環境を整えるために、投票用支援カードの導入している自治体が増えています。本市において、コミュニケーションボードと併せて投票用支援カードを備えてはどうか、お伺いをいたします。
○徳久研二議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
本市では投票の際に、代理投票など支援が必要な方につきましては、投票に来られた際に、御本人または一緒に来られた方からお申し出いただき、対応をしております。その際に、意思表示の方法として、口頭でお申し出いただくか、投票所に置いている支援の内容をイラストで図示したコミュニケーションボードの該当箇所を指で示していただく方法があります。御提案いただいた投票用支援カードは、投票所に来られる方がホームページや市の窓口などで取得した用紙に、必要な支援の内容を御記入いただいてお持ちいただくことで、投票の際の支援を円滑に受けられるようにするものです。
支援の意思表示を複数用意することで、より投票しやすい環境を整えることができる取組だと思います。
選挙管理委員会でも検討をさせていただきます。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
投票率向上に少しでもつながるよう、また、高齢者や障害者の方など、市民が投票の権利を一人でも多く生かせるよう、具体的に進めていただきたいと思っております。
導入検討ありがとうございます。
以上で一般質問を終わります。
○徳久研二議長 以上で、2番徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
応答、答弁者:危機管理課長、市長、健康介護課長、農林課長兼農業委員会事務局長、市民保険課長、選挙管理委員会事務局長
議事の経過
開議 午前10時
○徳久研二議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 通告に従い、一般質問をいたします。
1、災害防災対策について。
1、気象防災アドバイザーの連携による本市の取組について質問いたします。
近年激甚化、頻発化、大規模化する気象災害は、1市町村だけではなく、複数地域にまたがり、いつ訪れるか分からない多発的な自然災害について、平時から高度な知識を有する気象防災アドバイザーを活用しながら備えることは、自治体の防災対策を支援する上で、大変有意義だと言われます。
2020年7月豪雨に見舞われて、熊本県内の被災地では、自治体ごとに対策を講じていく際に、気象台からの気象情報について、気象台OBのアドバイスが役に立ったとの教訓を踏まえ、気象防災アドバイザーとしては、出水期を前に、防災マニュアルの作成や見直し、防災訓練への協力など幅広い活動が想定されており、自治体の防災力を向上させる即戦力として期待をされています。気象台OBも対象に加わり、47都道府県1人以上の配備ができるようですが、気象防災アドバイザーの活動についてお伺いをいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
気象防災アドバイザーとは、気象庁退職者で防災経験のある者や、気象予報士で、気象防災アドバイザー研修を修了した者など、一定の要件を満たす者になります。
気象防災アドバイザーの業務は、まず市町村等の地方公共団体と雇用契約を結び、平時は職員への研修、訓練の企画、運営等の人材育成、地域住民への防災対策の普及啓発を行い、災害時には避難情報発令についての市長、市長への進言、担当職員への気象情報の見通しや解説などを、気象防災の知識を生かした活動をしてもらうものになります。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 次に、本市の気象防災アドバイザーとの連携、また取組と効果をお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
高知地方気象台に問い合わせたところ、現在、高知県内の気象防災アドバイザーは1名しかおらず、その方はふだんの仕事の都合上、兼業ができない方とのことです。
しかしながら、安芸市は平時から県や気象庁による訓練、研修、講演会などにも参加し、災害時の対応も高知地方気象台とホットラインを構築しており、気象台からの防災支援メール、警報発令の事前の情報提供や直接の架電により、安芸市ピンポイントの今後の気象状況の見込みなど、きめ細かい情報をいただいております。
また、台風時などに避難情報を発令する判断に参考とする重要な情報・助言については、気象台長から直接市長にも電話連絡をいただき対応しています。
現状、気象台との連携で対応できているものと認識していますが、気象防災アドバイザーとの連携につきましては、今後、気象台とも相談し、研究していきたいと考えています。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 気象防災アドバイザーとの連携の取組について進めていただけますよう、よろしくお願いをいたします。
2、個別避難計画において、本市の防災トイレについてお伺いをいたします。
地震や台風、豪雨などの災害時には、高齢者や障害者が自ら避難することが困難な避難行動支援者への避難計画において、実際に多くの人が集まる避難所では、いろんな方が避難直後から必要となるトイレに多くの問題が起きてきます。
避難所でのストレスでトイレ問題は上位を占めています。特に、高齢者や障害者の方は、衛生面に対しての不安と敬遠から感染症や病気のリスクが高まり、災害関連死を引き起こす可能性が高まることは、過去の災害時の教訓となっています。
個別避難計画において、本市ではどこまで防災トイレについて考えているのか、どのような計画をされているのかお伺いをいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
避難所における要配慮者への対応として、お答えさせていただきます。
避難所などには105基のポータブルトイレとトイレ用テントを備蓄しています。このうち、個別避難計画を作成している避難行動要支援者の方に対応したトイレの備蓄につきましては、障害者対応トイレは19基、感染症対策として、排せつ物を自動でラッピング処理できる電動トイレは25基の備蓄があります。
また、避難所となる小中学校など9か所には、延べ17基の地下埋設型の大規模仮設トイレを設置しており、大規模仮設トイレ1基当たりに障害者用トイレブースを2台ずつ備えています。
以上となります。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
次に、トイレトレーラーの整備推進についてお伺いをいたします。
災害時、避難所には、自宅を失った人などたくさんの人が避難します。そんな避難所で最も困るトイレ問題が深刻化されています。トイレに並ぶことなく使用するためには、避難者50人につき1台のトイレが必要だと言われています。
トイレトレーラーは、災害時を想定し設計された移動設置型水洗トイレで、個室4室を有し、長期使用時の衛生環境維持に配慮した機能を備え、手洗い台、換気扇など電源においても、屋根に太陽光パネルが設置されるなど、平時においての使用も可能で、イベント会場等にも移動設置し、使用できます。現在の防災対策で備えてほしい必要不可欠な設備だと思っております。
能登半島地震では、高知市のトイレトレーラーが派遣されて利用をされています。助かった命を失わないように、避難生活の衛生的な環境整備のため、各自治体に1台のトイレトレーラーの常備が必要と言われています。
本市において整備推進への所見を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
最近頻繁に報道されておりますこのトイレトレーラーにつきましては、今後、導入に向けて現在検討しているところでございます。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
ユニバーサルデザイントイレのように、車椅子使用者、オストメイト対応の設備、おむつ替えシート、ベビーチェア、子供連れなど、多様な人が利用できるなどの多機能を備えるトイレとともに、災害時だけでなく、多くの人が集まるイベント会場など、平時への設置が望まれております。今後、整備推進をよろしくお願いを申し上げます。
次に、4、福祉防災計画でのBPSD対策についてお伺いいたします。
先日、福祉防災上級コーチによる、みんなで助かるみんなでつくる個別避難計画と題した防災研修会に参加して、東日本大震災、能登半島地震、また過去の豪雨災害の教訓から、最新の防災情報など、福祉防災について視聴でき、発災直後から避難所の避難生活環境において、高齢者や、障害者の問題が多く上がっていることを知りました。
その中で、災害時に在宅認知症の高齢者が、3日以上の避難生活においては環境に適応し切れず、BPSDの発症が原因となり、周囲とトラブルが起き、避難所にとどまれない家族が多く出てしまったと聞きました。
本市では、このような避難生活の問題に、どのような対策を考えているのかお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
まず、私のほうから、避難所運営マニュアルについて、答弁させていただきます。
認知症や精神疾患をお持ちの方に限らず、市内の各避難所単位で策定している避難所運営マニュアルでは、まず、受付の際に、要配慮者の方の把握や生活支援について聞き取りなどを行い、必要に応じて避難所の中での要配慮者スペースへ誘導することとなっています。
また、一般避難所での対応が困難な方については、福祉避難所への避難や受入れの可否を検討することとなっています。以上です。
○徳久研二議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 続きまして、私のほうから、初めにBPSDの内容と、次に対策について答弁させていただきます。
BPSDは行動心理症状のことで、周囲の不適切なケアや身体の不調や不快、ストレスや不安などの心理状態が原因となって現れる症状です。災害時は誰もがストレスや不安にさらされます。精神的な変化として、気分の落ち込み、意欲・食欲の低下、いら立ちなどが見られ、その多くは一時的なもので自然に回復しますが、ストレスが長引くと長期化し、鬱病やパニック発作などの精神疾患の診断がつくこともあります。
議員の御指摘のとおり、とりわけ災害弱者と呼ばれる高齢者などは、災害時の生活に適応することが難しく、ストレスの度合いが高いため、特に配慮が必要で、安心して避難生活を送るための重要な対策は、行動心理症状の方の混乱や不安の原因を理解することであると言われております。
本市の対策としましては、避難先で御本人が安心できる環境的配慮が行えるよう、日頃からの備え、顔なじみの関係づくり、理解促進のための普及啓発に取り組んでおります。また、災害時におきまして、症状が悪化し、医療機関での治療が必要な場合には、安芸市災害対策本部が高知県保健医療調整支部に患者受入れの要請を行います。さらに、必要に応じて災害派遣精神医療チームの派遣要請を行うこととしております。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) これまでの災害において、高齢者や障害者、乳幼児を支援するための計画など、いつ起こるか分からない緊急事態に平時から備えるべき重要な計画は、被災された現場からの声を生かし、一人一人ができることを見つけることが、地震や自然災害など緊急の混乱を防ぎ、被害を抑えると言われています。誰一人取り残さないための対策、本市においても、過去の教訓を生かし、さらに具体化し、新たなことを発信していただけますようお願いをいたします。
次の質問に移ります。
2、本市のアピアランスケアの実態と取組をお伺いいたします。
がんやがんの治療による外見の変化に対するケアについてお伺いいたします。
がんは現在2人に1人かかると言われていますが、検診の普及や先進の早期発見技術や治療技術が進む中、今は治る病気と言われています。がんが治った人や治療を受けている人も、社会生活を両立しながら暮らせる人はますます増えると思われます。
こうした中で注目されているのは、アピアランスケアです。アピアランスには外見という意味があります。がん患者の方は、手術や抗がん剤、放射線などで体に傷跡が残ったり、皮膚や爪の色が変わったり、脱毛といった外見に変化が生じることがあります。がん患者や家族にとって、治療前とは異なる自分の姿や家族の姿に悩むことも多いと思います。
こうした外見の変化に関する悩みに対して、医学的・心理的に支援するのがアピアランスケアです。そこで本市では、アピアランスケアについてどのような取組がされているのかお伺いをいたします。
○徳久研二議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 本市におきましては、がん検診に関することなどの一般相談に随時対応しております。
アピアランスケアにつきましては、がんの治療、療養生活などの医学的・心理的支援に関する専門相談であることから、がん患者や家族の相談窓口として、がん診療連携拠点病院や県などが設置しているがん相談支援センターへのつなぎを行っております。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 患者の方にとって外見の変化は、職場や学校生活、また通勤・通学においてもストレスは多くなり、子供や若者や女性などへの影響は多いものがあります。アピアランスの変化に悩む市民の心理的苦痛を軽減し、社会への復帰や参加を支援するために、本市で医療用ウィッグ、胸部補整具などの購入費用の助成についても取組をお願いをいたします。
次の質問に移ります。
みどり認定について、本市の取組をお伺いいたします。
みどり食料システム法は、2022年、令和4年7月に施行された法律です。どのような法律なのか、目的や具体的内容、認定制度についてお伺いいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えをいたします。
みどりの認定制度についての概要等の御質問でございますが、国におきまして環境と調和の取れた食料システムの構築に向け、令和3年5月にみどりの食料システム戦略を策定し、中長期的な観点から、調達、生産、加工、流通、消費の各段階における環境負荷低減の取組が推進されているところでございます。
このみどりの食料システム戦略では、農林水産業においてCO2排出ゼロや化学農薬、化学肥料の使用量低減、有機農業の取組面積拡大など、2050年までに目指すべき目標が掲げられており、この戦略を実現するため、令和4年7月にみどりの食料システム法が施行されております。
この法律に基づきまして、国のほうでは、基本方針も示されているところでございます。この法律におきましては、農林水産業の生産者や関連事業者が行う環境負荷低減を図るための活動計画について、国や都道府県が認定する計画認定制度、いわゆるみどり認定制度を設け、環境負荷低減に取り組む生産者や、新技術の提供を行う事業者を支援しているところでございます。
以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 御説明ありがとうございます。
みどり認定を受けるメリットと、本市の取組をお伺いいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 このみどり認定制度には、環境負荷低減に取り組む農林水産業の生産者を対象にした都道府県による認定と、新技術の提供などを通して持続可能な食料生産を支える機械や資材メーカー、支援サービス業者、食品業者などを対象にした国による認定の2通りの認定がございます。
都道府県が認定します農林水産業の生産者において、認定を受けた場合のメリットといたしましては、設備投資の際の所得税や法人税の税制優遇や国庫補助事業の優先採択などの支援が受けられることとなっております。
また、本市での取組といたしましては、現在、JA高知県安芸地区におきまして、市内3か所の集出荷場の将来的な再編統合に向け、具体的な協議・検討が進められておりますが、新施設の整備費用に対する財源として国の有利な財源であります強い農業づくり総合支援交付金が想定されているところでございます。
本交付金の事業採択に当たりましては、みどり認定取得が非常に優位に働くと考えられますことから、集出荷場の再編統合に関しても大きなメリットがあるというふうに考えております。このため、生産者の環境負荷低減の取組を支援するとともに集出荷場再編計画の円滑な進捗に向け、JA高知県ですとか、安芸農業振興センターと連携しながら、生産者によりますみどり認定取得を推進してまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
次の質問に移ります。
お悔やみ窓口の対応についてお伺いをいたします。
本市では、お悔やみ窓口は総合案内所の一角に設けられています。御遺族の心情に寄り添い、丁寧な説明がされていると思います。令和4年12月議会で御遺族の負担軽減を図るために、ワンストップで対応するお悔やみコーナーを設置してはと質問をいたしました。当時担当課よりは、できる限り御遺族の方は座ったままで、職員が移動するよう努めています。今後も御遺族の心情に寄り添い、御負担にならないよう、丁寧かつスムーズに、そして分かりやすく説明に努めてまいりますとの答弁をいただきましたが、設置には至っていません。
昨年9月議会で3番議員からも質問がありました。私のほうにも、その後に市民の方より御要望として伺っております。大切な人を亡くされたばかりの御遺族の状況を少しでも理解した上で、お悔やみコーナーの設置をお考えいただき、市民の方からいただきました御要望を御検討いただきたいと願っております。
そこで、市民のお悔やみ窓口の対応についてお考えをお伺いいたします。
○徳久研二議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お悔やみ窓口につきましては、一昨年の12月議会で徳広議員、昨年の9月議会に佐藤議員から御質問をいただいておりますが、再度お答えいたします。
1つの窓口に遺族の方が座ったままで、関係する全ての課の手続をすることができるワンストップ窓口については、これまでの答弁でも述べてきましたように、市民保険課、税務課では、複数の係での手続になりますが、御遺族は座ったままで、職員側が移動して対応しております。
ただ、課がまたがれば、関係する課に直接出向いていただいております。その理由としましては、担当課には、業務に精通した職員が在籍をしており、専用の端末で最新の情報を見ながら、より正確なことをお伝えして、手続をしていただけるからです。
1か所の窓口で手続を済ませるワンストップ窓口となると、手続に関する全ての業務、法律などを含めた知識を持った職員が必要になります。また、手続によって手続を取れる人が違うこともあり、窓口に来られた遺族の方1人に全てをお伝えすることができない場合もあります。そういったことから、現在の各課を回っていただくほうがより効率的であると考えます。
現在の方法でも、実際に御不便を感じられた方がいらっしゃったのは、御遺族の心情に応じた対応が十分でなかったと思われますが、手続を1か所の窓口で済ませるワンストップ窓口は、これまでの答弁どおり、現時点では考えておりません。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 御答弁ありがとうございます。
本市独自の取組として、ぜひ考えていただきたくて質問をいたしております。御家族を亡くした市民に寄り添う対応を心がけ、市民の皆様から喜んでいただける市民サービスをと願っております。
他市では、ワンストップでは実現されていないかもしれませんが、県外ではされているところもありますので、御検討をお願いいたします。
最後に、投票用支援カード導入についてお伺いいたします。
期日前や当日投票の投票所においては、声に出すのはちょっとと手助けをためらうような静寂さを感じている方の思いを込めて質問をいたします。
投票所において、投票にお手伝いが必要な方や投票所の係員と意思疎通に不安を感じる方の投票が円滑に行えるよう、誰もが気軽に投票できる環境を整えるために、投票用支援カードの導入している自治体が増えています。本市において、コミュニケーションボードと併せて投票用支援カードを備えてはどうか、お伺いをいたします。
○徳久研二議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
本市では投票の際に、代理投票など支援が必要な方につきましては、投票に来られた際に、御本人または一緒に来られた方からお申し出いただき、対応をしております。その際に、意思表示の方法として、口頭でお申し出いただくか、投票所に置いている支援の内容をイラストで図示したコミュニケーションボードの該当箇所を指で示していただく方法があります。御提案いただいた投票用支援カードは、投票所に来られる方がホームページや市の窓口などで取得した用紙に、必要な支援の内容を御記入いただいてお持ちいただくことで、投票の際の支援を円滑に受けられるようにするものです。
支援の意思表示を複数用意することで、より投票しやすい環境を整えることができる取組だと思います。
選挙管理委員会でも検討をさせていただきます。以上です。
○徳久研二議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
投票率向上に少しでもつながるよう、また、高齢者や障害者の方など、市民が投票の権利を一人でも多く生かせるよう、具体的に進めていただきたいと思っております。
導入検討ありがとうございます。
以上で一般質問を終わります。
○徳久研二議長 以上で、2番徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
添付ファイル1 一般質問 徳広洋子 (PDFファイル 335KB)