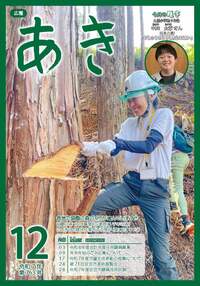議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 小松進也
質疑、質問者:小松進也
応答、答弁者:建設課長、危機管理課長、市長、企画調整課長、農林課長兼農業委員会事務局長、教育次長兼学校教育課長、教育長
○徳久研二議長 以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき、一般質問を行います。
表題は、1、市長の考えはという表題で、だんだんと質問をさせていただきます。
1つ目、道路計画についてお伺いいたします。
今年、石川県能登半島地震、それと宿毛などにも被害をもたらした豊後水道地震など、強い揺れの地震が起きております。安芸市も南海トラフ地震への事前復興として、事前復興まちづくり計画の策定に取り組んでおります。災害が来る前に、できるだけの対策と準備、そして災害後の混乱時から素早く道筋を立て、迅速に復興し、日常生活を取り戻すか、また、日本では地震災害は常に意識が必要ですが、津波災害には対策がありますので、その点も皆様と議論ができればと考え、これから1、2、3と質問をさせていただきます。
それでは、1の1、市道海岸線と中央線の路線拡張の目的と効果をお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
市道海岸線、中央線、両路線とも都市計画法に基づき都市計画決定された道路であり、令和2年3月に策定した安芸市都市計画マスタープランにおいて、産業の活性化や生活利便性の向上、防災ネットワークの形成及び渋滞緩和対策など、新たな地域連携軸となる道路として位置づけされております。
まず、海岸線につきましては、2次防災拠点港となる安芸漁港から沿岸部を通る外縁のルートとして、緊急時の海からの物資輸送や、沿岸部からの避難のための防災対策のネットワークの形成、また、安芸漁港、県立安芸中・高等学校跡地、元気館などを結ぶ海岸ルートとして、市民の健康や観光客のための魅力づくりに資するレクリエーションネットワークの形成を図ります。
次に、中央線につきましては、安芸中インターチェンジからの来訪者を街中へと運ぶ骨格軸であり、産業の活性化を担うネットワークの機能の形成、また県道安芸中インター線と合わせて、中山間地域から統合中学校、市役所、中心市街地を経由し、海岸を直接結ぶルートとして、市民の健康づくり、安全な通勤・通学、分かりやすい観光提供など、市民を支える生活軸となります。
以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。
2番、高規格道路安芸道路供用開始後の市の道路状況はどうなるかをお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
安芸市内で高規格道路が供用開始すれば、南海トラフ地震など大規模災害時の緊急輸送路としての役割や、県中心部へのアクセス性向上、通勤時間の短縮のほか、第3次救急医療機関への救急搬送の速達性、つまり早く到着すること、また、安定性の向上が大きく期待されるところです。
また、国道55号の交通分散が図られ、市内の混雑緩和や交通事故の減少にもつながり、一般道路の交通状況が改善されるものと考えております。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
3番、公共道路が供用開始までに要する参考的な期間、例えば既に完成している区間での参考になるものがあればお教えください。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 供用開始までの期間につきましては、各道路・路線によって、計画規模や地形条件、用地買収の進捗等諸条件が異なるため、一概に何年と申し上げることができませんが、一例としまして、高知南国道路高知インターから高知龍馬空港インター、延長15キロにつきましては、平成2年度に事業化され、暫定2車線で供用開始した令和2年度までの約30年間、また、南国安芸道路香南のいちから芸西西インター延長9キロにつきましては、平成12年度に事業化され、平成22から25年度までの約14年間となっております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
4番、市道海岸線と中央線の供用開始までの大まかな事業予定、工程ですよね、と事業の概算をお教えください。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 まず、海岸線につきましては、令和5年度から6年度で測量設計を実施しており、6年度から7年度にかけて用地補償調査、8年度から10年度に用地補償・交渉・契約、9年度から12年度にかけて工事を実施する計画とし、総事業費約10億円を見込んでおります。
次に、中央線につきましては、令和7年度から11年度の間に事業に着手する計画としており、測量設計で1年程度、用地補償調査で1年程度、用地補償・交渉・契約で3年程度、工事で2年程度、合計7か年、総事業費約5億円を見込んでおります。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) すみません、もうちょっとお聞きしたいんですけど、僕がちょっと聞き抜かったかもしれないので、その市道海岸線で既に測量が入ってまして、12年までなので12年間の10億円、中央線が7か年で5億円ということでよろしいでしょうか。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
海岸線は令和5年度から事業着手しておりますので、令和5年度から令和12年度までの8か年で10億円というふうに見込んでおります。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
次に、津波避難の考えと津波避難についての道路網状況と認識を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
津波避難の考えは、基本的には、素早く、高く、そして遠くです。
次に、津波避難についての道路状況と認識についてですが、安芸市地域防災計画地震対策編では、避難路には補助幹線道路、通学路や、中心地区への主要道路を位置づけるとしており、国道、県道、市道などの安芸市内の道路を災害対策基本法でいうところの避難路として考えています。また、各地区で実際に避難する経路は、地区住民が現地確認や話合いにより決めており、安芸市津波避難計画の関連計画である各地区の地域津波避難計画及び各自主防災会で作成した地区の津波ハザードマップに掲載しています。以上であります。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私のほうからもお答えさせていただきます。
先ほど議員のほうから市道海岸線と中央線の供用開始につきまして御質問が出ておりますが、私もこの海岸線と中央線は避難路としても非常に重要となるというふうに考えております。できるだけ早期、用地交渉等もスムーズに行って早期供用を開始できればというふうに考えております。
あと、津波避難路としての認識ということでございますが、ちょっと大き過ぎて明確かどうか分かりませんが、各地区で実際に避難する経路は古い木造住宅やブロック塀など、地震により倒壊の危険性があり、通行に注意する必要がある道路など、生活者だからこそ知っている危険箇所の情報を集約するなど、実態に即した避難路が重要であるというふうに考えております。
以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
市長も言われましたし、危機管理課の課長も言われましたように、それぞれその認識を基に次の6番の質問に入らせていただきますけど、市道海岸線事業を優先した理由を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 市道海岸線の優先した理由という御質問ですけれども、先ほどの答弁でも少し触れましたが、海岸線、中央線ともに安芸市都市計画マスタープランにおいて産業、観光、交通、防災等のネットワークを形成し、まちづくりを進める上で重要な路線として位置づけしており、市内全域の市道整備の中でも、両路線については、特に優先度が高い路線として認識しております。
現在実施している市道海岸線の整備につきましては、沿岸ルートの形成により、市中心部の渋滞緩和や地域交通の利便性の向上を図るため、当初段階より球場前につながる西工区の完了した後、引き続き元気館から安芸橋西詰までの東工区に着手する計画としていましたことから、令和5年度より本線に着手したものであります。以上です。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど、建設課長が全てちょっと答弁していただきましたので、もう建設課長の言うとおりでございます。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 御答弁ありがとうございました
私のちょっと思いでお話しさせていただくと、私としては市民の日常生活や現状の交通状況なども考えながら、災害の津波避難などのことをまず考えてですね、いまだ多くの市民の方が津波浸水地域内には住んでいらっしゃいまして、また、そこでなりわいも行っております。
ですから、津波浸水区域外への市民の命を逃がす避難道路の整備として、市道中道線の整備を先に行う必要があったのではないかと考えております。
市道海岸線を先行して整備をする場合の国道バイパス機能を持たす場合でもですね、渋滞の原因であります安芸橋西交差点の改修と、また安芸川及び江ノ川の治水工事も考えて、安芸川河口の右岸側から上流に向けて堤防道路を築く計画を持って、市道海岸線を選びます。それはまた、何回も工事をすると、工事期間や予算が多くかかりまして、また、御協力をいただく近隣の住民の方にも工事での御不便を何回もかけることになりますので、そういった点も考えて整備を進めていくと思います。
また、避難は基本的に徒歩でございますが、南北の道路状況がよくなれば、避難を諦めている高齢者の方や、身体が不自由な方などにも有効な避難ができる、車での避難ができると考えております。車での避難は、ここ最近、その後の避難生活にも、車の車中泊や避難後の物資の運送、また、けが人の搬送等にも大きな力を発揮するところだと私は考えております。
あと、都市計画当初とまちの状況や環境も刻々と変化する中で、再度計画実行の見直しも必要ではないかと考えるところではあります。しかし、幸いに市道中央線は後れを取りましたが、市道の道路避難の対応や、大きな幅員を取れる道路検討がこれからできると考えておりますので、その辺は、市としても徒歩だけではなく車を使った避難ができるような道の検討もしていただいて、着手していっていただければと思っております。
では、次の質問に入ります。
次、津波避難計画指定緊急避難場所についてお伺いいたします。
1、安芸第一小学校と某商業施設の避難者収容人数、例えば、安芸市の施設や他の公共施設、また、避難場所に指定されている民間施設をお伺いいたします。
○徳久研二議長 昼食のため休憩いたします。
午後1時再開いたします。
休憩 午後0時
再開 午後0時59分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 質問にお答えします。
指定緊急避難場所である安芸第一小学校屋上の収容人数は829人、近隣の商業施設は1,900人です。
また、安芸第一小学校周辺には、ほかにも2か所の津波避難ビルがあり、県立安芸中・高等学校の清和校舎の屋上に809人、NTT西日本安芸電話交換所ビルの屋上などに428人が収容可能です。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
次の2番、安芸第一小学校や某商業施設を避難場所とする対象地区及び世帯、それと避難者数をお聞きいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 安芸第一小学校屋上及び近隣の商業施設を利用する避難対象地域は、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、久世町、寿町、庄之芝町、清和町の8地区を主に想定しています。
対象地区8地区の世帯数と避難者数との御質問ですが、市内全域の避難想定はございますが、津波浸水区域内に限定した避難想定はございませんので、避難者数に関しては、地区内住民の避難者数が最大となる地区内の人口でお答えさせていただきます。
令和4年11月に改定した安芸市津波避難計画にある令和4年10月末現在の数では、8地区における世帯数及び人口は855世帯、1,576人です。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。ありがとうございます。
安芸第一小学校の屋上で避難できる人が829人で、商業施設が1,900人、某通信施設の屋上が428人、それと安芸中・高の清和の北舎で809人で、今回避難、そこの人口になるんですけど、人口が計855人ということで、第一小学校。
(「世帯」と呼ぶ者あり)
○5 番(小松進也議員) ごめんなさい、855世帯。人数としたら延べ1,576人、令和4年度の調べによるとですんで、安芸第一小学校のみではカバーできない人数ということで、次の質問に入らせていただきたいと思います。
安芸第一小学校や周辺の緊急避難場所が、移転などで機能しない場合の計画や避難空間の必要性を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 安芸第一小学校や小学校周辺の津波避難ビルが何らかの理由で移転等で使えなくなった場合の避難空間の整備ということでございますが、いろんなパターンがあるんですが、まず、安芸第一小学校の移転方向が決まれば、当然、避難施設等を念頭に置いた跡地活用を検討していくことになります。
また、安芸第一小学校の移転方向は決定し、近隣の避難ビルが何らかの理由で使えなくなった場合も、同じく避難施設等を念頭に置いた跡地活用を検討していくことになります。
そして、近隣の避難ビルが、これもまた何らかの理由で使えなくなった場合、近隣に例えば津波避難タワーとかそういう施設を整備する必要があるというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 第一小学校は小学校の移転統合で市としては2校、安芸第一小学校に対しては津波浸水、L2ですね、L2の津波浸水が想定できるので、安芸第一小学校の現地での建て替えはしないという発言があったと思うんですけど、となると第一小学校では基本的には、そこでの小学校の運営がないので建物としては残す可能性、地域の人の避難場所としては重要なので、残す方向で検討するなりはしていただきたいとは思うんですけど、それからまた、代替品の避難ができる施設ですが、その場合には必ず1,576人を救える、もしくはそこに交流人口の方もいらっしゃるので、その1,576人のみというわけにはいかないので、それを上回った避難施設が要ると思います。
先ほども市長のお話の中で、避難タワーなどのことも検討すると、しかしながら民間の施設に対しては、やはりお願いと御協力の下ってなっておりますので、安芸市からこうしてください、ああしてくださいというのは難しくて、そこの場所で常にいてくださいということも言えませんので、ある程度公的な取組というか、支援なり公的なものが必要だとは思っております。
先ほどの1番の質問の中でもあったんですけど、中央線、市道中央線の話なんですけど、そこを避難のために、例えば民間施設なり、安芸第一小学校が800そこそこしかできないので、やはり空間を、避難空間を確保できるのは現時点は難しいので、道路を早急にやっていただきたいと。その辺、市道中央線の着工予定とかっていうのは決まっているんでしょうか。
それと、徒歩避難でなく、車での避難についてのこれからの認識もお伺いしたいです。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
市道中央線の着工時期につきましては、先ほどの答弁でもございましたけれども、令和7年度から11年度の間でですね、他の事業等の進捗を見ながら、その間に着手すると。
(「7か8」と呼ぶ者あり)
○近藤雅彦建設課長 7から11年度の間ということですので、何年度というのはまだ現状ではよう決めておりませんけれども、その間に着手するという計画で進めております。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 今はやっぱり原則徒歩避難、これでやっていただこうという考えではおりまして、また、やはり車の移動になれば車が行きよって、どっかで通れなくなった場合、例えば道路が、何でしょう、崩落というか崩壊というか、なって進めなくなった場合に、やっぱり道路がどうしても通行できなくなる状況もあるかと思われますので、現状ではやっぱり原則徒歩避難を推奨したいところです。
ただ、今後いろいろな地震の検証とかもまた出てくるかと思いますので、それで、また改めて国なりから改められた検証結果とかが示されるようであったら、また研究・検討していきたいなとは考えています。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
第一小学校付近に1,576名の方がいらっしゃいますので、基本その方が逃げられるような環境整備と避難ができる施設の確保は、現時点では非常に重要だと思いますので、その辺は再度見直していただいて確認をしていただきたいと思います。
では、次の質問に入りたいと思うんですけど、津波浸水地域の事前復興を問うということで、津波浸水地域の、地域ですね、地域の世帯数と避難者数をお教えください。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
先ほどの答弁でも触れましたが、津波浸水区域内に限定した避難想定はございませんので、避難者数に関しては、区域内の住民の避難者数が最大となる地区内の人口でお答えさせてもらいます。
安芸市津波避難計画では、5,658世帯、1万1,312人を想定しています。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 避難者数というくくりはないと、明確なくくりはないとしても、そこの避難、ごめんなさい、津波浸水地域としてでお住まいの方の人口は1万1,312名ということですね。はい、ありがとうございます。
続きまして、津波浸水地域内の家屋の耐震化率及び未耐震化数をお伺いいたします。
ですが、昨日での全体でも89.7%っていうのは聞きましたので、地域でもし分かればお教えください。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 津波浸水区域内に限定した数字というものは、やはりこれに関しても持ってなくて、やっぱり市全域のお話で、先日9番議員の御質問にも答弁させていただいたとおりとなります。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。
そしたら、ごめんなさい、その地域の、先ほどちょっと僕人数は書けたんですけど、そこにいらっしゃった世帯数、すみません、合計幾らかもう一度お願いします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 避難の想定世帯数ですね。5,658世帯です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。ありがとうございました。
津波避難地域での世帯数は5,658世帯ということで、ありがとうございます。
では、次に、津波浸水地域の家屋の耐震化の計画等支援策をお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
耐震化の計画も浸水区域内に限定せず、安芸市全域を対象にした安芸市住宅耐震改修促進計画第2期を令和2年10月に策定しています。
この計画では、令和7年度末までに安芸市全域における住宅耐震化率を94%に上げていく目標を掲げ、戸別訪問などによる啓発も行っているところです。
支援策としては、昭和56年5月31日以前に建てた住宅を対象とした安芸市住宅耐震改修費等補助金があり、耐震診断は、木造住宅の場合は無料で行え、非木造住宅の場合は最大4万2,000円の補助金の交付を受けることができます。また、耐震設計は最大33万円の補助金、失礼しました。耐震改修工事は今年度から最大165万円の補助金の交付を受けることができます。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたのは、僕の質問が津波浸水地域内ということですけど、津波浸水地域内に限定したものはなくて全体としてありますよと。それと約33万円と165万円で200万円、198万円ぐらいの支援策があると、これは津波というか耐震ですよね、耐震でまず倒壊をしない建物で、倒壊しなければ、その後逃げれるとか、そういう観点で幅広く耐震を推奨してやっていただいているというところだと思います。
では、次の4番、南海トラフ地震の被災後の応急仮設住宅及び災害公営住宅の計画をお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
南海トラフ地震応急機能配置計画では、仮設住宅用地及び災害公営住宅用地に関して、仮設住宅の最大必要戸数を3,458戸としていますが、現状2,280戸分の用地が不足しており、用地の確保には苦慮しているところです。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 2,280戸分の用地は不足していると。
これ去年の質問でもお伺いいただいて、この数字が変わって今ないんですけど、ほかの議員さんの方とかもされて、この数字が常に出てくるんですけど。
それで、20日間以内に応急仮設住宅を着工して建てるような計画をしてくださいっていうことで、シミュレーションなども考えていただければという話で、副市長が議員御指摘のことにつきましても十分考慮して計画を立てていきますというお話でした。
2,280戸の今不足分があるんですけど、これどういうふうにこれから対応していかれますか。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
3月議会のときに、9番議員の質問への答弁としてお答えさせていただいた内容と重複しますけど、結局、引き続き啓発もしながら取り組んでいきたいというベースはありまして、また、あわせて、例えば仮設住宅、今、平野の何です、平家建てを想定しちゅうものがあるのですが、この仮設住宅を重ねて2階建て化するなど、少ない面積でも建てていくことが可能なような方向性について、県のほうとちょっと相談し検討しゆうところです。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 3月の御質問の後の進捗状況はありますか。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 進捗と言えるか分かりませんが、防災フェスタの会場に、県のCLT工法の仮設住宅が展示されていたのです。そのときに県の担当者の方、多分木材産業課の方やと思いますが、その方が現場で説明してくれよったがでちょっと聞いてみたのです。この県が推奨するCLTの仮設住宅でも2階建てが可能か、そういう話を聞いたら、その現場では可能という答えもいただいておりますので、仮設住宅の2階建て、2階化っていうのは比較的簡単なものかという手応えというか、そういう思いは持ってます。
また、ほんで今後も、それはまた県の住宅課などともちょっと相談していきたいと考えています。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) そうなるとですね、3,458棟の応急仮設住宅が必要で、そのうちに、ごめんなさい、1,178世帯の建てるスペースがあるということは、単純に2階建てにすると2,400ぐらいはできるということで、それはもう断言というか確認できるということなんですか。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 この時点で、その確約ということはちょっとはっきり申し上げることはできません。ちょっと県のほうともやっぱり相談していって、はっきりできるっていうことであったらですよね、またそこはそれで話したいと、公表していきたいとは考えています。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。次、ありがとうございます。
5番、安芸市の被災後の人口流出等の想定数をお聞きいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
能登半島地震による被災自治体からの人口流出は報道などで見聞きしていますが、南海トラフ地震による被災後の人口流出などを想定し、数字として示せるものは現状ございません。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 数字としてはないということですね。分かりました。ありがとうございます。
そしたら、私のほうから、2024年の5月9日の記事で、人口流出が3.8倍、2024年元旦の激震で大きな被災を受けた石川県の奥能登4市町村で人口の流出が急速に進んでいる。人口約6万人弱の4市町村で、1月から3月の転出超過は月を追うごとに増え、計1,582名、前年同期の3.8倍だ。ごめんなさい。再び人が戻りコミュニケーションを再生維持することができるのか。復興は時間との勝負である。また、西日本大震災で、全壊被害に遭った住宅の新築費用が平均約2,500万円で、それに対して、公的災害者生活再建支援金などとした受給できるのは、善意による義援金約100万円を合わせても約400万円にとどまる。これだけでなく、家具の引っ越しなど、生活の再建にはほかにもお金はかかるという記事がありました。このようにですね、なかなか難しい現状があります。
それで、先ほどの復興のための仮設住宅などの話もあったんですけど、やはり若い人ほど働く場所が必要なので、多くの方が場所がなければ、若い人ほど流出していきます。また、先ほど住む住宅の確保が1つ大きな鍵があるので、先ほどもお聞かせいただきました。また、中小企業の支援、これによって働く場が確保できるので、そういった手続の簡素化もなかなか進まない中で、早期の支援を行政としてはやる必要があると思っております。
そして、インフラの復旧が、やはり行政としては大事なところがあってですね、ここをいかに回復するか。それで事前の復興も計画をしておくか、災害に遭わないようにしておくかっていうのが非常に重要だと思っております。
これ全て今からお聞きするわけにはいきませんが、次の被災後の人口流出の問題についての考えと対策を市長、お伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議員御指摘のとおり、被災後の人口流出は地域の復興と再生における大きな課題でございます。地震などの自然災害が発生すると、多くの住民が安全な場所へ避難し、その後も元の地域に戻らないことが見られ、地域社会や経済に深刻な影響を与えております。
被災後の人口流出を防ぐ対策といいますか、具体的にこの場でちょっと明確にようお答えできないんですが、やはり現在、取り組んでおります事前復興まちづくり計画の策定で、より具体的なものが必要であるというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
事前復興まちづくり計画も非常に重要だと思います。それを羅針盤にしていただいて、市民に周知しておけば、だけでいいのかっていいますと、そういうわけには多分いかないと思います。やはり、事前の物質的な取組も必要だと思います。
津波浸水や川の氾濫などで一定災害がある予測できる場所ですよね。そういった場所は初めから住まなければ、被災後の避難所での避難生活や仮設住宅での生活などはもちろん、予測でき得る災害には遭う確率は極めて低くなります。命も財産も救えて守れる、災害後の人口流出、災害支援及び復興作業にも大きなメリットはあると考えますが、市長はどうでしょうか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議員のおっしゃるとおりなんですが、住み慣れた地域から移転していくということは、やはりそこで住んでる方、住民の方が第一になりますので、当然最初に議員が言われたとおりなんですが、そこはこれからの事前復興ではなくて、その前段での集団移転とかいろんな課題もございますが、そういう部分も踏まえて検討していかなあかんかなというふうには考えております。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
後の質問でもいろいろ出てくるんですけど、別に、何というんですかね、強制的にそこの土地を奪って生活を奪うわけではなくてですね、希望される方とかできる方法もあると思うので、そういったことも踏まえて、次の質問に入っていきたいと思うんですけど、7番の防災集団移転促進事業について、実施検討について、市長はどう思われますか。
この質問を書いた後に某新聞の記事にですね、須崎市が住宅向け高台整備、庁舎に推進チームと、要は高台への事前の補助金制度などを検討しながら、どういうふうにしたらいいかっていうチームを立ち上げております。その辺も、市長も須崎の市長とは懇意にされてると思うので、その辺の情報もあればお伺いしたいと思います。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 南海トラフ地震対策として1つの手段として考えられる、議員の質問にもあった防災集団移転促進事業については、現制度の補助対象要件が、津波災害特別警戒区域のオレンジゾーン、もしくはレッドゾーンが対象となっており、安芸市の沿岸部は、津波災害警戒区域のイエローゾーンであるため、制度を利用することは現時点では難しいものと思われます。
ただ、今後、要件緩和等があれば、対策の手段として研究していきたいと考えています。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 須崎市の情報ということでございますが、ちょっと私のほうは詳細については須崎市長からちょっとようお聞きしてないんで、今回、今度会いますので、またその時点でどういう内容かいうのもちょっと確認をしてみたいなというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
先ほどのイエローの地域があってですね、その方たちがもし5世帯集まればレッドゾーンにしてですよね、していただいて、避難できることもできますので、よくまた検討していただきたいと思います。
今大きくまちが変わる部分なので、昨日の議員さんの答弁、答弁というか質問というか発言の中にもあったんですけど、歴史は将来ですね、の方が判定しますので、そこに今いる私たちがどれだけ後世の方に、あのときの判断が正しかったのかっていうところも検証は今できませんが、そういうところを見据えながらしていただきたいと思います。
確かに今生きている私たちの命も財産も大事ではありますが、やはり安芸市をどう残していくか、命をどうつないでいくかっていうところの観点もありますので、議論としてはパワハラ、今ハラスメントの話とかもいろいろありますけど、議論はやはり同じ方向ないし大きく方向が同じであれば、発言ですよね、発言で、この言葉が今誰に向かって言ってるわけでもないですけど、あほとかばかとかっていう話ではなくて、例えばそれが議論する場では、ハラスメントを恐れて発言できないのは議論になりませんので、今言ってるのは、例えば、女性蔑視とか責任を押しつけるとかっていう話でなくて、やっぱり議論するところでは、ある程度勘違いというか変な方向に取られる場合もありますけど、議論としては言える環境はつくっていくべきだと思いますので、そういうことも考えて、またちょっとその点も考えていただきたいと思います。
そしてですね、ちょっと僕、楽観的かもしれませんけど、ちょっとお話しさせていただくと、津波診断にて耐震がないことが分かった場合ですよね、先ほどお話があった補助金を使ってですね、耐震をすると思うんですけど、津波浸水地域内で住宅を耐震改修する場合ですよね、耐震がないという判断で、その場合、住宅耐震費等の補助は利用できますが、これを機に、津波浸水区域外ですよね、外へ新築を建築した場合は、補助金は利用することができません。耐震をして、危険な場所で住むためには支援は受けられても、危険な場所から移転し安全な場所で住むには支援がない。これって何かおかしくないでしょうか。
津波浸水地域に税金で避難タワーを建設しても、避難浸水はします。安全ではありません。じゃあなぜ建てるのでしょうか。一時的な避難場所であり、いつ来るか分からない地震による津波へのすぐにできる応急処置であり、建てるときには有利な国等の支援がありますが、管理や建て替えのときは、安芸市独自の費用が捻出されるのではないでしょうか。津波浸水地域に公共施設を建てても、将来にその場所での必要性はあるのでしょうか。
また、津波浸水地域に公共の施設を建設する場合は、津波対策や、避難対策と、備蓄品などの管理、維持及び対策の費用や、施設建設費に津波からの安全を守るための特殊建設費用が大きな負担となります。また、津波災害後の応急仮設住宅や災害公営住宅、公営復興住宅などの建設予定地の確保はできているのでしょうか。安芸市の財源で、予定地確保や住宅の確保はできるのでしょうか。ましてや津波浸水地域に住んでいる全ての市民をどう避難させ、被災後も安芸市に住んでいただくことはできるのでしょうか。
その点について、次の質問をさせていただきます。
災害予測地域外への住宅建て替え及び未耐震化住宅の災害予測地域外への住宅建て替えや災害予測地域外への空き家利用への検討とその支援策ですね、を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 先ほど議員から御提案していただいた住宅支援策は、現在、安芸市が抱えている被災時の課題の解消につながるものと思われ、今後研究・検討したい提案だと考えます。
しかしながら、住宅移転等の支援に関して、防災集団移転促進事業など、国などの現行の支援制度の利用が難しい状況の中、市の財源だけで助成するのは困難な面もあるものとやはり思われますので、国に提案できる支援制度の創設や拡充について、県と協議をしていき、実現の可能性を模索したいと考えます。以上です。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 まず、災害予測地域、津波浸水想定区域という意味。災害、まさにちょっと災害、トータルの災害じゃなくて、そのまま浸水ということでしょうか。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 質問を受けます。
先ほどお話しした、災害予測地域っていうのは、そういう言葉があるかないかはちょっと分からないんですけど、僕が思うにはですね、津波浸水区域も災害が起きる地域です。それとか、津波浸水地域外のところでも崖があったり、例えば川の氾濫がある地域とか、そういうところも危険でありますので、そういう方も安全なところに移っていただければ、その後の被災を受けることもないですし、命も助かりますし、津波浸水地域以外の場合で危険な箇所には、基本的には住んでいただかないほうがいいのではないかなということで、発言させていただきました。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど議員がおっしゃった災害予測地域外、安芸市で予測地域外というのはどれぐらいあるのかいうところは、ちょっと私も存じ上げてないんで、それについてはちょっとなかなか答弁しにくいんですが、津波浸水想定区域という意味でいえば、当然先ほど議員がおっしゃられたとおりなんですが、全ての市民が、南海トラフであれば、その発生後全ての市民が流出しないようにというのは、当然行政としてはそれに努めていかなくてはならないのが行政の責務だと思っております。
そのために、どういう事業ができるかとなると、財源がどうしても問題になってくるんで、その財源については、やはり国、安芸市だけじゃないと思うんで、当然。安芸市だけじゃないんで、国のほうへもそういう支援制度の創設とか、拡充、これはもう県下、高知県であれば県下の市町村でちょっと協議をしながら、こういう細かい部分は国へ提案・要望していかなければならないかなというふうに考えております。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 予算の話がいつも出てくるので、その辺は国、県に要望していただいて、逆に独自でやろうとすれば、今行っている政策の中で地区引いて違うところに当てるとか、単純にさっき198万円という補助金があるので、これだけを受けられるようになっても多分建て替えする方にとってはありがたいと思います。ただで、ごめんなさい。建て替えした場合でも、お金が入れない、頂けないよりかは、少しでも足しにはなりますので、国、県、安芸市とで計画してやっていただけたら非常にありがたいです。それと要望もしていただきたいと思います。
その中で、また少しお話ししたいんですけど、これ先ほどのお話の中に2,500万円全て出せっていう話ではなくて、行政の支援が呼び水になってですね、住民の力、また民間の協力を得て、安全な地域で住んでいただく取組をするのが、市民の命、財産、人口定住、経済の発展にもなるのではないかと考えてお話ししました。
また、移住や新生活を始めるにも、津波浸水地域内しかその場所がないでは、安芸市に住みたいっていう方は少なくなると思います。そういうところに、また投資も、企業はしないと思います。人口がどんどん少なくなる将来に、津波被害があるまちで投資をしてどれぐらいの回収ができるかっていうのが民間の一つのポイントではあると思います。
ですので、住宅だけでなく店舗、例えば店舗というか共同住宅ですよね。安芸市が市営住宅を建てれば、財政的に新築を建てることが難しい方でも市営住宅に入れると思うんですけど、やはりその辺も共同住宅を民間の力を使っていただいて、建てていただくとか、それによって、市営住宅の代替として建設コストの支援をした場合に、支援をいただいた共同住宅は、その分の家賃の安価な金額でお貸しするとか、そういう話を進めていくと建物もできるし雇用も生まれると思いますので。また、その国等に進言する場合であれば、民間の力を共同住宅での建設のやり方等もちょっと念頭に入れてしていただきたいと思います。
それでは、次の質問に入ります。
4番、地域課題についてお伺いする前に、この地域課題の問題、題名の地域おこし協力隊の5番と6番の高知県人口減少対策総合交付金の順番を、入れ替えて質問させていただきます。
安芸市の人口推移ですが、社人研がですね、2060年には安芸市の人口が8,176人まで減少するという予想を出しております。安芸市の2060年の展望は、安芸市総合計画などにも書いておりますが、2060年の展望は1万4,000人であります。ですが、安芸市総合計画後期計画にも書いてますが、来年度、令和7年に安芸市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、将来展望を1万6,907人というふうに書いておりますが、昨日ホームページで見ますと、安芸市の総人口は1万5,764人、もう既に1,200人は早く減少しております。非常に悲しいことです。
次の質問に入っていきたいと思います。
1番、若年層の転出や流出理由と対策をお聞きいたします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
転出手続の際に御協力いただいておりますアンケート調査の結果によりますと、本市では20代の転出者が最も多く、次いで30代となっており、年度によっても異なりますが、10代から30代までで、全体の約80%を占めております。最も多い転出の理由といたしましては、就業・転勤で、次いで結婚や県外への進学によるものとなっております。
次に、対策でございますけれども、就業や転勤に対して転出抑制につながる対策といたしましては、企業誘致による雇用の確保やテレワークなどが可能となるよう、ビジネススキルを学ぶセミナーの開催、また、住まいの確保や企業支援のために空き家・空き店舗のストックと補助金制度の充実に努めております。
結婚や進学に対しましては、結婚新生活への引っ越し費用や家賃支援、県外への進学に対しては、転出抑制ではないですがUターン促進として、奨学金返還支援制度の充実、県内の進学に対しては、無料塾の開講や18歳までの医療費無償化などの支援制度をそろえ、転出抑制や定住策に取り組んでいるところでございます。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
いろいろな対策をしていただいて、目標値を何とか死守するために日夜努力はしていただいていると思います。
質問は、別に行政の方々がやってないっていう話を全然する気はないので、私たちが将来の安芸市のことを考えて、どういうふうな議論がこれからできるかっていうことで話していきたいと思います。
ですが、やっぱり流出に一番大事なところは20代、30代の80%の方、ここを抑制するという言葉がどうか分からないですけど、できるだけ安芸市に住んでいただく、安芸市から仕事をしていただくとか、いろんな理由があると思うんですけど、どういうふうに安芸市に関わっていただくかを考えたいと思います。
次の2番、消滅可能性自治体とされて、市長の考えと独自施策の進め方っていうところを聞きたいんですけど、昨日質問が、同じような質問で同じ答弁されてましたので、これに対してはその答弁を聞いてですね、僕の意見を少しお話ししたいと思います。
この消滅可能性自治体っていう話を聞いたときに、多分市長も自治体とされて非常に悲しいと思うんですけど、このされてる中でも改善されてるところもありますので、二十何市はあるので、安芸市もこれを機に改善できればと思っております。
そして、また20代から30代の女性の方ですよね、対象、これ。その方たちはもう本当当事者なのでもっとつらいとは思っております。昨日も少子化対策は、もちろん国が前面に立ってやる必要があるんですけど、しかしながら住むですよね、居住ですよね。居住についてはなかなか需要がありますので、若年層の女性や若い人が流出、離れることについては、別の要因があるのではないかと思っております。
先ほども進学ややりたい仕事がない、押しつけなどのいろいろな原因があると、私も思っておりますし、まだまだ自治体もできることはあると思います。人に行動変容を促すときは、不安、あと希望で誘導されます。女性の自己実現、楽しい生活を応援する自治体になれば男性も必然的に残る。まず、逆はなかなか難しいと思いますね。これ僕の意見ですので。
また、安芸市は消滅自治体とされたのを機に、全ての女性を応援し、働く、学ぶ、遊ぶ、暮らす、楽しみを、今まで以上に応援することができると思いますので、応援すればいいと思います。今の市の政策が若者層の考えと合っていないのでは、また、結婚もしかり、国・メディアなどの結婚や人口減少などの表現や言葉などの誘導表現で、本当のことが見えなかったりしてると思います。ミスリードしてると思います。本当は乖離があるのではないか。若者層に気軽に聞ける環境で本質と対策が見えるのではないでしょうか。もっと若年層と女性、男性に気軽に話せる場をつくっていただきたいと思います。
ここは、僕のもう感想だけになりますので、今までは人口がどんどん増えていく中での行政運営だったんですけど、今はどんどんどんどん人口が減っていく中での行政運営ですので、そこは今まで多分皆さん体験したことがないところもありますので、今までの政策が本当に正しいのか、その辺は立ち止まって検証する必要もあると思います。
では、次の3番、東京一極集中というが高知市一極集中を市長はどうお考えですか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 東京圏一極集中は、地方からの人口吸引力が強い一方、その圏域の出生率が低いことに問題があります。
本県でも県内人口の約半数が高知市に集中する一極集中型の都市構造となっておりますが、総合病院や中学校、高校、企業や観光機能など、政策誘導により県内バランスを意識した配置がされているように思っております。
こうした取組が結果に結びついているのかは分かりませんが、令和4年度の出生率は高知市も安芸市も同じ1.31、高知県全体でも1.36と大きな乖離はないことから、高知市一極集中は東京圏のようなブラックホール型ではないものというふうに認識をしております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) そしたら認識の中で、4番のれんけいこうち広域都市圏の所見と、これを使った対策などはありますか。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
れんけいこうち広域都市圏は、2018年以降、高知市を中心とした県内33市町村が連携協定の下、地域の活性化及び人口減少の克服に向け取り組んでおります。
本市におきましても、各分野において高知市等と連携し、様々な事業を実施しておりまして、新規就農者の確保に向けた就農相談会への参加や、今年度から新たに開設されます、れんけいこうち専用観光ウェブサイトによるプロモーションへの参加などに関わっているところです。
いろいろ取組しておりまして、2段階移住というようなお言葉もよく聞いたことがあると思いますけど、こうした取組も、高知市と連携してやっておりまして移住実績も出ているところでございます。
さらには、インバウンドの観光についてもですね、大型客船などを誘致してですね、そこからの展開が、まだまだ波及されてない部分がありますので、こういった部分をこれから広げていくというふうにも聞いております。
このように安芸市単独ではですね、なかなか取組効果が低いものとか、知名度の高い高知市との連携とでなければできない仕組み、こういうのは、れんけいこうちでなければ実現できなかったものというふうに認識しておりますので、今後もこの連携をうまく活用して、高い効果が得られるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後1時56分
再開 午後2時3分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます
次、6番改めて5番にいたしました。高知県人口減少対策総合交付金事業の所見とその取組についてお聞きいたします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
県が新設いたしましたこの交付金は、若年人口の減少に歯止めをかけ、持続可能な人口構造への転換を図ることを目的に、市町村の人口減少対策の取組に対して、県が伴走支援を行いながら総合的に支援を行う取組でございまして、これまで財源がなかった市単独事業においても拡充した中で対象とされるものもございますので、取組が強化されるというふうな認識でございます。
今年度、当該交付金を活用した取組については、まず少子化対策として出会い・結婚分野を強化するため、コンシェルジュを2名に増員配置し、男女の出会いイベントの開催数の増加や連絡先を交換し合った方同士のきめ細かいフォローアップなど取組を進めております。
子育て支援策といたしましては、ファミリーサポートセンター事業や高校生までの子ども医療費助成、保育士の加配も交付金の対象として実施をしております。
今後は利用者と市民ニーズと、現状の問題点とのギャップ解消となるよう取組を変化させながら、交付金を活用してまいりたいと考えております。
次に、移住施策や女性人材確保については、起業による移住定住を図るため、空き店舗対策確保事業やテレワークが可能となるよう、女性のためのキャリアアップ講座を実施することとしております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
1つ、今まで予算がなかなかないということでできなかったことも、これからできると思います。ちょっと課題、課題って言えばもう課題しかないような感じがしますので、先ほどの答弁の中にも20歳から30代の方が多く流出しますと、やはりその辺をどう改善していくか、やはり20代、30代の方に聞くのが僕はベストかなというふうに思っておりますので、その辺の方の意見を聞ける、高知市じゃないですけど、チームじゃないですけど、そういうふうな若い人の意見を取り入れていただくことも1つ計画していただきたいなと。今までできなかったことができますので、またこれもいつまであるか分かりませんので、いろいろ議論してやっていただきたいと思います。
次に、地域おこし協力隊の事業と所見及び隊員延べ数と定着率、これ延べ人数は7人の定着率、定着4人の57.1%と聞きましたので、どういうふうな事業内容でされているのか、所見だけで構いませんので。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
本市の協力隊の取組は、中山間地域の支援業務や観光振興業務、移住定住促進の業務に携わっていただいておりまして、任期はおおむね1年から3年となっております。
所見といたしまして協力隊の方々は、長年地域で暮らしてきた我々住民の視点とは違った角度から地域課題を捉え、これまでにない発想やスキルを持って、その課題にアプローチいただいておりまして、行政ではなかなか行き届かない住民ニーズ等にも柔軟かつきめ細やかに対応するなど、マンパワー不足の本市において欠かせない存在となっております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
住み慣れた、今住んでいる方とは違う目線で、また行政とも違う方法と、あとマンパワー不足の安芸市にとって有力なものだということを再認識しました。
そこで、次の7番、地域課題である担い手不足を共に地域おこし協力隊と解消ということで、先ほどもマンパワー不足、安芸市でいろいろなサービスや仕事があるんですけど、やはりその部分でも人口減少や若年層の働く人たちが減少して、どの分野の仕事もサービスや担い手が不足しております。
そこで、林業従事者や地域移行のスポーツ指導や、また兼業での起業、昨今、公共の運転手不足とか保育士、あと学童支援員の方々とか、そういうところも不足しております。地域おこし協力隊は、会計年度任用職員での契約ありの場合と団体委託型とか、あと業務委託型ですね。それと自分自身で起業できるなど、あと、その3年後の自分の企業運営が市民へのサービスにつながるような雇用の拡充もできますので、その辺も1年から3年の隊員の任務期間があるんですけど、その後も今57%と半分の方しか定住をしていただいておりませんので、もっと定住していくような、地域おこし協力隊を使った、地域協力隊の方々に協力していただくことで人手不足を解消できると思いますので、そういうふうな取組をもう少ししていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
先ほど答弁しましたように、移住や中山間地域観光振興など、そういった分野で協力隊を配置をしておるところですけども、協力隊のこの受入れについて、今年度は今林業分野における隊員の導入に向けて準備を進めているところです。
あと、検討しているところは運転手不足ですね、バスやハイヤー、タクシーとか、こういった分野が足元課題であるというふうな認識もございます。
議員の言われるように、そのほかの分野への導入も進めたいところでございますが、この協力隊の制度が始まって以降、隊員と受入れ地域とのミスマッチによる問題が、これ全国的な問題と、大きな問題となってきております。都会から見知らぬ地域の課題に挑戦する移住者を協力隊として受け入れるということは、周囲の一層心のこもった丁寧な対応が求められます。本市でも、これまで地域と協力隊との間でトラブルがあり、途中で隊員を離脱した方や、任期終了後は定住することを避け転出した方もいらっしゃいます。
協力隊の受入れについては、これまでの取組を振り返り、その地域課題が本当に協力隊でなくてはならないのか、隊員の高い志に対し負けない地域の熱意など、受入れ体制が本当にできているのか一つ一つ準備を重ね、慎重に隊員の受入れを進めなければならないというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
隊員の方も希望とかいろいろ持ってこられるんですけど、その3年間は会計年度任用職員、市の方という認識が市民の方もその当時はあったと思うんですけど、ほかの委託方法とか、例えばどっかの企業体で働いてくださいっていうことで、もう企業体にお預けして仕事をしてもらう場合とかもありますので、方法はいろいろあってですね、当初の考えと今とはまた違っていると思います。市民の方も、何て言うんですかね、その協力隊が会計年度任用職員なんで、市の職員としての当たり方とかもあると思うので、その辺もまた初めの契約体制によっても大分変わってくると思いますので、そこはまたこれから検討していただいて、7人っていうのはちょっと少ないと思いますので、できるだけ多くの方にトライしていただけたらと思います。
先ほどお話が少し、林業の話があったので、そこで次の8番の林業従事者の確保についての市の考えをお聞きいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
本市での林業従事者は、令和3年度末時点の83人から、令和5年度末時点には75人と減少傾向にあります。このため本市では、林業の担い手確保のために林業事業体への新規就業者確保支援として、新規就業者の住宅や資機材を確保する際に必要となる費用、賃借料ですとか、礼金、引っ越し、資機材等の支援になりますけども、これらへの補助制度と林業事業体が研修生を受け入れて研修指導を行う際の費用への補助制度を設けて支援をしておるところでございます。
また、林業への多様な担い手の確保・育成を目指し、自伐型林業の推進にも取り組んでおりまして、これまでに、フォーラムの開催をはじめ、体験研修やステップアップ研修等を開催しております。6年度には、先ほどお話もありました自伐型林業の実践者として、指導・育成すべく、新たに地域おこし協力隊として募集、雇用する計画でございます。
この林業従事者減少の問題に対しましては、林業事業体への就業者確保に継続して取り組むとともに、この地域おこし協力隊制度も活用した林業に関わる人材の確保、そして多様化を図ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
そしたら9番、林業従事者や担い手が育たない理由をどのように分析しておりますか。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 林業事業体における人材確保の面におきましては、林業従事者を思うように確保できない、あるいは林業事業体に就職しても数年で離職してしまうといった課題がございます。
要因として考えられますことといたしましては、林業という仕事の安全面、やはり急傾斜地での伐倒などの作業が危険というイメージもあると思っております。林業現場での労働災害件数は長期的に減少傾向でございますが、実際に他の産業と比べますと、まだ災害発生率は高い状況が続いておりまして、労働災害における死傷者数の割合は、全産業の約10倍となっております。
また、林業従事者の確保の難しさは、林業現場の安全面等の労働条件等によるものだけではなく、林業を学ぶ、あるいは林業を知ったり、触れたり、関心を持ったり、そういった機会が不足していることも要因として上げられるのではないかと考えております。
林業事業体の採用担当者からは、高知県立林業大学校で学んでも学生は生活している地域から近い就職先を選択する傾向があり、なかなか東部のほうの林業事業体までには来てくれないというような声も聞いておりますので、今後におきましては、学生等が林業を知り、関心を持つことができる学びの場や機会を創出することが必要ではないかと考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。
それでは、10番の森林環境譲与税、森林環境税の基金残高と令和6年度の配分予定額をお聞きいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 まず、森林環境譲与税を原資とします森林環境整備基金の基金残高でございますが、令和5年度末で1億918万5,000円となっております。
次に、森林環境譲与税の令和6年度譲与額につきましては、高知県からの試算資料での額となりますが1億505万9,000円の見込みとなっております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
先ほどの9番の課題の中にも、林業大学校を出ても近い地域を選んで学生が就職するということで、東部までは来ませんよというお話があったんですけど、そこで、11番、休校の校舎を使った林業学校の検討実施ということで、高知県立の林業学校へ入れない方々の受皿や、先ほどお話あったように地域での雇用、そして地域の企業の研修場所、スキルアップの機会の拡充や、東部地域などの企業等担い手のマッチング、あと森林経営管理制度や個人山主などの支援調整などの山の木材の管理保全、そして若年層の進路、雇用、森林への先ほどあったように理解と発信、そして森林のそういった部分の各拠点として、先ほど予算が6年度は1億550万9,000円でしたかね、入ってくる部分で、その森林環境譲与税を使いまして、森林学校の運営をしてはどうでしょうかと。今進学や学びの場所がないのであれば、そういった事業も必要だと思うんですけどいかがでしょうか。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
林業従事者や担い手が確保できない、育成できない要因の1つとしましては、先ほども答弁いたしましたように、林業に興味を持つ学生などが林業を知り、学ぶ場所や機会が少ないことが上げられると考えております。
全国では高知県立林業大学校のように、森林・林業に関する学科コースを設置している学校が令和5年4月現在で、県立林大を含め24校が設置されており、その中には、学校法に基づく専修学校に位置づけられた学校もございます。その運営形態は様々でございまして、研修期間も1年制から2年制、募集人員も10人から20人程度と様々でございます。
また、1日から1か月程度の短期間で学ぶことのできるようなコースもありまして、県内では林業事業体への派遣により、事業体での技術研修を学ぶ取組を実践されているケースもあるというふうに伺っております。
本市の中で林業を学べば、本市の山の現状を知ることや人脈も築くことができることから、本市でのスムーズな就業につながることが期待されます。また、高知県立林業大学校の募集定員を超える応募者の受皿となることも期待されますし、例えば本市で基礎課程を学び、さらに学びを深めたいと希望する学生は、県立林業大学校の専攻課程等に進むなど、学校間での連携も想定されるところです。
本市では、現在自伐型林業の体験からステップアップ研修を開催するなどしておりますが、議員御質問の学校形式ではなく、これらの研修の拡充版として基礎的な資格を取得できる数か月程度の研修に拡充するといったことも考えられます。このため、まずは学校形式を含めまして、どのような形式での学びの場の提供が最善かということを検討するため、県立林業大学校や県内外の事例の情報収集をはじめ、それぞれの精査すべき事項や課題について調査研究してまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
ぜひ検討して実施していただきたいと思います。
それでは、5番、市内小学校のトイレ状況と所見及びトイレの洋式化、乾式化、バリアフリー化へのお考えをお伺いいたします。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
小学校のトイレの洋式化率をちょっと述べさせていただきますが、洋式化率は35%となっております。これは全小学校の和便器の数と洋便器の数を合計したものを分母としまして、そのうちの洋便器が占める割合でございます。
次に、乾式トイレにつきましては、屋内の床材と壁材とは同様の建材で構成された一般的に段差のない仕様であります。この乾式化については、第一小学校の61%のトイレが洋式化と合わせて乾式化の整備を実施しております。一方でその他の7校ございますが、小学校が、そちらのほうは床や壁がモルタルですとか、タイル張りということで、湿式、水洗いができる湿式仕様という状況です。乾式は第一小学校だけということになっております
現在、各家庭で洋式便所が普及しておりますことや、学校の環境面からしても、トイレの洋式化については、必要であると考えております。
また、地域の防災拠点となります学校施設のトイレについては、災害時の避難所として洋式化と併せてバリアフリーに対応するため、乾式化をすることも一定必要であると認識をしております。
したがいまして、現在小学校の統合を控えておる中ではございますが、これまでどおり老朽化が著しいトイレについては、当然修繕対応いたしますほか、今後は全てを一気に洋式化することは無理ですが、学校ごとのバランスも見まして、活用できます交付金、補助金、それから避難所の指定の状況、緊急性や優先性を考慮して関係部署とも協議をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 今までそういう答弁が多かったと思うんですけど、小学校、中学校はもう統合しましたんで、小学校の統合も含めた話の中でですね、もう何年も置き去りになってる部分がありますので、またこれで小学校の統合に入りましたので、逆に統合する学校への維持管理の部分が、また置き去りにならないように、今各学校の状態はすごい悪いです。逆にそこから市立の中学校に行くと、多分子供たちの目が飛び出るぐらい、こんなきれいな学校があるのかなというふうに思うと思います。
なのでできるだけ、本来であれば費用もかけたくない部分もあるんですけど、やはりこれからの子供のためにトイレは非常に大事なことです。小学校入った場合のときは、やはり保育士さんとか、お家の方とかいませんので、例えばトイレに失敗する子とかいますので、なかなか行けない子とかもありますので、非常に重要なところだと思いますので、ぜひ改修はしていただきたいなと思います。
教育長どうでしょうか。
○徳久研二議長 教育長。
○藤田剛志教育長 御答弁させていただきます。
先ほど、教育次長が申し上げましたトイレの状況につきましては、私も御承知をしております。また、日頃各学校へ私訪問するわけですが、そうした中でも一部トイレがですね、環境はちょっとどうかなというところも見受けられますので、そうした中で子供たちが安全で安心な学校、そして楽しく快適に学べる学校としてですね、議員御指摘のようなトイレの改修もその一つではないかなというふうには思っております。
今後におきましても、順次、すぐということにはなりませんが、順次トイレの改修等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
よろしく、教育長お願いいたします。
それでは、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○徳久研二議長 以上で、5番小松進也議員の一般質問は終結いたしました。
以上で一般質問は全て終了いたしました。
21日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午後2時29分
応答、答弁者:建設課長、危機管理課長、市長、企画調整課長、農林課長兼農業委員会事務局長、教育次長兼学校教育課長、教育長
○徳久研二議長 以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき、一般質問を行います。
表題は、1、市長の考えはという表題で、だんだんと質問をさせていただきます。
1つ目、道路計画についてお伺いいたします。
今年、石川県能登半島地震、それと宿毛などにも被害をもたらした豊後水道地震など、強い揺れの地震が起きております。安芸市も南海トラフ地震への事前復興として、事前復興まちづくり計画の策定に取り組んでおります。災害が来る前に、できるだけの対策と準備、そして災害後の混乱時から素早く道筋を立て、迅速に復興し、日常生活を取り戻すか、また、日本では地震災害は常に意識が必要ですが、津波災害には対策がありますので、その点も皆様と議論ができればと考え、これから1、2、3と質問をさせていただきます。
それでは、1の1、市道海岸線と中央線の路線拡張の目的と効果をお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
市道海岸線、中央線、両路線とも都市計画法に基づき都市計画決定された道路であり、令和2年3月に策定した安芸市都市計画マスタープランにおいて、産業の活性化や生活利便性の向上、防災ネットワークの形成及び渋滞緩和対策など、新たな地域連携軸となる道路として位置づけされております。
まず、海岸線につきましては、2次防災拠点港となる安芸漁港から沿岸部を通る外縁のルートとして、緊急時の海からの物資輸送や、沿岸部からの避難のための防災対策のネットワークの形成、また、安芸漁港、県立安芸中・高等学校跡地、元気館などを結ぶ海岸ルートとして、市民の健康や観光客のための魅力づくりに資するレクリエーションネットワークの形成を図ります。
次に、中央線につきましては、安芸中インターチェンジからの来訪者を街中へと運ぶ骨格軸であり、産業の活性化を担うネットワークの機能の形成、また県道安芸中インター線と合わせて、中山間地域から統合中学校、市役所、中心市街地を経由し、海岸を直接結ぶルートとして、市民の健康づくり、安全な通勤・通学、分かりやすい観光提供など、市民を支える生活軸となります。
以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。
2番、高規格道路安芸道路供用開始後の市の道路状況はどうなるかをお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
安芸市内で高規格道路が供用開始すれば、南海トラフ地震など大規模災害時の緊急輸送路としての役割や、県中心部へのアクセス性向上、通勤時間の短縮のほか、第3次救急医療機関への救急搬送の速達性、つまり早く到着すること、また、安定性の向上が大きく期待されるところです。
また、国道55号の交通分散が図られ、市内の混雑緩和や交通事故の減少にもつながり、一般道路の交通状況が改善されるものと考えております。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
3番、公共道路が供用開始までに要する参考的な期間、例えば既に完成している区間での参考になるものがあればお教えください。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 供用開始までの期間につきましては、各道路・路線によって、計画規模や地形条件、用地買収の進捗等諸条件が異なるため、一概に何年と申し上げることができませんが、一例としまして、高知南国道路高知インターから高知龍馬空港インター、延長15キロにつきましては、平成2年度に事業化され、暫定2車線で供用開始した令和2年度までの約30年間、また、南国安芸道路香南のいちから芸西西インター延長9キロにつきましては、平成12年度に事業化され、平成22から25年度までの約14年間となっております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
4番、市道海岸線と中央線の供用開始までの大まかな事業予定、工程ですよね、と事業の概算をお教えください。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 まず、海岸線につきましては、令和5年度から6年度で測量設計を実施しており、6年度から7年度にかけて用地補償調査、8年度から10年度に用地補償・交渉・契約、9年度から12年度にかけて工事を実施する計画とし、総事業費約10億円を見込んでおります。
次に、中央線につきましては、令和7年度から11年度の間に事業に着手する計画としており、測量設計で1年程度、用地補償調査で1年程度、用地補償・交渉・契約で3年程度、工事で2年程度、合計7か年、総事業費約5億円を見込んでおります。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) すみません、もうちょっとお聞きしたいんですけど、僕がちょっと聞き抜かったかもしれないので、その市道海岸線で既に測量が入ってまして、12年までなので12年間の10億円、中央線が7か年で5億円ということでよろしいでしょうか。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
海岸線は令和5年度から事業着手しておりますので、令和5年度から令和12年度までの8か年で10億円というふうに見込んでおります。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
次に、津波避難の考えと津波避難についての道路網状況と認識を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
津波避難の考えは、基本的には、素早く、高く、そして遠くです。
次に、津波避難についての道路状況と認識についてですが、安芸市地域防災計画地震対策編では、避難路には補助幹線道路、通学路や、中心地区への主要道路を位置づけるとしており、国道、県道、市道などの安芸市内の道路を災害対策基本法でいうところの避難路として考えています。また、各地区で実際に避難する経路は、地区住民が現地確認や話合いにより決めており、安芸市津波避難計画の関連計画である各地区の地域津波避難計画及び各自主防災会で作成した地区の津波ハザードマップに掲載しています。以上であります。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私のほうからもお答えさせていただきます。
先ほど議員のほうから市道海岸線と中央線の供用開始につきまして御質問が出ておりますが、私もこの海岸線と中央線は避難路としても非常に重要となるというふうに考えております。できるだけ早期、用地交渉等もスムーズに行って早期供用を開始できればというふうに考えております。
あと、津波避難路としての認識ということでございますが、ちょっと大き過ぎて明確かどうか分かりませんが、各地区で実際に避難する経路は古い木造住宅やブロック塀など、地震により倒壊の危険性があり、通行に注意する必要がある道路など、生活者だからこそ知っている危険箇所の情報を集約するなど、実態に即した避難路が重要であるというふうに考えております。
以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
市長も言われましたし、危機管理課の課長も言われましたように、それぞれその認識を基に次の6番の質問に入らせていただきますけど、市道海岸線事業を優先した理由を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 市道海岸線の優先した理由という御質問ですけれども、先ほどの答弁でも少し触れましたが、海岸線、中央線ともに安芸市都市計画マスタープランにおいて産業、観光、交通、防災等のネットワークを形成し、まちづくりを進める上で重要な路線として位置づけしており、市内全域の市道整備の中でも、両路線については、特に優先度が高い路線として認識しております。
現在実施している市道海岸線の整備につきましては、沿岸ルートの形成により、市中心部の渋滞緩和や地域交通の利便性の向上を図るため、当初段階より球場前につながる西工区の完了した後、引き続き元気館から安芸橋西詰までの東工区に着手する計画としていましたことから、令和5年度より本線に着手したものであります。以上です。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど、建設課長が全てちょっと答弁していただきましたので、もう建設課長の言うとおりでございます。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 御答弁ありがとうございました
私のちょっと思いでお話しさせていただくと、私としては市民の日常生活や現状の交通状況なども考えながら、災害の津波避難などのことをまず考えてですね、いまだ多くの市民の方が津波浸水地域内には住んでいらっしゃいまして、また、そこでなりわいも行っております。
ですから、津波浸水区域外への市民の命を逃がす避難道路の整備として、市道中道線の整備を先に行う必要があったのではないかと考えております。
市道海岸線を先行して整備をする場合の国道バイパス機能を持たす場合でもですね、渋滞の原因であります安芸橋西交差点の改修と、また安芸川及び江ノ川の治水工事も考えて、安芸川河口の右岸側から上流に向けて堤防道路を築く計画を持って、市道海岸線を選びます。それはまた、何回も工事をすると、工事期間や予算が多くかかりまして、また、御協力をいただく近隣の住民の方にも工事での御不便を何回もかけることになりますので、そういった点も考えて整備を進めていくと思います。
また、避難は基本的に徒歩でございますが、南北の道路状況がよくなれば、避難を諦めている高齢者の方や、身体が不自由な方などにも有効な避難ができる、車での避難ができると考えております。車での避難は、ここ最近、その後の避難生活にも、車の車中泊や避難後の物資の運送、また、けが人の搬送等にも大きな力を発揮するところだと私は考えております。
あと、都市計画当初とまちの状況や環境も刻々と変化する中で、再度計画実行の見直しも必要ではないかと考えるところではあります。しかし、幸いに市道中央線は後れを取りましたが、市道の道路避難の対応や、大きな幅員を取れる道路検討がこれからできると考えておりますので、その辺は、市としても徒歩だけではなく車を使った避難ができるような道の検討もしていただいて、着手していっていただければと思っております。
では、次の質問に入ります。
次、津波避難計画指定緊急避難場所についてお伺いいたします。
1、安芸第一小学校と某商業施設の避難者収容人数、例えば、安芸市の施設や他の公共施設、また、避難場所に指定されている民間施設をお伺いいたします。
○徳久研二議長 昼食のため休憩いたします。
午後1時再開いたします。
休憩 午後0時
再開 午後0時59分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 質問にお答えします。
指定緊急避難場所である安芸第一小学校屋上の収容人数は829人、近隣の商業施設は1,900人です。
また、安芸第一小学校周辺には、ほかにも2か所の津波避難ビルがあり、県立安芸中・高等学校の清和校舎の屋上に809人、NTT西日本安芸電話交換所ビルの屋上などに428人が収容可能です。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
次の2番、安芸第一小学校や某商業施設を避難場所とする対象地区及び世帯、それと避難者数をお聞きいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 安芸第一小学校屋上及び近隣の商業施設を利用する避難対象地域は、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、久世町、寿町、庄之芝町、清和町の8地区を主に想定しています。
対象地区8地区の世帯数と避難者数との御質問ですが、市内全域の避難想定はございますが、津波浸水区域内に限定した避難想定はございませんので、避難者数に関しては、地区内住民の避難者数が最大となる地区内の人口でお答えさせていただきます。
令和4年11月に改定した安芸市津波避難計画にある令和4年10月末現在の数では、8地区における世帯数及び人口は855世帯、1,576人です。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。ありがとうございます。
安芸第一小学校の屋上で避難できる人が829人で、商業施設が1,900人、某通信施設の屋上が428人、それと安芸中・高の清和の北舎で809人で、今回避難、そこの人口になるんですけど、人口が計855人ということで、第一小学校。
(「世帯」と呼ぶ者あり)
○5 番(小松進也議員) ごめんなさい、855世帯。人数としたら延べ1,576人、令和4年度の調べによるとですんで、安芸第一小学校のみではカバーできない人数ということで、次の質問に入らせていただきたいと思います。
安芸第一小学校や周辺の緊急避難場所が、移転などで機能しない場合の計画や避難空間の必要性を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 安芸第一小学校や小学校周辺の津波避難ビルが何らかの理由で移転等で使えなくなった場合の避難空間の整備ということでございますが、いろんなパターンがあるんですが、まず、安芸第一小学校の移転方向が決まれば、当然、避難施設等を念頭に置いた跡地活用を検討していくことになります。
また、安芸第一小学校の移転方向は決定し、近隣の避難ビルが何らかの理由で使えなくなった場合も、同じく避難施設等を念頭に置いた跡地活用を検討していくことになります。
そして、近隣の避難ビルが、これもまた何らかの理由で使えなくなった場合、近隣に例えば津波避難タワーとかそういう施設を整備する必要があるというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 第一小学校は小学校の移転統合で市としては2校、安芸第一小学校に対しては津波浸水、L2ですね、L2の津波浸水が想定できるので、安芸第一小学校の現地での建て替えはしないという発言があったと思うんですけど、となると第一小学校では基本的には、そこでの小学校の運営がないので建物としては残す可能性、地域の人の避難場所としては重要なので、残す方向で検討するなりはしていただきたいとは思うんですけど、それからまた、代替品の避難ができる施設ですが、その場合には必ず1,576人を救える、もしくはそこに交流人口の方もいらっしゃるので、その1,576人のみというわけにはいかないので、それを上回った避難施設が要ると思います。
先ほども市長のお話の中で、避難タワーなどのことも検討すると、しかしながら民間の施設に対しては、やはりお願いと御協力の下ってなっておりますので、安芸市からこうしてください、ああしてくださいというのは難しくて、そこの場所で常にいてくださいということも言えませんので、ある程度公的な取組というか、支援なり公的なものが必要だとは思っております。
先ほどの1番の質問の中でもあったんですけど、中央線、市道中央線の話なんですけど、そこを避難のために、例えば民間施設なり、安芸第一小学校が800そこそこしかできないので、やはり空間を、避難空間を確保できるのは現時点は難しいので、道路を早急にやっていただきたいと。その辺、市道中央線の着工予定とかっていうのは決まっているんでしょうか。
それと、徒歩避難でなく、車での避難についてのこれからの認識もお伺いしたいです。
○徳久研二議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
市道中央線の着工時期につきましては、先ほどの答弁でもございましたけれども、令和7年度から11年度の間でですね、他の事業等の進捗を見ながら、その間に着手すると。
(「7か8」と呼ぶ者あり)
○近藤雅彦建設課長 7から11年度の間ということですので、何年度というのはまだ現状ではよう決めておりませんけれども、その間に着手するという計画で進めております。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 今はやっぱり原則徒歩避難、これでやっていただこうという考えではおりまして、また、やはり車の移動になれば車が行きよって、どっかで通れなくなった場合、例えば道路が、何でしょう、崩落というか崩壊というか、なって進めなくなった場合に、やっぱり道路がどうしても通行できなくなる状況もあるかと思われますので、現状ではやっぱり原則徒歩避難を推奨したいところです。
ただ、今後いろいろな地震の検証とかもまた出てくるかと思いますので、それで、また改めて国なりから改められた検証結果とかが示されるようであったら、また研究・検討していきたいなとは考えています。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
第一小学校付近に1,576名の方がいらっしゃいますので、基本その方が逃げられるような環境整備と避難ができる施設の確保は、現時点では非常に重要だと思いますので、その辺は再度見直していただいて確認をしていただきたいと思います。
では、次の質問に入りたいと思うんですけど、津波浸水地域の事前復興を問うということで、津波浸水地域の、地域ですね、地域の世帯数と避難者数をお教えください。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
先ほどの答弁でも触れましたが、津波浸水区域内に限定した避難想定はございませんので、避難者数に関しては、区域内の住民の避難者数が最大となる地区内の人口でお答えさせてもらいます。
安芸市津波避難計画では、5,658世帯、1万1,312人を想定しています。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 避難者数というくくりはないと、明確なくくりはないとしても、そこの避難、ごめんなさい、津波浸水地域としてでお住まいの方の人口は1万1,312名ということですね。はい、ありがとうございます。
続きまして、津波浸水地域内の家屋の耐震化率及び未耐震化数をお伺いいたします。
ですが、昨日での全体でも89.7%っていうのは聞きましたので、地域でもし分かればお教えください。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 津波浸水区域内に限定した数字というものは、やはりこれに関しても持ってなくて、やっぱり市全域のお話で、先日9番議員の御質問にも答弁させていただいたとおりとなります。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。
そしたら、ごめんなさい、その地域の、先ほどちょっと僕人数は書けたんですけど、そこにいらっしゃった世帯数、すみません、合計幾らかもう一度お願いします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 避難の想定世帯数ですね。5,658世帯です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。ありがとうございました。
津波避難地域での世帯数は5,658世帯ということで、ありがとうございます。
では、次に、津波浸水地域の家屋の耐震化の計画等支援策をお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
耐震化の計画も浸水区域内に限定せず、安芸市全域を対象にした安芸市住宅耐震改修促進計画第2期を令和2年10月に策定しています。
この計画では、令和7年度末までに安芸市全域における住宅耐震化率を94%に上げていく目標を掲げ、戸別訪問などによる啓発も行っているところです。
支援策としては、昭和56年5月31日以前に建てた住宅を対象とした安芸市住宅耐震改修費等補助金があり、耐震診断は、木造住宅の場合は無料で行え、非木造住宅の場合は最大4万2,000円の補助金の交付を受けることができます。また、耐震設計は最大33万円の補助金、失礼しました。耐震改修工事は今年度から最大165万円の補助金の交付を受けることができます。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたのは、僕の質問が津波浸水地域内ということですけど、津波浸水地域内に限定したものはなくて全体としてありますよと。それと約33万円と165万円で200万円、198万円ぐらいの支援策があると、これは津波というか耐震ですよね、耐震でまず倒壊をしない建物で、倒壊しなければ、その後逃げれるとか、そういう観点で幅広く耐震を推奨してやっていただいているというところだと思います。
では、次の4番、南海トラフ地震の被災後の応急仮設住宅及び災害公営住宅の計画をお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
南海トラフ地震応急機能配置計画では、仮設住宅用地及び災害公営住宅用地に関して、仮設住宅の最大必要戸数を3,458戸としていますが、現状2,280戸分の用地が不足しており、用地の確保には苦慮しているところです。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 2,280戸分の用地は不足していると。
これ去年の質問でもお伺いいただいて、この数字が変わって今ないんですけど、ほかの議員さんの方とかもされて、この数字が常に出てくるんですけど。
それで、20日間以内に応急仮設住宅を着工して建てるような計画をしてくださいっていうことで、シミュレーションなども考えていただければという話で、副市長が議員御指摘のことにつきましても十分考慮して計画を立てていきますというお話でした。
2,280戸の今不足分があるんですけど、これどういうふうにこれから対応していかれますか。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
3月議会のときに、9番議員の質問への答弁としてお答えさせていただいた内容と重複しますけど、結局、引き続き啓発もしながら取り組んでいきたいというベースはありまして、また、あわせて、例えば仮設住宅、今、平野の何です、平家建てを想定しちゅうものがあるのですが、この仮設住宅を重ねて2階建て化するなど、少ない面積でも建てていくことが可能なような方向性について、県のほうとちょっと相談し検討しゆうところです。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 3月の御質問の後の進捗状況はありますか。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 進捗と言えるか分かりませんが、防災フェスタの会場に、県のCLT工法の仮設住宅が展示されていたのです。そのときに県の担当者の方、多分木材産業課の方やと思いますが、その方が現場で説明してくれよったがでちょっと聞いてみたのです。この県が推奨するCLTの仮設住宅でも2階建てが可能か、そういう話を聞いたら、その現場では可能という答えもいただいておりますので、仮設住宅の2階建て、2階化っていうのは比較的簡単なものかという手応えというか、そういう思いは持ってます。
また、ほんで今後も、それはまた県の住宅課などともちょっと相談していきたいと考えています。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) そうなるとですね、3,458棟の応急仮設住宅が必要で、そのうちに、ごめんなさい、1,178世帯の建てるスペースがあるということは、単純に2階建てにすると2,400ぐらいはできるということで、それはもう断言というか確認できるということなんですか。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 この時点で、その確約ということはちょっとはっきり申し上げることはできません。ちょっと県のほうともやっぱり相談していって、はっきりできるっていうことであったらですよね、またそこはそれで話したいと、公表していきたいとは考えています。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。次、ありがとうございます。
5番、安芸市の被災後の人口流出等の想定数をお聞きいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
能登半島地震による被災自治体からの人口流出は報道などで見聞きしていますが、南海トラフ地震による被災後の人口流出などを想定し、数字として示せるものは現状ございません。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 数字としてはないということですね。分かりました。ありがとうございます。
そしたら、私のほうから、2024年の5月9日の記事で、人口流出が3.8倍、2024年元旦の激震で大きな被災を受けた石川県の奥能登4市町村で人口の流出が急速に進んでいる。人口約6万人弱の4市町村で、1月から3月の転出超過は月を追うごとに増え、計1,582名、前年同期の3.8倍だ。ごめんなさい。再び人が戻りコミュニケーションを再生維持することができるのか。復興は時間との勝負である。また、西日本大震災で、全壊被害に遭った住宅の新築費用が平均約2,500万円で、それに対して、公的災害者生活再建支援金などとした受給できるのは、善意による義援金約100万円を合わせても約400万円にとどまる。これだけでなく、家具の引っ越しなど、生活の再建にはほかにもお金はかかるという記事がありました。このようにですね、なかなか難しい現状があります。
それで、先ほどの復興のための仮設住宅などの話もあったんですけど、やはり若い人ほど働く場所が必要なので、多くの方が場所がなければ、若い人ほど流出していきます。また、先ほど住む住宅の確保が1つ大きな鍵があるので、先ほどもお聞かせいただきました。また、中小企業の支援、これによって働く場が確保できるので、そういった手続の簡素化もなかなか進まない中で、早期の支援を行政としてはやる必要があると思っております。
そして、インフラの復旧が、やはり行政としては大事なところがあってですね、ここをいかに回復するか。それで事前の復興も計画をしておくか、災害に遭わないようにしておくかっていうのが非常に重要だと思っております。
これ全て今からお聞きするわけにはいきませんが、次の被災後の人口流出の問題についての考えと対策を市長、お伺いいたします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議員御指摘のとおり、被災後の人口流出は地域の復興と再生における大きな課題でございます。地震などの自然災害が発生すると、多くの住民が安全な場所へ避難し、その後も元の地域に戻らないことが見られ、地域社会や経済に深刻な影響を与えております。
被災後の人口流出を防ぐ対策といいますか、具体的にこの場でちょっと明確にようお答えできないんですが、やはり現在、取り組んでおります事前復興まちづくり計画の策定で、より具体的なものが必要であるというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
事前復興まちづくり計画も非常に重要だと思います。それを羅針盤にしていただいて、市民に周知しておけば、だけでいいのかっていいますと、そういうわけには多分いかないと思います。やはり、事前の物質的な取組も必要だと思います。
津波浸水や川の氾濫などで一定災害がある予測できる場所ですよね。そういった場所は初めから住まなければ、被災後の避難所での避難生活や仮設住宅での生活などはもちろん、予測でき得る災害には遭う確率は極めて低くなります。命も財産も救えて守れる、災害後の人口流出、災害支援及び復興作業にも大きなメリットはあると考えますが、市長はどうでしょうか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議員のおっしゃるとおりなんですが、住み慣れた地域から移転していくということは、やはりそこで住んでる方、住民の方が第一になりますので、当然最初に議員が言われたとおりなんですが、そこはこれからの事前復興ではなくて、その前段での集団移転とかいろんな課題もございますが、そういう部分も踏まえて検討していかなあかんかなというふうには考えております。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
後の質問でもいろいろ出てくるんですけど、別に、何というんですかね、強制的にそこの土地を奪って生活を奪うわけではなくてですね、希望される方とかできる方法もあると思うので、そういったことも踏まえて、次の質問に入っていきたいと思うんですけど、7番の防災集団移転促進事業について、実施検討について、市長はどう思われますか。
この質問を書いた後に某新聞の記事にですね、須崎市が住宅向け高台整備、庁舎に推進チームと、要は高台への事前の補助金制度などを検討しながら、どういうふうにしたらいいかっていうチームを立ち上げております。その辺も、市長も須崎の市長とは懇意にされてると思うので、その辺の情報もあればお伺いしたいと思います。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 南海トラフ地震対策として1つの手段として考えられる、議員の質問にもあった防災集団移転促進事業については、現制度の補助対象要件が、津波災害特別警戒区域のオレンジゾーン、もしくはレッドゾーンが対象となっており、安芸市の沿岸部は、津波災害警戒区域のイエローゾーンであるため、制度を利用することは現時点では難しいものと思われます。
ただ、今後、要件緩和等があれば、対策の手段として研究していきたいと考えています。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 須崎市の情報ということでございますが、ちょっと私のほうは詳細については須崎市長からちょっとようお聞きしてないんで、今回、今度会いますので、またその時点でどういう内容かいうのもちょっと確認をしてみたいなというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
先ほどのイエローの地域があってですね、その方たちがもし5世帯集まればレッドゾーンにしてですよね、していただいて、避難できることもできますので、よくまた検討していただきたいと思います。
今大きくまちが変わる部分なので、昨日の議員さんの答弁、答弁というか質問というか発言の中にもあったんですけど、歴史は将来ですね、の方が判定しますので、そこに今いる私たちがどれだけ後世の方に、あのときの判断が正しかったのかっていうところも検証は今できませんが、そういうところを見据えながらしていただきたいと思います。
確かに今生きている私たちの命も財産も大事ではありますが、やはり安芸市をどう残していくか、命をどうつないでいくかっていうところの観点もありますので、議論としてはパワハラ、今ハラスメントの話とかもいろいろありますけど、議論はやはり同じ方向ないし大きく方向が同じであれば、発言ですよね、発言で、この言葉が今誰に向かって言ってるわけでもないですけど、あほとかばかとかっていう話ではなくて、例えばそれが議論する場では、ハラスメントを恐れて発言できないのは議論になりませんので、今言ってるのは、例えば、女性蔑視とか責任を押しつけるとかっていう話でなくて、やっぱり議論するところでは、ある程度勘違いというか変な方向に取られる場合もありますけど、議論としては言える環境はつくっていくべきだと思いますので、そういうことも考えて、またちょっとその点も考えていただきたいと思います。
そしてですね、ちょっと僕、楽観的かもしれませんけど、ちょっとお話しさせていただくと、津波診断にて耐震がないことが分かった場合ですよね、先ほどお話があった補助金を使ってですね、耐震をすると思うんですけど、津波浸水地域内で住宅を耐震改修する場合ですよね、耐震がないという判断で、その場合、住宅耐震費等の補助は利用できますが、これを機に、津波浸水区域外ですよね、外へ新築を建築した場合は、補助金は利用することができません。耐震をして、危険な場所で住むためには支援は受けられても、危険な場所から移転し安全な場所で住むには支援がない。これって何かおかしくないでしょうか。
津波浸水地域に税金で避難タワーを建設しても、避難浸水はします。安全ではありません。じゃあなぜ建てるのでしょうか。一時的な避難場所であり、いつ来るか分からない地震による津波へのすぐにできる応急処置であり、建てるときには有利な国等の支援がありますが、管理や建て替えのときは、安芸市独自の費用が捻出されるのではないでしょうか。津波浸水地域に公共施設を建てても、将来にその場所での必要性はあるのでしょうか。
また、津波浸水地域に公共の施設を建設する場合は、津波対策や、避難対策と、備蓄品などの管理、維持及び対策の費用や、施設建設費に津波からの安全を守るための特殊建設費用が大きな負担となります。また、津波災害後の応急仮設住宅や災害公営住宅、公営復興住宅などの建設予定地の確保はできているのでしょうか。安芸市の財源で、予定地確保や住宅の確保はできるのでしょうか。ましてや津波浸水地域に住んでいる全ての市民をどう避難させ、被災後も安芸市に住んでいただくことはできるのでしょうか。
その点について、次の質問をさせていただきます。
災害予測地域外への住宅建て替え及び未耐震化住宅の災害予測地域外への住宅建て替えや災害予測地域外への空き家利用への検討とその支援策ですね、を市長にお伺いいたします。
○徳久研二議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 先ほど議員から御提案していただいた住宅支援策は、現在、安芸市が抱えている被災時の課題の解消につながるものと思われ、今後研究・検討したい提案だと考えます。
しかしながら、住宅移転等の支援に関して、防災集団移転促進事業など、国などの現行の支援制度の利用が難しい状況の中、市の財源だけで助成するのは困難な面もあるものとやはり思われますので、国に提案できる支援制度の創設や拡充について、県と協議をしていき、実現の可能性を模索したいと考えます。以上です。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 まず、災害予測地域、津波浸水想定区域という意味。災害、まさにちょっと災害、トータルの災害じゃなくて、そのまま浸水ということでしょうか。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 質問を受けます。
先ほどお話しした、災害予測地域っていうのは、そういう言葉があるかないかはちょっと分からないんですけど、僕が思うにはですね、津波浸水区域も災害が起きる地域です。それとか、津波浸水地域外のところでも崖があったり、例えば川の氾濫がある地域とか、そういうところも危険でありますので、そういう方も安全なところに移っていただければ、その後の被災を受けることもないですし、命も助かりますし、津波浸水地域以外の場合で危険な箇所には、基本的には住んでいただかないほうがいいのではないかなということで、発言させていただきました。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど議員がおっしゃった災害予測地域外、安芸市で予測地域外というのはどれぐらいあるのかいうところは、ちょっと私も存じ上げてないんで、それについてはちょっとなかなか答弁しにくいんですが、津波浸水想定区域という意味でいえば、当然先ほど議員がおっしゃられたとおりなんですが、全ての市民が、南海トラフであれば、その発生後全ての市民が流出しないようにというのは、当然行政としてはそれに努めていかなくてはならないのが行政の責務だと思っております。
そのために、どういう事業ができるかとなると、財源がどうしても問題になってくるんで、その財源については、やはり国、安芸市だけじゃないと思うんで、当然。安芸市だけじゃないんで、国のほうへもそういう支援制度の創設とか、拡充、これはもう県下、高知県であれば県下の市町村でちょっと協議をしながら、こういう細かい部分は国へ提案・要望していかなければならないかなというふうに考えております。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 予算の話がいつも出てくるので、その辺は国、県に要望していただいて、逆に独自でやろうとすれば、今行っている政策の中で地区引いて違うところに当てるとか、単純にさっき198万円という補助金があるので、これだけを受けられるようになっても多分建て替えする方にとってはありがたいと思います。ただで、ごめんなさい。建て替えした場合でも、お金が入れない、頂けないよりかは、少しでも足しにはなりますので、国、県、安芸市とで計画してやっていただけたら非常にありがたいです。それと要望もしていただきたいと思います。
その中で、また少しお話ししたいんですけど、これ先ほどのお話の中に2,500万円全て出せっていう話ではなくて、行政の支援が呼び水になってですね、住民の力、また民間の協力を得て、安全な地域で住んでいただく取組をするのが、市民の命、財産、人口定住、経済の発展にもなるのではないかと考えてお話ししました。
また、移住や新生活を始めるにも、津波浸水地域内しかその場所がないでは、安芸市に住みたいっていう方は少なくなると思います。そういうところに、また投資も、企業はしないと思います。人口がどんどん少なくなる将来に、津波被害があるまちで投資をしてどれぐらいの回収ができるかっていうのが民間の一つのポイントではあると思います。
ですので、住宅だけでなく店舗、例えば店舗というか共同住宅ですよね。安芸市が市営住宅を建てれば、財政的に新築を建てることが難しい方でも市営住宅に入れると思うんですけど、やはりその辺も共同住宅を民間の力を使っていただいて、建てていただくとか、それによって、市営住宅の代替として建設コストの支援をした場合に、支援をいただいた共同住宅は、その分の家賃の安価な金額でお貸しするとか、そういう話を進めていくと建物もできるし雇用も生まれると思いますので。また、その国等に進言する場合であれば、民間の力を共同住宅での建設のやり方等もちょっと念頭に入れてしていただきたいと思います。
それでは、次の質問に入ります。
4番、地域課題についてお伺いする前に、この地域課題の問題、題名の地域おこし協力隊の5番と6番の高知県人口減少対策総合交付金の順番を、入れ替えて質問させていただきます。
安芸市の人口推移ですが、社人研がですね、2060年には安芸市の人口が8,176人まで減少するという予想を出しております。安芸市の2060年の展望は、安芸市総合計画などにも書いておりますが、2060年の展望は1万4,000人であります。ですが、安芸市総合計画後期計画にも書いてますが、来年度、令和7年に安芸市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、将来展望を1万6,907人というふうに書いておりますが、昨日ホームページで見ますと、安芸市の総人口は1万5,764人、もう既に1,200人は早く減少しております。非常に悲しいことです。
次の質問に入っていきたいと思います。
1番、若年層の転出や流出理由と対策をお聞きいたします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
転出手続の際に御協力いただいておりますアンケート調査の結果によりますと、本市では20代の転出者が最も多く、次いで30代となっており、年度によっても異なりますが、10代から30代までで、全体の約80%を占めております。最も多い転出の理由といたしましては、就業・転勤で、次いで結婚や県外への進学によるものとなっております。
次に、対策でございますけれども、就業や転勤に対して転出抑制につながる対策といたしましては、企業誘致による雇用の確保やテレワークなどが可能となるよう、ビジネススキルを学ぶセミナーの開催、また、住まいの確保や企業支援のために空き家・空き店舗のストックと補助金制度の充実に努めております。
結婚や進学に対しましては、結婚新生活への引っ越し費用や家賃支援、県外への進学に対しては、転出抑制ではないですがUターン促進として、奨学金返還支援制度の充実、県内の進学に対しては、無料塾の開講や18歳までの医療費無償化などの支援制度をそろえ、転出抑制や定住策に取り組んでいるところでございます。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
いろいろな対策をしていただいて、目標値を何とか死守するために日夜努力はしていただいていると思います。
質問は、別に行政の方々がやってないっていう話を全然する気はないので、私たちが将来の安芸市のことを考えて、どういうふうな議論がこれからできるかっていうことで話していきたいと思います。
ですが、やっぱり流出に一番大事なところは20代、30代の80%の方、ここを抑制するという言葉がどうか分からないですけど、できるだけ安芸市に住んでいただく、安芸市から仕事をしていただくとか、いろんな理由があると思うんですけど、どういうふうに安芸市に関わっていただくかを考えたいと思います。
次の2番、消滅可能性自治体とされて、市長の考えと独自施策の進め方っていうところを聞きたいんですけど、昨日質問が、同じような質問で同じ答弁されてましたので、これに対してはその答弁を聞いてですね、僕の意見を少しお話ししたいと思います。
この消滅可能性自治体っていう話を聞いたときに、多分市長も自治体とされて非常に悲しいと思うんですけど、このされてる中でも改善されてるところもありますので、二十何市はあるので、安芸市もこれを機に改善できればと思っております。
そして、また20代から30代の女性の方ですよね、対象、これ。その方たちはもう本当当事者なのでもっとつらいとは思っております。昨日も少子化対策は、もちろん国が前面に立ってやる必要があるんですけど、しかしながら住むですよね、居住ですよね。居住についてはなかなか需要がありますので、若年層の女性や若い人が流出、離れることについては、別の要因があるのではないかと思っております。
先ほども進学ややりたい仕事がない、押しつけなどのいろいろな原因があると、私も思っておりますし、まだまだ自治体もできることはあると思います。人に行動変容を促すときは、不安、あと希望で誘導されます。女性の自己実現、楽しい生活を応援する自治体になれば男性も必然的に残る。まず、逆はなかなか難しいと思いますね。これ僕の意見ですので。
また、安芸市は消滅自治体とされたのを機に、全ての女性を応援し、働く、学ぶ、遊ぶ、暮らす、楽しみを、今まで以上に応援することができると思いますので、応援すればいいと思います。今の市の政策が若者層の考えと合っていないのでは、また、結婚もしかり、国・メディアなどの結婚や人口減少などの表現や言葉などの誘導表現で、本当のことが見えなかったりしてると思います。ミスリードしてると思います。本当は乖離があるのではないか。若者層に気軽に聞ける環境で本質と対策が見えるのではないでしょうか。もっと若年層と女性、男性に気軽に話せる場をつくっていただきたいと思います。
ここは、僕のもう感想だけになりますので、今までは人口がどんどん増えていく中での行政運営だったんですけど、今はどんどんどんどん人口が減っていく中での行政運営ですので、そこは今まで多分皆さん体験したことがないところもありますので、今までの政策が本当に正しいのか、その辺は立ち止まって検証する必要もあると思います。
では、次の3番、東京一極集中というが高知市一極集中を市長はどうお考えですか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 東京圏一極集中は、地方からの人口吸引力が強い一方、その圏域の出生率が低いことに問題があります。
本県でも県内人口の約半数が高知市に集中する一極集中型の都市構造となっておりますが、総合病院や中学校、高校、企業や観光機能など、政策誘導により県内バランスを意識した配置がされているように思っております。
こうした取組が結果に結びついているのかは分かりませんが、令和4年度の出生率は高知市も安芸市も同じ1.31、高知県全体でも1.36と大きな乖離はないことから、高知市一極集中は東京圏のようなブラックホール型ではないものというふうに認識をしております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) そしたら認識の中で、4番のれんけいこうち広域都市圏の所見と、これを使った対策などはありますか。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
れんけいこうち広域都市圏は、2018年以降、高知市を中心とした県内33市町村が連携協定の下、地域の活性化及び人口減少の克服に向け取り組んでおります。
本市におきましても、各分野において高知市等と連携し、様々な事業を実施しておりまして、新規就農者の確保に向けた就農相談会への参加や、今年度から新たに開設されます、れんけいこうち専用観光ウェブサイトによるプロモーションへの参加などに関わっているところです。
いろいろ取組しておりまして、2段階移住というようなお言葉もよく聞いたことがあると思いますけど、こうした取組も、高知市と連携してやっておりまして移住実績も出ているところでございます。
さらには、インバウンドの観光についてもですね、大型客船などを誘致してですね、そこからの展開が、まだまだ波及されてない部分がありますので、こういった部分をこれから広げていくというふうにも聞いております。
このように安芸市単独ではですね、なかなか取組効果が低いものとか、知名度の高い高知市との連携とでなければできない仕組み、こういうのは、れんけいこうちでなければ実現できなかったものというふうに認識しておりますので、今後もこの連携をうまく活用して、高い効果が得られるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後1時56分
再開 午後2時3分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます
次、6番改めて5番にいたしました。高知県人口減少対策総合交付金事業の所見とその取組についてお聞きいたします。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
県が新設いたしましたこの交付金は、若年人口の減少に歯止めをかけ、持続可能な人口構造への転換を図ることを目的に、市町村の人口減少対策の取組に対して、県が伴走支援を行いながら総合的に支援を行う取組でございまして、これまで財源がなかった市単独事業においても拡充した中で対象とされるものもございますので、取組が強化されるというふうな認識でございます。
今年度、当該交付金を活用した取組については、まず少子化対策として出会い・結婚分野を強化するため、コンシェルジュを2名に増員配置し、男女の出会いイベントの開催数の増加や連絡先を交換し合った方同士のきめ細かいフォローアップなど取組を進めております。
子育て支援策といたしましては、ファミリーサポートセンター事業や高校生までの子ども医療費助成、保育士の加配も交付金の対象として実施をしております。
今後は利用者と市民ニーズと、現状の問題点とのギャップ解消となるよう取組を変化させながら、交付金を活用してまいりたいと考えております。
次に、移住施策や女性人材確保については、起業による移住定住を図るため、空き店舗対策確保事業やテレワークが可能となるよう、女性のためのキャリアアップ講座を実施することとしております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
1つ、今まで予算がなかなかないということでできなかったことも、これからできると思います。ちょっと課題、課題って言えばもう課題しかないような感じがしますので、先ほどの答弁の中にも20歳から30代の方が多く流出しますと、やはりその辺をどう改善していくか、やはり20代、30代の方に聞くのが僕はベストかなというふうに思っておりますので、その辺の方の意見を聞ける、高知市じゃないですけど、チームじゃないですけど、そういうふうな若い人の意見を取り入れていただくことも1つ計画していただきたいなと。今までできなかったことができますので、またこれもいつまであるか分かりませんので、いろいろ議論してやっていただきたいと思います。
次に、地域おこし協力隊の事業と所見及び隊員延べ数と定着率、これ延べ人数は7人の定着率、定着4人の57.1%と聞きましたので、どういうふうな事業内容でされているのか、所見だけで構いませんので。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
本市の協力隊の取組は、中山間地域の支援業務や観光振興業務、移住定住促進の業務に携わっていただいておりまして、任期はおおむね1年から3年となっております。
所見といたしまして協力隊の方々は、長年地域で暮らしてきた我々住民の視点とは違った角度から地域課題を捉え、これまでにない発想やスキルを持って、その課題にアプローチいただいておりまして、行政ではなかなか行き届かない住民ニーズ等にも柔軟かつきめ細やかに対応するなど、マンパワー不足の本市において欠かせない存在となっております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
住み慣れた、今住んでいる方とは違う目線で、また行政とも違う方法と、あとマンパワー不足の安芸市にとって有力なものだということを再認識しました。
そこで、次の7番、地域課題である担い手不足を共に地域おこし協力隊と解消ということで、先ほどもマンパワー不足、安芸市でいろいろなサービスや仕事があるんですけど、やはりその部分でも人口減少や若年層の働く人たちが減少して、どの分野の仕事もサービスや担い手が不足しております。
そこで、林業従事者や地域移行のスポーツ指導や、また兼業での起業、昨今、公共の運転手不足とか保育士、あと学童支援員の方々とか、そういうところも不足しております。地域おこし協力隊は、会計年度任用職員での契約ありの場合と団体委託型とか、あと業務委託型ですね。それと自分自身で起業できるなど、あと、その3年後の自分の企業運営が市民へのサービスにつながるような雇用の拡充もできますので、その辺も1年から3年の隊員の任務期間があるんですけど、その後も今57%と半分の方しか定住をしていただいておりませんので、もっと定住していくような、地域おこし協力隊を使った、地域協力隊の方々に協力していただくことで人手不足を解消できると思いますので、そういうふうな取組をもう少ししていただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。
○徳久研二議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 お答えいたします。
先ほど答弁しましたように、移住や中山間地域観光振興など、そういった分野で協力隊を配置をしておるところですけども、協力隊のこの受入れについて、今年度は今林業分野における隊員の導入に向けて準備を進めているところです。
あと、検討しているところは運転手不足ですね、バスやハイヤー、タクシーとか、こういった分野が足元課題であるというふうな認識もございます。
議員の言われるように、そのほかの分野への導入も進めたいところでございますが、この協力隊の制度が始まって以降、隊員と受入れ地域とのミスマッチによる問題が、これ全国的な問題と、大きな問題となってきております。都会から見知らぬ地域の課題に挑戦する移住者を協力隊として受け入れるということは、周囲の一層心のこもった丁寧な対応が求められます。本市でも、これまで地域と協力隊との間でトラブルがあり、途中で隊員を離脱した方や、任期終了後は定住することを避け転出した方もいらっしゃいます。
協力隊の受入れについては、これまでの取組を振り返り、その地域課題が本当に協力隊でなくてはならないのか、隊員の高い志に対し負けない地域の熱意など、受入れ体制が本当にできているのか一つ一つ準備を重ね、慎重に隊員の受入れを進めなければならないというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
隊員の方も希望とかいろいろ持ってこられるんですけど、その3年間は会計年度任用職員、市の方という認識が市民の方もその当時はあったと思うんですけど、ほかの委託方法とか、例えばどっかの企業体で働いてくださいっていうことで、もう企業体にお預けして仕事をしてもらう場合とかもありますので、方法はいろいろあってですね、当初の考えと今とはまた違っていると思います。市民の方も、何て言うんですかね、その協力隊が会計年度任用職員なんで、市の職員としての当たり方とかもあると思うので、その辺もまた初めの契約体制によっても大分変わってくると思いますので、そこはまたこれから検討していただいて、7人っていうのはちょっと少ないと思いますので、できるだけ多くの方にトライしていただけたらと思います。
先ほどお話が少し、林業の話があったので、そこで次の8番の林業従事者の確保についての市の考えをお聞きいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
本市での林業従事者は、令和3年度末時点の83人から、令和5年度末時点には75人と減少傾向にあります。このため本市では、林業の担い手確保のために林業事業体への新規就業者確保支援として、新規就業者の住宅や資機材を確保する際に必要となる費用、賃借料ですとか、礼金、引っ越し、資機材等の支援になりますけども、これらへの補助制度と林業事業体が研修生を受け入れて研修指導を行う際の費用への補助制度を設けて支援をしておるところでございます。
また、林業への多様な担い手の確保・育成を目指し、自伐型林業の推進にも取り組んでおりまして、これまでに、フォーラムの開催をはじめ、体験研修やステップアップ研修等を開催しております。6年度には、先ほどお話もありました自伐型林業の実践者として、指導・育成すべく、新たに地域おこし協力隊として募集、雇用する計画でございます。
この林業従事者減少の問題に対しましては、林業事業体への就業者確保に継続して取り組むとともに、この地域おこし協力隊制度も活用した林業に関わる人材の確保、そして多様化を図ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
そしたら9番、林業従事者や担い手が育たない理由をどのように分析しておりますか。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 林業事業体における人材確保の面におきましては、林業従事者を思うように確保できない、あるいは林業事業体に就職しても数年で離職してしまうといった課題がございます。
要因として考えられますことといたしましては、林業という仕事の安全面、やはり急傾斜地での伐倒などの作業が危険というイメージもあると思っております。林業現場での労働災害件数は長期的に減少傾向でございますが、実際に他の産業と比べますと、まだ災害発生率は高い状況が続いておりまして、労働災害における死傷者数の割合は、全産業の約10倍となっております。
また、林業従事者の確保の難しさは、林業現場の安全面等の労働条件等によるものだけではなく、林業を学ぶ、あるいは林業を知ったり、触れたり、関心を持ったり、そういった機会が不足していることも要因として上げられるのではないかと考えております。
林業事業体の採用担当者からは、高知県立林業大学校で学んでも学生は生活している地域から近い就職先を選択する傾向があり、なかなか東部のほうの林業事業体までには来てくれないというような声も聞いておりますので、今後におきましては、学生等が林業を知り、関心を持つことができる学びの場や機会を創出することが必要ではないかと考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 分かりました。
それでは、10番の森林環境譲与税、森林環境税の基金残高と令和6年度の配分予定額をお聞きいたします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 まず、森林環境譲与税を原資とします森林環境整備基金の基金残高でございますが、令和5年度末で1億918万5,000円となっております。
次に、森林環境譲与税の令和6年度譲与額につきましては、高知県からの試算資料での額となりますが1億505万9,000円の見込みとなっております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
先ほどの9番の課題の中にも、林業大学校を出ても近い地域を選んで学生が就職するということで、東部までは来ませんよというお話があったんですけど、そこで、11番、休校の校舎を使った林業学校の検討実施ということで、高知県立の林業学校へ入れない方々の受皿や、先ほどお話あったように地域での雇用、そして地域の企業の研修場所、スキルアップの機会の拡充や、東部地域などの企業等担い手のマッチング、あと森林経営管理制度や個人山主などの支援調整などの山の木材の管理保全、そして若年層の進路、雇用、森林への先ほどあったように理解と発信、そして森林のそういった部分の各拠点として、先ほど予算が6年度は1億550万9,000円でしたかね、入ってくる部分で、その森林環境譲与税を使いまして、森林学校の運営をしてはどうでしょうかと。今進学や学びの場所がないのであれば、そういった事業も必要だと思うんですけどいかがでしょうか。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えいたします。
林業従事者や担い手が確保できない、育成できない要因の1つとしましては、先ほども答弁いたしましたように、林業に興味を持つ学生などが林業を知り、学ぶ場所や機会が少ないことが上げられると考えております。
全国では高知県立林業大学校のように、森林・林業に関する学科コースを設置している学校が令和5年4月現在で、県立林大を含め24校が設置されており、その中には、学校法に基づく専修学校に位置づけられた学校もございます。その運営形態は様々でございまして、研修期間も1年制から2年制、募集人員も10人から20人程度と様々でございます。
また、1日から1か月程度の短期間で学ぶことのできるようなコースもありまして、県内では林業事業体への派遣により、事業体での技術研修を学ぶ取組を実践されているケースもあるというふうに伺っております。
本市の中で林業を学べば、本市の山の現状を知ることや人脈も築くことができることから、本市でのスムーズな就業につながることが期待されます。また、高知県立林業大学校の募集定員を超える応募者の受皿となることも期待されますし、例えば本市で基礎課程を学び、さらに学びを深めたいと希望する学生は、県立林業大学校の専攻課程等に進むなど、学校間での連携も想定されるところです。
本市では、現在自伐型林業の体験からステップアップ研修を開催するなどしておりますが、議員御質問の学校形式ではなく、これらの研修の拡充版として基礎的な資格を取得できる数か月程度の研修に拡充するといったことも考えられます。このため、まずは学校形式を含めまして、どのような形式での学びの場の提供が最善かということを検討するため、県立林業大学校や県内外の事例の情報収集をはじめ、それぞれの精査すべき事項や課題について調査研究してまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
ぜひ検討して実施していただきたいと思います。
それでは、5番、市内小学校のトイレ状況と所見及びトイレの洋式化、乾式化、バリアフリー化へのお考えをお伺いいたします。
○徳久研二議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
小学校のトイレの洋式化率をちょっと述べさせていただきますが、洋式化率は35%となっております。これは全小学校の和便器の数と洋便器の数を合計したものを分母としまして、そのうちの洋便器が占める割合でございます。
次に、乾式トイレにつきましては、屋内の床材と壁材とは同様の建材で構成された一般的に段差のない仕様であります。この乾式化については、第一小学校の61%のトイレが洋式化と合わせて乾式化の整備を実施しております。一方でその他の7校ございますが、小学校が、そちらのほうは床や壁がモルタルですとか、タイル張りということで、湿式、水洗いができる湿式仕様という状況です。乾式は第一小学校だけということになっております
現在、各家庭で洋式便所が普及しておりますことや、学校の環境面からしても、トイレの洋式化については、必要であると考えております。
また、地域の防災拠点となります学校施設のトイレについては、災害時の避難所として洋式化と併せてバリアフリーに対応するため、乾式化をすることも一定必要であると認識をしております。
したがいまして、現在小学校の統合を控えておる中ではございますが、これまでどおり老朽化が著しいトイレについては、当然修繕対応いたしますほか、今後は全てを一気に洋式化することは無理ですが、学校ごとのバランスも見まして、活用できます交付金、補助金、それから避難所の指定の状況、緊急性や優先性を考慮して関係部署とも協議をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 今までそういう答弁が多かったと思うんですけど、小学校、中学校はもう統合しましたんで、小学校の統合も含めた話の中でですね、もう何年も置き去りになってる部分がありますので、またこれで小学校の統合に入りましたので、逆に統合する学校への維持管理の部分が、また置き去りにならないように、今各学校の状態はすごい悪いです。逆にそこから市立の中学校に行くと、多分子供たちの目が飛び出るぐらい、こんなきれいな学校があるのかなというふうに思うと思います。
なのでできるだけ、本来であれば費用もかけたくない部分もあるんですけど、やはりこれからの子供のためにトイレは非常に大事なことです。小学校入った場合のときは、やはり保育士さんとか、お家の方とかいませんので、例えばトイレに失敗する子とかいますので、なかなか行けない子とかもありますので、非常に重要なところだと思いますので、ぜひ改修はしていただきたいなと思います。
教育長どうでしょうか。
○徳久研二議長 教育長。
○藤田剛志教育長 御答弁させていただきます。
先ほど、教育次長が申し上げましたトイレの状況につきましては、私も御承知をしております。また、日頃各学校へ私訪問するわけですが、そうした中でも一部トイレがですね、環境はちょっとどうかなというところも見受けられますので、そうした中で子供たちが安全で安心な学校、そして楽しく快適に学べる学校としてですね、議員御指摘のようなトイレの改修もその一つではないかなというふうには思っております。
今後におきましても、順次、すぐということにはなりませんが、順次トイレの改修等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございました。
よろしく、教育長お願いいたします。
それでは、これで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○徳久研二議長 以上で、5番小松進也議員の一般質問は終結いたしました。
以上で一般質問は全て終了いたしました。
21日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午後2時29分
添付ファイル1 一般質問 小松進也 (PDFファイル 496KB)