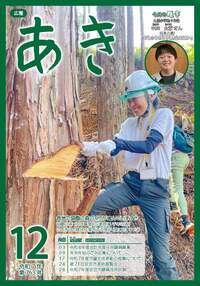議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 山下 裕
質疑、質問者:山下裕議員
応答、答弁者:危機管理課長、市長、市民保険課長、副市長、健康介護課長、福祉事務所長、企画調整課長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、発言取消しの件を議題といたします。
宇田卓志議員から、9月13日の本会議における議案第70号に関わる反対討論中の発言について、会議規則第65条の規定により、言葉が不適切で誤解を招くおそれがあるとの理由により、配付いたしました発言取消し申出書のとおり取り消したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。この取消し申出を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」「議長」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) その本会議の後に、議長が後で精査させていただきますいう内容と違う内容ですか。
○佐藤倫与議長 お答えします。
同じ内容です。
ほかに御意見はありませんか。
12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) これ議長が、ほいたら精査する言うて本会議場で宣言しちゅうがやきんよ、そこで終わっちゅうがやないですか。
○佐藤倫与議長 お答えします。
議長が精査しましたが、本人の申出を受け付けないという趣旨ではございません。本人から取消しの申出がありましたので、許可しました。
今、本人からの取消しの申出についてお諮りしております。
ほかに、御異議はありませんか。
再度、お諮りいたします。宇田卓志議員の取消しの申出につきまして、御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、宇田卓志議員からの発言の取消し申出を許可することに決しました。
日程第2、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。
1、市政全般について。
9月21日、石川県能登地方では、線状降水帯による記録的な豪雨により、複数の河川の氾濫や土砂災害が発生し、元旦の能登半島地震の被災者向けの仮設住宅も床上浸水など、地震から復旧を進める中、再び大きな災害に見舞われています。心が折れるという住民の声が胸に刺さる思いでした。何と言ってよいか言葉は見つかりませんが、被災された方々が一日も早く日常生活に戻れますよう、心より御祈念いたしまして、(1)防災についての質問に入ります。
(1)南海トラフ巨大地震臨時情報について。
ア、南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まった場合に出る臨時情報が8月8日に初めて発表されました。臨時情報という言葉が一般的に周知されてないようで、発表された際は、市民はどういう対応を取ればよいのか、まずは伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合の市民の対応は、報道等もされた政府としての特別な注意の呼びかけでもありましたが、避難場所や避難経路の確認、家庭における備蓄品の確認、家具の固定などの日頃からの地震の備えへの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をするといった対応を取っていただきたい。
なお、巨大地震注意が発表された場合は、特に事前の避難を求めるものではございません。また、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の市民の対応は、日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をする必要があります。
なお、巨大地震警戒が発表された場合は、地震発生後の避難では間に合わない可能性がある住民は、1週間の事前避難を行う必要があります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういったことを市民のほとんどの方が周知してないというか、分かってないということが今回初めて私も分かりました。
続いて、イ、巨大地震注意が発表されれば、先ほど課長言われました1週間の警戒期間が必要で、避難所を開設した自治体もあるが、安芸市の対応を伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 8月8日16時43分頃、日向灘を震源とする地震により、高知県沿岸部に津波注意報が発表されたことを受け、危機管理課及び消防本部による警戒体制となる震災第1配備をしき、情報収集に当たり、17時15分に海岸堤防より海側に避難指示を発令しました。南海トラフ震源域でのマグニチュード6.8以上の地震であったため、17時に気象庁から南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されました。その後、19時に高知県沿岸部に出されていた津波注意報は解除となりましたが、19時15分に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたことを受け、19時20分に災害対策本部設置の判断をし、震災第2配備に移行しました。20時に災害対策本部会議を開催し、津波浸水区域内の保育所は閉所し、児童は区域外の保育所及び市立安芸中学校体育館で受入れすることなどを決定しました。22時に防災行政無線放送及び個別受信放送により、沿岸部にお住まいの高齢者などに向けて、いつでも避難できるように準備を心がけることの注意喚起を行いました。その後は、政府としての特別な注意の呼びかけが終了した8月15日17時までの間、危機管理課及び消防本部当務隊において24時間体制で監視業務に当たりました。その間、自主避難のための避難所を2か所開設していました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) この臨時情報、あるいは半割れ、事前避難などはいつ頃から言われ出したのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 その質問に対する答弁を用意しておりませんので、お答えできません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) はい、通告なかったですかね、すみません。
この関係で、私も平成30年第4回定例会、平成31年第1回、第2回、第3回定例会と関連した質問をしていますが、当時から南国市の取組と比べると、安芸市はかなり遅れているように思います。今回の注意報で、南国市をはじめ11市町村が避難所を開設していますが、安芸市も2か所開設したということですが、こういう方針を事前に決めていたのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
自主避難の避難所を開設するということは決めておりましたが、具体的にどこを開けるかということまでは決めていませんでした。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 南国市は、事前のマニュアルで注意が出ると避難所を原則1週間開設すると決めていて、気象庁の発表の前に避難所を16か所設置したと聞いています。やはりこういう迅速な取組、今後必要ではないかと思います。
それでは、この日は安芸市制70周年の記念式典があり、その後祝賀会がありました。祝賀会終了後に対策会議を開いたとのことですが、判断が遅過ぎるのでは。臨時情報が発表された時点で、副市長だけでも庁舎に帰り、対策会議を開いていればよかったのではとの市民の声がありますが、市長どのようにお考えしますか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
市制70周年を祝う祝賀会は、17時30分から市内のホテルで開き、およそ130人が参加し、20時まで開く予定でしたが、気象庁が19時15分に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表したことを受けて、19時30分頃に終了となりました。並行して19時20分に災害対策本部設置の判断を市長に伺い設置し、震災第2配備への移行をしました。市長は20時から市役所で災害対策本部会議に出席となりました。
津波注意報の発表を受け、震災第1配備となった危機管理課職員などが情報収集に当たっていましたが、安芸市地域防災計画では、津波注意報が発表された時点では、災害対策本部の設置や市長を参集する計画にはなっていません。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
先ほど、危機管理課長のほうから流れにつきましてはお答えさせていただきましたが、当日17時、午後5時に気象庁から南海トラフ地震臨時情報(調査中)ということが発表されましたが、私といたしましては調査中という発表であり、また初めての南海トラフ地震臨時情報(調査中)の発表であり、はっきり言いまして戸惑い、中止すべきかと迷いましたが、市制70周年記念祝賀会の開始目前でもありまして、調査中ということですので、調査が終了した時点で南海トラフ地震臨時情報が発表されれば、開催途中での中止をしなければならないというふうに判断をしたところでございます。そのため、祝賀会挨拶では、津波注意報が出たため防災担当課で情報収集を行っている、状況等に変化があれば報告しますとの状況を冒頭で説明をするとともに、参加された皆さんに注意を促しながら祝賀会を開始させていただきました。
先ほども言いましたが、初めてのことであり、判断に、正直に申し上げますと戸惑いもございましたが、今後、今回のことを踏まえまして、南海トラフはいつ発生してもおかしくない状況ですので、臨時情報(調査中)の発表があった時点で、飲酒の場合はちゅうちょなく中止すべきと考えております。
また、飲酒を伴わないイベント行事等については、津波浸水区域内や区域外の状況等も含めて判断をしていかなければならないかなというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) はい、市長のお考えよく分かりました。
このときに早く退席した方なんかも何人かおりまして、私も6時過ぎには退席して家に帰りましたけど、そういうことが初めてのことですので、どうしてええか分からないということもありましたので、これからよろしく判断をお願いします。
次に、臨時情報が発表された後ですが、市民の方より避難路を使い避難しても、その後どうしたらよいのか。緊急の場合は食料品や水などを持ち出すことができないと思うので、避難した先に備蓄倉庫や一夜を明かせる場所などはあるのかなどの問合せがありました。今まで何度か質問していますが、下山地区の避難場所の進展状況と津久茂町には避難路が幾つあるのか、その先には備蓄倉庫や避難場所があるのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
まず、下山のほうについては、避難路を上った先のため池の辺りまで、危機管理課の職員で、8月13日に場所の確認は行っておりますが、ただ、具体にどの場所に置こうかどうしようかっていう話はまだ地元とは詰めれてない状況です。
また、津久茂町の避難路につきましては、ちょっと何路線あるかっていうがはちょっと用意しておりませんのでお答えはできにくいのですが、津久茂町の避難路を上ると、市道穴内線へ出ます。その道を通って穴内小学校まで行くと、まず備蓄倉庫があります。またほかにも、津久茂町公民館の北側にある高台にも備蓄倉庫は置いています。
なお、馬ノ丁集会所や八丁集会所がありますので、夜間に避難する場合は集会所で滞在することもできるものと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういうことは津久茂町の方々は周知しているのでしょうか。
私に聞いてきた方は、そういうこと全く知らないでいるみたいですけど、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 地元の自主防などとはそういうお話はしているかと思いますが、ただ、津久茂町にお住まいの全員にそこが周知されているかと言われれば、ちょっと不明なところもあります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 自主防の方は御存じかも分からないですけど、やはりそういった住民の方にもう少し周知させるような働きかけ、ぜひお願いしたいと思うのですが、1つ避難路で、西浜のとこ上がっていく避難路が、これは道路に、穴内の道路にはつながってないような、山の中で終わってるような図面が1つありますけど、今日課長この資料持ってきてないですか。
はい、そしたら、また次行きます。
続きまして、家族に障害者がいる方ですが、南海トラフ巨大地震が起こったら、なかなか逃げることができないので、2階でもう一緒にいるというようなことをしみじみ言っているのを聞きました。御主人は足に装具をつければ何とか歩くことができるが、取り付ける時間もかかるし、道路がどうなっているか分からない状況では、避難することは無理と諦めているそうです。また、つえをつかないと歩けない人なども家にいるしかないと諦めているという声も聞いています。そのような家庭が出ないような対策を、安芸市はどのように考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
障害者などの避難の取組についてということであると思いますが、障害者など、特に配慮が必要な方を要配慮者と呼び、要配慮者のうち避難について特に支援を必要とする方を避難行動要支援者と呼びます。避難行動要支援者本人からの同意を得て、災害時に自力での避難が困難な避難行動要支援者一人一人の状況に合わせて、誰が支援するか、どこの避難所などに避難するか、避難時にどのような配慮が必要かなどの避難支援に必要な情報を記載した個別避難計画を、本人とケアマネジャーなどを交えて作成しています。
また、避難行動要支援者名簿を平常時から、地域の民生委員や自主防災組織、警察などの避難支援等の関係者へ、いざというときに円滑で迅速な避難支援を行うために、本市においても情報の共有を行っております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今課長が言われたような情報招集を行っているということなら、こういう話は出ないと思うがです。
だから、本当に聞いたとき私もショックで、もう2階でおると、お父さんが逃げれんかったら私も一緒におりますいうような話を聞いたときは本当にショックで、やはりケアマネジャーさんとか、訪問介護、そういう方々が訪問されている中で、1人でおられる方は多分そういう話も同意をもらった人はしてると思うがですけど、保護者というか配偶者がおったりする場合の家庭ですよね、そういう家族のほうもちょっと見ていてあげていただきたいと思います。特に、訪問介護されてる方とか、ケアマネジャーの方なんかは、ちょこちょこ家庭に行かれてると思うがです。だから、そういう話をもっともっと進めていただいて、そういう話が出ないように、安芸市はこんな対策してくれてるというようなことをぜひお願いしておきたいと思います。
これ福祉のほうも関連してくると思いますので、よろしくお願いします。
続いて、(2)避難場所設置について。
アの高知県内では臨時情報が発表された直後の8日の夜、63人が避難されたと聞いています。今回の避難で熱中症被害は確認されていませんが、今年のような猛暑では、エアコンがない場所は避難する場所ではないと情報科学センター事務局長が言われています。現在、安芸市には避難所は何か所あり、全て冷暖房設備や非常用食品は設置されているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
安芸市が指定している避難所のうち、各地区の集会所、学校の体育館では、冷暖房を完備してないところがありますが、各学校の体育館や武道館、ドームなどには冷房用としてスポットクーラーを配置し、暖房器具の代替としてマットや毛布を備蓄しています。
また、食料や飲料水の備蓄は、備蓄倉庫など備蓄品を置けるスペースがある各地区の主要な避難所となる公民館や集会所などの施設に備蓄しています。以上となります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) だから、冷暖房が完備してないとことか、そういうところは今後避難場所としてどうなのかということが考えられますので、そういう対策もお願いしたいと思いますが、続いて、イの安芸市内の各公民館の非常用食品の管理はどの課がしているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
備蓄品に関しては、食料や飲料水は、基本的には地震・津波時に使用するよう備蓄しています。台風などの風水害時は、事前に避難ができることから持参していただくことにしております。
浸水区域にある公民館は、浸水区域外の施設に備蓄しているため、全ての公民館に備蓄しているわけではございませんが、備蓄した食料や飲料水は備蓄品の管理簿により危機管理課で管理しており、消費期限の半年から1年ほど前に入替えを行っています。入替え後の消費期限が近づいた食料や飲料水は、自主防災組織や小学校などの防災訓練や学習等で活用してもらうことや、台風などの風水害時に避難所を開設した際に、やむを得ない場合には使ってもらっている現状です。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 課長、すみません、丁寧な答弁ですが、どの課が管理しているかということでしたので、一応危機管理課ということですけど、ちょっと後で質問とダブってくるような答弁がちょこちょこ出てますので、よろしくお願いします。
続いて、非常用食品の賞味期限の確認はどのようにしているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
先ほどのちょっと答弁でもさせていただいたんですが、危機管理課で備蓄品の管理簿により、賞味期限・消費期限の管理は行っております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 安芸市内の各公民館には、非常用食品として、アルファ米ワカメ御飯という非常食と飲料水が保管されていると思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
公民館の中でも、地震・津波時に避難する避難所となるところには、そういったものを備蓄しております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木公民館には1箱50袋入りが4箱、平成29年11月に納入され、賞味期限は平成36年4月となっており、飲料水も2L、6本入りが4箱、賞味期限は同じ年月でした。
8月28日、台風10号の影響により、各地域の公民館が避難所として設置された際に、生涯学習課の職員だったと思いますが、巡回してきた際に賞味期限切れが初めて分かり、持ち帰ったということを聞いています。ほかの公民館も同じであったのだと思いますが、賞味期限が切れているという事態を危機管理課は把握できていなかったのでは、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
先ほども述べたとおり、備蓄品がある避難所は地震・津波時に使用する避難所としています。ただ、地震・津波時に避難所としなくても大雨とかで使用する避難所については、こういうものはふだんは備蓄はしておりません。
まず、ちょっと経緯は不明なんですが、伊尾木公民館とかに置かれていたものについては、台風により避難所として開設した際に、食料や飲料水をやむを得ず置いたものと思われます。議員が御指摘のとおり、ほかの公民館等でも同様のことがあるかもしれませんので、それぞれ確認して、後ほど回収したいと考えています。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 土居公民館なんかも同じように、食料品が34年11月賞味期限切れになってます。飲料水、マリンゴールドが35年5月賞味期限切れになってました。
だから、台風の影響で臨時避難所を設置しても、臨時避難した方が、もし食事取る、飲物を飲むときにどういうふうになるか、ちょっとびっくりしました。だから、危機管理課も担当の方が替わられるので、ただ、そういったいつ納入したということの引き継ぎはちゃんとできているのかちょっと心配になりましたが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
地震・津波時の備蓄品については、先ほどから述べているとおり、管理簿によってそこは管理しております。ただ、風水害等でやむを得ず持っていったものについては、例えば現場で、後ほど処分してもらいたい話とかもひょっとしたらしているかもしれませんので、そういったことについては、十分な引き継ぎがなされてないものと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)の発表があり、市長挨拶では自主避難所を開設したとのことでしたが、2か所言われたと思いますが、避難された方はいたのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
その日に関して言えば、8月8日の津波注意報が出た時点で、自主避難の方が1人いました。その方が臨時情報が出たことを受けて、引き続き避難所のほうに避難しておりました。合計、延べ1名です。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今回1名避難されたということですが、注意報になると、避難した市民が1週間、避難所で暮らす可能性はありますが、この時点で自主避難所には非常食などは保管されていたのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
自主避難できる場所として開設していましたので、本来自主避難の場合は、食事等は御自分で用意してきていただくことになります。このたびの巨大地震注意の場合は、日中は行動できていたので、その方も日中は御自宅に一度帰宅して家の様子を見たり、また、朝昼晩の食事も御自分で用意していました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今回は時間的にも余裕があり日中だったいうことで、そういう準備等してはいけると思うがですけど、夜間とかそういうことになるとちょっと状況が変わってくると思います。ただ、避難するということで、避難される方があまりそういったものを持っていけない方なんかも今後出てくると思うがです。だから非常食なんかの配置なんかは本当にお願いしたいと思いますが、その非常食ですが、伊尾木公民館では7月の8日に意見交換会があり、その会のときに期限切れの非常食があるということは言ってありましたが、危機管理課や市長のほうには伝わっていなかったということなのでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
誰からちょっとそういうお話を伺ったか忘れましたが、伊尾木公民館に期限切れの食料があることなどは聞いておりまして、職員等にも回収するようにの指示は出しておりましたが、実際にちょっと回収には至っておりませんでした。その点、迷惑おかけして申し訳ございません。
以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) やはり危機感がないというか、無責任と言わざるを得ません。1か月以上たってますよね、台風の避難場所、設置されたまでは1か月以上もたっている、そのまんま置いていたいうことで、それも生涯学習課の職員が来られて初めて知ったいうことながですので、ちょっとこういったことの伝達、もうちょっと市長よろしく指示をしておいてください。お願いします。
それでは、ウの避難タワーの備蓄品はどのようなものが配布されているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
避難タワーなどにも、先ほどの答弁と重複しますが、備蓄倉庫のある避難場所や避難タワーの備蓄には食料や飲料水もあります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木地区の避難所と避難タワーの備蓄品一覧表がここにあります。最終確認、令和2年7月となっています。その中で、1つ東部生コン、備蓄総数50人、食料200食配置されてます。避難タワー10号は備蓄総数が137人で、食料150食となっていますが、これはどういうことなのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えさせてもらいます。
議員のその質問に対する答えを今日は用意しておりませんので、答弁をちょっと控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) このタワー、避難所の備蓄品について質問しますということは言ってありましたが、課長、来てなかったので、話が伝わらんかったでしょうかね。
そしたら、ほかのことも入ってないでしょうかね。
次、そしたら、すみません。ちょっとポータブルトイレですが、東部生コン、8号タワー、9号タワー、各1つずつ配置されてます。10号タワーには2個ありますが、この中で、トイレ用パーソナルテントは東部生コンのみ1組配置されています。これはどういうことなのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
トイレについては、特にタワーのトイレについては、備蓄品を抜き出した後の倉庫をトイレブースとして使用する運用としておりました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 後で、この命を守る取組についてでちょっとその話も言うつもりでしたけど、備蓄倉庫の中をトイレに使え、避難タワーにある備蓄倉庫、どういう倉庫か、ここの職員の方見られた方いますか。手挙げてください。避難タワーに置いてある備蓄倉庫、どういう倉庫があるか、知ってる方おりますか。
はい、半分ぐらいおりますかね。あそこでトイレをしなさいということ自体がおかしいです。なかなか緊急の場合どうしようもなくするかも分からんですけど、なぜそんな考えになるかちょっと分からないですが、これ後でまた出てきます。
(3)の命を守る取組について。
避難タワー滞在の課題は、改善できているかについてです。
さきの臨時情報が発表されたとき、伊尾木地区の方が近くの避難タワーに避難されたそうですが、戸を開けることができなくて公民館の館長に連絡して開けにきてもらったそうです。緊急事態が起これば、誰が行っても戸を開けることができるようにしておかないと、高齢者では戸を蹴破ることが無理と思われます。今までにも、タワーの開放は何度も要望があったと思いますが、今後はそういうことへの対応を前向きに考える必要があるのではと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
臨時情報が出た場合にタワーにっていうお話ですが、もしタワーをやはり危ないという意識が働いてタワーに逃げることについては全く否定するものではございませんので、蹴破ることができればやっぱり蹴破って入っていただいても、そちらは後ほどうちのほうでまた修繕等で対応します。
それと、ちょっとやはり蹴破る前提でやっぱりタワーを造っておりますので、鍵等についてはやっぱり公民館とかやっぱり一部の者にしかちょっと貸し与えてはいないものと考えております。ちょっとそこについての対応については、ちょっと今具体的な案は思いつきません。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 戸もなかなか簡単に蹴破ることができないような、以前、夜避難訓練したときに小学生が蹴破りましたが、ちょっとけがしました。そんな状態ではないかと思うがで、高齢者の方はなかなか蹴破れないようで、もしそうやって、それなら簡単に蹴破れるような材質で作っておいたほうがええのではないかと思いますが、ほかの2つの避難タワーは鍵が割と簡単に取れるようになってます。開けていけますが、8号タワーはちょっと鍵が簡単に取れないので、塀というか上がってからちょっと取らないかんので高齢者の方ちょっと無理みたいですので、何かやはり今後そういった緊急なことが起こった場合、やはりすぐに開けれるような対策を取ってほしいと思います。これ本当にもうずっと何度も各議員さんも言ってきたと思います。
続いて、先ほどちょっと出ましたが、タワーにあるポータブルトイレを利用するとしてもどの場所でどのように使用するのか、囲いのない中でトイレを使用するということなのか、あまりにも配慮が足りないのではと思われるが、先ほど課長言われました倉庫の中でということですけど、こんなことでは、避難タワーに避難する人はいなくなると思いますが、市長どう思われます。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答え1つさせていただきたいことがあります。
先ほど、確かに備蓄品を取った後の倉庫をトイレブースとして使用する運用としていたという発言をさせていただきましたが、トイレ用のテントを新たに購入することは、自主防災組織の代表者の方にはお話ししておりますので、今後そこは備蓄していく予定となっております。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど危機管理課長が答弁いたしましたとおり、新たにトイレ用のテント購入に向けて進めております。
まだまだ津波避難タワーを利用するに当たりましては、いろんな不便なところがあるかも分かりませんが、また御指摘をいただいた中で自主防と協議をしながら取り組んでいきたいというふうに思います。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) タワーの備蓄品の中でもう一つお聞きします。
このタワーには専用の天幕や、ブルーシートなどがありますが、災害時において誰でもがすぐに張ったりすることはできるものなのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
今、タワーに備蓄していきゆう天幕やブルーシートについては、誰でもが初見で簡単にっていうことではないと思います。ですので、やはり張る訓練等もやっぱりしていっていただきたいと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 8月の暑い中、私を含め自主防の方4人で避難タワーの備蓄品の確認に行きました。障害者用のトイレ用テントの組立てや、ブルーシート、専用天幕の張り方などをどのようにするか試みましたが、説明を聞かないと無理ではないかとの結論に至りました。これでは避難してきた高齢者の方々では全く取り組むことができないだろうと、4人の意見でした。
備蓄品を準備しただけで、後は勝手にしてくださいでは、あまりにも無責任ではないでしょうか。これでは命を守る取組とはかけ離れているのではと思われます。
この8月いろいろなことがありましたので、私どももそうやってタワーへ行って確認してきて初めてこういうことが、たくさんの課題が見つかってきました。だから、9月1日の防災の日にこのタワーに来ていただいて説明を受けてということで、近隣の高齢者の方に声かけて準備してましたけど、中止になったので、今回、できてないですけど、今後こういうことを進めていくように危機管理課ももっと率先してやっていただかないと、本当に今の状況では、もう災害関連死を起こす可能性があるように思われますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
導入当初では、一度多分説明はしているかと思いますが、ただやはりコロナ等で避難ができない時間がかなり長かったかと思いますので、いま一度地元で説明会をということであれば、自主防災組織や公民館と協力して、各タワーを会場に備蓄品の説明することは可能と考えております。
以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) その自主防から要望があれば要望があればということをいつも言われますけど、要望当然それはあると思うがですけど、もうちょっと行政のほうから地域にもっと下ろして、地域の方でこういうことをどうですかということをもっと自主防にも言っていただき、公民館なんかにも言っていただいて、住民の方が動くようにやっぱりしていただきたいと思います。
声をかければ住民の方、確かに集まってくるようになってました、今回は。けど、それも多分今後、話が消えていくと思うがです。そういうときにやっぱり危機管理課、率先してから声を出していただいて、ほかの地区もあると思います。多分どの地区も同じような状況だと思いますので、やはり声がかかったら、上がったら行くじゃなしに、もっと行くから声をかけえということでもっともっと前向きな姿勢を出してほしいと思います。
ちょっと私昔の新聞記事見てまして、2年ほど前に高知大生が、四万十のほうかな、避難タワーで長期滞在する場合を想定し宿泊体験を実施したという新聞記事がありまして、このときはテントや寝袋を使って夜を明かしています。それでも課題がたくさん残ったということです。だから、夜間の寒いときなんかとか、そういうお湯を沸かしたりするもんとか、そういったいろいろ課題が出てきたということですので、今、本当にこの危機感が迫ってきている中、やはりもうちょっと避難タワー、避難場所のそういう備蓄品の管理、それから使用する使い方なんかも、もっともっと地域に下ろして説明していくようにしないと、多分危機管理課の職員も今来ても全部それ説明できんのじゃないか思います。天幕張ったりとか、そういうことを、やはりそういうことももうちょっと勉強もしていただいて、業者をよこすじゃなしに、職員自体が把握していただいて説明に来れるような体制をお願いしたいと思います。
続きまして、(2)マイナンバーカードについて。
(1)普及状況についてお伺いします。
安芸市の普及率はどれくらいになってるのか伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
安芸市のマイナンバーカードの普及についてですが、8月末時点における保有枚数は1万1,039枚で、人口に対する保有率は69.4%となっております。全国平均が74.8%、高知県が71.9%となっており、いずれに比べましても安芸市の保有率は下回っております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 他の市町村では、マイナンバーカードを活用した独自サービスに取り組んでいるということを聞いています。例えば、中土佐町のコミュニティバスは、マイナンバーカードをタッチするだけでバスの乗降ができる改札システムが令和5年10月より導入され、12月からは高知高陵交通、四万十交通にも拡大しているそうです。宿毛市はマイナンバーカードを活用した独自サービスの宿毛IDの拡大に取り組んでいるそうですが、安芸市ではそのような取組は考えていないのか、独自のサービスがあるのか伺います。
○佐藤倫与議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
安芸市におきましては、現在のところ、マイナンバーカードを利用した独自サービスは行ってはおりません。
今後におきましては、行政手続のデジタル化やデジタル技術を活用した市民サービスの向上に向けて、安芸市としてどういったサービスができるのか、各部署におきまして検討していきたいと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 例えば中土佐町のコミュニティバスは、2010年度から、65歳以上と障害者手帳を持つ町民の町内を経由する全バス路線の運賃を無料化していて、国の交付金を活用し、公共交通マイナンバー活用実証事業として実施しているそうです。もう安芸市もそういうことを参考に、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
続いて、(2)マイナ保険証の利用について。
現行の保険証が12月に廃止されるが、現在の利用率を伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
安芸市国保のマイナ保険証利用率は、令和6年7月現在で12.48%、後期高齢者医療のマイナ保険証利用率は6月現在で6.65%となっています。全国平均は、国保が12.83%、後期高齢者医療が10.99%で、高齢者の利用が全国より遅れぎみとなっております。
なお、6か月前の安芸市の利用率は、国保が4.35%、後期高齢者医療が1.67%であったため、半年で3~4倍ほど増えています。12月2日の保険証交付制度の廃止に向けて、今後も増加することが見込まれます。
安芸市におきましては、制度改正の周知広報を積極的に行い、全ての被保険者が必要なときに必要な医療が受けられる状態を確保しつつ、制度移行が円滑に行えるよう、適時適切な事務の執行に努めてまいります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今言われた数字は国保のみの方ですね。
続いて、障害のある人や介護施設入所者などの高齢者には不便性を持ったシステムではということをよく聞きます。例えば、車椅子の方には顔認証ができないとか、いろいろな問題が出ているらしく、そういうことの対策は考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
先ほど議員が再度言っていただきました率についてなんですが、国保が12.48%で、後期高齢者医療も申し上げまして、後期高齢者医療のほうは6.65%になっております。
続きまして、先ほどの御質問にお答えいたします。
現在、安芸市内37の医療機関及び薬局に顔認証つきカードリーダー、または顔認証機能のない汎用カードリーダーが設置されており、マイナンバーカードをカードリーダーに置き、顔認証や4桁の暗証番号の入力により、健康保険の資格情報の確認を受けることができるようになっています。カードリーダーは受付カウンターやその付近に設置されていることが多く、議員がおっしゃるように、受付がハイカウンターである場合は、車椅子を利用している方など、どうしても物理的に高さが合わないことがあるかと思います。このような場合以外にも、子供や障害がある方、高齢の方など、受付で自らカードリーダーの操作を行うことが難しいと思われるケースもあると思います。そのようなときは、家族や介助者、医療機関の職員の方などがマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力しても構わないこととなっております。
また、暗証番号による認証ができない場合は、医療機関等にその旨を伝え、システムを目視確認モードに切り替え、受付職員がマイナンバーカードの顔写真と、本人が同一であるかを目視で確認をし、本人確認とすることができる制度となっております。
マイナ保険証については、令和3年10月から運用が開始されておりますが、本格的な普及は現在進行中であり、国の新しい医療保険制度の改革については、利用する国民の不安や疑問を解消すべく、制度の周知広報が図られることが大事だと考えています。安芸市としては、こういった課題などについて、医師会などに情報提供していきたいと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういった方々に負担のかからないよう、対策をよろしくお願いします。
次、(3)カード使用状況についてですが、安芸市はマイナンバーカードで、コンビニでの住民票などは交付できないが、当初はコンビニでも交付できるのでと市民に伝えていたように聞きましたが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
議員のおっしゃるとおり、安芸市では現在、コンビニ交付をしておりません。マイナンバーカードの利用に当たりましては、全国的には、おっしゃるとおりコンビニで住民票が取れるということになっておりますが、安芸市で取れるということは、こちらのほうから伝えたかどうかはちょっと不明です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) コンビニで利用できると聞いていたので、マイナンバーカードを取得したのに、話が違うと立腹していた市民の方がいました。そのように勘違いをされている人がいるということは、もっと丁寧な説明が必要だったのではと思います。例えば、行く行くはコンビニで利用できますよとか、そういう話が、本人にはすぐコンビニで使えるとか、そういうふうに伝わっていたんではないかと思いますので、そこんとこ今言ってもいきませんが、ちょっと反省していただいて。
それでは、高知県内では幾つの市がコンビニで住民票の交付が受けられるようになっているのか伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
高知県内は、23市町村、67%が導入済みです。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市のほうでは、どうなってますか。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 市は11市のうち、まだ導入していない市は4市あります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ということは7市が導入しているということで、それだけの市ができるようにしているのに、安芸市はどうしてコンビニでの交付を受けられるようにできなかったのか、お伺いします。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
コンビニ交付を実現するに当たっては、住民基本台帳を扱うシステム業者などと、システム導入の契約が必要になります。安芸市もマイナンバーカードの普及に伴って、コンビニ交付の導入についての必要性を感じ、昨年度、導入に向けて資料収集や研修会にも参加するとともに、住基システムや戸籍システムの業者に相談いたしました。両方の業者ともに、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、令和7年度末までかかるシステムの標準化のため、作業が終了するまでコンビニ交付へのシステム改修対応は難しいとのことでした。
よって、当分の間、安芸市では導入することができず、現在のところ、令和8年度中の導入に向けて準備を進めているところです。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 早く取りかかればできていたことだと思いますが、ちょっとそこでも一歩遅れているような気がします。
いろいろ問題が発生しているマイナンバーカードですので、できるだけ市民の利便性が高まるような取組をお願いしておきます。
(3)高齢者の支援対策について。
(1)介護保険料高額の要因と保険料を抑え、要介護・要支援にならないための取組について伺います。
安芸市は県下で一番高い金額になっており、その理由として、在宅サービスの種類及び事業所数がともに充実しており、在宅サービスを利用しながら地域で暮らす介護サービス利用者が多い点との令和6年第2回定例会での担当課長の答弁でしたが、間違いないでしょうか伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時58分
再開 午前11時5分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 お答えします。
令和6年第2回定例会で、9番山下裕議員からの一般質問で、県平均は5,809円と聞いていますが、安芸市が高額になっている原因を伺いますとの御質問があり、それに対し、健康介護課長が、保険料が高額である主な要因は、安芸市は他市町村と比較して在宅サービスの種類及び事業所数がともに充実しており、在宅サービスなどを利用しながら地域で暮らす介護サービス利用者が多い点であると考えておりますと答弁しており、間違いございません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) それでは、安芸市は、他市町村と比較して、在宅サービスの種類及び事業所が充実しているとは、他市町村よりも、事業所数が多く利用者も多いということでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 お答えします。
この考えの基礎となるデータは、1つが、要介護認定を受けている方の介護サービス利用率であります。令和5年度の利用率は、安芸市81.7%、県75.1%となっており、安芸市が11市中、最も高い利用率であります。内訳は、施設サービスが安芸市17.7%、県17.1%で、ほぼ同じでありますが、在宅居住系サービスが安芸市64.1%、県58.1%で、県よりも6ポイント高い利用率となっております。
2つ目は、人口10万人に対する在宅サービス提供事業所数であります。最新データである令和4年度は、ヘルパー事業所は安芸市43.1、県32.6で、安芸市が1.32倍多く、デイサービス事業所は安芸市37.0、県23.7で安芸市が1.56倍多くなっております。在宅サービス事業所は、現在市内に16種類、36事業所あり、特に、過去5年間で4事業所が新規に立ち上がったことが影響しているものです。
これらのことから、在宅の介護サービス事業所数が多く、在宅の介護サービス利用率が高い点が他市町村と比較して、本市の介護保険料が高額である要因になっていると考える理由であります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 丁寧な答弁いただきましたが、ちょっと気になることがありますのでちょっとお聞きしますが、安芸市以外の施設へ入所あるいは通所している場合は、介護保険料は他市の施設に安芸市が支払いするわけですか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 介護保険給付費については、それぞれ利用に応じて利用された事業所のほうに支払いをすることとなっております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ちょっとこれ通告してなかったので分からなければ後で聞きますが、安芸市以外の施設を利用されている方の人数は把握できていますか。分かったらお願いします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 その件につきましては、事前通告をいただいておらず、明確なお答えができません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続きまして、第9期の給付額は、利用者の負担を考慮して保険料は引き上げずに基金を活用することで、第7期、第8期と同額とした答弁をしていますが、2018年から6年間も高額な給付額になっているのは、市の取組が悪いのではと思わざるを得ませんが、市長は安芸市の介護保険料が高知県11市の中で長期にわたり一番高額なということについてどう思われているのか、考えをお伺いします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 まず、第6期から7期に引上げとなった理由について御答弁申し上げます。
議員が御指摘の第6期から第7期は、介護保険料の基準額を月額5,880円から452円増額の6,332円としており、現在も同額に据え置いております。第7期における増額の要因は、介護保険給付費の財源の一つである第1号被保険者の負担率が22%から23%に改正されたこと、介護報酬改定や消費税の増額変更などによる増額のためであります。また、第7期の策定時、基金残高がゼロ円で基金が活用できなかったことも影響しており、保険制度維持のために必要な値上げであったと考えております。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど、担当課長のほうがお答えをいたしましたが、第9期の計画期間の給付額は、国が令和6年度に介護報酬を増額改定することで、第8期計画期間と比べ1.04倍増額となり、介護給付費の伸びへの影響は予想される中、収支が赤字になる見込みでございましたが、利用者の負担を考慮して保険料は引き上げずに基金を活用することで、第7期と第8期計画期間と同額としたというところでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 介護のことはなかなか難しいので、これから私も勉強していきながら質問していきたいと思いますが、安芸市もこういう在宅医療・介護保険についての冊子が出てます。私も気になって香美市、香南市、冊子いただいてきましたが、施設云々全然安芸市が飛び抜けて多いというふうには思いません、この内容を見てみますと。安芸市が出してる多いサービス、事業所のあれは、近隣の事業所が入ってますので、市外結構これ載ってます、中身見てみると。ほかのとこは、香美市なんかは、もう自分とこの香美市だけの施設で出てますので、これ見るとそんなに安芸市が飛び抜けて充実しているというふうにはちょっと思いませんでしたが、またこれもちょっと勉強して、また質問させていただきます。
先ほど、安芸市の高額な理由言われましたけど、例えば第7期、第8期と6,137円で、2番目に高額だった四万十市は第9期で5,900円に下がっています。これは介護予防取組の効果などではと思われますが、次の介護予防の取組についてお聞きします。
本市は、要介護・要支援にならないための取組について様々な支援を行っているとのことですが、その成果が出ているか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 要介護・要支援にならないための取組の成果についてお答えします。
いきいき百歳体操などの取組の効果によりまして、まず、この点を御説明させていただきます。
令和4年度から参加者を対象に、年に1回、フレイルチェックという体力測定によって、評価を実施しています。加齢による筋肉量の減少及び筋力の低下を判断する診断の結果では、該当者が令和4年度の4%から令和5年度には3%へと減少しております。また、筋肉量の減少はないのに筋力が低下した状態を判断する診断の結果では、令和4年度と令和5年度ともに12%で維持されております。
これらによりまして、介護予防の主な取組であります、いきいき百歳体操、サロンなどの御利用者の取組の効果が出ているものと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 6月定例会で、要支援者は令和元年294人から令和5年312人に、要介護者は令和元年1,012人から令和5年1,074人とどちらも増加傾向との答弁でした。この数字を見ると、その成果は現れていないような気がしますがいかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 成果につきまして、分かりやすいデータとなりますものを御答弁させていただきたいと思います。
○9 番(山下 裕議員) 単刀直入に、長くならないように。
○佐藤倫与議長 暫時休憩いたします。
休憩 午前11時17分
再開 午前11時17分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命を、高知県健康づくり支援システムデータで確認しております。第2期健康増進計画評価時点、最新データの平成26年と第3期健康増進計画評価時点、最新データの令和元年度を比較しますと、安芸市の健康寿命は、男性が0.3歳、女性は1.13歳長くなっているものの、県と比較して、男性が0.65歳、女性が0.01歳短い状況にあります。
先ほど、要介護認定増加しているという答弁があったということに関しましては、75歳以上の高齢者数が多くなってございますのが、主な要因と考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 介護保険料が高額というのは、その介護保険料を使ってる方が多いということで、やはり安芸市はそういう方が今増えている状況で、保険料を下げることができないという気がします。
先ほど答弁いただきました様々な支援というのはよく分かります。これはもうどこの市もしてることでありまして、安芸市が特別してるようなことではないと思います。いろいろ支援をしているのに、保険料が高いというところをちょっと言わせてもらいゆうがです。
支援は、いわゆるサロンとか、いきいき百歳体操に来られている方々は元気な方、主に高齢者でも元気な部類に入る方々が来られてます。伊尾木なんかでも95歳ぐらいの方が通ってきてますが、そういう方がやはり多いので、そういう方々は自分たちで健康管理して、外へ出て話をして体操してという気持ちがある方ながです。ただ、私言いたいのは、そういう方ではなしに、家に閉じ籠ってる方ながです。そういう方が、やはり病気になられる方が多いと思います。そういうサロンや百歳体操に参加していない方への応援とか要望、それから参加者が減少している地域もあると思います。そういう方、そういうとこへはどのような支援を、あるいは応援や対策を考えているのかお聞きします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 要介護・要支援にならないための取組は、先ほど議員も御指摘ございましたとおり、高齢者の閉じ籠り防止と青壮年世代の生活習慣病予防対策でございます。
令和5年度の要介護認定者1,362人の約6割が要支援1から要介護2で、その約3割が整形外科疾患でございます。転倒による骨折等で入院し、退院後の重度化防止のため、医療機関から新規認定を勧められる事例が多く、在宅サービスを充実させる傾向があります。退院後の在宅生活はもちろんのこと、日頃から家の中に閉じ籠らず、外出機会を多くすることや、地域の様々な活動に参加できることで、下肢筋力をはじめ、全身の筋力や柔軟性を維持・回復することが重要となります。
また、64歳以下で要介護認定を受けた人の平均年齢は56.3歳で、約半数が脳血管疾患や慢性腎不全などの生活習慣病を原因とし、全員が特定健診未受診者でありました。健診結果を基に、生活習慣の見直しができるよう、未受診者が健診受診できる支援の強化と将来を見通して、若い頃からの強い骨づくりが必要でございます。
保険料を抑える取組につきまして、介護保険料が最も低い市と安芸市との主な違いを見ますと、介護予防日常生活支援総合事業における日常生活に支援が必要な人への介護サービスの提供の仕方の違いでございまして、安芸市では、訪問型介護、通所介護などのサービスを国の基準を基本とする介護支援専門員などの有資格者が提供しております。
一方他市では比較的安価に提供できる多様なサービスとして、有資格者でなくても実施できる身体介護以外の家事支援や買物支援、移動支援などについて、緩和した基準によるサービスや生活支援サポーター、住民ボランティアなどが提供する体制となっておる点でございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 介護課長の答弁、すごく説明がたくさんあって答弁していただいてますけど、ちょっと時間もありますし、もうちょっと明確な答弁でお願いしたいと思います。
先ほど言われました安芸市と例えば土佐清水市を比較すると、1,500円ぐらい差がありますよね、介護保険料が。だから簡単に考えると、土佐清水市はこの介護を受けられる方が少ないということも関係してくると思います。ずっと4,850円で推移してますもんね。
そういったこともありまして、課長いろいろ言われましたけど、いろいろ安芸市もやってますということを言いたいと思うがですけど、やはり実際こういう金額になってますので、まだまだやりようは取組が足らないかと思いますので、ちょっと介護予防、もう少し取組していただいて、頻繁にやはり地域のほうに行って状況を聞いて、やはり回っていくとこなんかあれば行っていただいて、地域では声を掛け合ってます。サロンに来んかね、いきいき来んかね、地域の方々声かけてますが、なかなか出にくい方、たくさん人がいる中へ行きにくい方、特に男性少ないです。伊尾木のサロンも今ちょっと男性が増えてきてますけど、やはり声をかけていってますけど、また行政のほうからはそういったケアマネジャーとか、そういった方なんかのほうからもどんどん声かけていただいて、どうしてえいかということを伝えてあげてほしいです。自宅でいるよりは、やはりそうやって出ていって、どういうことが効果があるとか、そういうことまでちゃんと伝えていただくと、やはりもうちょっと増えてくるんではないかと思いますので、よろしくお願いします。
次に、(2)社会福祉協議会の移転について。
社会福祉協議会は、清水ケ丘中学校跡に移転するということですが、令和5年第3回定例会で、前市民課長は、多機能支援施設への社会福祉協議会の入居は、工事完了後、一部供用開始する他の機関の入居に合わせてできるだけ早い時期に移転する予定と答弁していましたので、多機能支援施設へ入居するものと思っていましたが、どういうことでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 高知県の多機能支援施設の整備につきましては、令和5年第3回定例会で、9番山下裕議員からの一般質問に対して、当時の市民課長が答弁しましたとおり、令和4年11月に県よりいただいたスケジュールでは、令和4年度から令和5年度にかけて実施設計を行い、令和5年9月に整備工事費の予算計上後、令和5年度から令和6年度にかけて改修工事を行い、令和6年10月頃より一部供用開始する案が示されておりました。
現状を県に確認しますと、施設の実施設計は完了しているが、一方で、建物の2階部分を使用する看護師養成校の運営事業者の選定に時間を要していることから、今後のスケジュールについては、再検討中であるとの回答がありました。以上です。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 先ほど健康介護課長から答弁がありましたように、県の多機能支援施設の整備が予定のスケジュールより遅れていることから、社会福祉協議会の同施設への移転についても、昨年、市民課長が御答弁した際の予定より遅れる状況となっております。このため、今月号の広報あきに社会福祉協議会のほうが折り込みチラシを入れておりましたが、今月の30日から旧清水ケ丘中学校のほうに一時的に移転をして業務を行うこととなっております。
旧清水ケ丘中学校への移転の理由につきましては、先ほど説明がありましたように、多機能支援施設の入居時期が遅れるということと、総合社会福祉センターの老朽化により多くの市民が利用する施設として安心安全な施設利用が困難であると社会福祉協議会のほうが判断したものでございます。今年の5月に社会福祉協議会のほうから市に対しまして、多機能支援施設の供用開始までの間、旧清水ケ丘中学校を一時的に使用させてほしいとの要望を受けまして、今回の移転に至ったものでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 多機能支援施設ですが、当初案では6年度の卒業生が対象になるということを聞いてましたけど、そういうことも遅れている、まだまだ未定ということでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 県から提供された令和4年10月時点のスケジュールでは、令和6年度10月頃に完成を予定し、令和7年4月から学生受入れ開始予定の案が示されておりました。
今後の具体的なスケジュールにつきましては、引き続き県に確認してまいりますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、令和4年時点のスケジュールからは大きく遅れ、施設の供用開始について、令和8年度以降となる見通しとなっており、看護学校の学生受入れも遅れるものと思われます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういった進捗状況を今まで、その後ですけど、議会への報告があったのか伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 先ほど申し上げました令和5年第3回定例会以降の御報告はございません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 令和3年第4回定例会、市長挨拶では、令和3年11月30日に、副知事及び県健康政策部長から看護師養成の機能を有する多機能支援施設の整備について説明がありました。途中の部分は省略しますが、最後に、県や東部市町村と連携して取り組んでまいりたいと考えておりますという報告でしたが、それ以降、議会での報告はありませんので、この計画も中止になるのではと心配してますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 議員御指摘のとおり、私としてもすごい気にかかってまして、ちょっと議会への報告は明確ではなかったんでようしてないですが、度々県のほうへ担当部長をはじめ副知事もそうなんですが、要望してまいりまして、今年の7月と8月に県のほうから多機能支援施設についての再度のお話がございまして、それをもって今東部の9市町村長と協議をといいますか、協議をしたところでございます。その中にはまだ県は入っておりませんが、ちょっと時期はかなりちょっと遅れますが、東部一体となってちょっと再度県のほうへも要望してまいりたいというふうに考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) この施設はできると思っていてよろしいですね。はい、分かりました。
続いて、(4)旧庁舎及び旧安芸中学校跡地利用について。
調査委託業務の進捗状況をお聞きします。
令和6年第2回定例会では、豊富な業務経験を有する県外事業者を選定した。スケジュールとしては、10月をめどに、両施設機能に係る活用策の絞り込みを行うとの市長挨拶でした。今議会挨拶では、活用策の絞り込みや参入意向に係る実現可能性を含めた調査を開始しているとのことですが、具体的な内容を伺います。
○佐藤倫与議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 はい、お答えをいたします。
現在は、両施設に配置する機能、規模等を明確にする基本計画の素案策定及び民間活力の導入可能性調査に取り組んでおります。
この導入可能性調査につきましては、当該跡地活用事業への参入が期待できる、あるいは参入の意向を示している企業14社から、提案等のヒアリングを今実施しておりまして、活用策の絞り込みとともに民間参入の実現の可能性について調査を進めているところでございます。
これまでのヒアリングでは、もうちょっと具体的に申し上げますと、旧市庁舎は、基本構想と同様に図書館や文化ホールなどの基礎的な機能とし、加えて、子育て支援機能やカフェなどを併設した複合施設とする提案が多く挙げられております。一方、旧安芸中学校、市立の安芸中学校は旧市庁舎と類似の活用策、例えば文化ホールなども考え得るため、並行して、これを検討を進めておりますが、グラウンドや校舎の敷地面積が非常に広いことや、インターチェンジの整備時期が、整備の時期が不明、ちょっといつ頃になるかということがはっきりしないということであることなど、民間の調査している相手方ですね、民間の事業者側からは、もうちょっと市のほうで核となる一層具体的な施設機能の絞り込みや活用時期の明確化が必要、そういう御意見を複数いただいております。旧市安芸中学校のほうはですね。そういう意見をいただいております。
こうした御意見など、まだ課題整理をいたしまして、民間事業者がよりよい活用策の提案や、事業参入の障壁が低くなるよう、引き続き委託事業者と調整しながら取組を進めてまいります。
そして、10月末までに活用策の絞り込みを行うとともに、従来の行政主導で進める手法と民間活力を活用した手法のいずれが合理性が高いのかを明らかにしたいと考えております。
議員の皆様には、年内を目途にこうした進捗状況・方向性などを御説明したいというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) はい、分かりました。
旧中学校跡地は、まだ具体的な絞り込みには至ってないということですね。分かりました。
続いて、(2)旧庁舎周辺のまちづくりについてお伺いします。
今議会市長挨拶では、企業誘致の取組として本町商店街に来年3月よりオフィスを開所し、初年度は20名の雇用を目指し、将来的には40名規模の雇用を計画するなど、人口減少対策の起爆剤として、鋭意取組を進めていくとの市長の熱い思いが伝わってきました。久しぶりに明るい話題ではないかと思います。
令和5年第2回定例会で、旧県立安芸中・高等学校清和校舎の跡地活用について質問をしていますが、市長はこの清和校舎は、まさしく本市が取り組むサテライトオフィスなど、企業誘致の受皿として、条件が整った適地であると考えている。このため、担当課長とともに、県議会の総務委員会に出向き、要望活動を行っているとの答弁でしたが、今回のコンタクトセンターの誘致を契機に、安芸市の活性化のためにも清和校舎跡地の活用策の働きかけをお願いしたいですが、市長の考えを伺います。
○佐藤倫与議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 先にちょっとお答えいたします。
旧県立安芸中・高等学校清和校舎の跡地活用につきましては、これももちろん御存じのとおり県所有の施設であるため、昨年度に引き続き、今年度も県議会要望にて、人の流れやにぎわいを創出する施設活用の早急な対応を要望してきたところでございます。
県からの今年度の回答は、当面、校舎グラウンド及び体育館については、安芸中学校・高等学校のクラブ、部活が使用するとのことであり、跡地活用については、現在、県庁内で利用希望調査を行っているということでございました。この調査結果を踏まえた上で、活用策について協議するとのことであり、その際は、本市、安芸市の意見を伺いながら進めていくということでございますので、引き続き有効活用について要望や提案をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど企画調整課長が答弁いたしましたとおり、これまでの取組と、それから県からの回答もそうなんですが、現在本市は旧市庁舎、それから旧市立安芸中学校の跡地活用に加え、安芸高校の清和校舎周辺の中心市街地の空洞化対策など、まちづくりにおいて重要な局面を迎えておりますが、コロナ禍を転機とした市民の方々の生活意識やリモートワーク等の急速なデジタル化など、ライフスタイルの変化は移住や企業誘致用施策として進める地方にとって追い風の状況にあると捉えております。
清和校舎は、まちの中心部に位置する商店街と近接をしているほか、施設の充実した設備環境、また太平洋が一望できるロケーションなど、立地特性はまさに本市が取り組んでおります移住や関係人口の創出、また、企業進出に伴う雇用の確保といった新たな人の流れを生み出す拠点として適した条件にあるのではないかというふうに考えております。人口減少、超少子高齢社会が進行する中、当該施設には周辺地域のにぎわいを創出する役目も求められております。
県に対しましては、本市の情勢やまちづくりへの考えを理解していただき、早急に施設の利活用方法や対応案をまとめていただけるよう、引き続き要望及び提案などを働きかけてまいります。
以上でございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市長、ぜひよろしくお願いしておきます。
最後になります。
歯止めのかからない人口減少対策として、人が行き交い、人が集える、そして、雄大な太平洋を一望できる魅力的な建物があるこの施設をぜひ活用していただき、安芸市の活性化に努めてもらいたいとお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。
○佐藤倫与議長 以上で、9番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
4番 宇田卓志議員。
応答、答弁者:危機管理課長、市長、市民保険課長、副市長、健康介護課長、福祉事務所長、企画調整課長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、発言取消しの件を議題といたします。
宇田卓志議員から、9月13日の本会議における議案第70号に関わる反対討論中の発言について、会議規則第65条の規定により、言葉が不適切で誤解を招くおそれがあるとの理由により、配付いたしました発言取消し申出書のとおり取り消したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。この取消し申出を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」「議長」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) その本会議の後に、議長が後で精査させていただきますいう内容と違う内容ですか。
○佐藤倫与議長 お答えします。
同じ内容です。
ほかに御意見はありませんか。
12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) これ議長が、ほいたら精査する言うて本会議場で宣言しちゅうがやきんよ、そこで終わっちゅうがやないですか。
○佐藤倫与議長 お答えします。
議長が精査しましたが、本人の申出を受け付けないという趣旨ではございません。本人から取消しの申出がありましたので、許可しました。
今、本人からの取消しの申出についてお諮りしております。
ほかに、御異議はありませんか。
再度、お諮りいたします。宇田卓志議員の取消しの申出につきまして、御異議はありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、宇田卓志議員からの発言の取消し申出を許可することに決しました。
日程第2、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。
1、市政全般について。
9月21日、石川県能登地方では、線状降水帯による記録的な豪雨により、複数の河川の氾濫や土砂災害が発生し、元旦の能登半島地震の被災者向けの仮設住宅も床上浸水など、地震から復旧を進める中、再び大きな災害に見舞われています。心が折れるという住民の声が胸に刺さる思いでした。何と言ってよいか言葉は見つかりませんが、被災された方々が一日も早く日常生活に戻れますよう、心より御祈念いたしまして、(1)防災についての質問に入ります。
(1)南海トラフ巨大地震臨時情報について。
ア、南海トラフ巨大地震発生の可能性が高まった場合に出る臨時情報が8月8日に初めて発表されました。臨時情報という言葉が一般的に周知されてないようで、発表された際は、市民はどういう対応を取ればよいのか、まずは伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合の市民の対応は、報道等もされた政府としての特別な注意の呼びかけでもありましたが、避難場所や避難経路の確認、家庭における備蓄品の確認、家具の固定などの日頃からの地震の備えへの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をするといった対応を取っていただきたい。
なお、巨大地震注意が発表された場合は、特に事前の避難を求めるものではございません。また、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合の市民の対応は、日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をする必要があります。
なお、巨大地震警戒が発表された場合は、地震発生後の避難では間に合わない可能性がある住民は、1週間の事前避難を行う必要があります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういったことを市民のほとんどの方が周知してないというか、分かってないということが今回初めて私も分かりました。
続いて、イ、巨大地震注意が発表されれば、先ほど課長言われました1週間の警戒期間が必要で、避難所を開設した自治体もあるが、安芸市の対応を伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 8月8日16時43分頃、日向灘を震源とする地震により、高知県沿岸部に津波注意報が発表されたことを受け、危機管理課及び消防本部による警戒体制となる震災第1配備をしき、情報収集に当たり、17時15分に海岸堤防より海側に避難指示を発令しました。南海トラフ震源域でのマグニチュード6.8以上の地震であったため、17時に気象庁から南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されました。その後、19時に高知県沿岸部に出されていた津波注意報は解除となりましたが、19時15分に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたことを受け、19時20分に災害対策本部設置の判断をし、震災第2配備に移行しました。20時に災害対策本部会議を開催し、津波浸水区域内の保育所は閉所し、児童は区域外の保育所及び市立安芸中学校体育館で受入れすることなどを決定しました。22時に防災行政無線放送及び個別受信放送により、沿岸部にお住まいの高齢者などに向けて、いつでも避難できるように準備を心がけることの注意喚起を行いました。その後は、政府としての特別な注意の呼びかけが終了した8月15日17時までの間、危機管理課及び消防本部当務隊において24時間体制で監視業務に当たりました。その間、自主避難のための避難所を2か所開設していました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) この臨時情報、あるいは半割れ、事前避難などはいつ頃から言われ出したのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 その質問に対する答弁を用意しておりませんので、お答えできません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) はい、通告なかったですかね、すみません。
この関係で、私も平成30年第4回定例会、平成31年第1回、第2回、第3回定例会と関連した質問をしていますが、当時から南国市の取組と比べると、安芸市はかなり遅れているように思います。今回の注意報で、南国市をはじめ11市町村が避難所を開設していますが、安芸市も2か所開設したということですが、こういう方針を事前に決めていたのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
自主避難の避難所を開設するということは決めておりましたが、具体的にどこを開けるかということまでは決めていませんでした。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 南国市は、事前のマニュアルで注意が出ると避難所を原則1週間開設すると決めていて、気象庁の発表の前に避難所を16か所設置したと聞いています。やはりこういう迅速な取組、今後必要ではないかと思います。
それでは、この日は安芸市制70周年の記念式典があり、その後祝賀会がありました。祝賀会終了後に対策会議を開いたとのことですが、判断が遅過ぎるのでは。臨時情報が発表された時点で、副市長だけでも庁舎に帰り、対策会議を開いていればよかったのではとの市民の声がありますが、市長どのようにお考えしますか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
市制70周年を祝う祝賀会は、17時30分から市内のホテルで開き、およそ130人が参加し、20時まで開く予定でしたが、気象庁が19時15分に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)を発表したことを受けて、19時30分頃に終了となりました。並行して19時20分に災害対策本部設置の判断を市長に伺い設置し、震災第2配備への移行をしました。市長は20時から市役所で災害対策本部会議に出席となりました。
津波注意報の発表を受け、震災第1配備となった危機管理課職員などが情報収集に当たっていましたが、安芸市地域防災計画では、津波注意報が発表された時点では、災害対策本部の設置や市長を参集する計画にはなっていません。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
先ほど、危機管理課長のほうから流れにつきましてはお答えさせていただきましたが、当日17時、午後5時に気象庁から南海トラフ地震臨時情報(調査中)ということが発表されましたが、私といたしましては調査中という発表であり、また初めての南海トラフ地震臨時情報(調査中)の発表であり、はっきり言いまして戸惑い、中止すべきかと迷いましたが、市制70周年記念祝賀会の開始目前でもありまして、調査中ということですので、調査が終了した時点で南海トラフ地震臨時情報が発表されれば、開催途中での中止をしなければならないというふうに判断をしたところでございます。そのため、祝賀会挨拶では、津波注意報が出たため防災担当課で情報収集を行っている、状況等に変化があれば報告しますとの状況を冒頭で説明をするとともに、参加された皆さんに注意を促しながら祝賀会を開始させていただきました。
先ほども言いましたが、初めてのことであり、判断に、正直に申し上げますと戸惑いもございましたが、今後、今回のことを踏まえまして、南海トラフはいつ発生してもおかしくない状況ですので、臨時情報(調査中)の発表があった時点で、飲酒の場合はちゅうちょなく中止すべきと考えております。
また、飲酒を伴わないイベント行事等については、津波浸水区域内や区域外の状況等も含めて判断をしていかなければならないかなというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) はい、市長のお考えよく分かりました。
このときに早く退席した方なんかも何人かおりまして、私も6時過ぎには退席して家に帰りましたけど、そういうことが初めてのことですので、どうしてええか分からないということもありましたので、これからよろしく判断をお願いします。
次に、臨時情報が発表された後ですが、市民の方より避難路を使い避難しても、その後どうしたらよいのか。緊急の場合は食料品や水などを持ち出すことができないと思うので、避難した先に備蓄倉庫や一夜を明かせる場所などはあるのかなどの問合せがありました。今まで何度か質問していますが、下山地区の避難場所の進展状況と津久茂町には避難路が幾つあるのか、その先には備蓄倉庫や避難場所があるのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えいたします。
まず、下山のほうについては、避難路を上った先のため池の辺りまで、危機管理課の職員で、8月13日に場所の確認は行っておりますが、ただ、具体にどの場所に置こうかどうしようかっていう話はまだ地元とは詰めれてない状況です。
また、津久茂町の避難路につきましては、ちょっと何路線あるかっていうがはちょっと用意しておりませんのでお答えはできにくいのですが、津久茂町の避難路を上ると、市道穴内線へ出ます。その道を通って穴内小学校まで行くと、まず備蓄倉庫があります。またほかにも、津久茂町公民館の北側にある高台にも備蓄倉庫は置いています。
なお、馬ノ丁集会所や八丁集会所がありますので、夜間に避難する場合は集会所で滞在することもできるものと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういうことは津久茂町の方々は周知しているのでしょうか。
私に聞いてきた方は、そういうこと全く知らないでいるみたいですけど、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 地元の自主防などとはそういうお話はしているかと思いますが、ただ、津久茂町にお住まいの全員にそこが周知されているかと言われれば、ちょっと不明なところもあります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 自主防の方は御存じかも分からないですけど、やはりそういった住民の方にもう少し周知させるような働きかけ、ぜひお願いしたいと思うのですが、1つ避難路で、西浜のとこ上がっていく避難路が、これは道路に、穴内の道路にはつながってないような、山の中で終わってるような図面が1つありますけど、今日課長この資料持ってきてないですか。
はい、そしたら、また次行きます。
続きまして、家族に障害者がいる方ですが、南海トラフ巨大地震が起こったら、なかなか逃げることができないので、2階でもう一緒にいるというようなことをしみじみ言っているのを聞きました。御主人は足に装具をつければ何とか歩くことができるが、取り付ける時間もかかるし、道路がどうなっているか分からない状況では、避難することは無理と諦めているそうです。また、つえをつかないと歩けない人なども家にいるしかないと諦めているという声も聞いています。そのような家庭が出ないような対策を、安芸市はどのように考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
障害者などの避難の取組についてということであると思いますが、障害者など、特に配慮が必要な方を要配慮者と呼び、要配慮者のうち避難について特に支援を必要とする方を避難行動要支援者と呼びます。避難行動要支援者本人からの同意を得て、災害時に自力での避難が困難な避難行動要支援者一人一人の状況に合わせて、誰が支援するか、どこの避難所などに避難するか、避難時にどのような配慮が必要かなどの避難支援に必要な情報を記載した個別避難計画を、本人とケアマネジャーなどを交えて作成しています。
また、避難行動要支援者名簿を平常時から、地域の民生委員や自主防災組織、警察などの避難支援等の関係者へ、いざというときに円滑で迅速な避難支援を行うために、本市においても情報の共有を行っております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今課長が言われたような情報招集を行っているということなら、こういう話は出ないと思うがです。
だから、本当に聞いたとき私もショックで、もう2階でおると、お父さんが逃げれんかったら私も一緒におりますいうような話を聞いたときは本当にショックで、やはりケアマネジャーさんとか、訪問介護、そういう方々が訪問されている中で、1人でおられる方は多分そういう話も同意をもらった人はしてると思うがですけど、保護者というか配偶者がおったりする場合の家庭ですよね、そういう家族のほうもちょっと見ていてあげていただきたいと思います。特に、訪問介護されてる方とか、ケアマネジャーの方なんかは、ちょこちょこ家庭に行かれてると思うがです。だから、そういう話をもっともっと進めていただいて、そういう話が出ないように、安芸市はこんな対策してくれてるというようなことをぜひお願いしておきたいと思います。
これ福祉のほうも関連してくると思いますので、よろしくお願いします。
続いて、(2)避難場所設置について。
アの高知県内では臨時情報が発表された直後の8日の夜、63人が避難されたと聞いています。今回の避難で熱中症被害は確認されていませんが、今年のような猛暑では、エアコンがない場所は避難する場所ではないと情報科学センター事務局長が言われています。現在、安芸市には避難所は何か所あり、全て冷暖房設備や非常用食品は設置されているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
安芸市が指定している避難所のうち、各地区の集会所、学校の体育館では、冷暖房を完備してないところがありますが、各学校の体育館や武道館、ドームなどには冷房用としてスポットクーラーを配置し、暖房器具の代替としてマットや毛布を備蓄しています。
また、食料や飲料水の備蓄は、備蓄倉庫など備蓄品を置けるスペースがある各地区の主要な避難所となる公民館や集会所などの施設に備蓄しています。以上となります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) だから、冷暖房が完備してないとことか、そういうところは今後避難場所としてどうなのかということが考えられますので、そういう対策もお願いしたいと思いますが、続いて、イの安芸市内の各公民館の非常用食品の管理はどの課がしているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
備蓄品に関しては、食料や飲料水は、基本的には地震・津波時に使用するよう備蓄しています。台風などの風水害時は、事前に避難ができることから持参していただくことにしております。
浸水区域にある公民館は、浸水区域外の施設に備蓄しているため、全ての公民館に備蓄しているわけではございませんが、備蓄した食料や飲料水は備蓄品の管理簿により危機管理課で管理しており、消費期限の半年から1年ほど前に入替えを行っています。入替え後の消費期限が近づいた食料や飲料水は、自主防災組織や小学校などの防災訓練や学習等で活用してもらうことや、台風などの風水害時に避難所を開設した際に、やむを得ない場合には使ってもらっている現状です。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 課長、すみません、丁寧な答弁ですが、どの課が管理しているかということでしたので、一応危機管理課ということですけど、ちょっと後で質問とダブってくるような答弁がちょこちょこ出てますので、よろしくお願いします。
続いて、非常用食品の賞味期限の確認はどのようにしているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
先ほどのちょっと答弁でもさせていただいたんですが、危機管理課で備蓄品の管理簿により、賞味期限・消費期限の管理は行っております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 安芸市内の各公民館には、非常用食品として、アルファ米ワカメ御飯という非常食と飲料水が保管されていると思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
公民館の中でも、地震・津波時に避難する避難所となるところには、そういったものを備蓄しております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木公民館には1箱50袋入りが4箱、平成29年11月に納入され、賞味期限は平成36年4月となっており、飲料水も2L、6本入りが4箱、賞味期限は同じ年月でした。
8月28日、台風10号の影響により、各地域の公民館が避難所として設置された際に、生涯学習課の職員だったと思いますが、巡回してきた際に賞味期限切れが初めて分かり、持ち帰ったということを聞いています。ほかの公民館も同じであったのだと思いますが、賞味期限が切れているという事態を危機管理課は把握できていなかったのでは、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
先ほども述べたとおり、備蓄品がある避難所は地震・津波時に使用する避難所としています。ただ、地震・津波時に避難所としなくても大雨とかで使用する避難所については、こういうものはふだんは備蓄はしておりません。
まず、ちょっと経緯は不明なんですが、伊尾木公民館とかに置かれていたものについては、台風により避難所として開設した際に、食料や飲料水をやむを得ず置いたものと思われます。議員が御指摘のとおり、ほかの公民館等でも同様のことがあるかもしれませんので、それぞれ確認して、後ほど回収したいと考えています。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 土居公民館なんかも同じように、食料品が34年11月賞味期限切れになってます。飲料水、マリンゴールドが35年5月賞味期限切れになってました。
だから、台風の影響で臨時避難所を設置しても、臨時避難した方が、もし食事取る、飲物を飲むときにどういうふうになるか、ちょっとびっくりしました。だから、危機管理課も担当の方が替わられるので、ただ、そういったいつ納入したということの引き継ぎはちゃんとできているのかちょっと心配になりましたが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
地震・津波時の備蓄品については、先ほどから述べているとおり、管理簿によってそこは管理しております。ただ、風水害等でやむを得ず持っていったものについては、例えば現場で、後ほど処分してもらいたい話とかもひょっとしたらしているかもしれませんので、そういったことについては、十分な引き継ぎがなされてないものと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)の発表があり、市長挨拶では自主避難所を開設したとのことでしたが、2か所言われたと思いますが、避難された方はいたのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
その日に関して言えば、8月8日の津波注意報が出た時点で、自主避難の方が1人いました。その方が臨時情報が出たことを受けて、引き続き避難所のほうに避難しておりました。合計、延べ1名です。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今回1名避難されたということですが、注意報になると、避難した市民が1週間、避難所で暮らす可能性はありますが、この時点で自主避難所には非常食などは保管されていたのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
自主避難できる場所として開設していましたので、本来自主避難の場合は、食事等は御自分で用意してきていただくことになります。このたびの巨大地震注意の場合は、日中は行動できていたので、その方も日中は御自宅に一度帰宅して家の様子を見たり、また、朝昼晩の食事も御自分で用意していました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今回は時間的にも余裕があり日中だったいうことで、そういう準備等してはいけると思うがですけど、夜間とかそういうことになるとちょっと状況が変わってくると思います。ただ、避難するということで、避難される方があまりそういったものを持っていけない方なんかも今後出てくると思うがです。だから非常食なんかの配置なんかは本当にお願いしたいと思いますが、その非常食ですが、伊尾木公民館では7月の8日に意見交換会があり、その会のときに期限切れの非常食があるということは言ってありましたが、危機管理課や市長のほうには伝わっていなかったということなのでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
誰からちょっとそういうお話を伺ったか忘れましたが、伊尾木公民館に期限切れの食料があることなどは聞いておりまして、職員等にも回収するようにの指示は出しておりましたが、実際にちょっと回収には至っておりませんでした。その点、迷惑おかけして申し訳ございません。
以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) やはり危機感がないというか、無責任と言わざるを得ません。1か月以上たってますよね、台風の避難場所、設置されたまでは1か月以上もたっている、そのまんま置いていたいうことで、それも生涯学習課の職員が来られて初めて知ったいうことながですので、ちょっとこういったことの伝達、もうちょっと市長よろしく指示をしておいてください。お願いします。
それでは、ウの避難タワーの備蓄品はどのようなものが配布されているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
避難タワーなどにも、先ほどの答弁と重複しますが、備蓄倉庫のある避難場所や避難タワーの備蓄には食料や飲料水もあります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木地区の避難所と避難タワーの備蓄品一覧表がここにあります。最終確認、令和2年7月となっています。その中で、1つ東部生コン、備蓄総数50人、食料200食配置されてます。避難タワー10号は備蓄総数が137人で、食料150食となっていますが、これはどういうことなのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えさせてもらいます。
議員のその質問に対する答えを今日は用意しておりませんので、答弁をちょっと控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) このタワー、避難所の備蓄品について質問しますということは言ってありましたが、課長、来てなかったので、話が伝わらんかったでしょうかね。
そしたら、ほかのことも入ってないでしょうかね。
次、そしたら、すみません。ちょっとポータブルトイレですが、東部生コン、8号タワー、9号タワー、各1つずつ配置されてます。10号タワーには2個ありますが、この中で、トイレ用パーソナルテントは東部生コンのみ1組配置されています。これはどういうことなのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
トイレについては、特にタワーのトイレについては、備蓄品を抜き出した後の倉庫をトイレブースとして使用する運用としておりました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 後で、この命を守る取組についてでちょっとその話も言うつもりでしたけど、備蓄倉庫の中をトイレに使え、避難タワーにある備蓄倉庫、どういう倉庫か、ここの職員の方見られた方いますか。手挙げてください。避難タワーに置いてある備蓄倉庫、どういう倉庫があるか、知ってる方おりますか。
はい、半分ぐらいおりますかね。あそこでトイレをしなさいということ自体がおかしいです。なかなか緊急の場合どうしようもなくするかも分からんですけど、なぜそんな考えになるかちょっと分からないですが、これ後でまた出てきます。
(3)の命を守る取組について。
避難タワー滞在の課題は、改善できているかについてです。
さきの臨時情報が発表されたとき、伊尾木地区の方が近くの避難タワーに避難されたそうですが、戸を開けることができなくて公民館の館長に連絡して開けにきてもらったそうです。緊急事態が起これば、誰が行っても戸を開けることができるようにしておかないと、高齢者では戸を蹴破ることが無理と思われます。今までにも、タワーの開放は何度も要望があったと思いますが、今後はそういうことへの対応を前向きに考える必要があるのではと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
臨時情報が出た場合にタワーにっていうお話ですが、もしタワーをやはり危ないという意識が働いてタワーに逃げることについては全く否定するものではございませんので、蹴破ることができればやっぱり蹴破って入っていただいても、そちらは後ほどうちのほうでまた修繕等で対応します。
それと、ちょっとやはり蹴破る前提でやっぱりタワーを造っておりますので、鍵等についてはやっぱり公民館とかやっぱり一部の者にしかちょっと貸し与えてはいないものと考えております。ちょっとそこについての対応については、ちょっと今具体的な案は思いつきません。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 戸もなかなか簡単に蹴破ることができないような、以前、夜避難訓練したときに小学生が蹴破りましたが、ちょっとけがしました。そんな状態ではないかと思うがで、高齢者の方はなかなか蹴破れないようで、もしそうやって、それなら簡単に蹴破れるような材質で作っておいたほうがええのではないかと思いますが、ほかの2つの避難タワーは鍵が割と簡単に取れるようになってます。開けていけますが、8号タワーはちょっと鍵が簡単に取れないので、塀というか上がってからちょっと取らないかんので高齢者の方ちょっと無理みたいですので、何かやはり今後そういった緊急なことが起こった場合、やはりすぐに開けれるような対策を取ってほしいと思います。これ本当にもうずっと何度も各議員さんも言ってきたと思います。
続いて、先ほどちょっと出ましたが、タワーにあるポータブルトイレを利用するとしてもどの場所でどのように使用するのか、囲いのない中でトイレを使用するということなのか、あまりにも配慮が足りないのではと思われるが、先ほど課長言われました倉庫の中でということですけど、こんなことでは、避難タワーに避難する人はいなくなると思いますが、市長どう思われます。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答え1つさせていただきたいことがあります。
先ほど、確かに備蓄品を取った後の倉庫をトイレブースとして使用する運用としていたという発言をさせていただきましたが、トイレ用のテントを新たに購入することは、自主防災組織の代表者の方にはお話ししておりますので、今後そこは備蓄していく予定となっております。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど危機管理課長が答弁いたしましたとおり、新たにトイレ用のテント購入に向けて進めております。
まだまだ津波避難タワーを利用するに当たりましては、いろんな不便なところがあるかも分かりませんが、また御指摘をいただいた中で自主防と協議をしながら取り組んでいきたいというふうに思います。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) タワーの備蓄品の中でもう一つお聞きします。
このタワーには専用の天幕や、ブルーシートなどがありますが、災害時において誰でもがすぐに張ったりすることはできるものなのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
今、タワーに備蓄していきゆう天幕やブルーシートについては、誰でもが初見で簡単にっていうことではないと思います。ですので、やはり張る訓練等もやっぱりしていっていただきたいと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 8月の暑い中、私を含め自主防の方4人で避難タワーの備蓄品の確認に行きました。障害者用のトイレ用テントの組立てや、ブルーシート、専用天幕の張り方などをどのようにするか試みましたが、説明を聞かないと無理ではないかとの結論に至りました。これでは避難してきた高齢者の方々では全く取り組むことができないだろうと、4人の意見でした。
備蓄品を準備しただけで、後は勝手にしてくださいでは、あまりにも無責任ではないでしょうか。これでは命を守る取組とはかけ離れているのではと思われます。
この8月いろいろなことがありましたので、私どももそうやってタワーへ行って確認してきて初めてこういうことが、たくさんの課題が見つかってきました。だから、9月1日の防災の日にこのタワーに来ていただいて説明を受けてということで、近隣の高齢者の方に声かけて準備してましたけど、中止になったので、今回、できてないですけど、今後こういうことを進めていくように危機管理課ももっと率先してやっていただかないと、本当に今の状況では、もう災害関連死を起こす可能性があるように思われますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
導入当初では、一度多分説明はしているかと思いますが、ただやはりコロナ等で避難ができない時間がかなり長かったかと思いますので、いま一度地元で説明会をということであれば、自主防災組織や公民館と協力して、各タワーを会場に備蓄品の説明することは可能と考えております。
以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) その自主防から要望があれば要望があればということをいつも言われますけど、要望当然それはあると思うがですけど、もうちょっと行政のほうから地域にもっと下ろして、地域の方でこういうことをどうですかということをもっと自主防にも言っていただき、公民館なんかにも言っていただいて、住民の方が動くようにやっぱりしていただきたいと思います。
声をかければ住民の方、確かに集まってくるようになってました、今回は。けど、それも多分今後、話が消えていくと思うがです。そういうときにやっぱり危機管理課、率先してから声を出していただいて、ほかの地区もあると思います。多分どの地区も同じような状況だと思いますので、やはり声がかかったら、上がったら行くじゃなしに、もっと行くから声をかけえということでもっともっと前向きな姿勢を出してほしいと思います。
ちょっと私昔の新聞記事見てまして、2年ほど前に高知大生が、四万十のほうかな、避難タワーで長期滞在する場合を想定し宿泊体験を実施したという新聞記事がありまして、このときはテントや寝袋を使って夜を明かしています。それでも課題がたくさん残ったということです。だから、夜間の寒いときなんかとか、そういうお湯を沸かしたりするもんとか、そういったいろいろ課題が出てきたということですので、今、本当にこの危機感が迫ってきている中、やはりもうちょっと避難タワー、避難場所のそういう備蓄品の管理、それから使用する使い方なんかも、もっともっと地域に下ろして説明していくようにしないと、多分危機管理課の職員も今来ても全部それ説明できんのじゃないか思います。天幕張ったりとか、そういうことを、やはりそういうことももうちょっと勉強もしていただいて、業者をよこすじゃなしに、職員自体が把握していただいて説明に来れるような体制をお願いしたいと思います。
続きまして、(2)マイナンバーカードについて。
(1)普及状況についてお伺いします。
安芸市の普及率はどれくらいになってるのか伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
安芸市のマイナンバーカードの普及についてですが、8月末時点における保有枚数は1万1,039枚で、人口に対する保有率は69.4%となっております。全国平均が74.8%、高知県が71.9%となっており、いずれに比べましても安芸市の保有率は下回っております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 他の市町村では、マイナンバーカードを活用した独自サービスに取り組んでいるということを聞いています。例えば、中土佐町のコミュニティバスは、マイナンバーカードをタッチするだけでバスの乗降ができる改札システムが令和5年10月より導入され、12月からは高知高陵交通、四万十交通にも拡大しているそうです。宿毛市はマイナンバーカードを活用した独自サービスの宿毛IDの拡大に取り組んでいるそうですが、安芸市ではそのような取組は考えていないのか、独自のサービスがあるのか伺います。
○佐藤倫与議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
安芸市におきましては、現在のところ、マイナンバーカードを利用した独自サービスは行ってはおりません。
今後におきましては、行政手続のデジタル化やデジタル技術を活用した市民サービスの向上に向けて、安芸市としてどういったサービスができるのか、各部署におきまして検討していきたいと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 例えば中土佐町のコミュニティバスは、2010年度から、65歳以上と障害者手帳を持つ町民の町内を経由する全バス路線の運賃を無料化していて、国の交付金を活用し、公共交通マイナンバー活用実証事業として実施しているそうです。もう安芸市もそういうことを参考に、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
続いて、(2)マイナ保険証の利用について。
現行の保険証が12月に廃止されるが、現在の利用率を伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
安芸市国保のマイナ保険証利用率は、令和6年7月現在で12.48%、後期高齢者医療のマイナ保険証利用率は6月現在で6.65%となっています。全国平均は、国保が12.83%、後期高齢者医療が10.99%で、高齢者の利用が全国より遅れぎみとなっております。
なお、6か月前の安芸市の利用率は、国保が4.35%、後期高齢者医療が1.67%であったため、半年で3~4倍ほど増えています。12月2日の保険証交付制度の廃止に向けて、今後も増加することが見込まれます。
安芸市におきましては、制度改正の周知広報を積極的に行い、全ての被保険者が必要なときに必要な医療が受けられる状態を確保しつつ、制度移行が円滑に行えるよう、適時適切な事務の執行に努めてまいります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今言われた数字は国保のみの方ですね。
続いて、障害のある人や介護施設入所者などの高齢者には不便性を持ったシステムではということをよく聞きます。例えば、車椅子の方には顔認証ができないとか、いろいろな問題が出ているらしく、そういうことの対策は考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
先ほど議員が再度言っていただきました率についてなんですが、国保が12.48%で、後期高齢者医療も申し上げまして、後期高齢者医療のほうは6.65%になっております。
続きまして、先ほどの御質問にお答えいたします。
現在、安芸市内37の医療機関及び薬局に顔認証つきカードリーダー、または顔認証機能のない汎用カードリーダーが設置されており、マイナンバーカードをカードリーダーに置き、顔認証や4桁の暗証番号の入力により、健康保険の資格情報の確認を受けることができるようになっています。カードリーダーは受付カウンターやその付近に設置されていることが多く、議員がおっしゃるように、受付がハイカウンターである場合は、車椅子を利用している方など、どうしても物理的に高さが合わないことがあるかと思います。このような場合以外にも、子供や障害がある方、高齢の方など、受付で自らカードリーダーの操作を行うことが難しいと思われるケースもあると思います。そのようなときは、家族や介助者、医療機関の職員の方などがマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力しても構わないこととなっております。
また、暗証番号による認証ができない場合は、医療機関等にその旨を伝え、システムを目視確認モードに切り替え、受付職員がマイナンバーカードの顔写真と、本人が同一であるかを目視で確認をし、本人確認とすることができる制度となっております。
マイナ保険証については、令和3年10月から運用が開始されておりますが、本格的な普及は現在進行中であり、国の新しい医療保険制度の改革については、利用する国民の不安や疑問を解消すべく、制度の周知広報が図られることが大事だと考えています。安芸市としては、こういった課題などについて、医師会などに情報提供していきたいと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういった方々に負担のかからないよう、対策をよろしくお願いします。
次、(3)カード使用状況についてですが、安芸市はマイナンバーカードで、コンビニでの住民票などは交付できないが、当初はコンビニでも交付できるのでと市民に伝えていたように聞きましたが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
議員のおっしゃるとおり、安芸市では現在、コンビニ交付をしておりません。マイナンバーカードの利用に当たりましては、全国的には、おっしゃるとおりコンビニで住民票が取れるということになっておりますが、安芸市で取れるということは、こちらのほうから伝えたかどうかはちょっと不明です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) コンビニで利用できると聞いていたので、マイナンバーカードを取得したのに、話が違うと立腹していた市民の方がいました。そのように勘違いをされている人がいるということは、もっと丁寧な説明が必要だったのではと思います。例えば、行く行くはコンビニで利用できますよとか、そういう話が、本人にはすぐコンビニで使えるとか、そういうふうに伝わっていたんではないかと思いますので、そこんとこ今言ってもいきませんが、ちょっと反省していただいて。
それでは、高知県内では幾つの市がコンビニで住民票の交付が受けられるようになっているのか伺います。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
高知県内は、23市町村、67%が導入済みです。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市のほうでは、どうなってますか。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 市は11市のうち、まだ導入していない市は4市あります。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ということは7市が導入しているということで、それだけの市ができるようにしているのに、安芸市はどうしてコンビニでの交付を受けられるようにできなかったのか、お伺いします。
○佐藤倫与議長 市民保険課長。
○福島由美市民保険課長 お答えします。
コンビニ交付を実現するに当たっては、住民基本台帳を扱うシステム業者などと、システム導入の契約が必要になります。安芸市もマイナンバーカードの普及に伴って、コンビニ交付の導入についての必要性を感じ、昨年度、導入に向けて資料収集や研修会にも参加するとともに、住基システムや戸籍システムの業者に相談いたしました。両方の業者ともに、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、令和7年度末までかかるシステムの標準化のため、作業が終了するまでコンビニ交付へのシステム改修対応は難しいとのことでした。
よって、当分の間、安芸市では導入することができず、現在のところ、令和8年度中の導入に向けて準備を進めているところです。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 早く取りかかればできていたことだと思いますが、ちょっとそこでも一歩遅れているような気がします。
いろいろ問題が発生しているマイナンバーカードですので、できるだけ市民の利便性が高まるような取組をお願いしておきます。
(3)高齢者の支援対策について。
(1)介護保険料高額の要因と保険料を抑え、要介護・要支援にならないための取組について伺います。
安芸市は県下で一番高い金額になっており、その理由として、在宅サービスの種類及び事業所数がともに充実しており、在宅サービスを利用しながら地域で暮らす介護サービス利用者が多い点との令和6年第2回定例会での担当課長の答弁でしたが、間違いないでしょうか伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時58分
再開 午前11時5分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 お答えします。
令和6年第2回定例会で、9番山下裕議員からの一般質問で、県平均は5,809円と聞いていますが、安芸市が高額になっている原因を伺いますとの御質問があり、それに対し、健康介護課長が、保険料が高額である主な要因は、安芸市は他市町村と比較して在宅サービスの種類及び事業所数がともに充実しており、在宅サービスなどを利用しながら地域で暮らす介護サービス利用者が多い点であると考えておりますと答弁しており、間違いございません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) それでは、安芸市は、他市町村と比較して、在宅サービスの種類及び事業所が充実しているとは、他市町村よりも、事業所数が多く利用者も多いということでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 お答えします。
この考えの基礎となるデータは、1つが、要介護認定を受けている方の介護サービス利用率であります。令和5年度の利用率は、安芸市81.7%、県75.1%となっており、安芸市が11市中、最も高い利用率であります。内訳は、施設サービスが安芸市17.7%、県17.1%で、ほぼ同じでありますが、在宅居住系サービスが安芸市64.1%、県58.1%で、県よりも6ポイント高い利用率となっております。
2つ目は、人口10万人に対する在宅サービス提供事業所数であります。最新データである令和4年度は、ヘルパー事業所は安芸市43.1、県32.6で、安芸市が1.32倍多く、デイサービス事業所は安芸市37.0、県23.7で安芸市が1.56倍多くなっております。在宅サービス事業所は、現在市内に16種類、36事業所あり、特に、過去5年間で4事業所が新規に立ち上がったことが影響しているものです。
これらのことから、在宅の介護サービス事業所数が多く、在宅の介護サービス利用率が高い点が他市町村と比較して、本市の介護保険料が高額である要因になっていると考える理由であります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 丁寧な答弁いただきましたが、ちょっと気になることがありますのでちょっとお聞きしますが、安芸市以外の施設へ入所あるいは通所している場合は、介護保険料は他市の施設に安芸市が支払いするわけですか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 介護保険給付費については、それぞれ利用に応じて利用された事業所のほうに支払いをすることとなっております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ちょっとこれ通告してなかったので分からなければ後で聞きますが、安芸市以外の施設を利用されている方の人数は把握できていますか。分かったらお願いします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 その件につきましては、事前通告をいただいておらず、明確なお答えができません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続きまして、第9期の給付額は、利用者の負担を考慮して保険料は引き上げずに基金を活用することで、第7期、第8期と同額とした答弁をしていますが、2018年から6年間も高額な給付額になっているのは、市の取組が悪いのではと思わざるを得ませんが、市長は安芸市の介護保険料が高知県11市の中で長期にわたり一番高額なということについてどう思われているのか、考えをお伺いします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 まず、第6期から7期に引上げとなった理由について御答弁申し上げます。
議員が御指摘の第6期から第7期は、介護保険料の基準額を月額5,880円から452円増額の6,332円としており、現在も同額に据え置いております。第7期における増額の要因は、介護保険給付費の財源の一つである第1号被保険者の負担率が22%から23%に改正されたこと、介護報酬改定や消費税の増額変更などによる増額のためであります。また、第7期の策定時、基金残高がゼロ円で基金が活用できなかったことも影響しており、保険制度維持のために必要な値上げであったと考えております。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど、担当課長のほうがお答えをいたしましたが、第9期の計画期間の給付額は、国が令和6年度に介護報酬を増額改定することで、第8期計画期間と比べ1.04倍増額となり、介護給付費の伸びへの影響は予想される中、収支が赤字になる見込みでございましたが、利用者の負担を考慮して保険料は引き上げずに基金を活用することで、第7期と第8期計画期間と同額としたというところでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 介護のことはなかなか難しいので、これから私も勉強していきながら質問していきたいと思いますが、安芸市もこういう在宅医療・介護保険についての冊子が出てます。私も気になって香美市、香南市、冊子いただいてきましたが、施設云々全然安芸市が飛び抜けて多いというふうには思いません、この内容を見てみますと。安芸市が出してる多いサービス、事業所のあれは、近隣の事業所が入ってますので、市外結構これ載ってます、中身見てみると。ほかのとこは、香美市なんかは、もう自分とこの香美市だけの施設で出てますので、これ見るとそんなに安芸市が飛び抜けて充実しているというふうにはちょっと思いませんでしたが、またこれもちょっと勉強して、また質問させていただきます。
先ほど、安芸市の高額な理由言われましたけど、例えば第7期、第8期と6,137円で、2番目に高額だった四万十市は第9期で5,900円に下がっています。これは介護予防取組の効果などではと思われますが、次の介護予防の取組についてお聞きします。
本市は、要介護・要支援にならないための取組について様々な支援を行っているとのことですが、その成果が出ているか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 要介護・要支援にならないための取組の成果についてお答えします。
いきいき百歳体操などの取組の効果によりまして、まず、この点を御説明させていただきます。
令和4年度から参加者を対象に、年に1回、フレイルチェックという体力測定によって、評価を実施しています。加齢による筋肉量の減少及び筋力の低下を判断する診断の結果では、該当者が令和4年度の4%から令和5年度には3%へと減少しております。また、筋肉量の減少はないのに筋力が低下した状態を判断する診断の結果では、令和4年度と令和5年度ともに12%で維持されております。
これらによりまして、介護予防の主な取組であります、いきいき百歳体操、サロンなどの御利用者の取組の効果が出ているものと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 6月定例会で、要支援者は令和元年294人から令和5年312人に、要介護者は令和元年1,012人から令和5年1,074人とどちらも増加傾向との答弁でした。この数字を見ると、その成果は現れていないような気がしますがいかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 成果につきまして、分かりやすいデータとなりますものを御答弁させていただきたいと思います。
○9 番(山下 裕議員) 単刀直入に、長くならないように。
○佐藤倫与議長 暫時休憩いたします。
休憩 午前11時17分
再開 午前11時17分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命を、高知県健康づくり支援システムデータで確認しております。第2期健康増進計画評価時点、最新データの平成26年と第3期健康増進計画評価時点、最新データの令和元年度を比較しますと、安芸市の健康寿命は、男性が0.3歳、女性は1.13歳長くなっているものの、県と比較して、男性が0.65歳、女性が0.01歳短い状況にあります。
先ほど、要介護認定増加しているという答弁があったということに関しましては、75歳以上の高齢者数が多くなってございますのが、主な要因と考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 介護保険料が高額というのは、その介護保険料を使ってる方が多いということで、やはり安芸市はそういう方が今増えている状況で、保険料を下げることができないという気がします。
先ほど答弁いただきました様々な支援というのはよく分かります。これはもうどこの市もしてることでありまして、安芸市が特別してるようなことではないと思います。いろいろ支援をしているのに、保険料が高いというところをちょっと言わせてもらいゆうがです。
支援は、いわゆるサロンとか、いきいき百歳体操に来られている方々は元気な方、主に高齢者でも元気な部類に入る方々が来られてます。伊尾木なんかでも95歳ぐらいの方が通ってきてますが、そういう方がやはり多いので、そういう方々は自分たちで健康管理して、外へ出て話をして体操してという気持ちがある方ながです。ただ、私言いたいのは、そういう方ではなしに、家に閉じ籠ってる方ながです。そういう方が、やはり病気になられる方が多いと思います。そういうサロンや百歳体操に参加していない方への応援とか要望、それから参加者が減少している地域もあると思います。そういう方、そういうとこへはどのような支援を、あるいは応援や対策を考えているのかお聞きします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 要介護・要支援にならないための取組は、先ほど議員も御指摘ございましたとおり、高齢者の閉じ籠り防止と青壮年世代の生活習慣病予防対策でございます。
令和5年度の要介護認定者1,362人の約6割が要支援1から要介護2で、その約3割が整形外科疾患でございます。転倒による骨折等で入院し、退院後の重度化防止のため、医療機関から新規認定を勧められる事例が多く、在宅サービスを充実させる傾向があります。退院後の在宅生活はもちろんのこと、日頃から家の中に閉じ籠らず、外出機会を多くすることや、地域の様々な活動に参加できることで、下肢筋力をはじめ、全身の筋力や柔軟性を維持・回復することが重要となります。
また、64歳以下で要介護認定を受けた人の平均年齢は56.3歳で、約半数が脳血管疾患や慢性腎不全などの生活習慣病を原因とし、全員が特定健診未受診者でありました。健診結果を基に、生活習慣の見直しができるよう、未受診者が健診受診できる支援の強化と将来を見通して、若い頃からの強い骨づくりが必要でございます。
保険料を抑える取組につきまして、介護保険料が最も低い市と安芸市との主な違いを見ますと、介護予防日常生活支援総合事業における日常生活に支援が必要な人への介護サービスの提供の仕方の違いでございまして、安芸市では、訪問型介護、通所介護などのサービスを国の基準を基本とする介護支援専門員などの有資格者が提供しております。
一方他市では比較的安価に提供できる多様なサービスとして、有資格者でなくても実施できる身体介護以外の家事支援や買物支援、移動支援などについて、緩和した基準によるサービスや生活支援サポーター、住民ボランティアなどが提供する体制となっておる点でございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 介護課長の答弁、すごく説明がたくさんあって答弁していただいてますけど、ちょっと時間もありますし、もうちょっと明確な答弁でお願いしたいと思います。
先ほど言われました安芸市と例えば土佐清水市を比較すると、1,500円ぐらい差がありますよね、介護保険料が。だから簡単に考えると、土佐清水市はこの介護を受けられる方が少ないということも関係してくると思います。ずっと4,850円で推移してますもんね。
そういったこともありまして、課長いろいろ言われましたけど、いろいろ安芸市もやってますということを言いたいと思うがですけど、やはり実際こういう金額になってますので、まだまだやりようは取組が足らないかと思いますので、ちょっと介護予防、もう少し取組していただいて、頻繁にやはり地域のほうに行って状況を聞いて、やはり回っていくとこなんかあれば行っていただいて、地域では声を掛け合ってます。サロンに来んかね、いきいき来んかね、地域の方々声かけてますが、なかなか出にくい方、たくさん人がいる中へ行きにくい方、特に男性少ないです。伊尾木のサロンも今ちょっと男性が増えてきてますけど、やはり声をかけていってますけど、また行政のほうからはそういったケアマネジャーとか、そういった方なんかのほうからもどんどん声かけていただいて、どうしてえいかということを伝えてあげてほしいです。自宅でいるよりは、やはりそうやって出ていって、どういうことが効果があるとか、そういうことまでちゃんと伝えていただくと、やはりもうちょっと増えてくるんではないかと思いますので、よろしくお願いします。
次に、(2)社会福祉協議会の移転について。
社会福祉協議会は、清水ケ丘中学校跡に移転するということですが、令和5年第3回定例会で、前市民課長は、多機能支援施設への社会福祉協議会の入居は、工事完了後、一部供用開始する他の機関の入居に合わせてできるだけ早い時期に移転する予定と答弁していましたので、多機能支援施設へ入居するものと思っていましたが、どういうことでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 高知県の多機能支援施設の整備につきましては、令和5年第3回定例会で、9番山下裕議員からの一般質問に対して、当時の市民課長が答弁しましたとおり、令和4年11月に県よりいただいたスケジュールでは、令和4年度から令和5年度にかけて実施設計を行い、令和5年9月に整備工事費の予算計上後、令和5年度から令和6年度にかけて改修工事を行い、令和6年10月頃より一部供用開始する案が示されておりました。
現状を県に確認しますと、施設の実施設計は完了しているが、一方で、建物の2階部分を使用する看護師養成校の運営事業者の選定に時間を要していることから、今後のスケジュールについては、再検討中であるとの回答がありました。以上です。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 先ほど健康介護課長から答弁がありましたように、県の多機能支援施設の整備が予定のスケジュールより遅れていることから、社会福祉協議会の同施設への移転についても、昨年、市民課長が御答弁した際の予定より遅れる状況となっております。このため、今月号の広報あきに社会福祉協議会のほうが折り込みチラシを入れておりましたが、今月の30日から旧清水ケ丘中学校のほうに一時的に移転をして業務を行うこととなっております。
旧清水ケ丘中学校への移転の理由につきましては、先ほど説明がありましたように、多機能支援施設の入居時期が遅れるということと、総合社会福祉センターの老朽化により多くの市民が利用する施設として安心安全な施設利用が困難であると社会福祉協議会のほうが判断したものでございます。今年の5月に社会福祉協議会のほうから市に対しまして、多機能支援施設の供用開始までの間、旧清水ケ丘中学校を一時的に使用させてほしいとの要望を受けまして、今回の移転に至ったものでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 多機能支援施設ですが、当初案では6年度の卒業生が対象になるということを聞いてましたけど、そういうことも遅れている、まだまだ未定ということでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 県から提供された令和4年10月時点のスケジュールでは、令和6年度10月頃に完成を予定し、令和7年4月から学生受入れ開始予定の案が示されておりました。
今後の具体的なスケジュールにつきましては、引き続き県に確認してまいりますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、令和4年時点のスケジュールからは大きく遅れ、施設の供用開始について、令和8年度以降となる見通しとなっており、看護学校の学生受入れも遅れるものと思われます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういった進捗状況を今まで、その後ですけど、議会への報告があったのか伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 先ほど申し上げました令和5年第3回定例会以降の御報告はございません。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 令和3年第4回定例会、市長挨拶では、令和3年11月30日に、副知事及び県健康政策部長から看護師養成の機能を有する多機能支援施設の整備について説明がありました。途中の部分は省略しますが、最後に、県や東部市町村と連携して取り組んでまいりたいと考えておりますという報告でしたが、それ以降、議会での報告はありませんので、この計画も中止になるのではと心配してますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 議員御指摘のとおり、私としてもすごい気にかかってまして、ちょっと議会への報告は明確ではなかったんでようしてないですが、度々県のほうへ担当部長をはじめ副知事もそうなんですが、要望してまいりまして、今年の7月と8月に県のほうから多機能支援施設についての再度のお話がございまして、それをもって今東部の9市町村長と協議をといいますか、協議をしたところでございます。その中にはまだ県は入っておりませんが、ちょっと時期はかなりちょっと遅れますが、東部一体となってちょっと再度県のほうへも要望してまいりたいというふうに考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) この施設はできると思っていてよろしいですね。はい、分かりました。
続いて、(4)旧庁舎及び旧安芸中学校跡地利用について。
調査委託業務の進捗状況をお聞きします。
令和6年第2回定例会では、豊富な業務経験を有する県外事業者を選定した。スケジュールとしては、10月をめどに、両施設機能に係る活用策の絞り込みを行うとの市長挨拶でした。今議会挨拶では、活用策の絞り込みや参入意向に係る実現可能性を含めた調査を開始しているとのことですが、具体的な内容を伺います。
○佐藤倫与議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 はい、お答えをいたします。
現在は、両施設に配置する機能、規模等を明確にする基本計画の素案策定及び民間活力の導入可能性調査に取り組んでおります。
この導入可能性調査につきましては、当該跡地活用事業への参入が期待できる、あるいは参入の意向を示している企業14社から、提案等のヒアリングを今実施しておりまして、活用策の絞り込みとともに民間参入の実現の可能性について調査を進めているところでございます。
これまでのヒアリングでは、もうちょっと具体的に申し上げますと、旧市庁舎は、基本構想と同様に図書館や文化ホールなどの基礎的な機能とし、加えて、子育て支援機能やカフェなどを併設した複合施設とする提案が多く挙げられております。一方、旧安芸中学校、市立の安芸中学校は旧市庁舎と類似の活用策、例えば文化ホールなども考え得るため、並行して、これを検討を進めておりますが、グラウンドや校舎の敷地面積が非常に広いことや、インターチェンジの整備時期が、整備の時期が不明、ちょっといつ頃になるかということがはっきりしないということであることなど、民間の調査している相手方ですね、民間の事業者側からは、もうちょっと市のほうで核となる一層具体的な施設機能の絞り込みや活用時期の明確化が必要、そういう御意見を複数いただいております。旧市安芸中学校のほうはですね。そういう意見をいただいております。
こうした御意見など、まだ課題整理をいたしまして、民間事業者がよりよい活用策の提案や、事業参入の障壁が低くなるよう、引き続き委託事業者と調整しながら取組を進めてまいります。
そして、10月末までに活用策の絞り込みを行うとともに、従来の行政主導で進める手法と民間活力を活用した手法のいずれが合理性が高いのかを明らかにしたいと考えております。
議員の皆様には、年内を目途にこうした進捗状況・方向性などを御説明したいというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) はい、分かりました。
旧中学校跡地は、まだ具体的な絞り込みには至ってないということですね。分かりました。
続いて、(2)旧庁舎周辺のまちづくりについてお伺いします。
今議会市長挨拶では、企業誘致の取組として本町商店街に来年3月よりオフィスを開所し、初年度は20名の雇用を目指し、将来的には40名規模の雇用を計画するなど、人口減少対策の起爆剤として、鋭意取組を進めていくとの市長の熱い思いが伝わってきました。久しぶりに明るい話題ではないかと思います。
令和5年第2回定例会で、旧県立安芸中・高等学校清和校舎の跡地活用について質問をしていますが、市長はこの清和校舎は、まさしく本市が取り組むサテライトオフィスなど、企業誘致の受皿として、条件が整った適地であると考えている。このため、担当課長とともに、県議会の総務委員会に出向き、要望活動を行っているとの答弁でしたが、今回のコンタクトセンターの誘致を契機に、安芸市の活性化のためにも清和校舎跡地の活用策の働きかけをお願いしたいですが、市長の考えを伺います。
○佐藤倫与議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 先にちょっとお答えいたします。
旧県立安芸中・高等学校清和校舎の跡地活用につきましては、これももちろん御存じのとおり県所有の施設であるため、昨年度に引き続き、今年度も県議会要望にて、人の流れやにぎわいを創出する施設活用の早急な対応を要望してきたところでございます。
県からの今年度の回答は、当面、校舎グラウンド及び体育館については、安芸中学校・高等学校のクラブ、部活が使用するとのことであり、跡地活用については、現在、県庁内で利用希望調査を行っているということでございました。この調査結果を踏まえた上で、活用策について協議するとのことであり、その際は、本市、安芸市の意見を伺いながら進めていくということでございますので、引き続き有効活用について要望や提案をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど企画調整課長が答弁いたしましたとおり、これまでの取組と、それから県からの回答もそうなんですが、現在本市は旧市庁舎、それから旧市立安芸中学校の跡地活用に加え、安芸高校の清和校舎周辺の中心市街地の空洞化対策など、まちづくりにおいて重要な局面を迎えておりますが、コロナ禍を転機とした市民の方々の生活意識やリモートワーク等の急速なデジタル化など、ライフスタイルの変化は移住や企業誘致用施策として進める地方にとって追い風の状況にあると捉えております。
清和校舎は、まちの中心部に位置する商店街と近接をしているほか、施設の充実した設備環境、また太平洋が一望できるロケーションなど、立地特性はまさに本市が取り組んでおります移住や関係人口の創出、また、企業進出に伴う雇用の確保といった新たな人の流れを生み出す拠点として適した条件にあるのではないかというふうに考えております。人口減少、超少子高齢社会が進行する中、当該施設には周辺地域のにぎわいを創出する役目も求められております。
県に対しましては、本市の情勢やまちづくりへの考えを理解していただき、早急に施設の利活用方法や対応案をまとめていただけるよう、引き続き要望及び提案などを働きかけてまいります。
以上でございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下 裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市長、ぜひよろしくお願いしておきます。
最後になります。
歯止めのかからない人口減少対策として、人が行き交い、人が集える、そして、雄大な太平洋を一望できる魅力的な建物があるこの施設をぜひ活用していただき、安芸市の活性化に努めてもらいたいとお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。
○佐藤倫与議長 以上で、9番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
4番 宇田卓志議員。
添付ファイル1 一般質問 山下 裕(令和6年第3回定例会) (PDFファイル 519KB)