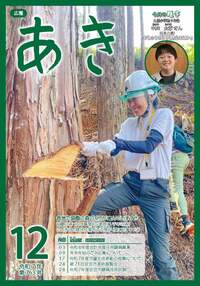議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 山下 裕(令和7年第1回定例会)
質疑、質問者:山下裕議員
応答、答弁者:危機管理課長、上下水道課長、建設課長、教育次長兼学校教育課長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。
東日本大震災が発生して今年で14年になります。あの大惨事の記憶がだんだん薄れかけていく中で、3月11日に各テレビ局で幾度となく放映される震災の場面を目の当たりにし、忘れてはいけないという思いと、災害に対する備えをすることの大切さを改めて認識させられました。亡くなられた方々に対して改めて哀悼の意を表しまして、(1)防災について、(1)緊急避難場所について質問いたします。
南海トラフ巨大地震の発生リスクが年々高まってきていますので、やはり各地域での避難訓練は大事だと思われますが、定期的に避難訓練を独自でされている地域はどれくらいあるのか把握できていますか、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
9月の第1日曜日に行う安芸市総合防災訓練を除き、独自に避難訓練を行った地域は、把握しているものでは、大字単位で言えば令和6年度実績は6地域、令和5年度実績は8地域となります。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木小学校では、就学時間内において毎月避難訓練を行っているようです。そして夜間の避難訓練も、以前は偶数月の第4土曜日に行われていましたが、令和5年度より学期に1回の実施になっているそうです。このように、夜間の避難訓練を定期的に行っている地域はどのくらいあるのか把握できていますか、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 把握しているものでは、令和5年度・6年度ともに夜間訓練を行った地域は、安芸、伊尾木、それと川北です。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木地区、赤野地区には野外テントが設置できる緊急避難場所を準備していますが、気がかりなのは真夏の暑さ対策、真冬の防寒対策はどのように考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 避難場所での屋外避難にはテントを用いますので、外気から身を守ることができます。また、令和6年度から避難所や避難場所へ寝袋の備蓄も順次進めています。
防暑対策は、屋内の避難所であればスポットクーラーを備蓄したりもしていますが、屋外の避難場所では、おのおのテントの小窓などを開けて風が通るよう対処することを想定しています。今後、防暑対策としてより効果の高いものがあれば、工夫し、取り入れていきたいと考えています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 2月22日、伊尾木地区での夜間訓練に参加しました。当時はかなりの寒さでしたので、ほとんどの参加者は防寒着で来ていました。当然、私も頭・首・手などは完全防備で参加しました。
約30名ほどでしたが、参加者の皆さんが口々に言っていたのは、巨大地震が発生したらこんな格好で避難場所に来ることはできるんだろうか、着のみ着のままで来るようになったら、テントでは一昼夜過ごすことができるだろうかと心配の声が上がっていました。
先ほど課長が言われましたけど、特にこのテント内での真冬の防寒対策はもう少し考えていっていただかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 先ほども防暑対策としては、一定工夫したものを取り入れていきたいというお話をさせていただきましたが、防寒対策としても、より、また効果の高いものがあれば、やっぱり同じように工夫して取り入れることも考えていきたいと思います。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 私も実際にこういう経験をしたので、今後の課題などが分かってきています。安芸市もハード面の整備は大分進んできていますので、今後はソフト面の対応が大事になるのではと思われます。
全国的にも野外にある避難場所の防寒対策はできていないと言われており、3月8日ですか、川北地区で夜間の避難訓練を行ったときに141人が参加という記事が出ていました。避難タワーとか一時避難所を使って数か所で避難訓練をしたということで、これだけ大々的にするのは安芸市では初めてではないかと思います。
だから避難訓練に参加された方がいろいろな課題を発見できたと思いますので、そういう課題を安芸市も危機管理課も、川北地区でまた確認を取っていただいて各地域で共有していきたいと思いますので、そういうことをよろしくお願いします。
続いて、令和6年第1回定例会で、避難タワーの外壁・屋根を設ける改修工事が可能かどうかの意匠設計を行っており、改修可能か検討するとの答弁がありました。
令和6年第2回定例会では、今後、港町1丁目と2丁目の津波避難タワーについて、改修可能となれば来年度改修工事にかかりたいと考えている。また、ほかのタワーについても今年度やる再計算委託業務の結果を見て、来年度から順次再計算などを行いたいとの答弁でしたが、そろそろ年度が替わりますが、どこまで進んでいるのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 令和6年度に津波避難タワーの屋上階への屋根・壁の増築及び屋上直下にある避難階への外壁増設の検討を行うため、安芸市津波避難タワー1号・2号改修工事設計委託業務を実施しました。
その結果を申しますと、1号タワー・2号タワーともに、屋上の直下にある避難階については外壁の増設は可能ですが、屋上階への屋根・壁については建築基準法等に適合しないため、屋根・壁を増築することはできないという結果となりました。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) あと、そのほかの順次取りかかるというところの対策というか、進んでいるのか再度伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
この結果を受けて、1号・2号では避難階の壁ということで増設する道筋は一定見えてきているのですが、今までのタワー全体で見ると、特に川北には屋上階しかないタワーもありますので、全体に適合するような方法もちょっと再検討が必要になってきて、今それらについても特に壁のほうを先にやれるような方法を、財源も含めてちょっと調整、検討しゆうところです。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) できることを先に、取りあえず取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
続いて、(2)津波新想定について質問します。
南海トラフ巨大地震発生時の被害見直しについて、県は来年3月に新想定を取りまとめるとのことですが、安芸市としてはどのような対策を考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 国の想定が、まず今年、この3月に出るという話です。それでまた、それを受けて高知県も8年3月を目途に被害想定の見直しを始めているところです。安芸市のほうでも、また県の被害想定が発表されるその8年3月、言うても年明けの4月になるかと思いますが、それ以降に国・県の動向を見つつ、高知県が来年発表する新たな被害想定を基に、安芸市地域防災計画などの各計画を見直し、南海トラフ地震対策や避難行動につなげていきたいと考えています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続いて、県の第6期行動計画案の目標に対して安芸市の計画はどうなっているのか。津波避難意識率、住宅耐震率、災害関連死の防止に向けた避難環境の整備や支援、受援体制の強化、臨時情報への対応強化などの目標に向けての取組はできているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 高知県南海トラフ地震対策行動計画の第6期については、今日までを意見公募期間として素案が公表されています。内容は5期までの取組の成果や課題を分析・評価し、総括した上で対策を見直し、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の教訓を基に、新たな対策を取り入れることが示されています。
こうした成果や課題を踏まえ、4つの観点で事前の備えを強化するとして、第1に自助・共助の取組の強化、第2に避難環境の整備の強化、第3に復旧・復興作業に向けた事前の備えの強化、第4に災害に強いインフラ整備の加速化が示されています。安芸市においても第6期行動計画に沿って取組を強化・加速化していき、南海トラフ地震に備えたいという考えを持っています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 次に、事前復興まちづくり計画の策定は進んでいるのか。令和6年度作成の安芸市復興方針案を基に、7年度予算に2,100万円の委託料予算を計上していますが、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 現在、安芸市事前復興まちづくり計画基本方針案及び業務手順書案を作成しているところです。この基本方針は、令和7年の5月か6月に開催する防災会議に諮り、その後公表する予定です。また、その後に順次各地域と基本方針に沿った南海トラフ地震、大規模災害後の各地域におけるまちの形について話合いを行い、地域ごとの事前復興まちづくり計画を作成する予定となっています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 黒潮町は令和7年2月20日に県内で初めて事前復興計画を策定していると聞きました。室戸市でも策定される予定だということを聞いていますので、安芸市も順次取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、堤防整備による津波対策はどのように考えているのか。
以前何度か質問していて、安芸海岸の堤防はL1津波には対応できるとの答弁をいただいています。ただ、現状の堤防を見ると高さが確保できているとは思えないほどになっています。
高知市・南国市・土佐市は国と県が連携して、21年度に堤防補強整備が完成しています。香南市も国直轄での堤防補強が決まり、L1津波に対し人的・物的被害をゼロにできるとのことです。安芸市としても今後は県・国への要望をもっともっと積極的に行い、沿岸部の市民が少しでも避難時間を稼ぐことができ、被害範囲を縮小する効果が期待できるような取組をお願いしたいですが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 堤防につきまして、特に防潮堤につきましては過去にも一般質問で出よってて答弁していたとおりのことで、その点に関しては、今の進捗も踏まえてちょっと高知県のほうにはお聞きさせてもらいました。
結果としましては、前に答えたとおり、L1では最大9.1メートルが想定されて、安芸海岸の防潮堤高さは9.6~11.4メートルであるため、津波高さに対する防潮堤の整備基準を満たしており、また揺れに対する耐震力も基準を満たしているとのことです。
ただし、過去にも答弁したとおり、防潮堤の水圧に対する耐力調査につきましては、高知県下においてより危険度の高い海岸から整備計画を立て、順次改修を行っている中、安芸海岸の整備計画はまだ今も上がっていない状況であるため、耐力調査はまだ実施していないと確認しています。
それで、こういうこともまた前に進めていくためにはこういう要望も必要だと考えますので、高知県に安芸海岸の整備計画を上げるよう、また防潮堤の水圧に対する耐力調査を行い、結果を踏まえ、必要となれば防潮堤の改修など具体的な手段を取るよう、県へ要望も上げていきたいと考えています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ぜひ積極的に要望をお願いしたいと思います。
安芸町内の方によく言われます。あの堤防で津波を止めることができるか。心配してるのは庁舎だけ移転して職員は北へ逃げて、我々はそのままほったらかしやいう声が出てます。だから、ああいう堤防を補強することによって市民もやっぱり逃げる時間が稼げる、安芸市もそういうことを考えてくれているという思いが出てくると思いますので、積極的な要望をぜひお願いしたいと思います。
続いて、(2)上下水道管の老朽化対策について、(1)上下水道管の耐震化状況について質問します。
埼玉県では下水管の破損で道路が陥没し、トラックが転落した事故が発生しています。安芸市の場合はこのような大規模の下水管はないと思いますが、やはり老朽化や耐震化が十分なのか心配だとの市民の声を聞きますので、現在の状況について質問させていただきます。
まず、安芸市の上下水道施設の耐震化はどれほど進んでいるのか伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えいたします。
まず、水道管の耐震化につきましては、水道施設設計指針によりまして基幹管路は最大級のL2クラスの地震への耐震性、それから配水支管につきましては発生頻度の高いL1クラスの地震への耐震性のある管種が定められております。その定められた管種は適合管として認定されておりまして、その適合管により布設されている水道管は耐震性を有するとされております。
この指針に基づきます現在の耐震化の状況につきましては、令和5年度末で基幹管路は、総延長75キロメートルのうち約30%の23キロメートルが耐震適合管となっております。配水支管につきましては、総延長約128キロのうち約70%の約90キロメートルが耐震適合管となっております。
続きまして、主要な水道施設につきましては、配水池11か所のうち4か所が耐震性を有しております。
続きまして、下水道の状況について御説明します。下水道の管渠及び施設の耐震化につきましては、下水道施設の耐震対策指針と解説に基づき実施することとなっております。
本指針に基づきます耐震化の実施状況は、管路につきましては令和5年度末で、汚水幹線、防災拠点となる施設までの汚水管路及び雨水幹線等重要な管路の約7.7キロメートルのうち、約32.5%の約2.5キロにつきましては、耐震性を有しておるということになっております。
その他汚水管路につきましては、総延長約42キロメートルのうち約62%の約26キロメートルについて、耐震性を有する管路となっております。
処理施設につきましては、人命、揚水機能の確保のため、管理棟及びポンプ棟の耐震化から着手し、耐震診断が完了しましたことから、耐震工事に順次着手いたします。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) なかなか大変なことだと思いますけど、予定としてはいつ頃完了するという予定は立てているでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えします。
今後は、国により策定を求められましたあき総合病院など重要拠点への給水確保、汚水処理機能確保などを主要観点とした安芸市上下水道耐震化計画を主要計画と位置づけ、被害軽減と早期機能回復を図るため耐震化を進めることといたしております。
先ほど御答弁させていただきましたように非常に管路も多うございますので、いつということはなかなか明確にお答えはできませんけれども、できる限り対策を早期に進めていきたいというふうに考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 病院や避難所というところなどを重点的に思ってましたけど、課長が既に答弁してくれましたので、これは抜かします。
次に、(2)の耐用年数が過ぎた水道管の補修状況について伺います。耐用年数の過ぎた水道管は全体の何%ですか、伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えいたします。安芸市の水道管は、基幹管路・配水支管の合計で、先ほどお話しさせていただきましたけれども、203キロメートルございます。そのうち耐用年数40年を経過した水道管につきましては、令和5年度末で約43キロとなっております。
維持管理につきましては、専門業者による漏水調査を毎年実施しておりまして、管路の破損の有無などを適宜確認いたしております。本調査により確認された漏水箇所につきましては迅速に修理を実施し、重大事故につながることのないように努めております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) これも整備がいつ頃完了するかということを伺いたいがですが、なかなか難しいと思いますけど。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 耐用年数を経過した管路の更新につきましては、なかなか、計画的にやっておりますけれども、最近は基幹管路等の重要な管路の更新を優先的に進めておりまして、いつということを明確的にお答えすることはできませんが、布設年度や管の種類、それとか道路工事の実施計画との調整などを図りまして、適宜更新に努めているところでございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 先ほども言いましたが、老朽化した下水管の破裂で大事故が発生していますが、老朽化対策への対策は進んでいるのか伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 水道管、それから下水道管につきましても適宜調査を行っておりまして、職員による目視等をするとか、建設課とタイアップして路面状況を確認するとかいたしておりまして、変調等があれば直ちに対応を図っているところでございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 全国的に見ても耐震化・老朽化の調査がなかなか難しいいうこともいろいろ聞いていますので、人員不足なんかもあり大変だということも聞いてますけど、対策よろしくお願いします。
続いて、南海トラフ巨大地震などの大規模災害による水道管の破裂などが想定されますが、対応はどのように考えているのか。資材などのストックは、市はしていないと以前は言っていましたが、水道などのインフラの壊滅的被害により復旧が大幅に遅れたという事例もあるようですので事前計画が大事ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えします。
上水道・下水道につきましては、日本水道協会、それから日本下水道事業団等と災害援助協定を結んでおります。また、市内組織としては安芸市上下水道工事業協同組合などとも災害援助協定を締結いたしております。こういった組織と十分連携を図りながら、早期復旧に向けて取り組んでいくことといたしております。
それから資材の備蓄につきましては、その備蓄する資材の選定、それから保管場所、保管時の品質管理などの課題により、使用頻度の高い通常時の補修材のみ今現状備蓄しておりますので、以前御答弁させていただいた内容と変わってはおりません。
ただ、災害発生時におきましては、先ほど答弁させていただきました災害援助協定を締結している機関と連携して、資材の調達を速やかに行い、水道水、それから下水道の機能の早期復旧に取り組むことといたしております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市内で確保されているというのなら少し安心できるがですけど、その日本水道協会高知県支部なんかで保管してあるとなると、災害が県下的に起こりますので、なかなかすぐの援助というか、そういうのは難しくなるのではないかと思いますので、やはりある程度市内でそれなりの確保ができることが望ましいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。
続いて、(3)市道整備について。安芸橋西詰からの市道整備についてですが、現在の整備状況についてどこまでできているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
御質問の市道につきましては、令和4年度に測量設計、令和5年度より舗装の打ち替え工事及び側溝改修に着手いたしております。現在、黒岩デパート跡地前から東方面に向けて梶橋までの区間、約210メートルの舗装と側溝整備が完了しております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今後の計画についてはどのようになっているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 今後の予定としましては、令和7年度に土居橋から南方面に向けて、本町通りまでの区間約200メートルの舗装の打ち替え工事と、一部側溝改修を実施いたします。また、梶橋から安芸橋西詰交差点までの区間約190メートルにつきましては、令和8年度から工事に着手する予定としております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 先ほど課長のほうからも答弁がありました、安芸橋西詰より梶橋までの区間ですが、道路状況が非常に悪く下水工事の跡が凸凹状態であり、市街地の道路では一番ひどいのではと思われます。また、家屋の入り口周辺は排水路の準備ができておらず、道路と家との間に段差ができており、危ないという声を聞いています。こういう道路状況が悪い箇所を優先的にできないものでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 先ほどの答弁で、御質問の区間につきましては令和8年度に工事着手予定と答弁させていただきましたが、優先的に工事ができないかとの御質問に対しましては、令和7年度に実施予定の、先ほど答弁しました土居橋から本町通りまでの南北の区間につきましても同様に路面舗装の状況が悪いこと、また比較的交通量の多い黒岩デパート跡地前の四差路交差点におけるマンホール等の段差解消などもございますことから、令和7年度は、まず当該区間南北を整備することとしております。
なお、議員御指摘の区間につきましても令和8年度より順次整備してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 令和8年度にはできるということで、よろしくお願いします。
続いて、(2)市道安芸伊尾木線の道路状況について質問します。
メルトセンターを下りてきて県道を渡ったところから春日橋までの区間、市道安芸伊尾木線の道路状況が非常に悪くなっていて、整備する必要があるのではという市民からの要望が出ています。
新庁舎、そして統合中学校ができてから乗用車の往来が増えてきており、その上、高規格道路の整備のために大型のダンプカーが毎日数十台の往来があります。メルトセンターを下りて有ノ木橋までの約200メートルの区間では道路が波を打っているような箇所が幾つかあり、その上この区間に2つある横断側溝もかなり傷んでおり段差ができている状態ですが、建設課としてはどこまで確認できているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 御指摘のとおり、当該区間には横断側溝2か所、それから路面の底に暗渠が通っておることから、舗装がちょっと波打っているところも現地のほうで確認をしております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続いて、有ノ木橋から西に坂を下ったところの横断側溝の段差もかなりあり、東向きの大型ダンプカーなどは北側を避けて中央線をオーバーして通っているところをよく見かけます。また、JA東支所の前も補修してある箇所が剥がれていて、凸凹が次第に増えてきています。また、たくさん見られる亀裂箇所はだんだんと幅が広がってきていると感じられますが、確認できているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 先ほどと同様に、安芸伊尾木線の舗装の状況、また横断側溝の状況、がたつき等段差でありますとか舗装のひび割れ等も、現地で状況については把握しております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 私も庁舎へ来るときはその道を通ってきますので、通るたんびに気になって見ていると、やっぱり亀裂もだんだん幅が広がってきているように思います。
その市道周辺のハウスの農家の方が、ちりを積んだ車が、軽トラックとかありますけど、その車がそういう悪いところを通るときに、がたんがたんバウンドして上下しているそうです。ちりをよく捨てていくそうです。ちりが飛んでいくということですね、振動で。そういう苦情も出ています。
これらは、先ほども言っていますが、高規格道路建設のために大型トラックが毎日数十台土砂を積載して往来していることが原因の1つではないかと思われます。市道ですので安芸市の管轄になり、補修工事は大変だと思いますが、ただ、高規格道路の周辺整備事業で整備費を国から捻出することができないものか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 御指摘のとおり、現在、高規格道路の整備工事が川北・伊尾木地区でも進んでおりまして、それに伴う大型車両の通行というのが非常に多い状況というのは確認をしておるところです。
高規格道路の周辺整備というお話でありますけれども、周辺整備といいますのは、一定その実施基準というのがございまして、市町村道等を整備する場合は高規格道路の中心線から500メートルの範囲にある市町村道、その他道路とすると、そういったように基準がございます。
議員御指摘の市道安芸伊尾木線の伊尾木地区~川北地区につきましては、現在、高規格道路の本線から500メートル以上離れておりましてこの実施基準を満たさないことから、周辺整備事業の対象ということにはなりません。
ただ、本市道に限らず日常の道路維持管理につきましては、市単独の道路維持予算により横断側溝の段差解消やグレーチングの騒音対策、車道舗装の補修等、これまでも適宜実施しています。今後におきましても、限られた予算の中で緊急性・必要性等を見極め、計画的に修繕に取り組んでまいりたいと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市の単独でなかなか大変な事業になると思います。そこだけではないですのでね、安芸市の道路状況の悪いところは。
先ほども言いましたように、そういう高規格道路の工事のための車両が多く通っているので、こういう悪い道というか、段差ができたり亀裂が入ったりするのが大きな要因だと思いますので、やはり市単独はなかなか厳しいと思いますので、県・国にそういった話の要望をして、県・国に一度確認に来ていただいて、大型ダンプは、トラックが数十台も毎日通るような想定は、あの道はしてなかったと思うんですよね。だから、ますますこれからはひどくなると思いますので、できるだけそういった要望もお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次、(3)市立安芸中学校通学路についてですが、中道線の整備計画は予算審議でも質問されていたと思いますが、今後の状況を一度お聞きします。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 通学路の、まず南北の市道中道線につきまして答弁させていただきます。
本年度末までに、計画延長550メートルのうち340メートルが完成しています。残り210メートルにつきましては、令和7年度に用地買収及び移転補償の完了が見込まれる区間170メートルを整備する計画としております。
なお、令和7年度末の全線供用を目指して鋭意取り組んでいるところでございますが、移転先の手続や代替地の選定等に不測の期間を要しており、一部区間の完了が令和8年度末となる見込みとなっております。市民の皆様並びに学校関係者・保護者の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き御協力をお願いいたします。
東西もですか。南北だけでよろしいですか。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) その中道線から中学校へ向けての市道と、天神坊橋に向けては東西の市道ですね。その工事計画と終了予定を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 東西の西木戸一ノ宮線につきましては、天神坊橋西詰から西方面へ、安芸中学校南側を経由し、旧県道安芸物部線の、現在市道安芸井ノ口線までの全長1.2キロメートルのうち、学校敷地前の整備済み区間200メートルを除く約1キロメートルを整備するものでございます。
進捗状況としましては、東から順に、天神坊橋から市道中道交差点までの区間については現在測量設計を実施しており、令和7年度より用地買収に着手する予定としております。
次に、市道中道交差点から中学校東側までの区間140メートルの歩道整備については、4月初旬、来月の新学期が始まるまでに工事が完成する見込みです。
また、学校から帯谷川までの区間180メートルの整備につきましては、現在、埋蔵文化財の発掘調査を行っておりますので、その調査が完了後、工事を発注する計画といたしております。
最後に、帯谷川から市道安芸井ノ口線の区間につきましては、他工区の事業進捗を見ながら適宜実施してまいります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 中道線の車の往来が非常に増えているため、安芸中学校へ左折するところの交差点に横断歩道が必要との市民の要望が出ていますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 御質問の交差点の横断歩道の設置につきましては、これまで所轄の警察署と何度か協議を進めてきており、現在安芸署のほうから県警本部へ上申されております。
南北の横断歩道につきましては、今後県警本部のほうで、先ほど答弁しました歩道整備の工事が完了した後、現地等を確認するというふうに伺っております。
なお、南北の横断歩道が設置されるまでの間につきましては、横断する場所をラインで明確化して車のドライバーに視覚的に認識させ、注意喚起を促すための横断指導線を市のほうで整備し、通学路としての安全確保に努めてまいります。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 市道中道線で交通量が増えて危険ということで、桐ヶ内団地北西の交差点に東西に渡るための横断歩道というところで、教育委員会のほうから報告させていただきます。
学校教育課のほうでは、令和6年4月の統合中学校、安芸中学校開校時点で交通安全上の懸念がありましたことから、通学時間帯の通行量等の状況を整理・確認をした上で、昨年の4月に桐ヶ内団地北西の交差点の南側に東西方向の横断歩道の設置を安芸警察署に要望し、県警本部に上申をしていただいておりました。その結果、現状の交差点の構造では歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所が現在ないということから、横断歩道の設置はできないということで公安委員会が判断をしたというような回答を、安芸警察署からもらっております。
そのため現在の対応としては、学校において生徒の交通安全に対する注意喚起をしていただいているというところです。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) それでは、あの交差点が南北の横断歩道は可能だと、今後。東西は無理だということだと思いますが、市道の整備をするに当たり、その東西の横断歩道ができるような用地というか、そういうのは見込めないのでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 南北の横断歩道につきましては、現在、完成した後に県警本部のほうが現地を確認するということを伺っておりますというのを、先ほど答弁させていただいたところです。
東西の横断歩道につきましては、先ほど学校教育課のほうから答弁しました、滞留場所がないということですけれども、東西の市道西木戸一ノ宮線の現在、測量設計を実施しておりまして、その中で歩道整備を進めてまいります。
その中で交差点協議、当然必要になってきておりますので、その整備の中で滞留所については新たにつくるということになってくると思われますので、滞留所ができた後に横断歩道は整備されると思われますので、引き続きその所轄の警察署と、設置に向けての協議は進めてまいりたいと思っております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 安全確保のために、ぜひよろしくお願いします。
続いて(4)小学校統廃合について、(1)各地域の保護者の意見・要望についてですが、令和6年10月に保護者対象の説明会が終了していると思いますが、どのような意見などが出ていたのか伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
小学校及び保育所の保護者を対象に、8小学校と安芸おひさま保育所、それから矢ノ丸保育園の10か所で保護者説明会を、令和6年8月から10月までの間で実施しました。前回の説明が平成29年度の説明ということで7年が経過をしておりましたことから、改めて個々の意見を伺う形で行っております。
まず、説明をした内容でございますが、これまでの統廃合の経緯とか児童数の推移、それから学校施設の現状、それからこれまでの小学校2校案を継続をし、旧清水ケ丘中学校区は同校の跡地に建て替え、それから旧安芸中学校区は場所は未定だが1校とし、立地場所については、これまで市街地に近く津波浸水想定区域外を条件に一定規模の用地を探してきましたけれども、条件を満たす場所を見つけるに至っておりませんことから、今後は津波浸水想定区域内まで範囲を広げ、津波浸水対策とセットで立地場所の検討を考えるということ、具体的には市街地付近の農地等を造成、かさ上げして新設するケースでありますとか、または安芸第一小学校の用地をかさ上げをして建て替えをするというのを例示して説明をいたしました。
またスクールバスでの通学、それから学童保育所の併設、それから開校準備委員会の設置、この3点を検討するということをお伝えをしております。
お尋ねの要望とか意見につきましては、旧清水ケ丘中学校であります下山・伊尾木・川北・土居・井ノ口小学校の5校では統合に反対する意見はなく、そのうちの4校、下山・川北・土居・井ノ口で市に1校でもよいのではとの意見があり、旧清水ケ丘中学校が適地ではないかとの意見や、現在の安芸中学校の近くになれば兄弟の送迎に便利であるとの意見がありました。
旧安芸中校区である安芸第一小学校では、浸水想定区域外へ移転してほしいとの意見もありましたが、大半が利便性を重視するという意見で、地域の避難所として機能強化を図る観点からも、現在地での建て替えを望むものでございました。
穴内小学校では地域に学校を残すべきとの意見もありましたが、大半が学校の移転統合には反対はしないが、現在の安全な浸水想定区域外から危険を伴う浸水想定区域内への通学については納得ができないとの意見でございました。
赤野小学校では、一貫して地域に学校は必要であり、統合の前に小規模校への支援や地域の活性化の取組をすることが優先であるとの意見でございました。また、要望としましてはスクールバスが必要ですよというようなことや、旧清水ケ丘中学校に設置する場合には、隣接をします県道の安全を高める道路改良が必要だというような要望がありました。以上でございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 説明会は保育所の保護者も対象にということだったと思いますが、その保護者ですけど、小学校の保護者と保育所の保護者の参加数はどういう状況でした。というのも、現在在学の児童、多分、新統合小学校には入学できないと思うがですよね。だからその保育所の保護者のほうが当然対象になり、真剣に考えているのではないかと思いますので、ちょっとどういう状況やったかお伺いします。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
保護者につきましては一応68名の参加がございまして、特におひさま保育所では4名、矢ノ丸保育所では3名でございました。
ただ、各小学校で行った説明会の中にもその保育の保護者の方がいたことは間違いありませんが、その人数まではちょっと把握ができておりません。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続いて、各地域住民の意見・要望についてですが、学校の保護者と大分意見が違ってくるのではないかと思いますが、令和7年2月で地域説明会が終了していると思いますので、どのような意見が出たのか、これもお伺いします。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
地域住民に対しましては、公民館単位の15か所で説明会を令和6年11月から令和7年2月まで実施し、説明資料と説明内容につきましては保護者説明会と同様のものというふうになっております。
赤野地区では、移転統合は受け入れられない、まず小規模校への支援、それから人口減少対策・少子化対策・地域活性化など、市がやるべきことに取り組む説明をすることがまず必要。地域に学校は必要であり、学校を残す話を先にしなければならないとの意見があり、小規模校であっても、学力を含め地域の子供たちの育ちを見ているとデメリットはない。津波浸水想定区域内に立地していても避難訓練をしているので問題ないとの意見がありました。
穴内地区では、小規模校の限界が来ており統合は仕方がないが、津波浸水想定区域に子供を通わせられない。第一小学校の建て替えについては、かさ上げをしたとしても津波火災による危険性が高く反対であるとの意見や、市に1校でもいいのではないかとの意見がありました。一方で、地域に学校は必要、保育所と小学校は地域に置いてほしいとの意見もありました。
市民会館・黒鳥公民館では、第一小学校に建て替えを前提として、敷地の狭さというものを懸念する意見がありました。
井ノ口、それから川北・土居地区では、安芸市に1校でいいのではないかとの意見でございました。
伊尾木地区では、市が2校ありきだからこれまで話が進んでいないと。地域に小学校は必要で、伊尾木小学校を高台移転して特認校の指定を受けたらどうかとの意見と、とにかく早く子供の安全が確保されるよう進めてほしいとの意見もありました。また、人口減少に対する市の取組ができていないとの指摘を受けました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 要は、小学校の統廃合の進捗がすごく遅れているということで、いろいろ保護者の間には不満がかなり出ていると思います。
地域では地域に学校を残してほしいと、廃れるからというような声も出ていると思いますが、この説明会は今後はもう行わないということですか、伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
今回の保護者及び地域説明会での意見を踏まえ、統合の方針を整理した上で再度説明会を開催したいというふうに考えています。
現段階では説明会の方法はちょっと決めておりませんが、地域と保護者を対象に、一緒にというようなことも含めて、そうした説明会を小学校区ごとか、または旧中学校区ごとに開催するというようなことも考えられます。
いずれにしても集約をした後、また説明には赴くつもりでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 地域住民の意見で一番多かったと思いますのが、学校がなくなると地域が廃れるという声をよく聞きます。
この件に関して、学校教育課としてはどのように受け止めているのか伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
学校の統廃合に関する課題は、単に教育施設が地域になくなるというものではなく、地域のコミュニティーや活力に大きな影響を及ぼすということが懸念をされておりますので、教育委員会としても非常に重要な課題で、深く考慮しているところです。
このたびの地域説明会においても、どの地域も学校との結びつきというのは非常に深く、学校がなくなるということをよしとしている人は1人もいませんでした。しかし、子供の安全や教育環境を考慮して統合もやむなしと、苦渋の判断をしたというような声も聞き取っています。
教育委員会としましては地域との連携を強化をし、統合後の地域と学校のありようといいますか在り方について話合いをしながら、例えば移転後の学校施設を地域のコミュニティー施設や子供たちの学びの場として活用する検討のほか、総合的な学習の時間や放課後、土曜日等の教育活動を通じて、地域資源を活用した学習プログラムや、地域イベントを通じて地域に出向き、あるいは地域で学ぶ、それから地域課題の解決に向けて学校・子供たちが積極的に貢献するなど、学校と地域の双方向の関係づくりを創出するなど、これまでの地域との関係を残しながら、より活気あるコミュニティーとして発展していくことを目指したい。そして学校統廃合による影響を最小限に抑えつつ、地域の活性化に向けた取組の方向性を検討してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういうことをいろいろ検討していただいて、ある程度納得はできる。取りあえずは生徒の、子供の命を守る取組がまず大事ですので、よろしくお願いします。
(3)第一小学校移転についてですが、先ほど学校教育課長から、住民の意見・要望で大分、第一小学校のことが出てましたので、ちょっと重複することがあるかも分かりませんが、続いて質問していきます。
第一小学校も取りあえずは移転するということを言っていますが、安芸町内の住民が避難できる施設であり、避難場所としては建物を残すのか伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前10時59分
再開 午前11時6分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えします。
第一小学校を避難場所として残すかという御質問です。
第一小学校につきましては、校舎の屋上が指定緊急避難場所になっております。また、体育館は風水害の際の避難所の指定も受けております。避難所の運営マニュアルというようなものも存在しております。学校の機能がなくなったとしても、避難所としての機能は存続するものと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 第一小学校は屋上に行かなくても大丈夫な高さが確保できていると思うがです。大学の教授が、あそこの場所は大丈夫だと言われたということも聞いています。
先ほどから学校教育課長が言われるように、保護者の要望も、第一小学校を残せという要望が大分出ているということも聞きましたが、移転先がまだ決まってません。よく聞くのは、津波が来るので学校は移転するが、市民がその場所へ避難するというのはおかしな話じゃないかという声も聞きます。
市民が安心して暮らせるためにも、小学校をかさ上げするか、ピロティー工法での建設で津波に対応できる取組をし、安全な建物として児童生徒、そして市民の避難場所となる現地での建て替えができないものかという要望がたくさん聞かれますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 今回の説明会におきまして、市の小学校2校設置案として、旧安芸中学校区は設置場所が未定だが、考え方の1つとして安芸第一小学校のかさ上げによる建て替えが考えられると例示して説明したところではありますが、先ほど来、私が答弁申しましたように、保護者、地域説明会での御意見の中には、第一小学校の建て替えを望む声があった一方で、津波による浸水は防げたとしても津波火災の懸念があること、そもそも津波浸水想定区域内に小学校を設置するべきではないといった意見がありました。また、多くの地域で小学校は1校でいいのではないかというような意見もございました。
現時点では、これらの意見を基に子供たちのために何が一番最善であるかを検討し、小学校の設置案を改めてお示ししたいというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 火災災害とか、一番の原因が港のタンクがというようなことが、東日本は多かったですよね。安芸市においてもハウスのタンクが、まだ十分耐震化されていないものがあります。そういったところも、危険なところがたくさんあると思います。
東日本大震災以降で、浸水区域に学校建設したところがあります。宮城県亘理町荒浜中学校は、平成23年3月11日、東日本大震災による大津波で被害を受け、当時は移転建設の意見もあったそうですが、地区の復興には学校が必要との意見が多く、震災発生場所と同じ場所で平成26年8月に、1階を柱だけの高床式、いわゆるピロティー工法で校舎を建設し、現在、まちの教育行政の復興のシンボルとして新しい校風を築いているそうです。
同じく長瀞小学校、児童191人も、津波被害を受けた現地で26年8月に校舎の落成をしています。小学校で現地再建を果たしたのは宮城県では初めてだそうですが、現在、両校は亘理町の一時避難所と位置づけられているそうです。
以前執行部は、東日本では災害地に公共施設を建設していないとの答弁でしたが、実際にこのような事例もありますが、教育長、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
安芸第一小につきましてはちょっと別になりますけど、高知県の防災マップで液状化の可能性が大きいとされております。今後第一小学校での建て替えをするとなった場合は、ボーリング調査など必要な地盤調査を行った上で、浸水しない高さに一、二メートルのかさ上げ造成をし、ピロティー構造ではなく一般的な壁で囲んだ建物構造で建て替えたいなというふうに、現在では考えています。
ただし、駐車場スペースが第一小学校は少ないとかいうようなことで、そういった確保が必要な事情によってはその用地費とか建築費の比較検討をせないかんので、そのピロティー方式が採用される可能性はゼロではないというふうには考えています。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ピロティーで建設すると、その下、1階が駐車場になりますよね。そういったところの利点もありますし、かさ上げして盛土にするよりはピロティーにしたほうが波が抜けます。だから、その火災発生も少なくなってくると思いますよね。だから2メートルかさ上げすると十分波が抜けていくようなら、もう十分な建物ができるのではないかと思いますので、そういった検討をぜひ前向きにお願いします。
3月11日ですか、岩手県釜石市で行われた追悼式では、命があれば何とかなる、とにかく安全な場所に避難してくださいと訴えています。そのためには、身近に市民が安心して避難できる場所が必要と思われます。
第一小学校がなくなれば子供たちの姿が見えなくなり、まち全体が寂れてしまうのではという多くの声も聞かれます。高床式の校舎にすれば児童生徒が安心して通学でき、そして安芸町内の方々も避難できる、安全で安心な場所となるはずです。第一小学校の現地での建て替えをお願いいたしまして、私の一般質問を終了いたします。
○佐藤倫与議長 以上で、9番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
応答、答弁者:危機管理課長、上下水道課長、建設課長、教育次長兼学校教育課長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。
東日本大震災が発生して今年で14年になります。あの大惨事の記憶がだんだん薄れかけていく中で、3月11日に各テレビ局で幾度となく放映される震災の場面を目の当たりにし、忘れてはいけないという思いと、災害に対する備えをすることの大切さを改めて認識させられました。亡くなられた方々に対して改めて哀悼の意を表しまして、(1)防災について、(1)緊急避難場所について質問いたします。
南海トラフ巨大地震の発生リスクが年々高まってきていますので、やはり各地域での避難訓練は大事だと思われますが、定期的に避難訓練を独自でされている地域はどれくらいあるのか把握できていますか、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
9月の第1日曜日に行う安芸市総合防災訓練を除き、独自に避難訓練を行った地域は、把握しているものでは、大字単位で言えば令和6年度実績は6地域、令和5年度実績は8地域となります。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木小学校では、就学時間内において毎月避難訓練を行っているようです。そして夜間の避難訓練も、以前は偶数月の第4土曜日に行われていましたが、令和5年度より学期に1回の実施になっているそうです。このように、夜間の避難訓練を定期的に行っている地域はどのくらいあるのか把握できていますか、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 把握しているものでは、令和5年度・6年度ともに夜間訓練を行った地域は、安芸、伊尾木、それと川北です。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 伊尾木地区、赤野地区には野外テントが設置できる緊急避難場所を準備していますが、気がかりなのは真夏の暑さ対策、真冬の防寒対策はどのように考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 避難場所での屋外避難にはテントを用いますので、外気から身を守ることができます。また、令和6年度から避難所や避難場所へ寝袋の備蓄も順次進めています。
防暑対策は、屋内の避難所であればスポットクーラーを備蓄したりもしていますが、屋外の避難場所では、おのおのテントの小窓などを開けて風が通るよう対処することを想定しています。今後、防暑対策としてより効果の高いものがあれば、工夫し、取り入れていきたいと考えています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 2月22日、伊尾木地区での夜間訓練に参加しました。当時はかなりの寒さでしたので、ほとんどの参加者は防寒着で来ていました。当然、私も頭・首・手などは完全防備で参加しました。
約30名ほどでしたが、参加者の皆さんが口々に言っていたのは、巨大地震が発生したらこんな格好で避難場所に来ることはできるんだろうか、着のみ着のままで来るようになったら、テントでは一昼夜過ごすことができるだろうかと心配の声が上がっていました。
先ほど課長が言われましたけど、特にこのテント内での真冬の防寒対策はもう少し考えていっていただかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 先ほども防暑対策としては、一定工夫したものを取り入れていきたいというお話をさせていただきましたが、防寒対策としても、より、また効果の高いものがあれば、やっぱり同じように工夫して取り入れることも考えていきたいと思います。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 私も実際にこういう経験をしたので、今後の課題などが分かってきています。安芸市もハード面の整備は大分進んできていますので、今後はソフト面の対応が大事になるのではと思われます。
全国的にも野外にある避難場所の防寒対策はできていないと言われており、3月8日ですか、川北地区で夜間の避難訓練を行ったときに141人が参加という記事が出ていました。避難タワーとか一時避難所を使って数か所で避難訓練をしたということで、これだけ大々的にするのは安芸市では初めてではないかと思います。
だから避難訓練に参加された方がいろいろな課題を発見できたと思いますので、そういう課題を安芸市も危機管理課も、川北地区でまた確認を取っていただいて各地域で共有していきたいと思いますので、そういうことをよろしくお願いします。
続いて、令和6年第1回定例会で、避難タワーの外壁・屋根を設ける改修工事が可能かどうかの意匠設計を行っており、改修可能か検討するとの答弁がありました。
令和6年第2回定例会では、今後、港町1丁目と2丁目の津波避難タワーについて、改修可能となれば来年度改修工事にかかりたいと考えている。また、ほかのタワーについても今年度やる再計算委託業務の結果を見て、来年度から順次再計算などを行いたいとの答弁でしたが、そろそろ年度が替わりますが、どこまで進んでいるのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 令和6年度に津波避難タワーの屋上階への屋根・壁の増築及び屋上直下にある避難階への外壁増設の検討を行うため、安芸市津波避難タワー1号・2号改修工事設計委託業務を実施しました。
その結果を申しますと、1号タワー・2号タワーともに、屋上の直下にある避難階については外壁の増設は可能ですが、屋上階への屋根・壁については建築基準法等に適合しないため、屋根・壁を増築することはできないという結果となりました。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) あと、そのほかの順次取りかかるというところの対策というか、進んでいるのか再度伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
この結果を受けて、1号・2号では避難階の壁ということで増設する道筋は一定見えてきているのですが、今までのタワー全体で見ると、特に川北には屋上階しかないタワーもありますので、全体に適合するような方法もちょっと再検討が必要になってきて、今それらについても特に壁のほうを先にやれるような方法を、財源も含めてちょっと調整、検討しゆうところです。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) できることを先に、取りあえず取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
続いて、(2)津波新想定について質問します。
南海トラフ巨大地震発生時の被害見直しについて、県は来年3月に新想定を取りまとめるとのことですが、安芸市としてはどのような対策を考えているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 国の想定が、まず今年、この3月に出るという話です。それでまた、それを受けて高知県も8年3月を目途に被害想定の見直しを始めているところです。安芸市のほうでも、また県の被害想定が発表されるその8年3月、言うても年明けの4月になるかと思いますが、それ以降に国・県の動向を見つつ、高知県が来年発表する新たな被害想定を基に、安芸市地域防災計画などの各計画を見直し、南海トラフ地震対策や避難行動につなげていきたいと考えています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続いて、県の第6期行動計画案の目標に対して安芸市の計画はどうなっているのか。津波避難意識率、住宅耐震率、災害関連死の防止に向けた避難環境の整備や支援、受援体制の強化、臨時情報への対応強化などの目標に向けての取組はできているのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 高知県南海トラフ地震対策行動計画の第6期については、今日までを意見公募期間として素案が公表されています。内容は5期までの取組の成果や課題を分析・評価し、総括した上で対策を見直し、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の教訓を基に、新たな対策を取り入れることが示されています。
こうした成果や課題を踏まえ、4つの観点で事前の備えを強化するとして、第1に自助・共助の取組の強化、第2に避難環境の整備の強化、第3に復旧・復興作業に向けた事前の備えの強化、第4に災害に強いインフラ整備の加速化が示されています。安芸市においても第6期行動計画に沿って取組を強化・加速化していき、南海トラフ地震に備えたいという考えを持っています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 次に、事前復興まちづくり計画の策定は進んでいるのか。令和6年度作成の安芸市復興方針案を基に、7年度予算に2,100万円の委託料予算を計上していますが、伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 現在、安芸市事前復興まちづくり計画基本方針案及び業務手順書案を作成しているところです。この基本方針は、令和7年の5月か6月に開催する防災会議に諮り、その後公表する予定です。また、その後に順次各地域と基本方針に沿った南海トラフ地震、大規模災害後の各地域におけるまちの形について話合いを行い、地域ごとの事前復興まちづくり計画を作成する予定となっています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 黒潮町は令和7年2月20日に県内で初めて事前復興計画を策定していると聞きました。室戸市でも策定される予定だということを聞いていますので、安芸市も順次取り組んでいただきたいと思います。
続きまして、堤防整備による津波対策はどのように考えているのか。
以前何度か質問していて、安芸海岸の堤防はL1津波には対応できるとの答弁をいただいています。ただ、現状の堤防を見ると高さが確保できているとは思えないほどになっています。
高知市・南国市・土佐市は国と県が連携して、21年度に堤防補強整備が完成しています。香南市も国直轄での堤防補強が決まり、L1津波に対し人的・物的被害をゼロにできるとのことです。安芸市としても今後は県・国への要望をもっともっと積極的に行い、沿岸部の市民が少しでも避難時間を稼ぐことができ、被害範囲を縮小する効果が期待できるような取組をお願いしたいですが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 堤防につきまして、特に防潮堤につきましては過去にも一般質問で出よってて答弁していたとおりのことで、その点に関しては、今の進捗も踏まえてちょっと高知県のほうにはお聞きさせてもらいました。
結果としましては、前に答えたとおり、L1では最大9.1メートルが想定されて、安芸海岸の防潮堤高さは9.6~11.4メートルであるため、津波高さに対する防潮堤の整備基準を満たしており、また揺れに対する耐震力も基準を満たしているとのことです。
ただし、過去にも答弁したとおり、防潮堤の水圧に対する耐力調査につきましては、高知県下においてより危険度の高い海岸から整備計画を立て、順次改修を行っている中、安芸海岸の整備計画はまだ今も上がっていない状況であるため、耐力調査はまだ実施していないと確認しています。
それで、こういうこともまた前に進めていくためにはこういう要望も必要だと考えますので、高知県に安芸海岸の整備計画を上げるよう、また防潮堤の水圧に対する耐力調査を行い、結果を踏まえ、必要となれば防潮堤の改修など具体的な手段を取るよう、県へ要望も上げていきたいと考えています。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ぜひ積極的に要望をお願いしたいと思います。
安芸町内の方によく言われます。あの堤防で津波を止めることができるか。心配してるのは庁舎だけ移転して職員は北へ逃げて、我々はそのままほったらかしやいう声が出てます。だから、ああいう堤防を補強することによって市民もやっぱり逃げる時間が稼げる、安芸市もそういうことを考えてくれているという思いが出てくると思いますので、積極的な要望をぜひお願いしたいと思います。
続いて、(2)上下水道管の老朽化対策について、(1)上下水道管の耐震化状況について質問します。
埼玉県では下水管の破損で道路が陥没し、トラックが転落した事故が発生しています。安芸市の場合はこのような大規模の下水管はないと思いますが、やはり老朽化や耐震化が十分なのか心配だとの市民の声を聞きますので、現在の状況について質問させていただきます。
まず、安芸市の上下水道施設の耐震化はどれほど進んでいるのか伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えいたします。
まず、水道管の耐震化につきましては、水道施設設計指針によりまして基幹管路は最大級のL2クラスの地震への耐震性、それから配水支管につきましては発生頻度の高いL1クラスの地震への耐震性のある管種が定められております。その定められた管種は適合管として認定されておりまして、その適合管により布設されている水道管は耐震性を有するとされております。
この指針に基づきます現在の耐震化の状況につきましては、令和5年度末で基幹管路は、総延長75キロメートルのうち約30%の23キロメートルが耐震適合管となっております。配水支管につきましては、総延長約128キロのうち約70%の約90キロメートルが耐震適合管となっております。
続きまして、主要な水道施設につきましては、配水池11か所のうち4か所が耐震性を有しております。
続きまして、下水道の状況について御説明します。下水道の管渠及び施設の耐震化につきましては、下水道施設の耐震対策指針と解説に基づき実施することとなっております。
本指針に基づきます耐震化の実施状況は、管路につきましては令和5年度末で、汚水幹線、防災拠点となる施設までの汚水管路及び雨水幹線等重要な管路の約7.7キロメートルのうち、約32.5%の約2.5キロにつきましては、耐震性を有しておるということになっております。
その他汚水管路につきましては、総延長約42キロメートルのうち約62%の約26キロメートルについて、耐震性を有する管路となっております。
処理施設につきましては、人命、揚水機能の確保のため、管理棟及びポンプ棟の耐震化から着手し、耐震診断が完了しましたことから、耐震工事に順次着手いたします。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) なかなか大変なことだと思いますけど、予定としてはいつ頃完了するという予定は立てているでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えします。
今後は、国により策定を求められましたあき総合病院など重要拠点への給水確保、汚水処理機能確保などを主要観点とした安芸市上下水道耐震化計画を主要計画と位置づけ、被害軽減と早期機能回復を図るため耐震化を進めることといたしております。
先ほど御答弁させていただきましたように非常に管路も多うございますので、いつということはなかなか明確にお答えはできませんけれども、できる限り対策を早期に進めていきたいというふうに考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 病院や避難所というところなどを重点的に思ってましたけど、課長が既に答弁してくれましたので、これは抜かします。
次に、(2)の耐用年数が過ぎた水道管の補修状況について伺います。耐用年数の過ぎた水道管は全体の何%ですか、伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えいたします。安芸市の水道管は、基幹管路・配水支管の合計で、先ほどお話しさせていただきましたけれども、203キロメートルございます。そのうち耐用年数40年を経過した水道管につきましては、令和5年度末で約43キロとなっております。
維持管理につきましては、専門業者による漏水調査を毎年実施しておりまして、管路の破損の有無などを適宜確認いたしております。本調査により確認された漏水箇所につきましては迅速に修理を実施し、重大事故につながることのないように努めております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) これも整備がいつ頃完了するかということを伺いたいがですが、なかなか難しいと思いますけど。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 耐用年数を経過した管路の更新につきましては、なかなか、計画的にやっておりますけれども、最近は基幹管路等の重要な管路の更新を優先的に進めておりまして、いつということを明確的にお答えすることはできませんが、布設年度や管の種類、それとか道路工事の実施計画との調整などを図りまして、適宜更新に努めているところでございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 先ほども言いましたが、老朽化した下水管の破裂で大事故が発生していますが、老朽化対策への対策は進んでいるのか伺います。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 水道管、それから下水道管につきましても適宜調査を行っておりまして、職員による目視等をするとか、建設課とタイアップして路面状況を確認するとかいたしておりまして、変調等があれば直ちに対応を図っているところでございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 全国的に見ても耐震化・老朽化の調査がなかなか難しいいうこともいろいろ聞いていますので、人員不足なんかもあり大変だということも聞いてますけど、対策よろしくお願いします。
続いて、南海トラフ巨大地震などの大規模災害による水道管の破裂などが想定されますが、対応はどのように考えているのか。資材などのストックは、市はしていないと以前は言っていましたが、水道などのインフラの壊滅的被害により復旧が大幅に遅れたという事例もあるようですので事前計画が大事ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 お答えします。
上水道・下水道につきましては、日本水道協会、それから日本下水道事業団等と災害援助協定を結んでおります。また、市内組織としては安芸市上下水道工事業協同組合などとも災害援助協定を締結いたしております。こういった組織と十分連携を図りながら、早期復旧に向けて取り組んでいくことといたしております。
それから資材の備蓄につきましては、その備蓄する資材の選定、それから保管場所、保管時の品質管理などの課題により、使用頻度の高い通常時の補修材のみ今現状備蓄しておりますので、以前御答弁させていただいた内容と変わってはおりません。
ただ、災害発生時におきましては、先ほど答弁させていただきました災害援助協定を締結している機関と連携して、資材の調達を速やかに行い、水道水、それから下水道の機能の早期復旧に取り組むことといたしております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市内で確保されているというのなら少し安心できるがですけど、その日本水道協会高知県支部なんかで保管してあるとなると、災害が県下的に起こりますので、なかなかすぐの援助というか、そういうのは難しくなるのではないかと思いますので、やはりある程度市内でそれなりの確保ができることが望ましいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。
続いて、(3)市道整備について。安芸橋西詰からの市道整備についてですが、現在の整備状況についてどこまでできているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
御質問の市道につきましては、令和4年度に測量設計、令和5年度より舗装の打ち替え工事及び側溝改修に着手いたしております。現在、黒岩デパート跡地前から東方面に向けて梶橋までの区間、約210メートルの舗装と側溝整備が完了しております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 今後の計画についてはどのようになっているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 今後の予定としましては、令和7年度に土居橋から南方面に向けて、本町通りまでの区間約200メートルの舗装の打ち替え工事と、一部側溝改修を実施いたします。また、梶橋から安芸橋西詰交差点までの区間約190メートルにつきましては、令和8年度から工事に着手する予定としております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 先ほど課長のほうからも答弁がありました、安芸橋西詰より梶橋までの区間ですが、道路状況が非常に悪く下水工事の跡が凸凹状態であり、市街地の道路では一番ひどいのではと思われます。また、家屋の入り口周辺は排水路の準備ができておらず、道路と家との間に段差ができており、危ないという声を聞いています。こういう道路状況が悪い箇所を優先的にできないものでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 先ほどの答弁で、御質問の区間につきましては令和8年度に工事着手予定と答弁させていただきましたが、優先的に工事ができないかとの御質問に対しましては、令和7年度に実施予定の、先ほど答弁しました土居橋から本町通りまでの南北の区間につきましても同様に路面舗装の状況が悪いこと、また比較的交通量の多い黒岩デパート跡地前の四差路交差点におけるマンホール等の段差解消などもございますことから、令和7年度は、まず当該区間南北を整備することとしております。
なお、議員御指摘の区間につきましても令和8年度より順次整備してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 令和8年度にはできるということで、よろしくお願いします。
続いて、(2)市道安芸伊尾木線の道路状況について質問します。
メルトセンターを下りてきて県道を渡ったところから春日橋までの区間、市道安芸伊尾木線の道路状況が非常に悪くなっていて、整備する必要があるのではという市民からの要望が出ています。
新庁舎、そして統合中学校ができてから乗用車の往来が増えてきており、その上、高規格道路の整備のために大型のダンプカーが毎日数十台の往来があります。メルトセンターを下りて有ノ木橋までの約200メートルの区間では道路が波を打っているような箇所が幾つかあり、その上この区間に2つある横断側溝もかなり傷んでおり段差ができている状態ですが、建設課としてはどこまで確認できているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 御指摘のとおり、当該区間には横断側溝2か所、それから路面の底に暗渠が通っておることから、舗装がちょっと波打っているところも現地のほうで確認をしております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続いて、有ノ木橋から西に坂を下ったところの横断側溝の段差もかなりあり、東向きの大型ダンプカーなどは北側を避けて中央線をオーバーして通っているところをよく見かけます。また、JA東支所の前も補修してある箇所が剥がれていて、凸凹が次第に増えてきています。また、たくさん見られる亀裂箇所はだんだんと幅が広がってきていると感じられますが、確認できているのか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 先ほどと同様に、安芸伊尾木線の舗装の状況、また横断側溝の状況、がたつき等段差でありますとか舗装のひび割れ等も、現地で状況については把握しております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 私も庁舎へ来るときはその道を通ってきますので、通るたんびに気になって見ていると、やっぱり亀裂もだんだん幅が広がってきているように思います。
その市道周辺のハウスの農家の方が、ちりを積んだ車が、軽トラックとかありますけど、その車がそういう悪いところを通るときに、がたんがたんバウンドして上下しているそうです。ちりをよく捨てていくそうです。ちりが飛んでいくということですね、振動で。そういう苦情も出ています。
これらは、先ほども言っていますが、高規格道路建設のために大型トラックが毎日数十台土砂を積載して往来していることが原因の1つではないかと思われます。市道ですので安芸市の管轄になり、補修工事は大変だと思いますが、ただ、高規格道路の周辺整備事業で整備費を国から捻出することができないものか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 御指摘のとおり、現在、高規格道路の整備工事が川北・伊尾木地区でも進んでおりまして、それに伴う大型車両の通行というのが非常に多い状況というのは確認をしておるところです。
高規格道路の周辺整備というお話でありますけれども、周辺整備といいますのは、一定その実施基準というのがございまして、市町村道等を整備する場合は高規格道路の中心線から500メートルの範囲にある市町村道、その他道路とすると、そういったように基準がございます。
議員御指摘の市道安芸伊尾木線の伊尾木地区~川北地区につきましては、現在、高規格道路の本線から500メートル以上離れておりましてこの実施基準を満たさないことから、周辺整備事業の対象ということにはなりません。
ただ、本市道に限らず日常の道路維持管理につきましては、市単独の道路維持予算により横断側溝の段差解消やグレーチングの騒音対策、車道舗装の補修等、これまでも適宜実施しています。今後におきましても、限られた予算の中で緊急性・必要性等を見極め、計画的に修繕に取り組んでまいりたいと考えております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 市の単独でなかなか大変な事業になると思います。そこだけではないですのでね、安芸市の道路状況の悪いところは。
先ほども言いましたように、そういう高規格道路の工事のための車両が多く通っているので、こういう悪い道というか、段差ができたり亀裂が入ったりするのが大きな要因だと思いますので、やはり市単独はなかなか厳しいと思いますので、県・国にそういった話の要望をして、県・国に一度確認に来ていただいて、大型ダンプは、トラックが数十台も毎日通るような想定は、あの道はしてなかったと思うんですよね。だから、ますますこれからはひどくなると思いますので、できるだけそういった要望もお願いしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次、(3)市立安芸中学校通学路についてですが、中道線の整備計画は予算審議でも質問されていたと思いますが、今後の状況を一度お聞きします。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 通学路の、まず南北の市道中道線につきまして答弁させていただきます。
本年度末までに、計画延長550メートルのうち340メートルが完成しています。残り210メートルにつきましては、令和7年度に用地買収及び移転補償の完了が見込まれる区間170メートルを整備する計画としております。
なお、令和7年度末の全線供用を目指して鋭意取り組んでいるところでございますが、移転先の手続や代替地の選定等に不測の期間を要しており、一部区間の完了が令和8年度末となる見込みとなっております。市民の皆様並びに学校関係者・保護者の皆様には御不便をおかけしますが、引き続き御協力をお願いいたします。
東西もですか。南北だけでよろしいですか。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) その中道線から中学校へ向けての市道と、天神坊橋に向けては東西の市道ですね。その工事計画と終了予定を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 東西の西木戸一ノ宮線につきましては、天神坊橋西詰から西方面へ、安芸中学校南側を経由し、旧県道安芸物部線の、現在市道安芸井ノ口線までの全長1.2キロメートルのうち、学校敷地前の整備済み区間200メートルを除く約1キロメートルを整備するものでございます。
進捗状況としましては、東から順に、天神坊橋から市道中道交差点までの区間については現在測量設計を実施しており、令和7年度より用地買収に着手する予定としております。
次に、市道中道交差点から中学校東側までの区間140メートルの歩道整備については、4月初旬、来月の新学期が始まるまでに工事が完成する見込みです。
また、学校から帯谷川までの区間180メートルの整備につきましては、現在、埋蔵文化財の発掘調査を行っておりますので、その調査が完了後、工事を発注する計画といたしております。
最後に、帯谷川から市道安芸井ノ口線の区間につきましては、他工区の事業進捗を見ながら適宜実施してまいります。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 中道線の車の往来が非常に増えているため、安芸中学校へ左折するところの交差点に横断歩道が必要との市民の要望が出ていますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 御質問の交差点の横断歩道の設置につきましては、これまで所轄の警察署と何度か協議を進めてきており、現在安芸署のほうから県警本部へ上申されております。
南北の横断歩道につきましては、今後県警本部のほうで、先ほど答弁しました歩道整備の工事が完了した後、現地等を確認するというふうに伺っております。
なお、南北の横断歩道が設置されるまでの間につきましては、横断する場所をラインで明確化して車のドライバーに視覚的に認識させ、注意喚起を促すための横断指導線を市のほうで整備し、通学路としての安全確保に努めてまいります。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 市道中道線で交通量が増えて危険ということで、桐ヶ内団地北西の交差点に東西に渡るための横断歩道というところで、教育委員会のほうから報告させていただきます。
学校教育課のほうでは、令和6年4月の統合中学校、安芸中学校開校時点で交通安全上の懸念がありましたことから、通学時間帯の通行量等の状況を整理・確認をした上で、昨年の4月に桐ヶ内団地北西の交差点の南側に東西方向の横断歩道の設置を安芸警察署に要望し、県警本部に上申をしていただいておりました。その結果、現状の交差点の構造では歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所が現在ないということから、横断歩道の設置はできないということで公安委員会が判断をしたというような回答を、安芸警察署からもらっております。
そのため現在の対応としては、学校において生徒の交通安全に対する注意喚起をしていただいているというところです。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) それでは、あの交差点が南北の横断歩道は可能だと、今後。東西は無理だということだと思いますが、市道の整備をするに当たり、その東西の横断歩道ができるような用地というか、そういうのは見込めないのでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 南北の横断歩道につきましては、現在、完成した後に県警本部のほうが現地を確認するということを伺っておりますというのを、先ほど答弁させていただいたところです。
東西の横断歩道につきましては、先ほど学校教育課のほうから答弁しました、滞留場所がないということですけれども、東西の市道西木戸一ノ宮線の現在、測量設計を実施しておりまして、その中で歩道整備を進めてまいります。
その中で交差点協議、当然必要になってきておりますので、その整備の中で滞留所については新たにつくるということになってくると思われますので、滞留所ができた後に横断歩道は整備されると思われますので、引き続きその所轄の警察署と、設置に向けての協議は進めてまいりたいと思っております。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 安全確保のために、ぜひよろしくお願いします。
続いて(4)小学校統廃合について、(1)各地域の保護者の意見・要望についてですが、令和6年10月に保護者対象の説明会が終了していると思いますが、どのような意見などが出ていたのか伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
小学校及び保育所の保護者を対象に、8小学校と安芸おひさま保育所、それから矢ノ丸保育園の10か所で保護者説明会を、令和6年8月から10月までの間で実施しました。前回の説明が平成29年度の説明ということで7年が経過をしておりましたことから、改めて個々の意見を伺う形で行っております。
まず、説明をした内容でございますが、これまでの統廃合の経緯とか児童数の推移、それから学校施設の現状、それからこれまでの小学校2校案を継続をし、旧清水ケ丘中学校区は同校の跡地に建て替え、それから旧安芸中学校区は場所は未定だが1校とし、立地場所については、これまで市街地に近く津波浸水想定区域外を条件に一定規模の用地を探してきましたけれども、条件を満たす場所を見つけるに至っておりませんことから、今後は津波浸水想定区域内まで範囲を広げ、津波浸水対策とセットで立地場所の検討を考えるということ、具体的には市街地付近の農地等を造成、かさ上げして新設するケースでありますとか、または安芸第一小学校の用地をかさ上げをして建て替えをするというのを例示して説明をいたしました。
またスクールバスでの通学、それから学童保育所の併設、それから開校準備委員会の設置、この3点を検討するということをお伝えをしております。
お尋ねの要望とか意見につきましては、旧清水ケ丘中学校であります下山・伊尾木・川北・土居・井ノ口小学校の5校では統合に反対する意見はなく、そのうちの4校、下山・川北・土居・井ノ口で市に1校でもよいのではとの意見があり、旧清水ケ丘中学校が適地ではないかとの意見や、現在の安芸中学校の近くになれば兄弟の送迎に便利であるとの意見がありました。
旧安芸中校区である安芸第一小学校では、浸水想定区域外へ移転してほしいとの意見もありましたが、大半が利便性を重視するという意見で、地域の避難所として機能強化を図る観点からも、現在地での建て替えを望むものでございました。
穴内小学校では地域に学校を残すべきとの意見もありましたが、大半が学校の移転統合には反対はしないが、現在の安全な浸水想定区域外から危険を伴う浸水想定区域内への通学については納得ができないとの意見でございました。
赤野小学校では、一貫して地域に学校は必要であり、統合の前に小規模校への支援や地域の活性化の取組をすることが優先であるとの意見でございました。また、要望としましてはスクールバスが必要ですよというようなことや、旧清水ケ丘中学校に設置する場合には、隣接をします県道の安全を高める道路改良が必要だというような要望がありました。以上でございます。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 説明会は保育所の保護者も対象にということだったと思いますが、その保護者ですけど、小学校の保護者と保育所の保護者の参加数はどういう状況でした。というのも、現在在学の児童、多分、新統合小学校には入学できないと思うがですよね。だからその保育所の保護者のほうが当然対象になり、真剣に考えているのではないかと思いますので、ちょっとどういう状況やったかお伺いします。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
保護者につきましては一応68名の参加がございまして、特におひさま保育所では4名、矢ノ丸保育所では3名でございました。
ただ、各小学校で行った説明会の中にもその保育の保護者の方がいたことは間違いありませんが、その人数まではちょっと把握ができておりません。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 続いて、各地域住民の意見・要望についてですが、学校の保護者と大分意見が違ってくるのではないかと思いますが、令和7年2月で地域説明会が終了していると思いますので、どのような意見が出たのか、これもお伺いします。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
地域住民に対しましては、公民館単位の15か所で説明会を令和6年11月から令和7年2月まで実施し、説明資料と説明内容につきましては保護者説明会と同様のものというふうになっております。
赤野地区では、移転統合は受け入れられない、まず小規模校への支援、それから人口減少対策・少子化対策・地域活性化など、市がやるべきことに取り組む説明をすることがまず必要。地域に学校は必要であり、学校を残す話を先にしなければならないとの意見があり、小規模校であっても、学力を含め地域の子供たちの育ちを見ているとデメリットはない。津波浸水想定区域内に立地していても避難訓練をしているので問題ないとの意見がありました。
穴内地区では、小規模校の限界が来ており統合は仕方がないが、津波浸水想定区域に子供を通わせられない。第一小学校の建て替えについては、かさ上げをしたとしても津波火災による危険性が高く反対であるとの意見や、市に1校でもいいのではないかとの意見がありました。一方で、地域に学校は必要、保育所と小学校は地域に置いてほしいとの意見もありました。
市民会館・黒鳥公民館では、第一小学校に建て替えを前提として、敷地の狭さというものを懸念する意見がありました。
井ノ口、それから川北・土居地区では、安芸市に1校でいいのではないかとの意見でございました。
伊尾木地区では、市が2校ありきだからこれまで話が進んでいないと。地域に小学校は必要で、伊尾木小学校を高台移転して特認校の指定を受けたらどうかとの意見と、とにかく早く子供の安全が確保されるよう進めてほしいとの意見もありました。また、人口減少に対する市の取組ができていないとの指摘を受けました。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 要は、小学校の統廃合の進捗がすごく遅れているということで、いろいろ保護者の間には不満がかなり出ていると思います。
地域では地域に学校を残してほしいと、廃れるからというような声も出ていると思いますが、この説明会は今後はもう行わないということですか、伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
今回の保護者及び地域説明会での意見を踏まえ、統合の方針を整理した上で再度説明会を開催したいというふうに考えています。
現段階では説明会の方法はちょっと決めておりませんが、地域と保護者を対象に、一緒にというようなことも含めて、そうした説明会を小学校区ごとか、または旧中学校区ごとに開催するというようなことも考えられます。
いずれにしても集約をした後、また説明には赴くつもりでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 地域住民の意見で一番多かったと思いますのが、学校がなくなると地域が廃れるという声をよく聞きます。
この件に関して、学校教育課としてはどのように受け止めているのか伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
学校の統廃合に関する課題は、単に教育施設が地域になくなるというものではなく、地域のコミュニティーや活力に大きな影響を及ぼすということが懸念をされておりますので、教育委員会としても非常に重要な課題で、深く考慮しているところです。
このたびの地域説明会においても、どの地域も学校との結びつきというのは非常に深く、学校がなくなるということをよしとしている人は1人もいませんでした。しかし、子供の安全や教育環境を考慮して統合もやむなしと、苦渋の判断をしたというような声も聞き取っています。
教育委員会としましては地域との連携を強化をし、統合後の地域と学校のありようといいますか在り方について話合いをしながら、例えば移転後の学校施設を地域のコミュニティー施設や子供たちの学びの場として活用する検討のほか、総合的な学習の時間や放課後、土曜日等の教育活動を通じて、地域資源を活用した学習プログラムや、地域イベントを通じて地域に出向き、あるいは地域で学ぶ、それから地域課題の解決に向けて学校・子供たちが積極的に貢献するなど、学校と地域の双方向の関係づくりを創出するなど、これまでの地域との関係を残しながら、より活気あるコミュニティーとして発展していくことを目指したい。そして学校統廃合による影響を最小限に抑えつつ、地域の活性化に向けた取組の方向性を検討してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) そういうことをいろいろ検討していただいて、ある程度納得はできる。取りあえずは生徒の、子供の命を守る取組がまず大事ですので、よろしくお願いします。
(3)第一小学校移転についてですが、先ほど学校教育課長から、住民の意見・要望で大分、第一小学校のことが出てましたので、ちょっと重複することがあるかも分かりませんが、続いて質問していきます。
第一小学校も取りあえずは移転するということを言っていますが、安芸町内の住民が避難できる施設であり、避難場所としては建物を残すのか伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前10時59分
再開 午前11時6分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えします。
第一小学校を避難場所として残すかという御質問です。
第一小学校につきましては、校舎の屋上が指定緊急避難場所になっております。また、体育館は風水害の際の避難所の指定も受けております。避難所の運営マニュアルというようなものも存在しております。学校の機能がなくなったとしても、避難所としての機能は存続するものと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 第一小学校は屋上に行かなくても大丈夫な高さが確保できていると思うがです。大学の教授が、あそこの場所は大丈夫だと言われたということも聞いています。
先ほどから学校教育課長が言われるように、保護者の要望も、第一小学校を残せという要望が大分出ているということも聞きましたが、移転先がまだ決まってません。よく聞くのは、津波が来るので学校は移転するが、市民がその場所へ避難するというのはおかしな話じゃないかという声も聞きます。
市民が安心して暮らせるためにも、小学校をかさ上げするか、ピロティー工法での建設で津波に対応できる取組をし、安全な建物として児童生徒、そして市民の避難場所となる現地での建て替えができないものかという要望がたくさん聞かれますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 今回の説明会におきまして、市の小学校2校設置案として、旧安芸中学校区は設置場所が未定だが、考え方の1つとして安芸第一小学校のかさ上げによる建て替えが考えられると例示して説明したところではありますが、先ほど来、私が答弁申しましたように、保護者、地域説明会での御意見の中には、第一小学校の建て替えを望む声があった一方で、津波による浸水は防げたとしても津波火災の懸念があること、そもそも津波浸水想定区域内に小学校を設置するべきではないといった意見がありました。また、多くの地域で小学校は1校でいいのではないかというような意見もございました。
現時点では、これらの意見を基に子供たちのために何が一番最善であるかを検討し、小学校の設置案を改めてお示ししたいというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) 火災災害とか、一番の原因が港のタンクがというようなことが、東日本は多かったですよね。安芸市においてもハウスのタンクが、まだ十分耐震化されていないものがあります。そういったところも、危険なところがたくさんあると思います。
東日本大震災以降で、浸水区域に学校建設したところがあります。宮城県亘理町荒浜中学校は、平成23年3月11日、東日本大震災による大津波で被害を受け、当時は移転建設の意見もあったそうですが、地区の復興には学校が必要との意見が多く、震災発生場所と同じ場所で平成26年8月に、1階を柱だけの高床式、いわゆるピロティー工法で校舎を建設し、現在、まちの教育行政の復興のシンボルとして新しい校風を築いているそうです。
同じく長瀞小学校、児童191人も、津波被害を受けた現地で26年8月に校舎の落成をしています。小学校で現地再建を果たしたのは宮城県では初めてだそうですが、現在、両校は亘理町の一時避難所と位置づけられているそうです。
以前執行部は、東日本では災害地に公共施設を建設していないとの答弁でしたが、実際にこのような事例もありますが、教育長、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 お答えいたします。
安芸第一小につきましてはちょっと別になりますけど、高知県の防災マップで液状化の可能性が大きいとされております。今後第一小学校での建て替えをするとなった場合は、ボーリング調査など必要な地盤調査を行った上で、浸水しない高さに一、二メートルのかさ上げ造成をし、ピロティー構造ではなく一般的な壁で囲んだ建物構造で建て替えたいなというふうに、現在では考えています。
ただし、駐車場スペースが第一小学校は少ないとかいうようなことで、そういった確保が必要な事情によってはその用地費とか建築費の比較検討をせないかんので、そのピロティー方式が採用される可能性はゼロではないというふうには考えています。以上です。
○佐藤倫与議長 9番 山下裕議員。
○9 番(山下 裕議員) ピロティーで建設すると、その下、1階が駐車場になりますよね。そういったところの利点もありますし、かさ上げして盛土にするよりはピロティーにしたほうが波が抜けます。だから、その火災発生も少なくなってくると思いますよね。だから2メートルかさ上げすると十分波が抜けていくようなら、もう十分な建物ができるのではないかと思いますので、そういった検討をぜひ前向きにお願いします。
3月11日ですか、岩手県釜石市で行われた追悼式では、命があれば何とかなる、とにかく安全な場所に避難してくださいと訴えています。そのためには、身近に市民が安心して避難できる場所が必要と思われます。
第一小学校がなくなれば子供たちの姿が見えなくなり、まち全体が寂れてしまうのではという多くの声も聞かれます。高床式の校舎にすれば児童生徒が安心して通学でき、そして安芸町内の方々も避難できる、安全で安心な場所となるはずです。第一小学校の現地での建て替えをお願いいたしまして、私の一般質問を終了いたします。
○佐藤倫与議長 以上で、9番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
添付ファイル1 一般質問 山下 裕(令和7年第1回定例会) (PDFファイル 374KB)