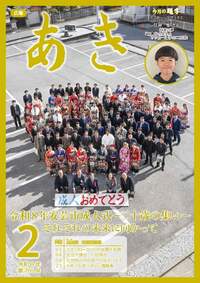議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 令和7年 » 令和7年第2回定例会(開催日:2025/06/06) »
一般質問 徳広洋子
質疑、質問者:徳広洋子議員
応答、答弁者:危機管理課長、健康介護課長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、欠員1人、現在数13人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 通告に従い一般質問をいたします。
1、市民の安全と安心を守る防犯灯について。
防犯灯は、通学路や生活道路において、通行者の安全確保や夜間の事故防止など、明るい環境によって犯罪の発生が抑制されるなど、防犯灯を設置することで、地域住民の安全・安心が守られています。本市では、維持管理について、設置は市で行い、電気料金の維持は受益者負担地域や町内会などで支払っています。自治体によっては逆の場合もあるようです。
令和5年12月議会の一般質問で、防犯灯について、本市の状況は詳しくお聞きいたしました。お困り事の相談は、現状を確認の上、協議しますと答弁をいただいております。
現在、人口減少、高齢化が進む中で、町内会が解散という現実が起こっています。既設の防犯灯の維持管理について、どうしていけばいいのかとの問題が起きていることは、本市の今後において喫緊の課題の一つと考えています。
人口減少、高齢化はいろんな問題へとつながっていますが、防犯灯の電気料金の支払いなど、維持管理が困難となる状況について、対策を考え、現状を少しでも軽減できないかとの思いでお伺いをいたします。
(1)本市に設置の防犯灯の種類と設置数について、令和5年12月時点での市内防犯灯は1,411基、うち地域が電気料金を負担している防犯灯は740基と承知していますが、その種類別設置数をお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えをさせていただきます。
令和7年5月末時点の市全体の防犯灯総設置数は1,426基、うち地域が負担しているものは725基で、前回答弁いたしたものより負担区分の見直しや廃止などの関係から若干減少をしております。
地域負担の防犯等における種類別設置数でございますが、防犯灯の種類は蛍光灯タイプとLEDタイプの2種類ございまして、地域負担725基のうち、蛍光灯タイプが258基、LEDタイプが467基でございます。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 現在、蛍光管を交換するタイミングで、同程度の明るさで消費電力が少ないLEDへ順次切替えられています。LEDは、蛍光灯に比べて明るさやエネルギー効率と耐久性に優れ、省エネ、CO2の削減など、地球温暖化対策や維持管理経費の削減などに効果があり、電気料金は蛍光灯の約半分だと言われています。
そこで、本市での防犯灯のLED化は、令和5年当時からどの程度進んでいるのか、LED化によって消費負担の軽減の効果は市民にどの程度届いているのでしょうか。
(2)既設の防犯灯のLED化の割合を伺います。
そして、現在の進捗と今後の課題を含めて、早期LED設置への見解を併せてお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えいたします。
市全体の防犯灯設置1,426か所のうち、LED化している箇所は936か所あり、割合で申しますと65.6%となります。
早期LED設置への見解との御質問でございますけれども、まず、本市の防犯灯の設置につきましては、安芸市防犯灯の設置及び管理に関する要綱に基づきまして、設置を希望する地域の代表者等から、新設、移設、形態の変更、休止または廃止について申請をしていただくことになっておりまして、それらの申請があった場合に、現地調査の上、設置の可否を決定をしております。
LED化に向けての御質問でございますけれども、現在、申請が新設箇所の場合には、LEDタイプを当初から設置することとしており、また、既設の蛍光管タイプの防犯灯に故障や不具合が生じた場合においても、LEDタイプへの交換を行っておるとこでございます。
現在、LED化の割合は市全体では65.6%でありますので、残り34%余りの部分につきましては最大限予算を確保しながら継続してLED化に取り組んでまいりたいと考えております。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 蛍光管の交換時にLED照明への切替えで、ランニングコスト全体が抑えられます。LEDの省エネ性能は高く、長期的に見るととても経済的です。LED導入は電気代だけではなく、交換費用やコスト削減にもつながることからも、早期のLED化を進めていただきますようお願いいたします。
次に、(3)人口減少に伴う防犯灯維持対策について。
本市において、今後10年、20年と防犯灯を維持し続けるためには、電気料金は市が負担することが必要となるのではと考えています。町内会はあくまでも任意団体のため、未加入者は電気料金を負担しておらず、不公平な状態でもあります。
また、今後においても減少化は進み、電気料金の支払いも困難となり、今回のような町内会が解散したり、防犯灯自体を取り外すことも避けられなくなる可能性があります。
そこで、今後の本市の未来図として、現時点での市の防犯灯維持のための対策をお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えいたします。
まず、防犯灯の電気代についてでございますけれども、防犯灯の設置を希望する地域からの申請をもって、これまでも場所ごとに都度設置の可否を決定した上で、地域負担か市負担か明確に区分をし、現在、地域負担となっている箇所におきましては、そこに防犯灯を設置した目的から鑑みて、やはり今後も地域での負担はやむを得ないものと考えております。
現在、地域での電気代の支払いにつきましては、地域によっては防犯灯周辺の数戸のおうちが負担し合っているところもあれば、個人が負担しているところもございます。将来、地域の人口の減少が見込まれる中、防犯灯を維持していくための対策をとの御質問でございますけれども、そのときの状況にもよりますが、直ちに市が負担することは公平性の観点からも困難であると考えております。
しかし、中長期的な課題として捉えておりまして、当面市としては、引き続きLED化に取り組み、まずはランニングコストの縮減につなげてまいりたいと考えております。
一方、各地域におかれましても、時代の変化に応じて、どこかのタイミングで設置基数や設置場所が適正かどうか、移設や廃止なども含め御検討いただくことも必要ではないかなと考えております。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 人口減少、高齢化が進む中、今後どのように市民生活の安心安全を守っていくのか。具体的な対策と取組を早急に示してほしいと思います。
次に、2、空き家の老朽化問題について。
総務省は5年ごとの調査で、2023年、日本の空き家は900万戸で、空き家率13.8%と過去最多であると示しました。少子高齢化の進展、人口移動の変化などが空き家増加の背景として挙げられ、高齢者の増加や都市への人口集中、住宅供給の過剰などが原因とされています。
空き家のうち、賃貸や売却、別荘などの2次利用を除いた利用目的のない空き家は、385万戸で、総住宅数に占める割合も5.9%と過去最大となっています。増え続ける空き家問題は、防災、衛生、景観面など生活環境へと社会問題となっています。空き家対策は既に空き家になったものをどう活用するかという点以外に、将来、いずれ空き家になる可能性がある築数年の家に対しても、早めの対策が必要と考え、空き家対策においては、空き家になる前の啓発が、発生抑制のために重要であり、予防の観点から、持ち主が住んでいるときから、将来、空き家にならないよう準備することが何より大切と考えます。
高齢者が施設入所や入院など、福祉、介護、医療の問題で留守になり、その後、空き家化するケースが多く、住まなくなった家は驚くほどのスピードで老朽化、衛生悪化が進むことからも、発生抑制のための対策として、本市の空き家の老朽化問題について見解をお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えをいたします。
空き家の増加は、長年少子高齢化や人口減少、さらには相続問題などもあり、これら複合的な原因によって引き起こされてきた、全国的にも大きな社会問題の一つであり、本市においても同様であります。
住む予定がなくても所有者において管理責任があり、維持していくためには、小まめな手入れが必要ですし、毎年固定資産税の支払いも生じております。逆に一たび放置されてしまうと、老朽化が進行し危険家屋にさま変わりしてしまい、仮に飛散物で他人にけがをさせた場合には、損害賠償の管理責任を問われることもあるなど、所有者や御家族、地域の方、双方にとっていいことはございません。
議員から、そのおうちが空き家になってしまう前に、事前に所有者に御自宅の将来を考えてもらうための何か市の取組といった趣旨の御質問でございますが、高知県住宅課が空き家になる前や、空き家になった後のおうちをどうしたらよいかといった、おうちの今後を考えるきっかけとして活用いただける「空き家のトリセツ」や「わが家の思い出ノート」、こちらにその冊子がございますけれども、こういった冊子を作成しており、空き家の活用法や空き家にしないための対策を紹介しております。
また、専門家によるアドバイス等が受けられる高知県空き家相談窓口という無料の相談窓口も設けております。「空き家のトリセツ」及び「わが家の思い出ノート」の冊子につきましては、市役所の企画調整課の窓口にて配布をしておりますほか、高知県住宅課のホームページでも御覧いただくことができるようになっております。
また、高知県空き家相談窓口につきましては、インターネットで御検索いただくか、先ほどの冊子に連絡先やQRコードが記載されておりますので、そちらから御相談いただくことが可能となっております。
また、本市においては、これまで地域の座談会にて先ほどの県冊子を御紹介させていただいたほか、使用しなくなったおうちの有効活用、また、安芸市に移住・定住を希望する方への移住住居の確保を目的に、空き家バンク制度なども設けております。
さらには、老朽化した木造住宅を、この際、取壊しをしようとお考えになられている所有者様に対しまして補助制度を設けており、現地調査の上、老朽度が著しいと判定された場合という要件がございますが、補助額は除却費の80%、金額の上限は167万5,000円を御用意しております。
家は個人の大きな財産であるため、将来必ず訪れる家じまいについて家族であっても、ふだんなかなか話題にしづらかったり、どこに相談したらいいか分からず先送りにした結果が現状空き家の増加につながってきた要因の一つであると考えており、将来、よりよい地域の住まいの環境を維持していくためには、やはり所有者の決断や協力なくしては成り立ちません。
市としましても、今後引き続き市民の皆様に御自身や御家族の住まいの将来について考えていただく機会を今後も提供してまいりたいと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 詳しい御答弁ありがとうございます。
空き家対策と同じ視点で考えなければいけない問題として、空き地対策があります。住宅地、公園に隣接する広い空き地には、雑草・雑木が繁茂し、害虫発生、子育て中の保護者にとっての危険箇所、背丈の高い草の中に何が放置されていても分からない場所についても、景観を乱す空き家同等の問題が起きてきます。空き地に繁茂した雑草の除去に関しては、その都度に対策が必要と考えます。
空き家、空き地対策は、所有者の事情などから、時間がかかることが多く、また労力・費用など、地方創生を進めていく上には、一つ一つ粘り強い取組が必要となりますが、国・県の補助を受け、新たな条例づくりなどからも、問題解決に向けての取組をお願いいたします。
次に、3、RSウイルス感染症について。
(1)感染症の症状と予防法について。
RSウイルス感染症は、古くから1960年代に認知された感染症で、出産後、母親からの免疫が消失していく乳幼児または小児において見られる風邪症状を伴う呼吸器感染症として知られています。特に60歳以上の成人、高齢者においては、加齢とともに、免疫力が落ちてきたり、様々な基礎疾患やその治療薬などにより、免疫が低下するなどのことから感染し、重症化すると言われています。
コロナ禍以前では、高齢者におけるインフルエンザ様症状疾患の原因の第3位が、RSウイルスであったと報告をされています。また、呼吸器感染症と言われるように、高齢者においては、肺炎などの重篤な症状により、入院後亡くなるという報告があります。
感染症を発症した方の10人に1人が入院し、入院された方の15人に1人が、肺炎等で亡くなっているという状況から、日本では毎年約70万人のRSウイルス感染者が出ており、うち約6万3,000人が入院、約4,500人の方が入院中に亡くなられる可能性があると推計をされています。
RSウイルス感染症は、乳幼児から高齢者がかかる感染症ですが、その症状と予防法を伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 初めに、症状につきまして、RSウイルス感染症は、RSウイルスの感染による急性の呼吸器感染症で、年齢を問わず何度も感染を繰り返します。潜伏期は2日から8日とされ、主に発熱、鼻水、せきなどの風邪のような症状が数日続き、多くは軽症で回復しますが、重症化した場合は、細気管支炎、肺炎などを起こします。
特に生後6か月以内に感染した場合や、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患のある高齢者や、免疫不全者では、先ほど議員がおっしゃられましたとおり、重症化するリスクがあり、注意が必要とされています。
次に、予防方法につきまして、RSウイルスは感染した人のせきやくしゃみなどによる飛沫感染や、ウイルスの付着した手・指や物などを介して、接触により感染が広がりますので、基本的な感染対策である手洗い、消毒、マスク着用が重要です。ふだんから日常的に触れるおもちゃ、手すりなどは小まめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒し、流水、石けんによる手洗い、またはアルコール製剤による手指衛生を行うことや、鼻水、せきなどの呼吸器症状がある場合は、マスクが着用できる年齢の子供や大人は、マスクを使用するといった基本的な感染対策の徹底を行うことが大切です。
また、任意接種として接種できるワクチンなどがございます。以上です。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 続いて、(2)ワクチン費用助成について。
RSウイルス感染症には治療方法がなく、2024年9月、高齢者への接種を目的としたワクチンが薬事承認されています。肺炎への重症化を防ぐには、ワクチン接種が有効となります。RSウイルスは、乳幼児だけでなく、生涯繰り返し感染し、高齢者では重症化リスクが高く、過去には、福祉施設で集団感染を発生し、入院してから致死率を増加させ、集中治療室の入室の必要な肺炎患者からも高頻度でウイルスが検出されています。
60歳以上の成人高齢者において、呼吸器系に悪影響を与え、肺炎などを引き起こす可能性の高いRSウイルス感染症を回避することは、基礎疾患を持つ多くの高齢者の健康維持を守り、また、医療費の削減や地域の医療資源、介護現場における負担軽減に大きく寄与するものと考えられます。
令和6年1月にRSウイルス感染症予防ワクチンが発売され、1回2万円、2年に1回の接種間隔となり、高額な費用となっています。RSウイルス感染症ワクチン接種の有効性が認められている現在、RSウイルスワクチン予防接種費用の一部助成の検討をしてはどうか、お伺いをいたします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 お答えします。
RSウイルスワクチンは、現在、任意接種として接種できるもので、議員がおっしゃられた60歳以上と50歳以上の重症化リスクが高い人を対象としたワクチンのほか、生まれてくる子の予防のため、妊婦に接種するワクチンは60歳以上の人も接種することができます。これらのワクチンは、予防接種法に規定される定期接種とは異なり、国がワクチンの使用を認めてはいるものの、接種する場合の費用は自己負担となるものです。
ワクチンの定期接種化に関する議論は、現在、国において検討が進められており、今後、RSウイルスワクチンが定期接種の対象となる際には、一部の自己負担で接種が受けられるよう取り組みたいと考えております。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
世界保健統計2023年版によると、日本人の平均寿命は84.3歳で世界1位、健康寿命、健康で自立した生活が過ごせるについては74.1歳で、これらも世界1位となっています。平均寿命は延ばすことは難しいが、日常生活において、生活習慣病などで医療や介護が必要となる可能性がある期間を少しでも短くすることが健康寿命延伸の重要ポイントになります。
健康で自立した生活が過ごせる健康寿命の延伸のためにも、今後の超高齢化社会を迎えるに当たり、RSウイルス及び肺炎に対する対策は一層重要になってきます。今後本市においても、RSウイルス予防ワクチンの公費助成導入を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
以上で一般質問を終わります。
○佐藤倫与議長 以上で、2番徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
応答、答弁者:危機管理課長、健康介護課長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、欠員1人、現在数13人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 通告に従い一般質問をいたします。
1、市民の安全と安心を守る防犯灯について。
防犯灯は、通学路や生活道路において、通行者の安全確保や夜間の事故防止など、明るい環境によって犯罪の発生が抑制されるなど、防犯灯を設置することで、地域住民の安全・安心が守られています。本市では、維持管理について、設置は市で行い、電気料金の維持は受益者負担地域や町内会などで支払っています。自治体によっては逆の場合もあるようです。
令和5年12月議会の一般質問で、防犯灯について、本市の状況は詳しくお聞きいたしました。お困り事の相談は、現状を確認の上、協議しますと答弁をいただいております。
現在、人口減少、高齢化が進む中で、町内会が解散という現実が起こっています。既設の防犯灯の維持管理について、どうしていけばいいのかとの問題が起きていることは、本市の今後において喫緊の課題の一つと考えています。
人口減少、高齢化はいろんな問題へとつながっていますが、防犯灯の電気料金の支払いなど、維持管理が困難となる状況について、対策を考え、現状を少しでも軽減できないかとの思いでお伺いをいたします。
(1)本市に設置の防犯灯の種類と設置数について、令和5年12月時点での市内防犯灯は1,411基、うち地域が電気料金を負担している防犯灯は740基と承知していますが、その種類別設置数をお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えをさせていただきます。
令和7年5月末時点の市全体の防犯灯総設置数は1,426基、うち地域が負担しているものは725基で、前回答弁いたしたものより負担区分の見直しや廃止などの関係から若干減少をしております。
地域負担の防犯等における種類別設置数でございますが、防犯灯の種類は蛍光灯タイプとLEDタイプの2種類ございまして、地域負担725基のうち、蛍光灯タイプが258基、LEDタイプが467基でございます。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 現在、蛍光管を交換するタイミングで、同程度の明るさで消費電力が少ないLEDへ順次切替えられています。LEDは、蛍光灯に比べて明るさやエネルギー効率と耐久性に優れ、省エネ、CO2の削減など、地球温暖化対策や維持管理経費の削減などに効果があり、電気料金は蛍光灯の約半分だと言われています。
そこで、本市での防犯灯のLED化は、令和5年当時からどの程度進んでいるのか、LED化によって消費負担の軽減の効果は市民にどの程度届いているのでしょうか。
(2)既設の防犯灯のLED化の割合を伺います。
そして、現在の進捗と今後の課題を含めて、早期LED設置への見解を併せてお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えいたします。
市全体の防犯灯設置1,426か所のうち、LED化している箇所は936か所あり、割合で申しますと65.6%となります。
早期LED設置への見解との御質問でございますけれども、まず、本市の防犯灯の設置につきましては、安芸市防犯灯の設置及び管理に関する要綱に基づきまして、設置を希望する地域の代表者等から、新設、移設、形態の変更、休止または廃止について申請をしていただくことになっておりまして、それらの申請があった場合に、現地調査の上、設置の可否を決定をしております。
LED化に向けての御質問でございますけれども、現在、申請が新設箇所の場合には、LEDタイプを当初から設置することとしており、また、既設の蛍光管タイプの防犯灯に故障や不具合が生じた場合においても、LEDタイプへの交換を行っておるとこでございます。
現在、LED化の割合は市全体では65.6%でありますので、残り34%余りの部分につきましては最大限予算を確保しながら継続してLED化に取り組んでまいりたいと考えております。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 蛍光管の交換時にLED照明への切替えで、ランニングコスト全体が抑えられます。LEDの省エネ性能は高く、長期的に見るととても経済的です。LED導入は電気代だけではなく、交換費用やコスト削減にもつながることからも、早期のLED化を進めていただきますようお願いいたします。
次に、(3)人口減少に伴う防犯灯維持対策について。
本市において、今後10年、20年と防犯灯を維持し続けるためには、電気料金は市が負担することが必要となるのではと考えています。町内会はあくまでも任意団体のため、未加入者は電気料金を負担しておらず、不公平な状態でもあります。
また、今後においても減少化は進み、電気料金の支払いも困難となり、今回のような町内会が解散したり、防犯灯自体を取り外すことも避けられなくなる可能性があります。
そこで、今後の本市の未来図として、現時点での市の防犯灯維持のための対策をお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えいたします。
まず、防犯灯の電気代についてでございますけれども、防犯灯の設置を希望する地域からの申請をもって、これまでも場所ごとに都度設置の可否を決定した上で、地域負担か市負担か明確に区分をし、現在、地域負担となっている箇所におきましては、そこに防犯灯を設置した目的から鑑みて、やはり今後も地域での負担はやむを得ないものと考えております。
現在、地域での電気代の支払いにつきましては、地域によっては防犯灯周辺の数戸のおうちが負担し合っているところもあれば、個人が負担しているところもございます。将来、地域の人口の減少が見込まれる中、防犯灯を維持していくための対策をとの御質問でございますけれども、そのときの状況にもよりますが、直ちに市が負担することは公平性の観点からも困難であると考えております。
しかし、中長期的な課題として捉えておりまして、当面市としては、引き続きLED化に取り組み、まずはランニングコストの縮減につなげてまいりたいと考えております。
一方、各地域におかれましても、時代の変化に応じて、どこかのタイミングで設置基数や設置場所が適正かどうか、移設や廃止なども含め御検討いただくことも必要ではないかなと考えております。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 人口減少、高齢化が進む中、今後どのように市民生活の安心安全を守っていくのか。具体的な対策と取組を早急に示してほしいと思います。
次に、2、空き家の老朽化問題について。
総務省は5年ごとの調査で、2023年、日本の空き家は900万戸で、空き家率13.8%と過去最多であると示しました。少子高齢化の進展、人口移動の変化などが空き家増加の背景として挙げられ、高齢者の増加や都市への人口集中、住宅供給の過剰などが原因とされています。
空き家のうち、賃貸や売却、別荘などの2次利用を除いた利用目的のない空き家は、385万戸で、総住宅数に占める割合も5.9%と過去最大となっています。増え続ける空き家問題は、防災、衛生、景観面など生活環境へと社会問題となっています。空き家対策は既に空き家になったものをどう活用するかという点以外に、将来、いずれ空き家になる可能性がある築数年の家に対しても、早めの対策が必要と考え、空き家対策においては、空き家になる前の啓発が、発生抑制のために重要であり、予防の観点から、持ち主が住んでいるときから、将来、空き家にならないよう準備することが何より大切と考えます。
高齢者が施設入所や入院など、福祉、介護、医療の問題で留守になり、その後、空き家化するケースが多く、住まなくなった家は驚くほどのスピードで老朽化、衛生悪化が進むことからも、発生抑制のための対策として、本市の空き家の老朽化問題について見解をお伺いいたします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○大坪 純危機管理課長 お答えをいたします。
空き家の増加は、長年少子高齢化や人口減少、さらには相続問題などもあり、これら複合的な原因によって引き起こされてきた、全国的にも大きな社会問題の一つであり、本市においても同様であります。
住む予定がなくても所有者において管理責任があり、維持していくためには、小まめな手入れが必要ですし、毎年固定資産税の支払いも生じております。逆に一たび放置されてしまうと、老朽化が進行し危険家屋にさま変わりしてしまい、仮に飛散物で他人にけがをさせた場合には、損害賠償の管理責任を問われることもあるなど、所有者や御家族、地域の方、双方にとっていいことはございません。
議員から、そのおうちが空き家になってしまう前に、事前に所有者に御自宅の将来を考えてもらうための何か市の取組といった趣旨の御質問でございますが、高知県住宅課が空き家になる前や、空き家になった後のおうちをどうしたらよいかといった、おうちの今後を考えるきっかけとして活用いただける「空き家のトリセツ」や「わが家の思い出ノート」、こちらにその冊子がございますけれども、こういった冊子を作成しており、空き家の活用法や空き家にしないための対策を紹介しております。
また、専門家によるアドバイス等が受けられる高知県空き家相談窓口という無料の相談窓口も設けております。「空き家のトリセツ」及び「わが家の思い出ノート」の冊子につきましては、市役所の企画調整課の窓口にて配布をしておりますほか、高知県住宅課のホームページでも御覧いただくことができるようになっております。
また、高知県空き家相談窓口につきましては、インターネットで御検索いただくか、先ほどの冊子に連絡先やQRコードが記載されておりますので、そちらから御相談いただくことが可能となっております。
また、本市においては、これまで地域の座談会にて先ほどの県冊子を御紹介させていただいたほか、使用しなくなったおうちの有効活用、また、安芸市に移住・定住を希望する方への移住住居の確保を目的に、空き家バンク制度なども設けております。
さらには、老朽化した木造住宅を、この際、取壊しをしようとお考えになられている所有者様に対しまして補助制度を設けており、現地調査の上、老朽度が著しいと判定された場合という要件がございますが、補助額は除却費の80%、金額の上限は167万5,000円を御用意しております。
家は個人の大きな財産であるため、将来必ず訪れる家じまいについて家族であっても、ふだんなかなか話題にしづらかったり、どこに相談したらいいか分からず先送りにした結果が現状空き家の増加につながってきた要因の一つであると考えており、将来、よりよい地域の住まいの環境を維持していくためには、やはり所有者の決断や協力なくしては成り立ちません。
市としましても、今後引き続き市民の皆様に御自身や御家族の住まいの将来について考えていただく機会を今後も提供してまいりたいと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 詳しい御答弁ありがとうございます。
空き家対策と同じ視点で考えなければいけない問題として、空き地対策があります。住宅地、公園に隣接する広い空き地には、雑草・雑木が繁茂し、害虫発生、子育て中の保護者にとっての危険箇所、背丈の高い草の中に何が放置されていても分からない場所についても、景観を乱す空き家同等の問題が起きてきます。空き地に繁茂した雑草の除去に関しては、その都度に対策が必要と考えます。
空き家、空き地対策は、所有者の事情などから、時間がかかることが多く、また労力・費用など、地方創生を進めていく上には、一つ一つ粘り強い取組が必要となりますが、国・県の補助を受け、新たな条例づくりなどからも、問題解決に向けての取組をお願いいたします。
次に、3、RSウイルス感染症について。
(1)感染症の症状と予防法について。
RSウイルス感染症は、古くから1960年代に認知された感染症で、出産後、母親からの免疫が消失していく乳幼児または小児において見られる風邪症状を伴う呼吸器感染症として知られています。特に60歳以上の成人、高齢者においては、加齢とともに、免疫力が落ちてきたり、様々な基礎疾患やその治療薬などにより、免疫が低下するなどのことから感染し、重症化すると言われています。
コロナ禍以前では、高齢者におけるインフルエンザ様症状疾患の原因の第3位が、RSウイルスであったと報告をされています。また、呼吸器感染症と言われるように、高齢者においては、肺炎などの重篤な症状により、入院後亡くなるという報告があります。
感染症を発症した方の10人に1人が入院し、入院された方の15人に1人が、肺炎等で亡くなっているという状況から、日本では毎年約70万人のRSウイルス感染者が出ており、うち約6万3,000人が入院、約4,500人の方が入院中に亡くなられる可能性があると推計をされています。
RSウイルス感染症は、乳幼児から高齢者がかかる感染症ですが、その症状と予防法を伺います。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 初めに、症状につきまして、RSウイルス感染症は、RSウイルスの感染による急性の呼吸器感染症で、年齢を問わず何度も感染を繰り返します。潜伏期は2日から8日とされ、主に発熱、鼻水、せきなどの風邪のような症状が数日続き、多くは軽症で回復しますが、重症化した場合は、細気管支炎、肺炎などを起こします。
特に生後6か月以内に感染した場合や、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患のある高齢者や、免疫不全者では、先ほど議員がおっしゃられましたとおり、重症化するリスクがあり、注意が必要とされています。
次に、予防方法につきまして、RSウイルスは感染した人のせきやくしゃみなどによる飛沫感染や、ウイルスの付着した手・指や物などを介して、接触により感染が広がりますので、基本的な感染対策である手洗い、消毒、マスク着用が重要です。ふだんから日常的に触れるおもちゃ、手すりなどは小まめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒し、流水、石けんによる手洗い、またはアルコール製剤による手指衛生を行うことや、鼻水、せきなどの呼吸器症状がある場合は、マスクが着用できる年齢の子供や大人は、マスクを使用するといった基本的な感染対策の徹底を行うことが大切です。
また、任意接種として接種できるワクチンなどがございます。以上です。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) 続いて、(2)ワクチン費用助成について。
RSウイルス感染症には治療方法がなく、2024年9月、高齢者への接種を目的としたワクチンが薬事承認されています。肺炎への重症化を防ぐには、ワクチン接種が有効となります。RSウイルスは、乳幼児だけでなく、生涯繰り返し感染し、高齢者では重症化リスクが高く、過去には、福祉施設で集団感染を発生し、入院してから致死率を増加させ、集中治療室の入室の必要な肺炎患者からも高頻度でウイルスが検出されています。
60歳以上の成人高齢者において、呼吸器系に悪影響を与え、肺炎などを引き起こす可能性の高いRSウイルス感染症を回避することは、基礎疾患を持つ多くの高齢者の健康維持を守り、また、医療費の削減や地域の医療資源、介護現場における負担軽減に大きく寄与するものと考えられます。
令和6年1月にRSウイルス感染症予防ワクチンが発売され、1回2万円、2年に1回の接種間隔となり、高額な費用となっています。RSウイルス感染症ワクチン接種の有効性が認められている現在、RSウイルスワクチン予防接種費用の一部助成の検討をしてはどうか、お伺いをいたします。
○佐藤倫与議長 健康介護課長。
○国藤美紀子健康介護課長 お答えします。
RSウイルスワクチンは、現在、任意接種として接種できるもので、議員がおっしゃられた60歳以上と50歳以上の重症化リスクが高い人を対象としたワクチンのほか、生まれてくる子の予防のため、妊婦に接種するワクチンは60歳以上の人も接種することができます。これらのワクチンは、予防接種法に規定される定期接種とは異なり、国がワクチンの使用を認めてはいるものの、接種する場合の費用は自己負担となるものです。
ワクチンの定期接種化に関する議論は、現在、国において検討が進められており、今後、RSウイルスワクチンが定期接種の対象となる際には、一部の自己負担で接種が受けられるよう取り組みたいと考えております。
○佐藤倫与議長 2番 徳広洋子議員。
○2 番(徳広洋子議員) ありがとうございます。
世界保健統計2023年版によると、日本人の平均寿命は84.3歳で世界1位、健康寿命、健康で自立した生活が過ごせるについては74.1歳で、これらも世界1位となっています。平均寿命は延ばすことは難しいが、日常生活において、生活習慣病などで医療や介護が必要となる可能性がある期間を少しでも短くすることが健康寿命延伸の重要ポイントになります。
健康で自立した生活が過ごせる健康寿命の延伸のためにも、今後の超高齢化社会を迎えるに当たり、RSウイルス及び肺炎に対する対策は一層重要になってきます。今後本市においても、RSウイルス予防ワクチンの公費助成導入を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
以上で一般質問を終わります。
○佐藤倫与議長 以上で、2番徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
添付ファイル1 一般質問 徳広洋子 (PDFファイル 298KB)