HOME > 応急手当 止血
応急手当 止血
消防本部 : 2009/07/25
■出血の種類
■動脈性出血
動脈性出血は動脈の破綻によるもので、拍動性で鮮紅色を呈し、大きな血管では瞬間的に多量の血液を失って、失血死の恐れがあります。緊急に応急手当を必要とするのは、この動脈性出血です。
(2)静脈性出血
静脈性出血は滲出性で暗赤色を呈し、四肢損傷では静脈圧が低く、短時間に多量出血になることは少ない。応急処置として創部をガーゼで圧迫することにより止血できます。
(3)毛細血管性出血
毛細血管性出血は動脈血と静脈血の中間色で、普通そのままにしておいても自然に止血します。
■出血量と症状
出血量が循環血液量の10%以内であれば脈拍数がわずかに増加する程度であるが、10%以上になると様々な変化が出現してきます。一般に20%が急速に失われると出血性ショックという重い状態になり、30%を失えば生命の危機に瀕するといわれています。成人の全血液量は、体重の約1/13で、男性1キログラムあたり80CC、女性1キログラムあたり70CCと推定されます。
出血による生体の反応
■止血の仕方
(1)直接圧迫止血
傷口の上をガーゼやハンカチで、直接強く押さえてしばらく圧迫します。この方法が基本的で確実な方法です。包帯を少しきつめに巻くことでも、同様の止血効果があります。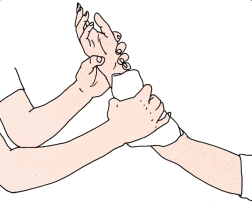

(2)間接圧迫止血
動脈と止血点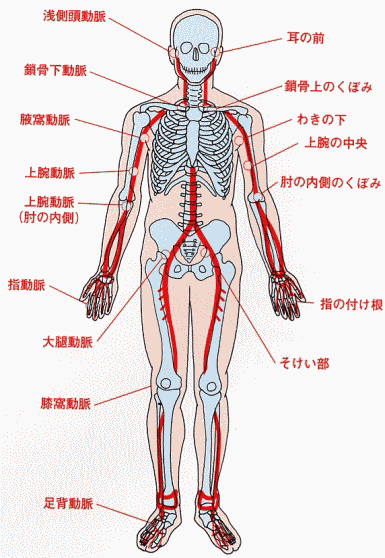
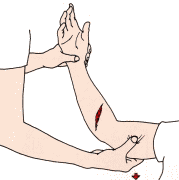 1肘の内側の窪みでの止血
1肘の内側の窪みでの止血
肘の内側の窪みにある上腕動脈を圧迫する
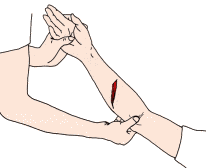 2上腕で止血
2上腕で止血
上腕中央側の上腕動脈を圧迫する
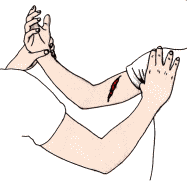 3腋の下での止血
3腋の下での止血
腋の下の窪みの中央から親指で上腕骨に向けて脇窩動脈を圧迫する
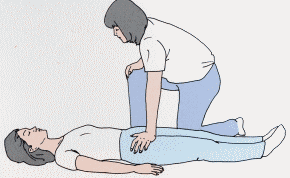 4鼠経部での圧迫
4鼠経部での圧迫
掌を鼠経部に当て、肘を伸ばして体重をかけ、大腿動脈を圧迫する
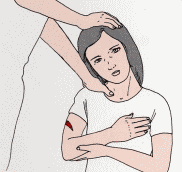 5鎖骨上の窪みでの止血
5鎖骨上の窪みでの止血
鎖骨上の窪みに親指を当て、鎖骨下動脈を体の中央下方に向かって圧迫します。他方の手で頭部を受傷側に強く傾け、鎖骨上窩の緊張をとり、圧迫を助けるのが止血の要領です。
(3)止血帯
棒を用いる場合
 上腕(大腿)に止血帯を1回巻き
上腕(大腿)に止血帯を1回巻き
その上で半結びをする

 そこに長さ20cm程度の丈夫な棒を通し,それを回転させてしめていく
そこに長さ20cm程度の丈夫な棒を通し,それを回転させてしめていく
止血できたところで棒を固定し
 必ず、止血時間を書いた傷票をつけておきましょう
必ず、止血時間を書いた傷票をつけておきましょう
棒を用いない場合
 三角巾などを適当な幅にして,それを中央から2つ折にする
三角巾などを適当な幅にして,それを中央から2つ折にする
そこへ両端を交互に差し込んで
 出血が止まる程度、引きしめる
出血が止まる程度、引きしめる
「救急法講習教本」日本赤十字社より
■動脈性出血
動脈性出血は動脈の破綻によるもので、拍動性で鮮紅色を呈し、大きな血管では瞬間的に多量の血液を失って、失血死の恐れがあります。緊急に応急手当を必要とするのは、この動脈性出血です。
(2)静脈性出血
静脈性出血は滲出性で暗赤色を呈し、四肢損傷では静脈圧が低く、短時間に多量出血になることは少ない。応急処置として創部をガーゼで圧迫することにより止血できます。
(3)毛細血管性出血
毛細血管性出血は動脈血と静脈血の中間色で、普通そのままにしておいても自然に止血します。
■出血量と症状
出血量が循環血液量の10%以内であれば脈拍数がわずかに増加する程度であるが、10%以上になると様々な変化が出現してきます。一般に20%が急速に失われると出血性ショックという重い状態になり、30%を失えば生命の危機に瀕するといわれています。成人の全血液量は、体重の約1/13で、男性1キログラムあたり80CC、女性1キログラムあたり70CCと推定されます。
出血による生体の反応
| 程度 | 欠乏量 | 出血量(CC) | 臨 床 症 状 |
| 軽 度 | 10~20% | 500~1000 | 一過性、めまい、立ちくらみ |
| 中等度 | 20~30% | 1000~1500 | 青白く冷たい皮膚、低血圧、口渇、頻脈 |
| 重 度 | 30%以上 | 1500以上 | 強度の皮膚蒼白、意識障害、高度の血圧低下 |
(1)直接圧迫止血
傷口の上をガーゼやハンカチで、直接強く押さえてしばらく圧迫します。この方法が基本的で確実な方法です。包帯を少しきつめに巻くことでも、同様の止血効果があります。
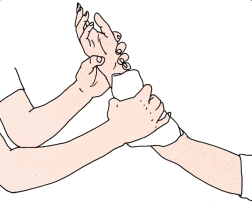

(2)間接圧迫止血
動脈と止血点
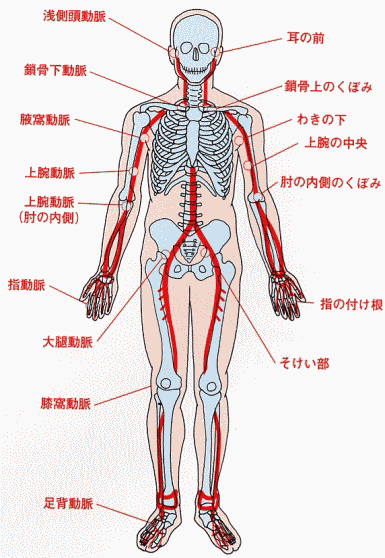
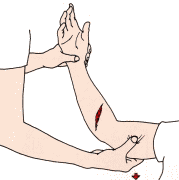
肘の内側の窪みにある上腕動脈を圧迫する
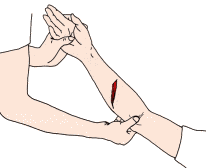
上腕中央側の上腕動脈を圧迫する
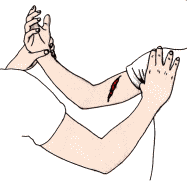
腋の下の窪みの中央から親指で上腕骨に向けて脇窩動脈を圧迫する
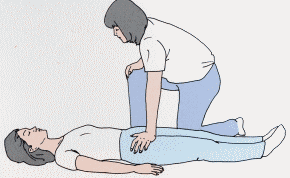
掌を鼠経部に当て、肘を伸ばして体重をかけ、大腿動脈を圧迫する
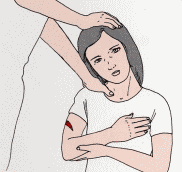
鎖骨上の窪みに親指を当て、鎖骨下動脈を体の中央下方に向かって圧迫します。他方の手で頭部を受傷側に強く傾け、鎖骨上窩の緊張をとり、圧迫を助けるのが止血の要領です。
(3)止血帯
棒を用いる場合


その上で半結びをする


止血できたところで棒を固定し

棒を用いない場合


そこへ両端を交互に差し込んで

「救急法講習教本」日本赤十字社より












